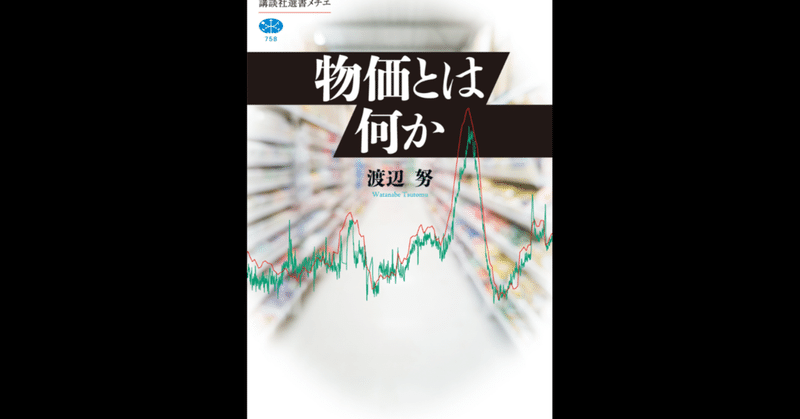
インフレを知らない子供たち
良書です。物価研究の第一人者による平易で分かりやすく物価の仕組みを説明しています。
ただ、日本の平成のデフレ時代に育った、あるいは海外でインフレを経験したことがない人にとっては現実感がないかもしれません。
考えてみると日本は90年代のバブル崩壊後ずっとデフレで、インフレに至らなくても物価が上がることを経験していません。原油価格の動向でガソリン価格が週次で変動し、ときに家計を直撃することがニュースになるぐらいでしょう。
2000年代初頭にニューヨークに赴任した時のニューヨークタイムズの価格は0.75ドルでした。それが1ドル、1.5ドルと上がっていき、久しぶりに出張で訪問したときの価格にびっくりしました。
新聞に限らず、アメリカでは物価が上昇していきます。スターバックスのコーヒーも、地下鉄も、食料品も。
ビジネスでは、年間の予算を策定しますが、物価上昇・賃金上昇を想定して計画します。物価上昇分を盛り込むことを忘れていると計画と実績が狂ってしまい大変なことになります。
ヨーロッパも同じです。特に、Indexation(インデックスゼーション)といって物価連動で賃金や料金が上昇する制度がある国では、年間の予算策定に必ず賃金の上昇を見込みます。賃金だけでなく、学校の授業料、などほとんどすべての料金が連動して上がります。
物価が上がるから物価インデックスが上がる、のではなく、物価インデックスが上がるから物価スライドで世の中の物価が上がる、のではないかと文句を言っても、社会の制度なので仕方がありません。
このインデックスゼーションは日本に説明してもなかなか理解を得られず、従わなければいいではないか、と言われ海外駐在員の苦しみの1つでした。社会全体が物価スライドする仕組みが日本にはないこともありますが、そもそも何十年も日本ではインフレを経験してないから異国の出来事にピンとこないのです。
インデックスゼーションは日本だけではなかったようで、私が関わっていたビジネスの現地の協会が、本国に説明できるようにと「インデックスゼーションとは」というレポートを出していたぐらいでした。
翻って、日本。ワンコイン弁当のみならず、500円もあれば牛丼を店で座って食べることができます。そして水は無料。ヨーロッパで座って食べる店では水は3ユーロはしますので、500円だと水しか注文できないのですが、日本ではコンビニで100円のおにぎりもあるし、水は水道からいくらでも飲むことができます。とにかく、日本は物価が安くて安定しています。
最近、日本では原油高、鋼材高、輸送費高などでいろいろな製品の値上げがニュースになっています。新築マンションの価格はバブル期を超えたそうです。インフレ懸念から長期金利は上昇気味です。さらに金利上昇を懸念して株式市場が不安定になっています。おそらく、インフレを経験したことがないので、インフレに対する心理的耐性がないことも一因だと考えます。
世界的にインフレについてのニュースが増えており、これまで長い間、物価上昇を意識することがなかった人たちが物価について考えてみるきっかけになる本です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
