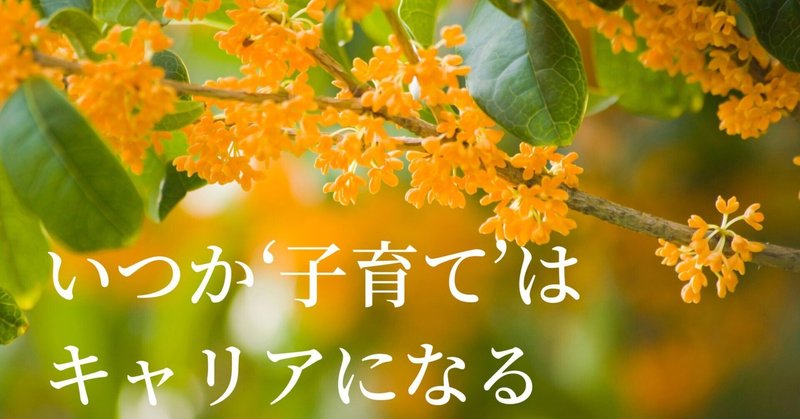
29歳でメーカー総合職を離脱し、14年の“子育てと働く”がキャリアとなり、42歳でナチュラルに法人化した話
私が小学生の時、卒業アルバムに書いた将来の夢は「キャリアウーマン」でした。(今は死語になりつつありますね)
今から30年前、1992年はバブルが崩壊した頃。しかし頭の中には『ジュリアナ東京』が根付いている、そんな「まだイケるんじゃ無いか」と希望が残存する時代でした。
私の母は、小学校の教師であり、あの時代にはマイノリティな働く女。
学校の運動会や式典は当然に自身の行事と被るので来れない事もあったかと思いますが、大事な式など少し遅れてでも来る、しかも綺麗なスーツを着て、主婦のお母さんとは明らかに違う。といった印象が私の「キャリアウーマン」像を造ったと考えます。
(学校では、体操ジャージや簡単な格好をしていたはずなので、きっと母も意識して綺麗な格好をしていたかと。なんというか・・・働く女性のプライドを見ていた気もします)
そして時を経て、新卒で化粧品会社に就職。総合職(営業・教育)でキャリアを積みまた。
なぜその会社に入ったのかはシンプルで、「働く女性は美しい」を掲げて女性が活躍できると打ち出していたこと。年俸制・実力主義。女性の管理職が20代後半から経験できる会社だったから。
余談ですが、この会社の今でもリスペクトしている点、私の血肉となった点は、プロモーションブランディングに長けていたこと。「自然を科学する」という企業理念と共に、社員全員がそのストーリーを自分ごととして話せるように教育を徹底していたし、プロモーションにはアートや音楽の力を一貫して使い続けていること。20年以上前のC Mから常に、商品ではなくイメージをずっと打ち出しているような、そんな【ナラティブ】を徹底した会社だった。
29歳で会社員を離脱
自分でも不思議ですが、キャリアに向かっていた中で、結婚・出産。これは意識と行動が一致していない?と言ってもいいような流れでしたが、若いとは、愛とはそういうもの?
又違う観点で、共働き家庭でしたので、祖父母と過ごす事が多かった私に、祖母がずっと耳元で言っていたこと。
「30歳までに結婚して産みきりや」
祖母は戦後、あの時代に子どもを授かるのに苦労し、長男を産後すぐに亡くしたことなど、結局母ひとりっ子という経験から私に言い続けたのだと思います。
サブミナル効果というものが有りますが、「結果そうなる」というこれも不思議な体験です。
実際、30歳までに次男を産み切りました。
そんなこんなで、怒涛の結婚・出産。まだ時代は女性活躍・保活も皆無といった霧中に投げ出されるような体験です。
育休を取得しましたが、実際に1年後戻ろうとした際に、
そもそも総合職で転勤がつきもの(その当時は浜松に居ました)→旦那も当然フルで働き、両親も近くに居ない。どう子どもを育てるのか?
そこそこ営業成績も良く自分の立ち位置を会社でつくれていた私は、「会社には自分が必要だ」と思い込んでいましたが、産休で不在となった時に、私の替え玉なんて星の数ほどいた。それはそうですよね、150人ほど新卒を取るような企業にとって、いちコマでしかなかった。その反面、目の前の息子の母親は私しかおらず、私が目を離したら「死ぬ」と言った哺乳類の生存戦略を目の当たりにし、母になり優先順位いちが「子」になった時、会社員を「離脱」しました。
そんな経緯で放り出された感を味わった私でしたが、
今考えてみると、1つのユニークネス・ニッチさとして違っていたなと思うのはマインドの「デフォルト」→初期設定です。
母親であっても仕事を持つ、働くこと、は当たり前だった。そう、私の母がそうだったように、その姿しか見ていなかったので当然ですよね。
社会の流れが【女性活躍】に傾き出したその頃、世の中の女性たちは
「なぜ私たちだけが」
「保育園に入れない悲劇」
→つまりそれは基盤をつくれていない日本が悪い!という社会批判の流れが増していった。
「かわいそうな母親たち」「弱者である女性」を創り出す事で社会が変わっていく運動。
これには前提に【女性が家を守るもの・子育ては母親がするもの】とい
った思い込み(アンコンシャス・バイアス)があり、苦しさを自分達で助長するような働きかけのようにも思います。
その点、私の見ていた先は少し違った。
諦めたくないのは、子育てだった。教育だった。子どもとの時間だった。
働く術はどうにでもなるだろう。それよりも、
『どうやったら2人の子育てを10年楽しみ、共に満たされた状態のマインドを持って、自身の能力を社会に還元する(ビジネスってそういうこと)仕組みを創れるか』
ということを常に考えていました。
“こそだてもキャリアも前進する“
つまり、何か問題にフォーカスするとか、原因を追求する、といった事ではなく、どうやったら【一緒に】今を、未来を楽しめるのか、という事でしかなかった。

子育てから14年が経ち、
金木犀が咲く季節、いつも長男が
「ママ、今日、金木犀の香りがしたよ」とニタッと笑い報告してくれる。
幼稚園時代、片道20分ママチャリを漕いて幼稚園まで送っていました。幼稚園に近い駅で自転車を置き、その頃立上げ・コミュニティマネージャーを担っていた「こそだてビレッジ」という子連れシェアオフィスに向かう。16時にビレッジを出て、途中駅で自転車を回収し、16時50分→家の近くに停まる幼稚園バスを追いかけ、息子たちをピックアップする。といった今思うと怒涛の日々。ちなみに迎えバスに間に合わなかったのは1回だけ。幼稚園まで迎えに行って驚いたのは追加延長料金の額でした(笑)
しかし毎朝の道中は、季節を息子たちと共に感じる時間であり、
秋になるとアクセサリーが入る布袋を持って、途中金木犀が咲くお宅に、「少しいただきますー!」と言ってその袋に金木犀を入れる。その袋を持って、幼稚園の先生にプレゼントする。少し遅れても、園の先生はすごく喜んでくれた。という彼と私の中できっと永遠に訪れる『秋』の記憶です。
身につけたスキルセット
そんなことを実践し続けた私は、確実に
①マルチタスクを徹底的にこなす術を身につけた。
キッチンでのSlack・メッセンジャー・オンライン対応はスパイスの1つのようなもの。お風呂・洗濯場で思い付いたものを頭の膨大キャンパスに描きながら家事を進め、PCに向かった瞬時に企画書に落としていく速さと集中力はそこそこだと自負しています。
②ジャマイカ精神「じゃ・まっ・いっか」というマインドも身につけた。
これは夜泣き・ぐずりという原因不明、ゴールの見えない何かと向き合った人は身につけているだろう能力。ガン泣きする乳児を抱えて遠いサバンナを脳裏で浮かべていると、フツフツと湧き上がるジャマイカ精神。
とにかく反射アクションを繰り返すと、『成功の10倍失敗する』
いや、失敗を全部成功のタネにする、と言ったところでしょうか。
現に今、事業開発・サービス開発において「この流れはこうなるな」という私用語でいう“開通ジャーニー”が瞬時につながる。逆を言えばこの先は危険。道は無い。といった勘が働く。
何らか事業設計する・要件定義するにあたって、経験と感覚が物を言います。それは、【こうしたらいい】を導き出す為の人の行動パターンであって、人の行動は当然に【微細】。論理的というよりは感覚的。点で捉えるのではなく空間で捉える。コミュニケーションそのものです。
私が考えるコミュニケーション定義とは?
あいだの距離を知る、あいだを捉えること
この領域は、やはり少し負荷が掛かる経験とその時の前へ進むマインドによって拡がっていくものだと考えます。その点で、子育て✖️働くことほど、想定外な経験から自身の領域を拡げてくれるものは無い。
アウトカム-社会デザインとはこういうものか-
「働くことを諦めない」のでは無く、「子育てを諦めない」スタンスで14年間走ってきました。子どもは驚くほど成長します。「未来そのもの」と言っても過言では無い。
そこに焦点をあてて進むことで、一緒に未来を創り、母である私も大きく成長する。そして何よりみんなが手を差し伸べてくれた。
きっと社会デザインとはそういうものなんだと実感しています。
課題感や足りなさを他責にして主張するだけでは社会は創られない。
社会の構成要素1はやはり【人】であって、人の向かう方向によって結果、社会が創られる。じゃあ向かう方向は? 自分で決めるしかない。
決めて走った足元に、キャリアができる。キャリアとは車輪の通った跡(轍・わだち)が語源であるように。
-余談2-
とはいえ、私も社会にムカついたこともある。
つわりが長男・次男ともに酷かったので、次男が生まれるまでの半年、自宅にいた長男の子育てがしんどかった。田舎の母に相談したら「保育園に入れてもらえばいいじゃない。こちらでもそういう人いるよ」と。
私は長男を抱えて、練馬の区民事務所に向かった。そしてだいぶ待った後、窓口で状況を説明。開口いちばんに「入れるとしても、1年先とか?もう産まれちゃってますよソレ」と半笑いでそのおじさんは言った。
帰り道、グズる息子を抱えながら、道中泣いた。悲しいとかじゃ無い。完全にムカつきを越えた殺意レベルのパワーを纏っていたと思う。この日、私はスーパーサイヤ人にレベルアップした。
10年間子育てしながら、あらゆる経験をさせてもらった私は2年半ほど前から個人事業主となり、修行期間的に内省をはじめました。※ストレングスファインダーでも内省力が下位なので。
子育てという修行はある程度落ち着き、経営という面での修行をイチからしようと、「とりあえず声が掛かればやってみよう」精神で。(ジャマイカが効いてますね)
近くの誰かの「これやってみたら?」にも素直に心を傾ける。

ナチュラルに経営を担うようになった
そうしていたら、周りの方々が私の持っている潜在的能力を引き出してくれるような流れが起きて、
2021年10月に株式会社ナラティブベースの取締役になりました。遙か昔から共鳴していたような存在の代表ハルさん。2020年から経営企画チームに参画しており、私自身の輪郭が確実に重なる事業体・企業ビジョンでもあり。
コロナ禍において、メンバー全員がいち商店(事業主)・フルリモートチームのチームビルディング手法やマインドセットが社会に強く求められるようになっています。
私にとってナラティブベースは、組織・チーム骨頂と言える「希望」のような存在でもあります。
そしてもう1つ。自身の事業として2年間実施してきた、経営企画や事業開発パートナーとして、在るものが活かされコミュニケーション(ユーザー含めあらゆる面において)が円滑になる経営体制を創出していく伴走サービスもコンスタントに拡がってきました。
コンサルティングという、自身の意思決定に基づたスピード感を持って、コミュニティ経営を中小企業に拡張していくことを目的に、個人事業Managemateを2022年11月1日に株式会社マネジメイトとして法人化。
こちらは代表取締役として、マネージメント(経営)のメイト(相棒)となる存在価値を引き続き創っていきます。
ちなみにこの屋号を付けたのは、2015年頃だったかと思います。
コミュニティマネジメントをただのコミュニティ管理人ではなく、法人格のコミュニケーション形成におけるスペシャリストにしていこうと。その為のマネジメント【経営】におけるメイト【相棒・仲間】として寄与する存在になることを目指して→マネジメイトと名付けました。

2020年カラーチェンジ。彼女が描いたデザイン通りの世界を創れていることに感謝です。
7年の活動と共に、そうなっていくプロセスの渦中にいることに、言霊の力を感じます。
▼事業についてはこちら
とても自然な流れで、何も気負うことも無く法人化に至りました。(インボイス等きっかけは有りますが、クライアントでもある経営者パートナーとのフラットな関係性を担保し、未来創造を共に拡張していく手段として)
もちろん、いつも小鹿のようなブルブル感はありますが、それはいつものこと。笑
何か始めよう!と前頭前野(脳)が判断する前に始まっているというのが【わたしらしい】
終わりに
確実に私のキャリアは子育てと働くことの延長線が道となって出現しています。つまりキャリアって失う・諦めるものなんかじゃ無いといういち例です。
「なりますよ。その毎日が確実にわだちに!」と13年前の悔し泣きした私&若いお母さん(お父さん)達に伝えたくて今日はnoteを書きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
