
ダンバー数150人とドラッカー組織へのチャレンジ!
ダンバー数という言葉を聞いたことはありますか?
ダンバー数は知らなくとも、コミュニティに関わるなら一度は聞き、何となく体感しているであろう「150人 /円満説」
ダンバー数(ダンバーすう、英: Dunbar's number)とは、人間が安定的な社会関係を維持できるとされる人数の認知的な上限である。ダンバー数は、1990年代に、イギリスの人類学者であるロビン・ダンバーによって初めて提案された。
詳しくはWikipediaへ
先日、対話の中で自己効力感・無力感の話から、自分が人の役に立つ事で得られる喜びが、オンライン化によっての浅い関係性の中でどれだけ発揮できるのか、なんて事を考えながらこのダンバー数が頭に浮かびました。
ある個人が、各人の事を知っていて、さらに、各人がお互いにどのような関係にあるのかをも知っている、というものを指す
自己効力を感じる上で絶対的に必要なのは各人(他人)の存在。「どのような関係にあるのかも知っている」このあたりの前提もオンライン化によって変化してきていると思います。
今まで立体的(3D)に捉えてきたものが、簡単に言うと1画面2Dになった時にこの150人ダンバー数も変わってくるなあ、と思ったり。
ダンバーは、平均的な人間の脳の大きさを計算し、霊長類の結果から推定する事によって、人間が円滑に安定して維持できる関係は150人程度であると提案した
このあたりの親密さに関係していくであろう、アフターコロナ→ニューノーマル時代のコミュニティ論は今後の探究テーマでもあるかなと思いながら、脇にそっと置きまして・・・笑
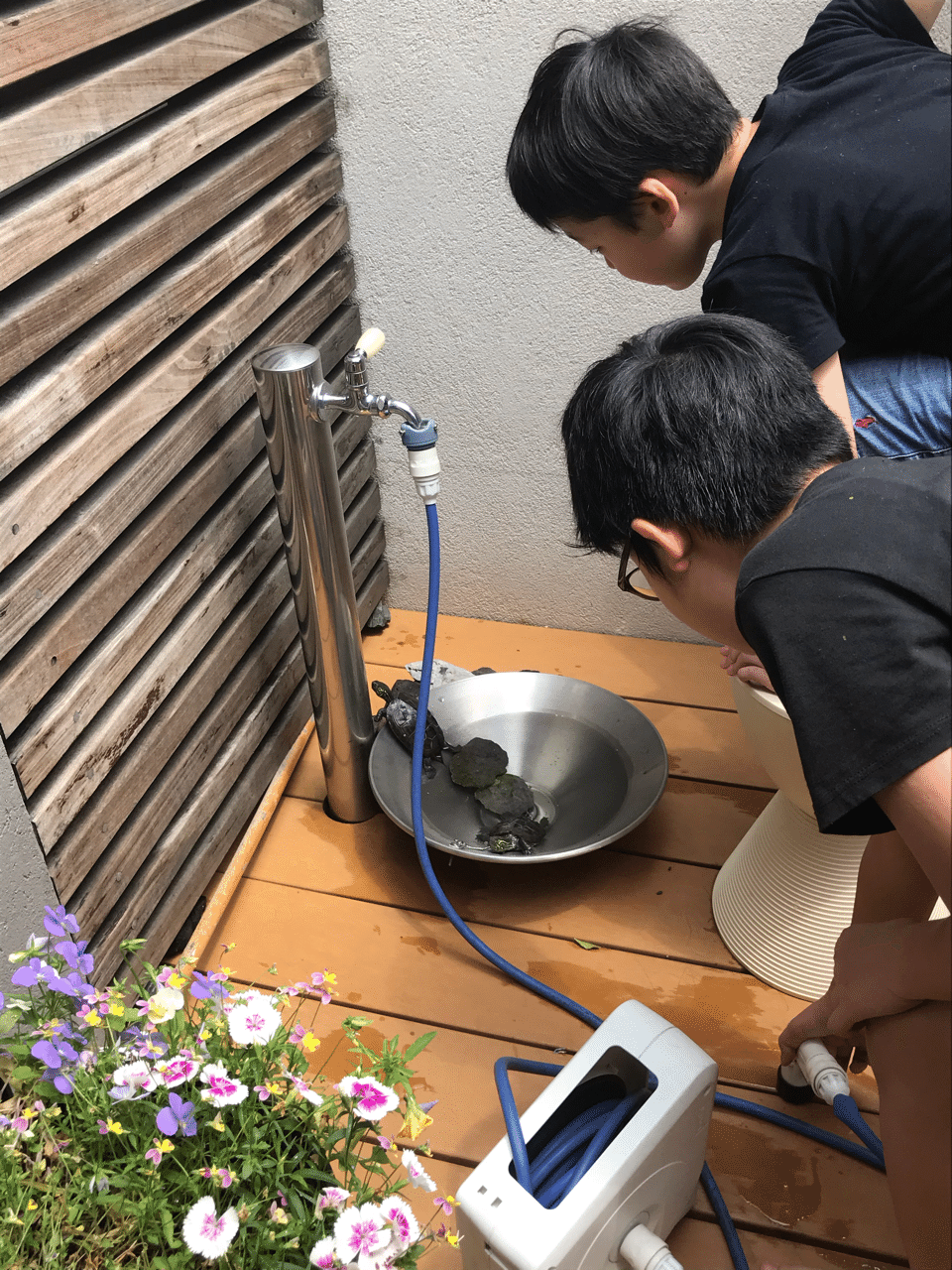
※我が家の自粛リモートワーク中に一番喜んでいたのは、亀きちでした。放し飼いで世界が広がりました
150人という実感値
実は、私もコミュニティマネージメントの世界で6年間試行錯誤しながら、コミュニティというものを捉えてきた中で、やはり実感値として感じたものでもありました。
ある一定数(150人コミュニティ領域)になった時に、どうも求心的な力が働く。どこが境で仲間と言えるのか・・・という領土的、支配的な感覚に変わっていくことに私の嗅覚は敏感に反応する。
ダンバー数理論でいうと、
ダンバー数を超えると、大抵の場合で、グループの団結と安定を維持するためには、より拘束性のある規則や法規や強制的なノルマが必要になると考えられている
これが安定要因である“コミュニティ”と相反していくというのはとても残念でもあって。
安心・安全を担保しながらも、創造的にスケールしていける方法はないのかしら??
これが私のコミュニティマネジメントにハマる“問い&起点”でもあります。
そもそも【コミュニティ】は確実な定義もなくて、世界最小コミュニティとよく言われている『家族』だってコミュニティだし、ご近所だって地域コミュニティだし、ママ友だってママ友コミュニティ。会社だってその側面を持つ場合もある、もっと言えば社会全体がコミュニティと言える。
更に私持論で、わたし自身の体組織がコミュニティネットワークだと思っているから、コミュニティというwordにはそこまで敏感でもなく、これだ!という定義付けもしたくないという気持ちはあり。→詳しくはホルモン✖️組織記事より
✳︎しかしながら、マネジメントという創造的な拡がりの世界と掛け合わせた時に150人も超えていけるのでは?
✳︎経済循環という更に広い地球規模でのネットワークの中に、安心・安全なコミュニティが活かされたら、私たちは生きやすいのでは?
ドラッカーが突きつけた真実⁈
P.F.ドラッカー。マネジメントの父。経営に携わる上で、知らない人はいないし、私もとても学び多く愛読書は多数。
その中で、
組織は創造的破壊のためにある
社会、コミュニティ、家族は、いずれも安定要因である。それらは安定を求め、変化を阻止し、あるいは少なくとも減速しようとする。これに対し、組織は不安定要因である。組織はイノベーションをもたらすべく組織される。
組織には破壊的な側面がある。コミュニティに根づかなければならないが、コミュニティの一部になり切ることはできない。・・・組織自体はコミュニティに埋没することを許されない。・・・組織はコミュニティを超越する。・・・組織を規定するものは、組織がその中に置いて機能を果たすべくコミュニティではなく、機能そのものである。 Lプロフェッショナルの条件ーいかに成果をあげ、成長するかー 著者:P.F.ドラッカー 編訳者:上田惇生より
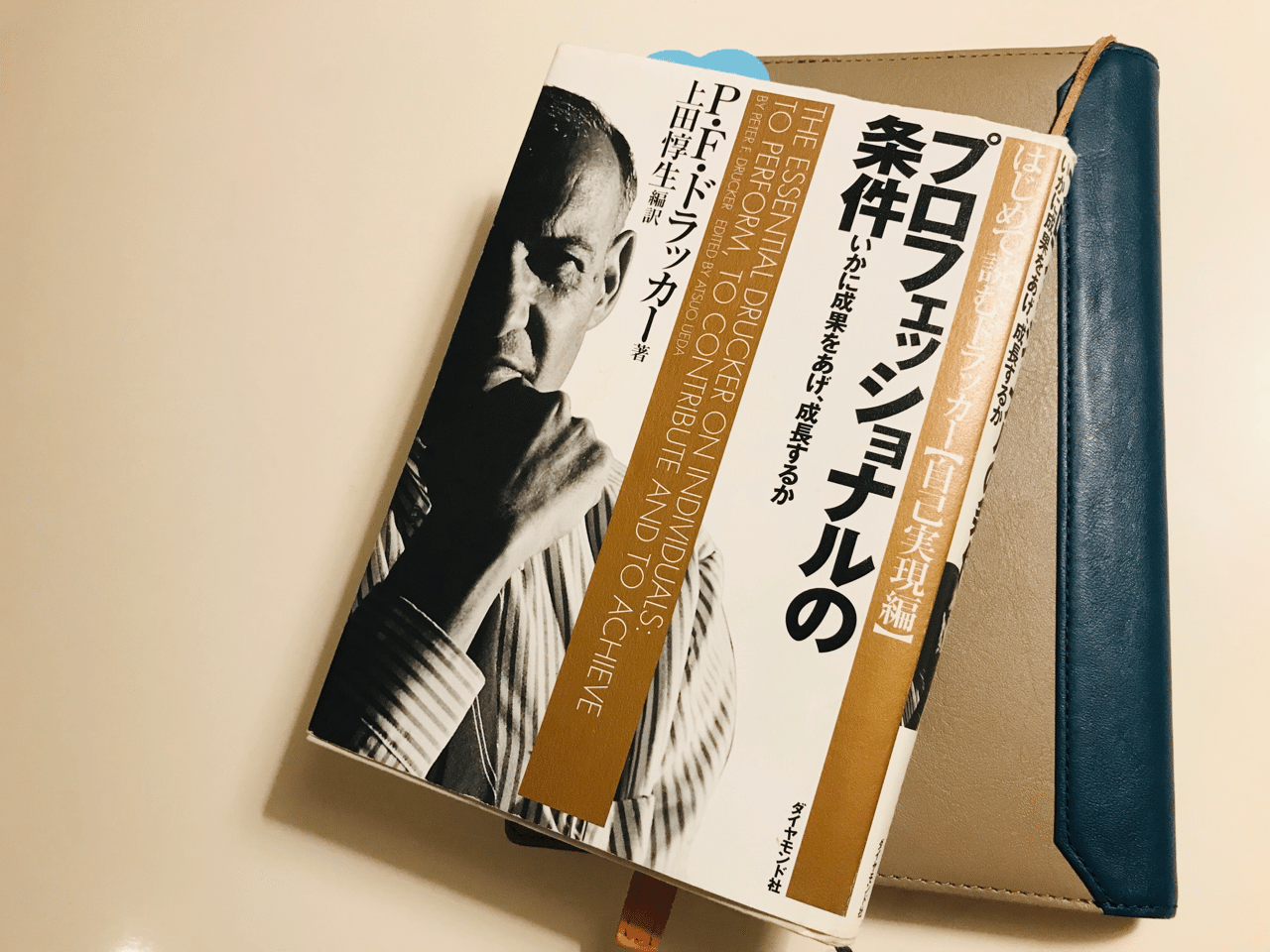
とあり、唯一、これだけは私にとって大きな問いをいただいた内容でした。
ドラッカーが心理的安全・コミュニティが基盤となるこの時代に生きていたら、何を語るのだろうか
コミュニティを経営に活かす、コミュニティマネジメントについて、もっと聞いてみたかった。
でも、私は、これからの時代には、安心安全が前提にあってこそ、個々が源泉として湧き上がる創造力を発揮し、イノベーションが持続可能になっていくという経済循環を信じていて。それが集合知となってのエネルギー循環が強い組織となっていく経営スタイルが求められていくと・・・
まだまだです、精進します!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
