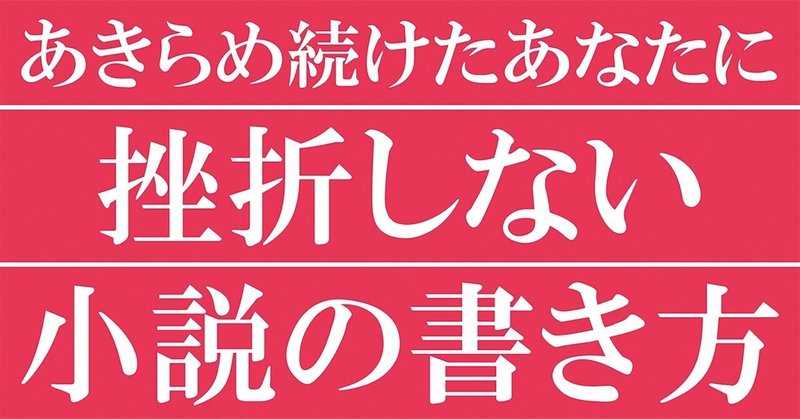
#020 復習は「ごほうび&おまけ付」
拝啓 この連載記事を一度でも読んでくださった方へ
[1]予習 ⇒[2]受業(学ぶ&実践)⇒[3]復習 ⇒[4]?
今回は[3]復習 と[4]? について、
お話しさせていただきます。
全4回の4回目にあたる今回は、
脱稿後、つまり原稿を書き終えたあとのことです。
…… では [3]復習 から始めます。
[3]復習/ごほうび&おまけ
とにかく作品1本書き終えて(実践・実行し終えて)、
1本また1本と、創りつづけていくと、こんないいことがあります。
…… っていう、近い将来の「ごほうび」について、お話しします。
最近ほとんど聞かなくなった、いわゆる「ベネフィット」です。
まず最初に、
わたしが申し上げる「復習」の定義ですが、
お手許にあるハウツー本や、
講座で使用したテキスト類などを読み返すことです。
あるいは、新しく見つけたハウツー本を読んだり、
新たに検索したネット上の手順やマニュアルなどを見ること。
またその両方することを「復習」と定義させていただきました。
では、復習すると、どんな「ごほうび」が得られるのか?
まず、自信がつきます。そして、結構楽しいです。
「知ってる知ってる。やってるやってる」
「そうそう、仰るとおり。分かってますよ」
実践(実行)済みだからこその振り返りは、
学んで身につけたことの再確認に加え、
「なるほど。そういうメリットもあるんだ」
「確かに確かに。納得、納得。次回作にその要素取り入れてみよう」
など、実践(実行)済みだからこその、
再認識・再発見もたくさんあります。
わたしは、こうした自信プラス気持ちに余裕ができることを、
過去の自分の頑張りのおかげ、
つまり過去の自分からの「ごほうび」だと思っています。
また、過去の自分へ向けて、
「がんばったね」「努力した甲斐があったね」
そんなふうに褒めてあげられる良い機会にもなります。
おそらく処女作1本書き上げたときに、
自分で自分を褒めているはずなので、
2度目なのか、3度目なのか、
まぁ、自分を褒めてあげることは、何度あってもいいので、
…… いずれにせよ「ごほうび」なのです。
確実に成長できた証でもあります。
この「ごほうび」は、
作品を何本か書き終えた(実践・実行し終えた)うえで、
復習した者のみが得られる「覚醒」です。
自信と余裕、モチベーションの維持、
そして次回作への動機にもつながります。
また副次的な効果として、読書の仕方にオプションが追加されます。
小説やエッセイをはじめ、評論やビジネス書などを読む際、
自分が習得している知識・テクニックを背景に、
正しい日本語&正しくなくてもOKな日本語をはじめ、あらゆる言語表現、
さまざまな表現技法、起承転結・序破急に基づく全体の構成 etc.
それらを確認しながら読むことができるようになります。
このオプション追加は、
もれなく3つの「おまけ」も付いてきます。
■おまけ①:書評っぽいモノが書ける
書かれてある文章や内容について、またその書籍について、
自分なりの「善し悪し」の判断が可能になります。
すると、細かい箇所を含めて、自分なりの意見を語れるようになります。
ただ、書評となると、なにがしかの「軸」が必要で、
その確固たる評論の「軸」を手に入れるためには、
これまた、なにがしかの勉強が必要な気がします。
それがどんな勉強なのか、わたしにはまだ分かりかねますので、
「書評っぽいモノが書ける」としか言えません。
でも、いち読書としての感想だったモノが、
書評っぽいモノに進化するのは、とてもいいことだと思います。
■おまけ②:ひとに教えられる
「善し悪し」の判断と、その理由が説明できるようになれば、
自信を持って、ひとに的確なアドバイスができるようになります。
わたしの場合、広告制作の現場にて、
後輩や部下を指導したこともありますが、とても苦手です。
メキメキ上達・成長したひともいました。
しかし、サボるひとへの指導方法が分からないため、
決して得意ではなく、むしろとても苦手です。
アドバイスの上手さに加えて、マネジメント力に自信のある方は、
教える側に立つこともいいのでは? と思います。
■おまけ③:その後の独学(勉強)に役立つ
何よりも、この「おまけ」が、
いちばん大きな「おまけ」です。
人の振り見て我が振り、直せる。
さらなる上達・成長のための独学(勉強)には、
この「おまけ」がとても役立ちます。
手にした書籍を、
これまでの読書の仕方で読むも良し、
習得したオプションの読み方で読むも良しですが、
オプションの読み方をした場合、
--------------------------------------------------------------------------------------
良いところは見習って、
悪いところは「自分はどうだろう」と確認し、
自分も ✖ だったら、改善する。
--------------------------------------------------------------------------------------
ということが、容易にできるようになります。
容易にできるは、さすがに言い過ぎかもしれませんが、
良いところを抵抗なく受け容れ、
確認できた自分の悪いところ、その改善に対しても、
前向きに捉えられるようになります。
この変化は、とても大きな収穫なので、
わたしが先ほど、いちばん大きな「おまけ」と表現したのも、
コレが理由です。
上達・成長のための独学(勉強)は、
小説を書き続けるひとにとって不可欠な学びで、半永久的に続きます。
(なのでわたしも、絶えず独学し続けています)
みなさんも、このいちばん大きな「おまけ」を手に入れて、
ズンズンガンガン作品を書いて、どんどんどんどこ独学しましょう!
…… はい。
以上で、[3]復習/ごほうび&おまけ は、おしまいです。
…… 次は、最後の [4]? についてです。
このクエスチョンマークの意味ですが、
もうすでにお気づきの方も当然いらっしゃるかと思います。
お気づきではない方のために「答え」を申し上げます。
[4]「#001 身の丈にあった文章でいい」からお読みください
わたしは「#017 予習から始めよう」の冒頭にて、
「この連載記事のイントロダクションをいまさらながら書くことにします」
と申し上げたうえで「#017 ~ 今回の #020」を書いてきました。
もうすでに気づいていらっしゃった方には「やっぱりね~」でしたね。
注意力もあって、洞察力も優れた方だと思います。
ちなみに、わたしは「#017 ~ #020」の全4回を書く前に、設計しました。
細かい内容については、書き進めていくなかで調整しましたし、
また予想外の文字量になったりもしましたが、
それらすべて、想定の範囲内で、おおむね「設計図どおり」です。
なので、小説執筆の際にも、
設計図としての役割も担ってくれる「プロット」は、
作っておいて損はなく、あったら便利だと思います。
全4回「#017 ~ 今回の #020」を読んでくださった方、
誠にありがとうございました。(わたしも少々疲れました 笑)
※次回「#021」からは、通常営業(従来の連載記事)に戻ります。
[告知]
とても売れているようなので、
この本を買いました。
~ 5月中に読後の感想を記事にします ~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
