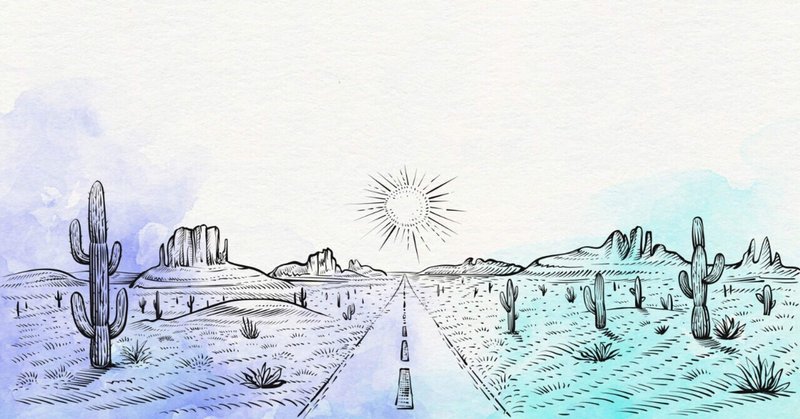
私を回復の一例として眺める
著書が重版となった。パニック症で困っている人は、こんなにもたくさんいたのだなあ。驚く一方で、そうよねわかるー的な合点やら共感やらもある。
表紙に本文中から抜粋したマンガ(イラストはホリグチイツさん)がデザインされていて、そこに登場するショートカットの人が「まーる」こと私である。本書では、マンガやイラストをふんだんに取り入れている。当事者が読むことをめいっぱい想定して書いたので、とにかく読みやすさに注力した。
で、「安全行動」について書いたセクションがある。そこにマンガもついている。

ここ、ちょっとこだわった。当初、このマンガもまた他ページと同じく私が主人公になる段取りだった。それをあえて「私でない人」に変えてもらって、私が「安全行動ってこんな感じだよ」と解説している体にした。わざわざ描き直してもらうほどでもないかと悩んだのだけど、結局ちょっとこだわらせてもらった。
なぜかって、まず私自身がほとんど安全行動をやっていなかったからだ。私の場合、早い段階で「安全行動をしてはいけない」ことを知ったので、その点は急性期からずっと気をつけていた。なので曝露療法なんかは、安全行動をしなくてもできる範囲の、ごく身近なところから進めていった。けっこう教科書どおりのスモールステップだったと思う。
認知行動療法って、やっぱり特異的ではある。その人がどういう状況かによって、細かいプロセスに揺らぎが出るものだと思う。でも私はその揺らぎを具体的に提示することはできない。なんてったって私は専門家じゃないし、私でない人のケースについてはとんと未経験だし。ただ、とりわけ安全行動をしているかどうか、薬物療法を併用しているかどうかは、かなりプロセスに影響してくるんじゃないかという気がしていた。だから少なくとも「私が安全行動をしていなかった」ことについては、とりあえず明確にしておこうと思ったのだ。
ついでにここで改めて、私が認知行動療法をやったときの、もろもろを書いておく。私は急性期から認知行動療法を始めた。薬物療法(抗不安薬の頓服も含む)はしていない。安全行動の習慣もまだなかった。急性期は仕事をしていなかった(回復期に短期バイトから始めて、維持期へかけて長期就業に移ったかたち)。子育てなどもなかった。ストレスの大元っぽかった母娘関係については、物理的距離を取る(隣県に引越し)ことでいい感じに決着。で、寛解までトータル2年弱。そんな感じ。
そんな私の個人的な印象として、もしも私が安全行動をやっていたら、または薬物療法を併用していたら、とくに曝露療法辺りでもうちょっと紆余曲折あったかもしれないなというのがある。紆余曲折というか、何か別の介入が必要だったりとか、介入のタイミングが変わってきたりとかしそうだよなーと。いや、すごくシンプルに、曝露のとき、頓服を飲むか飲まないかの葛藤がものすごく沸き起こりそうだなって。
私も実際、発作のとき「あーー手元に抗不安薬があったら!」と感じることは何度もあった。たぶん手元にあったら飲んでいたろうと思う。なかったから飲まなかっただけに過ぎない。安全行動だって、それが習慣化していたらどうしてもやりたくなっていただろう。そういう葛藤をどういうかたちでプロセスに組み込んでいけば認知行動療法が成り立つか。その辺がまさに専門知の範ちゅうだろうし、私には何とも言えない部分だし、当然著書にも記せないんだけど、少なくとも何かしらのアルファ部分だよなー、ニアリーイコールの部分だよなーというね。そのニュアンスを込めつつの、あのマンガのこだわりだったというわけだ。瑣末かもしれないけど。
プラスアルファの部分は、未経験なりにいろいろ想像できる。例えば、頓服や安全行動ありきでの外的曝露の効果は、それらをしないときと比べてどの程度か。外的曝露と内的曝露の進捗に差異が出ることによる曝露療法全体の効果はどうか。頓服や安全行動のあとに、また別の内省とそれに伴う認知再構成などが必要にならないか(「あー飲んじゃった」的な後悔への対処)、とかとか。
ちなみに本書では、これまた未経験なりに一応提案も書いてみた。「安全行動をしないで5分家から離れてみる」などの小さなハードルからスモールステップで曝露療法をしていくのはどうかとか、頓服を飲むこと自体は頭痛薬を飲むのとあまり変わらないのじゃないかとか。普段それほど広いわけでもない視野を、できるかぎりギュンと引っぱり広げて書いたつもりだ。まあ、それでもたかが知れてはいるので、もちろんぜんぜんこの限りではないのだけど。
監修の伊藤絵美先生の後書きにも、こうある。「曝露療法一つとっても(中略)中程度の課題から取り組む場合もありますし、もっと不安の高い課題に最初からチャレンジする場合もあります。」「パニック症の方々の回復の道のりはさまざまです。」本当にそうなのだろうと思う。私個人は、とかく認知行動療法って、どうにかこうにか自分を励ましつつ、なんとかかんとか進めていくもののような印象がある。それは単に私が独学だったからかもしれないが、まあ、そんなふうに転がりながらでも治ってしまったわけだから、これもまた不正解ではなかったのだろう。
回復はたぶんいろいろだ(その”いろいろ”の懐に付け込んだビジネスなんかもあるから気をつけないといけないが)。だからこそ回復した一例を本にまとめられたことはよかったのじゃないかと、今改めて感じている。我ながら。書かせてもらえたことに、大感謝。(おわり)
サポート、励みになります。
