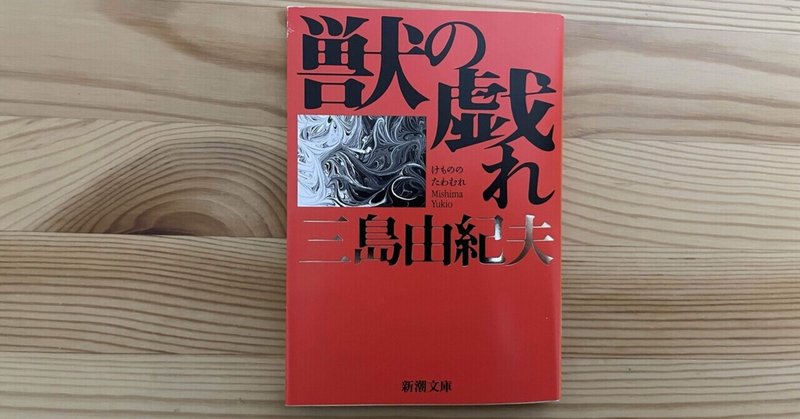
三島由紀夫がラディゲに対抗した小説「獣の戯れ」
本(獣の戯れ)
三島由紀夫の長編小説で、昭和36年6月から9月まで13回に渡って週刊新潮に連載され、その後単行本として出版されました。「文豪ナビ 三島由紀夫」ではこの小説を、フランスの小説家ラディゲに対抗した作品との解説があり、その影響を受けたとも書いてあります。
個人的にも大学生の頃、当時女子大生の間でラディゲブーム(多分)が起きており、私も読んでみましたが「ダイヤモンドのような硬質で華麗な文体」に衝撃を受けた記憶があります。
ラディゲの「ドルジェル伯の舞踏会」は、青年フランソワと伯爵夫人マオのとの関係を描いたものですが、「獣の戯れ」では青年幸二と逸平の妻である優子との関係が描かれています。
先述した「文豪ナビ 三島由紀夫」にも書いてあるように、三島は山よりも海を愛したと言われるように、物語の舞台は西伊豆の小さな魚村となります。物語の冒頭、村の寺にある2つの墓とその隣にある寿蔵が紹介されますが、この描写が物語の結末を端的に物語っているといっても過言ではありません。さらに幸二の刑務所での生活も描写されており、この事実も徐々に解明されていきます。
東京銀座の陶器商だった逸平の店に、大学の後輩である幸二がアルバイトに来たことから、逸平とその妻優子との付き合いが始まります。逸平夫婦が西伊豆に移り住んだのは、ある重大な事件が原因であり、文中に何度も出てくる幸二の「悔悟」という言葉に集約されています。さらに比喩を多用した文章は、思わす比喩マニアの村上春樹を思い出してしまいました。
西伊豆での3人の共同生活は、愛情や嫉妬、羨望や妬みなど、あらゆる感情が複雑に交錯するものであり、心理小説の「ドルジェル伯の舞踏会」をも凌ぐ展開になっています。3人の関係では身体が半ば不自由になった逸平が、幸二と優子の中間に位置し、この立ち位置が両者に微妙に影響を与えています。
この作品は心理小説なので、明快なストーリー展開はここでは書けませんが、読み終わった後に各個人がそれぞれに感想を抱くものだと思います。複雑な3人の心理描写を読みながら、冒頭の2つの墓と1つの寿像は、作者が意図する猟奇的とも言える結末に向かうことになり、まさに20歳で夭折した天才作家ラディゲの才能に対抗心も露わな作品になったのではと感じました。もっともラディゲの作品の内容は、もはやほとんど記憶にありませんが。
最後にあくまでも個人的な感想ですが、「仮面の告白」以来、三島はゲイであるとの先入観からの定説がありましたが、この作品を読む限りでは、女性も愛せるバイ(セクシュアル)ではなかったかと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
