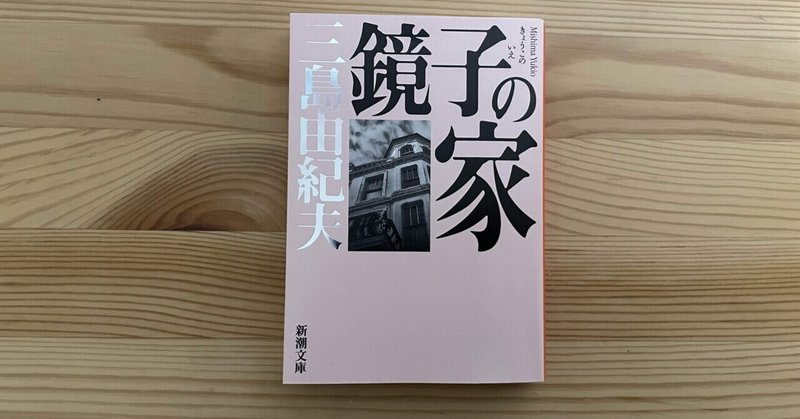
三島由紀夫が描いたスノビズムとデカダンスの長編「鏡子の家」
本(鏡子の家)(長文失礼します)
三島由紀夫の長編小説です。文庫本で620ページ程もあるので、なかなか読み進まず読了まで1カ月近くかかってしまいました。資産家の令嬢である鏡子の家に集まる4人の男性の変貌を描いたもので、物語は1954年から56年までの2年間がその舞台となります。
この作品の書評を読む限りでは、作品としては成功作といえず三島自身もそのことを気にしていたとのことですが、確かに私も読んでいる途中で今後どのように物語が展開するのか、中だるみに近い状態になり、読む速度が遅くなったことも事実です。
主人公の鏡子を中心に、その知り合いである4人の男性の詳細が徐々に明らかになっていきますが、各章ごとにそれぞれの人物を描き、それが交互に登場する形式を取っています。
エリートサラリーマンの清一郎、画家の夏雄、俳優の収、ボクサーの峻吉とそれぞれのキャラも様々です。
資産家の令嬢であり、生まれ育った環境もそうしたハイソな鏡子ですが、そうした上流社会の常識や規律に束縛されない自由奔放な女性として描かれており、それは性についても奔放な感情を持ち合わせています。この物語の核というのがこの鏡子の生き方であり、価値観でもあります。以下のような鏡子の言葉があります。
「私は、決して買うことのできない娼婦、という道を選んだのだから。それが私の生き甲斐なのだから。」
当然その家に集まってくる4人の男性もその奔放な生き方に共感した者たちであり、他人を束縛しない開放的な人間関係を前提にしています。
それはスノビズム(俗物ではなく耽美主義を含意するもの)がベースにありながら、デカダンスが漂う空間でもあります。さらにソフィスティケーションという言葉も、肝要な要素として加味されると思います。
そこまで行くと、思わずフィッツジェラルドの「華麗なるギャツビー」を連想してしまいますが、生活感のない金持ちの鏡子も、物語の後半はさすがに金策として会員制のパーティーを自宅で開くようになります。
父親亡き後は、その豪奢な邸宅で夫を追い出した後、娘の真砂子と2人暮らしの生活を送っていましたが、遂にその奔放な生活にも終止符を打つ日がやってきます。同時に4人の男性もそれぞれの結果が出つつあるようになります。
解説にもありましたが、成功作ではなかった本作は、三島作品を理解する上で重要な意味合いを持つ小説と位置付けられています。戦後の復興期を背景に、三島自身の青春も回顧しながら挑んだ実験作であり、意欲作の長編小説ではなかったかと思います。
今回も流麗な文体には、いくつもの印象的な言葉がありました。
蟠踞(ばんきょ):根を張って動かないこと
瞋恚(しんい):怒ること
恬淡(てんたん):欲がなく物事に執着しないこと
狷介(けんかい):頑固で自分の信じるところを固く守り、他人に心を開こうとしないこと
憐憫(れんびん):哀れに思い同情すること。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
