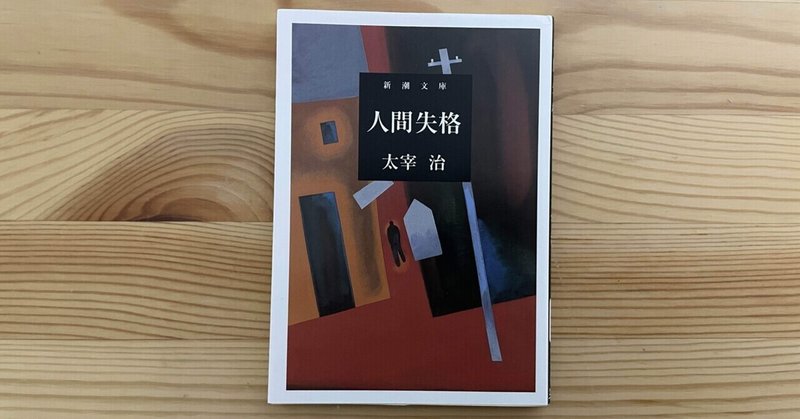
時代を超えて読み継がれる太宰治の自伝的小説「人間失格」
本(人間失格)
太宰治の自伝的小説と言われ、太宰の代表作とも評される作品です。ある資料によれば新潮文庫の歴代ベストセラーを夏目漱石の「こころ」と競っているとのことですが、それほどまでに近代日本文学では多くの読者に読み継がれている名作です。
正直私は太宰の愛読者ではなく、本書を読むきっかけになったのは、三島由紀夫の同様な自伝的小説である「仮面の告白」との対比で「人間失格」が登場したことであり、いわば三島を経て読むようになった訳です。
青森で父が国会議員も務めた富豪の六男として生まれた主人公は、弘前高校から東京大学へと進学します。ただ本人が語るように平穏な学生生活などではなく、最初の心中未遂を21歳の時に起こし、相手の女性だけが死亡して本人は生き残ってしまいます。さらに後半は薬の過剰摂取による精神の異常により、専門病院へと入院させられてしまいます。
太宰自身は玉川上水での入水により、女性と心中して生涯を終えます。こうした人格形成には、最後の解説にもありましたが、青森の富豪が生家ながらも嫡男ではない六男という出自が影響していると書いてありました。東北の田舎ゆえの封建的な嫡男重視の風習が、その原因であるということです。
赤裸々に描かれる情景は、人間が持つ精神の弱さを抉り出すものであり、まさに文学は人生のカタルシス(浄化)であると言われる所以です。破滅型ではなく自己否定(人間失格)を事実として認識し、そのありのままの心情と身体を受け入れることで、自己の存在というものを再度確認する。
太宰が世代を超えて読み継がれる背景には、こうした自己の存在の潜在的な肯定観に対する読者の共感があると推測します。それは漱石が人間の持つエゴイズムなど倫理観に基づく作品を発表することで、その価値観を再認識して、その大切さを自覚することが読者の共感を得ていることと同様なものだと考えます。
太宰の自伝的小説とも言えるこの作品で、その生涯を共有することにより、作家の人生観を理解すると共に、読者自身の人生観ともオーバーラップさせることが可能ではないかと考えました。
一時期は結婚し職業作家として、いくつもの秀作を発表した太宰でしたが、晩年は自己の弱さなり本性に向き合った時期ではなかったかと感じます。
作家それぞれの価値観や人生観は、概ね常識とは異次元に存在するものであり、それがまた作家の評価になるのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
