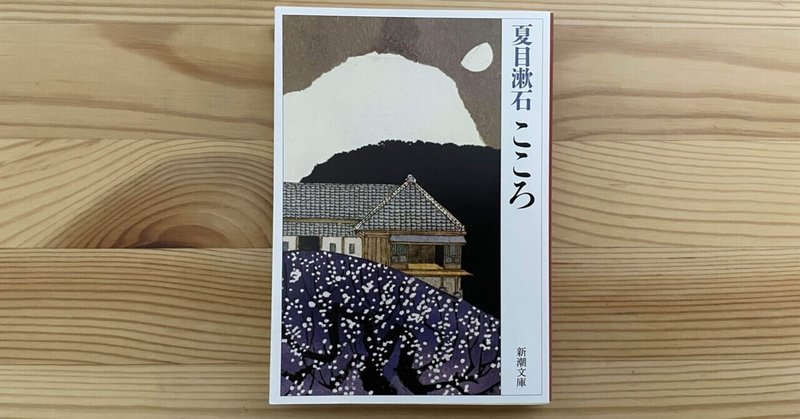
恋愛とエゴイズムの葛藤を描いた文豪夏目漱石の名作「こころ」
本(こころ)
文豪夏目漱石の長編小説です。有名な小説であり、私も学生の頃、日本文学の教科書的意味合いで読んだと思いますが、恋愛とエゴイズムの葛藤といった漠然とした記憶しかありません。
今回再読しようと思ったのは、読書グループでの三島由紀夫の「仮面の告白」の感想文を読み、同様の自伝的作品に挙げられていたのが、太宰治の「人間失格」とこの本でした。「こころ」は正確には自伝的というよりは自己投入型の作品であると言えます。
学生の頃、美学や芸術学に傾倒していた自分は、文学も唯美主義・耽美主義などの作品を好んで読み、かなり偏った読書傾向であったと思います。
オスカー・ワイルドやレーモン・ラディゲ、日本でも永井荷風や谷崎潤一郎などの作品を愛読していましたが、中でも当時女子大生の間でブームになっていたラディゲの作品には衝撃を受けました。三島由紀夫も影響を受け、「ラディゲの死」という小説を発表しているぐらいですから。
そうした個人的な読書傾向を背景でこの小説を読んでいくと、その対比として先ず文体から当時の知識人の倫理観を伺い知ることができますし、それは恋愛に対しても同様であり、恋愛を崇高な対象として捉えています。それは恋愛の対象となる女性に対しても、崇高であるべきという潜在的ともいえる願望をベースにしたものでもあります。
ややもするとそれらを理想化しすぎて、現実とギャップが生じてしまい、その感情と理性の狭間で苦悩する状況も生じてきます。当時の知識人はかろうじて理性による自らの欲望を抑制する選択をせざるを得なかったのでしょうか。
それでもそうした理性でも抑えきれなかったのが、主人公の「先生」であり、読んでいる私の率直な感想でも、「それはないよな~」という甚だモラルに劣るものだったと思います。
要は理性で感情をコントロールする、つまりは理詰めで考えることの限界があったのであり、感情が理性とは別の次元にあることを理解しようとはしなかったのではと思います。
私がかつて読んだラディゲの「ドルジェル伯の舞踏会」は、フランス文学特有の心理小説の傑作であり、ある意味この小説とは対極に位置するのかもしれません。
漱石の詳しい解説や分析は多くの研究者に任せるとして、文学にも様々な主義や主張がありますが、漱石が描きたかったのは、恋愛に限らず明治時期の知識人のモラル(理性)と感情(本能)との葛藤であり、苦悩であったと思います。それらを抉り出すことで、その文学を確立していき、文豪として後世に名を残したと考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
