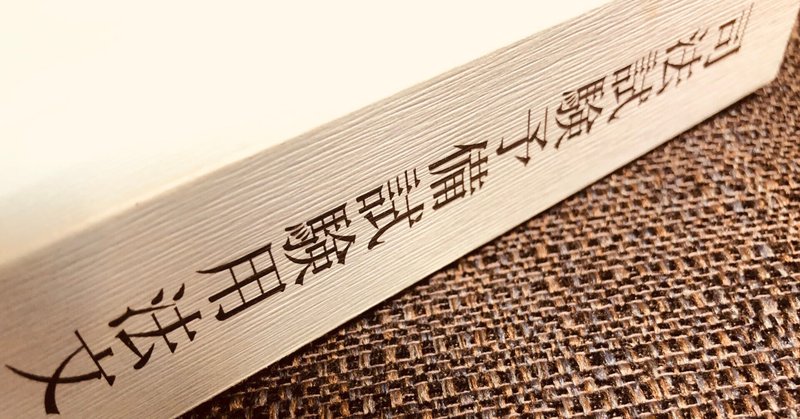
刑事事実認定問題に強くなる(素材:R4刑実・設問1小問⑴)
1 刑事事実認定問題を得点源に!
刑事事実認定は法律知識が少ない状態でも戦える分野です。そのため、特に、勉強期間が短い方や勉強時間の短い社会人には得意になっていただきたいです。もっとも、刑実の事実認定問題では、事実をできるだけ拾うことが大事といわれますが、そのためには、事実を拾うための着眼点を予め押さえている必要がありますし、また、たくさんの事実・情報を整理して答案にまとめられるようになることが大切です。そこで、今回は、刑事事実認定問題が得点源になるよう、令和4年の刑実の設問1小問⑴を素材として、事実認定問題の解答プロセスを確認していきたいと思います。
2 設問の分析
本問で、解答を求められているのは「B供述のうち本件被告事件に関与したのはAであるとする供述部分の信用性が認められると判断した検察官の思考過程」です。
そのため、B供述は証拠⑩と⑰ですが、そのうちの「本件被告事件に関与したのはAであるとする供述部分」が信用性の検討対象になります。(なお、証拠⑩と⑰を除いた、証拠①から⑨及び証拠⑪から⑯に記載された内容については信用性が認められることが前提とされているため、後述のとおり、これらの証拠から認定できる事実は、必要に応じて、B供述の信用性を支える補助事実として用いられることになります。)
3 共犯者供述の信用性を判断する際の観点
供述の信用性の確認は、一般的に、
①供述が他の証拠・事実と整合しているか、
②供述者が「事件・被疑者・被害者等」と利害関係を有するか、有するとしたらどの程度か、
③供述態度は真摯か、供述内容に変遷はないか、
④供述内容は詳細で具体的か、
などといった観点から行います。この中では、やはり①が重要で、①を中心に据えて、②から④は補強素材として検討するのが良いです。①がダメダメなのに、②から④だけで供述の信用性を肯定するのは危険すぎます。というのは、②は、例えば利害関係がない者でも必ず事実を語るとは限らないですし、③は、変遷があったとしても最終的に語ったところが事実の場合も普通にあり得ますし、いやいや供述しても事実を語っている場合もあり得ますからね。また、④については詳細かつ具体的で迫真性のある虚偽の供述をする者もいます。これらに対し、①は、当該供述とそれとは別の証拠や事実と照合した結果であるため、合致・整合する部分があれば、その信用性を積極的に肯定しやすいということになります。
また、本問では、A(が本件犯行に関与しているとしたら)から見てBは共犯者であるところ、一般論として、Bが本件とは無関係であるAを黒幕として引き込んでいる危険性もあるため、引き込みの危険性の有無も考慮しつつ、B供述の信用性を検討することになります。
なお、これらの観点については、事前に知っていることが求められるので、問題文の事実を見ながら思い出せる程度に記憶しましょう。
4 「B供述に信用性がある」といえるためには何が必要か?
では、戦うための武器の仕込みはこれくらいして、本題に入っていきましょう。
B供述のメインは証拠⑩です。証拠⑩では、本件犯行に関する一連の流れが一つのストーリーとして語られています。そして、その中には、Aの言動も含まれています。
でも、証拠⑩で語られているストーリーの全部が嘘かもしれませんし、全部が嘘でないとしてもAの言動に関する部分については嘘かもしれません。もしかしたら、Bは、Aではない別の人物Cと協力して本件犯行を実行していたかもしれません。Aが、BとCにはめられているかもしれないです。
Bは、Aと侵入強盗の計画を立てて、犯行時はAに車に乗せてもらった…等と供述していますが、裁判ではもとより検察の起訴段階でも冤罪につながる人違いは絶対に許されません。そのため、B供述から、本件犯行に関与したのは「Aである」ことが認められる必要があり、「Aである可能性もあるがAではない可能性もある」ということでは足りないことになります。
そして、本問で、検察官は、「B供述のうち本件被告事件に関与したのはAであるとする供述部分の信用性が認められる」と判断していますが、その判断のためには、まず、「他でもないAが関与したこと」につきB供述以外の他の証拠・事実による裏付けがあることが必要になります。
5 B供述と他の証拠・客観的事実との整合性の検討の方針
供述は、ストーリーであり、いわば線であるところ、線全部の裏付けをとることはおよそできません。でも、供述に含まれる複数の重要なポイントで客観的事実との整合性・一致が確認できれば、嘘を言っているわけではないだろうという経験則が働き、供述全体の信用性が認められる方向に進みます。
ただし、その整合性は、Aの関与に関して意味のある部分・重要な部分で認められる必要があります。本問では、Aの関与に関するB供述の信用性の有無が問題となっていますから、Aの関与に直接関係しないB供述部分について客観的事実との整合性が認められたとしても、Aの関与に関するB供述部分までも信用性を肯定できるということにはなりません。たとえば、Bは、犯行時の自己の着衣を供述しており、その裏付けは防犯カメラなどからとることができていますから、Bは、この部分についてはきちんと事実を供述していたことになります。でも、だからといって、それを理由に、Aが車で現場に同行した等と語るBの供述部分まで信用できると判断するのは飛躍があるでしょう。他にも、Bはキャッシュカードが利用停止になっていたことを供述しており、このことは、証拠①のVの供述内容や証拠⑥から裏付けられますが、この供述が信用できることとAの関与に関するB供述が信用できるかどうかの問題は区別する必要があります。
そのため、本問の信用性の判断では、B供述のうちAの関与に関する事実関係を押さえて、それを支える証拠・客観的事実がないかを探ることになります。
6 証拠⑩(と⑰)以外で「Aの関与」を認定できる証拠はどれか?
そこで、ここでは、「Aの関与を認定できる証拠(群)」を洗い出します。他方、「AかもしれないけどAじゃないかもしれない人物の関与を認定できる証拠(群)」にとどまるものは、Aの関与に関するB供述部分の積極的な裏付けには使えないので外す方針で行きます。
「Aの関与を認定できる証拠(群)」を探す際は、まず、一見してAに関する情報が書かれているかどうかに着目するのが良いです。そのような観点からは、証拠⑪、⑫、⑬、⑯がこれに当たります。また、証拠⑭は、証拠⑫で発見されたナイフに付着していたBの指紋の話なので証拠⑫とセットにすると良いです。
では、証拠④、⑦、⑮はどうでしょうか。これらの証拠からは、本件の犯行関与者が男2人であることが認定できます。そして、証拠⑤、⑧、⑨からは、証拠④及び⑦で茶色の作業着を着ている男(証拠⑦では「乙」)がBであることが認定できます。ただ、もう一人の男(証拠⑦では「甲」)がAであることまでは、証拠④、⑦、⑮と⑤、⑧、⑨を組み合わせても認定できません。甲はAと背格好の似たCかもしれず、「AかもしれないけどAじゃないかもしれない人物の関与」しか認定できません。つまり、証拠④、⑦、⑮と⑤、⑧、⑨は、「Aの関与」に関するB供述の信用性を支えるものではなく、むしろ、そのようなB供述の信用性が認められた場合において、そのことを前提に、「ああ、そうすると、Bといた甲はやっぱりAなんだ!」と確認するためのものになるといえます。
7 B供述と他の証拠・客観的事実との整合性の具体的検討
では、B供述が、証拠⑪、⑫、⑬、⑭、⑯及びこれらの証拠から認定できる客観的事実と整合するかを見ていきましょう。ここでは、B供述のどの部分が他の証拠・客観的事実とどのように整合するかを意識しながら検討を進めましょう。
⑴ キャッシュカード
証拠⑩で、Bは、Vから奪ったキャッシュカード1枚をAに渡した旨供述しています(以下「供述㋐」)。他方、V名義のキャッシュカード1枚は被害品です(証拠①)が、これがAの部屋から発見されたという事実が証拠⑫から認められます。そうすると、「BがAにカードを渡した→カードがAの部屋にある」という自然な因果の流れがあるので、供述㋐は、他の証拠・客観的事実と整合性があるといえそうです。
⑵ ナイフ
また、証拠⑩で、Bは、犯行で使用したナイフは、Aから渡されたA父の物であり、犯行後にAに返した旨供述しています(以下「供述㋑」)。他方、証拠⑬からA父はBに最近会ったこともなく自己所有のナイフを貸したこともないことが、また、証拠⑫・⑬・⑭からAの部屋からBの指紋の付着したA父のナイフが発見されたことが、それぞれ認められるところ、これらの事実は、Bが当該ナイフをAから渡されてこれに触れた後にAに返却した結果であるといえるため、供述㋑も、他の証拠・客観的事実と整合するといえそうです。
⑶ 現金300万円
さらに、証拠⑩で、Bは、Vから奪った現金500万円のうちAの取り分は300万円であった旨供述しています(以下「供述㋒」)。他方、証拠⑯からAは犯行前日の3月9日時点で総額325万円の債務を負っていたのに3月10日午前9時半頃に総額300万円の返済をしていることが認められるところ、この事実は、Aがこの短時間に現金300万円を取得した結果といえるため、供述㋒も、他の証拠・客観的事実と整合するといえそうです。
このように、供述㋐から㋒の部分の信用性が認められるとすると、Aが本件犯行に関与していることに関するB供述は全体として信用できそうだということになってきます。
なお、証拠⑪及びそこから認定できる事実(AとBが頻繁に電話連絡を取り合っていたり、3月1日午後8時32分から14分間、A発信で通話があったこと等)は、Aの関与を示す事実ですが、日常的にあり得る通話履歴であり、通話の日時や時間帯がBの供述と一致していたとしても、本件犯行とは別の話題で通話している可能性が相当程度あります。そのため、この点における整合性があるとしても、上記と比較すると、Aの関与に関するB供述の信用性との関連度合いが弱いです。逆に、例えば、Bが犯行中にVの面前で何者かと犯行の進め方について相談の電話をしており(これにつきVの供述があるとして)、その通話の相手番号がAの携帯番号だったということであれば、Aの関与に関するB供述の信用性を支える事実・証拠として絶対に指摘したいところです。
8 B供述に反する事実が成立する可能性に対するフォロー
ここまでの検討で、供述㋐、㋑、㋒はそれぞれ信用できそうだということは確認できましたが、若干、スキが感じられます。
たとえば、供述㋐で裏付けとなっているのは、キャッシュカードがAの部屋から発見されたという事実だけですから、「BがAに」渡したかどうかの裏付けは取れていません。そのため、Bが真の共犯者Cにカードを渡して、Cがこれを落として、Aが拾ったかもしれないですし、CからAが強取品と知らずに買い取ったかもしれません。つまり、「AがBからカードを受け取っていない」という、供述㋐に反する事実が成り立つ余地・可能性があります。
このように、供述㋐から㋒は、他の証拠等からの裏付けがあり、整合性ありといえるでしょうが、裏付けられている部分が限定的であるため、整合性一本では、信用性を直ちに肯定してよいものか悩ましいところがあります。
そこで、以下では、供述㋐から㋒のそれぞれについて、各供述に反する事実の成立可能性を踏まえながら、各供述の内容自体が合理性があるか、といった観点からの検討も加えることにします。
⑴ 供述㋐
A方の捜索開始時刻が3月10日午後3時という犯行時刻から約26時間後ですから、その間にAが当該カードを拾得したりB以外の第三者から取得した可能性も想定できますね。でも、強取品である当該カードが不用意に扱われたり流通過程に置かれる現実的可能性は低いといえます。そのため、供述㋐の内容は合理的なので、やはり信用できると考えられます。
⑵ 供述㋑
当該ナイフは、V側の痕跡が付着したものではなく、また、Bの指紋も犯行時とは別の機会に付着したものだとすると、犯行で使用されたナイフでない可能性も想定できます。本問のナイフには、被害者側の痕跡が付いていないため、凶器であることを直ちに認定できないという特殊性があります。凶器じゃないナイフをAが保管していても、そのことはAの犯行関与を何ら示すものではないことになります。
でも、Bが当該ナイフに触れることができたのは3月8日からA方捜索開始時刻までの約2日間に限定されています(証拠⑬)。そして、その約2日間に犯行時刻が含まれており、かつ、B方及びB使用車両からはBが犯行で使用した衣服その他の物件及び取得した現金が発見された(証拠⑨)のに凶器のナイフ(証拠①)が発見されていないということですから、当該ナイフが犯行で使用された凶器であると合理的に認定できます。したがって、供述㋑は信用できるという結論で良いでしょう。
⑶ 供述㋒
一般論として、Aは、本件と無関係に返済資金を準備した可能性も想定できますね。でも、従前、Aは、300万円を超えるまで消費者金融への借金の返済ができておらず負債が膨れ上がっていたのですから、ここにきて急にそのような大金を準備できる現実的可能性は低いので、供述㋒の内容には合理性があります。
あと、Bが供述するAの取り分の金額とAが返済した金額が一致していることも供述㋒の信用性を高めます。そうすると、供述㋒は信用できるということになります。
9 その他の観点からの検討(まとめ)
以上から、改めて、供述㋐から㋒が信用できることが確認されました。
最後に、ここまでで検討しなかった観点からの検討も加えて結論をまとめす。
引き込みの危険性についてみると、実行犯であるBには、本件と無関係の者を背後者・指示者として引き込んでいる危険性が一応あります。でも、供述㋐から㋒が客観的事実に裏付けられているため、無関係であるAが引き込まれている危険性は低いといえます。
また、供述内容・態様等についてみると、Bは取調べ当初から素直にAの関与を含む本件犯行の全容を詳細かつ具体的に供述しており、内容に変遷もありませんね(証拠⑩、⑰)。
そうすると、結論として、B供述のうちAの関与に関する部分は全体として信用性が認められるということになると考えられます。
10 答案例
非常に長い記事にもかかわらず最後まで読んでいただきありがとうございました。以上は、検討・解答プロセスの一例にすぎませんが、これを答案例にまとめましたので、参考にしていただければと思います。お疲れ様でした。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
