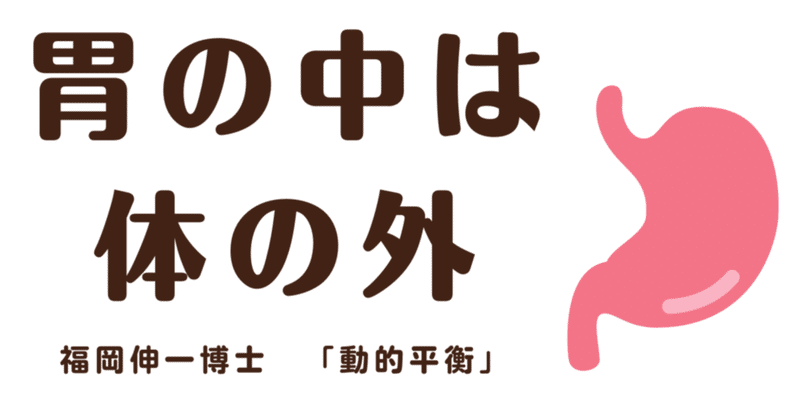
胃の中は体の外〜福岡伸一博士の「動的平衡」
福岡博士の本,「動的平衡」が面白いので,メモをしておきたいと思います。
胃の中は体の外

人間の体は,ちくわと同じく一本の管のようなもの。
食べたものが体内に入ると言っていいのは,口から食べた時ではなく,消化管から血液中に取り込まれた時。
胃でも腸でも、その表面はまだ体の外だ。
これは実に腑に落ちる話。
「胃の中は身体の外」だと福岡伸一先生が言ってるぞー。確かにそのとおりだ。
— Lyustyle@(りゅ〜)毎日投稿1400日10年ブロガー (@Lyustyle) May 11, 2023
「動的平衡〜生命はなぜそこに宿るのか」から。
消化とは情報の衝突を回避するもの

タンパク質をそのまま取り込むと,そこにある「誰のタンパク質であったか」という情報と私のたんぱく質に書き込まれた情報とが衝突し,トラブルを起こす。
だから、低分子レベルまで解体すれば、元は誰のタンパク質であったかという情報は消える。
そうやって,取り込んだ後,たんぱく質に再構成することで,「自分のタンパク質」となる。
消化とは,体に吸収されやすくするために分解するのだと思っていたが,もう一段落上の理由があった。
それがとても面白かった。
消化管に入ったタンパク質は、タンパク質という情報を無くすまで解体されてから吸収される。誰のタンパク質だったと言う情報を無くすことで情報同士で衝突することを避ける。それが消化。文章がアルファベットまで解体されるような物。その後再構築されることで、自分のタンパク質になる。😳おー😳
— Lyustyle@(りゅ〜)毎日投稿1400日10年ブロガー (@Lyustyle) May 11, 2023
自分の体をも食べる

タンパク質が入ってくると,たくさんの消化酵素が分泌されて,じゃぶじゃぶ振りかけられて,分解にかかる。
消化酵素自体も自分のタンパク質から合成されているので,食べたタンパク質の分解が終わったら,自分自身を分解する。
そして改めてたんぱく質に再構成される。
これで,そのタンパク質は,元自分の体内にあったたんぱく質なのか,外から入ってきたたんぱく質なのかわからなくなる。
この話はとても面白い。確かに自分自身を食べるのだ,ということだなと思う。
生き物のこのような精巧な働きは,まだ私たちが単なる筒のような生物であった時代から億の単位の時間を経て身につけてきたのだと思うと,とても興味深い。
追記中です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
