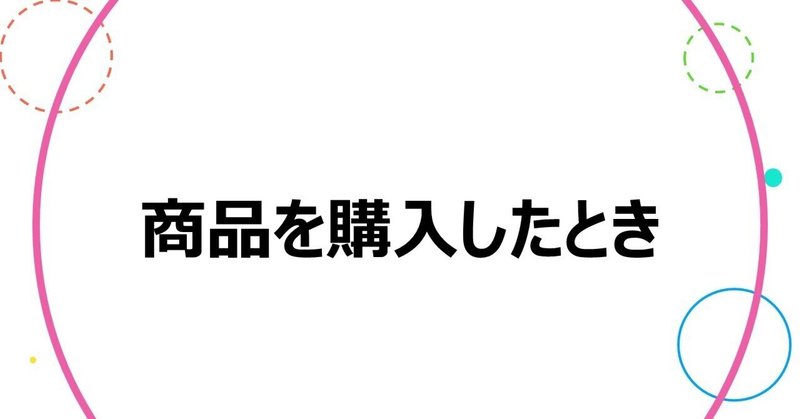
【簿記3級】商品を買ったとき
商品を購入したときの仕訳について説明します。
「商品」の定義
あまりにも馴染みのある「商品」という言葉。
普段何気なく使っていると思いますが、言葉の定義を再確認しておきましょう。

「車両を購入した」「パソコンを購入した」という取引を見て、「使うために買ったに違いない!」と先入観で判断してはいけません。
自動車販売店を営む会社にとっての車、パソコン販売店を営む会社にとってのパソコンは、販売目的で買った「商品」かもしれませんよね。
商品を購入した取引の共通点
商品を取得するためにかかった金額=費用の発生額として考えます。
費用カテゴリーに属する「仕入」という勘定科目を用いて仕訳しますので、商品を購入したら借方に「仕入」と記入することは確定です。

<費用>
サービスや物品を提供してもらったことで発生した支払うべき対価。決済が完了していなくても、対価が発生した時点で費用として計上する。
貸方科目は決済方法によって変わりますので、決済方法別に確認していきましょう。
決済方法ごとに異なる会計処理
①現金決済
現金という資産が減少するため、貸方には現金が入ります。

これで取引は完結しますので一番かんたんです。
②掛け
(購入者側から見た)掛け=商品代金をあとで支払うという意味ですが、「未払金」勘定と間違えないように注意しましょう。

商品代金の未払額を意味する「買掛金」勘定で処理します。

あとで決済するということは、まだ取引は完結していません。
商品を仕入れたあと、代金の決済を行った日に以下の仕訳を行うことで一連の取引が完結します。

いやいや、買掛金の管理大変だし、取引先ごとに直接振り込むのもめんどうだし…という場合、「でんさいネット」を活用して業務の負担を減らすこともできます。
取引先の承諾を得た上で、取引銀行を通じて発生記録を行ったら、「買掛金」勘定から「電子記録債務」勘定に修正します。

そして、引落日には次の仕訳を行うことで一連の取引が完結します。

以上、掛け取引でした。
③小切手
「支払うために現金持ち歩くの怖いわぁ」
「お金引き出したり、振り込んだりするのめんどうだわぁ」
という会社に最適な小切手。
「私の当座預金口座から○○円引き出していいよ~」という許可証のようなものです。
当座預金口座を開設したら、銀行から小切手帳を交付してもらいます。
小切手帳をぺらりとめくり、支払額など必要事項の記入・押印をして、ちぎって相手に渡すだけで支払いが完了できる魔法のツールです。
小切手を作成することを「振り出し」といい、
1.当社が振り出した小切手を相手に渡す
2.相手が銀行に持ち込んで呈示する
3.当社の当座預金口座からお金が引き出され決済される
というシステムになっています。
会計処理は「1.小切手を振り出して相手に渡した時点」、つまり支払った時点で当座預金が減少したという仕訳を行います。

「え?まだ当座預金なくなってないのに、嘘ついてええの?」
と初めて勉強した時に先生に尋ねた記憶があります。

支払と決済にズレがある小切手取引ですが、小切手を受け取った相手は原則10日以内に銀行に持ち込まなければならず、支払から決済まで短期間で完結します。
そのため、
支払時:当座預金を減少させる仕訳を行う
決済時:何も会計処理しない
という会計処理にした方が「どうせ短期間だし、支払時と決済時の2段階で処理しなくても問題ないじゃん?」「この方が楽ちんじゃん!」ということで決済に先立って仕訳を行うのがポイントです。
以上、小切手は振り出して支払うだけで取引は完結します。
④約束手形
最後は手形です。
小切手と同じ紙切れを想像してしまうため混在しがちですが、小切手よりも「掛け」に近い取引です。
買掛金は「あとで払ってくれるはず…!」と相手から信じてもらい、後日直接相手に対して決済を行います。
仲介人がおらず直接的な取引のため、支払期日まで1ヵ月~2ヵ月程度の比較的短期間になります。
そこで、もう少し長めの支払期日を設定したい場合、自社と相手の間に金融機関が入り、約束手形というものを作成することで、支払期日を3ヵ月~6ヵ月程度にすることができます。
掛けと同じように、支払時から決済時までに長いタイムラグがあるため、支払時と決済時の両方で仕訳をしなければなりません。
まず約束手形を振り出した時点、つまり支払時には支払手形という「あとで払うね~」という勘定科目を置いておきます。
※約束手形も小切手同様に作成することを「振り出し」といいます。

そして支払期日を迎えて決済が完了したら次の仕訳を行います。

約束手形も掛け同様に、でんさいネットに発生記録を行うことも可能ですが試験では見かけませんね…。
以上、決済方法別の仕訳処理でした。
返品をした場合
購入した商品について、不良品や品違いを理由に返品した場合には、仕入勘定をキャンセルします。
返金方法が現金なのか?掛けと相殺なのか?必ず指示がありますので問題文に従ってください。

問題を解く際のポイント
ポイント①商品かどうかの判別
問題文に「商品」というワードが明記されていれば、すぐに「仕入」という科目を仕訳することができると思います。
しかし、試験には「販売目的の○○を購入し、代金は後日支払うこととした」など、まるで使用目的の物品を購入したような表現の問題が出題されます。
「販売目的の○○=商品」と置き換えて問題を読めば動じないはず、です…!
ポイント②附随費用の処理
「仕入」という勘定科目は商品の取得にかかった金額を指しますので、送料などの附随費用が発生した場合、仕入の金額に含めて処理します。
選択肢に「支払手数料」や「発送費」があっても惑わされないよう要注意です。

ポイント③時系列に注意
「掛けで仕入れていたが~」など過去の話を参考情報として与えられる問題もあります。
「~が」という逆説の言葉がある場合、そのあとに続く情報こそが今やるべき処理ですので引っかからないように注意してください。
以上、商品を購入したときの仕訳でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
