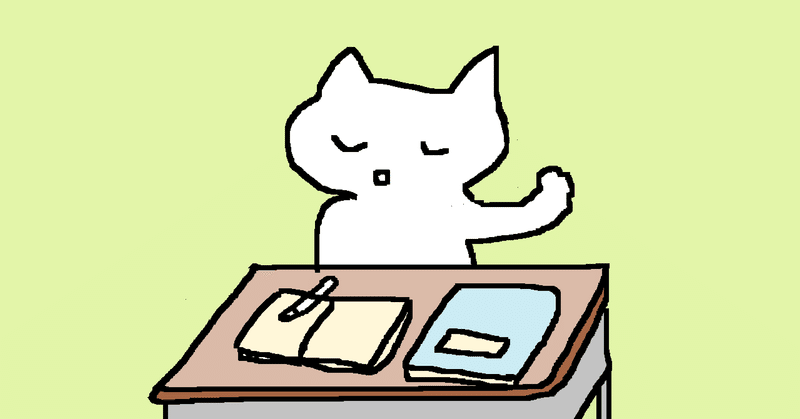
IQ120の人が最も社会的成功度が高く、生きやすい理由
最近言われる俗説として、「IQ120の人の社会的成功度が一番高い」というものがある。一見高ければ高いほど良いようにも見えるが、そうではないらしい。もちろんこの数値がどこまで正確かは分からない。本当は118かもしれないし、131かもしれない。ただ便宜上ここでは120くらいとしておこう。今回はこの説の理由について考えてみたいと思う。
IQが高すぎると話が噛み合わない?
なぜ120という値がベストなのか。それは「IQが20違うと話が噛み合わない」というこれまた俗説が根拠となっている。この値もまた30かもしれないし15かもしれないが、便宜上20ということにしておく。
IQ120の人は話が通じる範囲内の人がIQ100からIQ140と幅広い。世の中の上半分の人がほとんどコミュニケーション可能となるわけである。ある程度有能な仕事相手の大半と話が通じ、なおかつボリュームゾーンよりもIQが高いので優位に立てる。
これがIQ140となると途端に大変になる。話が通じる範囲がIQ120から160なので、社会の大半を占めるボリュームゾーンの人間と話が通じないことになる。処理能力は高いのかもしれないが、社会で成功するには周囲の同僚と絶えずコミュニケーションを取ったり、部下の気持ちを察してあげる度量が必要であることが多く、IQが140オーバーとなるとかえって不利だ。
IQ140の人間から見た光景はどのようなものなのか。想像するしかないが、友人の1人が興味深いことを言っていた。彼は東大を卒業したあとメーカーで工場勤務をしていた時期がある。地方時代は「現地社員は地元の高卒が多く、風俗の話とパチンコの話ばかりで全く気が合わなかった」とのことだ。きっとIQ140の人から見たボリュームゾーンの人は多分こんな感じなのだと思う。
IQと実務能力は無関係?
それでも高IQの人は優秀なのだから、どの環境でも活躍するに違いないという見方もある。ただ、この見方も正しいとは思えない。まずIQの高さは学業や実務との相関がそこまで高くない。足の早い人間がサッカーがうまいとは限らないのと同じだ。社会的な成功度はIQ以外にも家庭環境・人柄・体力・手先の器用さなど様々な要素が絡んでおり、IQが高くても優秀とはかぎらないのだ。
高IQの凡人は周りのレベルの低さに辟易しながらも、仕事やコミュニケーション能力が高いわけではない。能力を持て余し、周囲からは孤立しがちだ。高IQが活かせる場所を見つければ良いが、多くの人間は一般人に混ざって生活する。したがって生きづらさを抱える人が多い。
高IQの人ばかりの集団は不安定?
「それではIQ140の人はIQ140の人ばかりの環境に行けばいいじゃん」という見方もある。これは完全な間違いとは言えない。しかし、恐らく期待したほどには効用は改善されないだろう。MENSAはあまり空気のいい集団ではないという噂を聞いたことがある。私の友人の1人はギフテッドのたまり場と思われる学科にいたことがあるのだが、悪口や足の引っ張り合いばかりで、あまり快適とは言えなかったそうだ。IQが高すぎる人間同士は余計な探り合いが多く、うまく協調できないのではないかと思った。
能力値はある段階で頭打ちに?
IQは数ある人間の要素のほんの1つに過ぎない。したがって、ある段階で効用は頭打ちになるのかもしれない。例えば身長がそうだ。ある程度までは身体能力が強かったり、女性にモテたりするが、それもせいぜい180くらいまでであり、それ以上になるとメリットは頭打ちになる。むしろ腰痛や天井に頭をぶつける等のデメリットが出てくる。バスケ選手のような特殊な分野を除けば実用性も低い。
IQも似た性質があるのかもしれない。IQも120辺りまでは効用はどんどん伸びていくが、それ以上になると実用性が低くなる。IQをそれ以上伸ばすよりも、体力やコミュニケーション能力を伸ばした方が社会で役に立つだろう。
学歴で例えると
IQと学歴は異なる。相関はそこまで高くない。高学歴という要素には家庭環境や競争心など様々なものが含まれているので、IQはそこまで決定的ではないと思う。ただし、IQと性質は似ているところがある。
IQ120といえば丁度上位10%の辺りだ。同様に、どの環境でも大体学歴が上位10%辺りに位置するのが一番効用が高いように思う。周囲からは高学歴として一目置かれるし、能力も生かしやすいだろう。これより上になってくると、実務能力との相関が頭打ちになるし、周囲から浮いてしまうリスクの方が高くなる。
転職を繰り返している東大出身の友人がいるのだが、彼も似たようなことを言っていた。東大の肩書が生きるのはある程度の高学歴が多い職場に限られ、それより下がるとむしろマイナスになるとのことだ。日東駒専から大東亜帝国がボリュームゾーンの職場は東大とMARCHが似たような扱いになるし、誰とも話が合わなくて苦痛だという。むしろ周囲から余計な妬みを買う危険性の方が高くなる。それでいて、学歴に見合った実務能力を発揮するのは難しいので、イニシアチブを取れるわけではない。
そもそも上位1%に立つのは良いことなのか
そもそも論として、集団内で上位1%に立つことは良いことなのか、という疑問も湧いてくる。
例えばわかりやすく受験で考えよう。学校で成績が上位1%の生徒は確かに見晴らしが良いだろう。ただし、ここまで高いと学校のレベルが合っていないと考えた方がいい。それほどできるのだったらより上位の学校に行けたはずだ。田舎の場合は仕方がないが、都会の場合はこのような生徒は運悪く中学受験に失敗したケースだろう。
また、同レベルの生徒と切磋琢磨することは大切なので、学年順位が高すぎると学力を十分に伸ばせない可能性が高い。進学校で下位に入ってしまうと意欲を喪失して落ちこぼれるという話はしばしば聞くが、上位1%に入ってしまうと逆に刺激が少なく学力が伸びにくいだろう。都会の場合は塾が多いので心配無用だが、地方の場合は深刻な問題となっている。自分が上位10%に入れる進学校が一番QOLが高く、学力も伸びるのではないかと思われる。東大志望であれば最近伸びている日比谷や渋渋辺りだ。
同様の構図はあらゆる事物に言える。日本で上位10%の所得を得るのと、途上国で上位1%の暮らしを得るのとどちらが良いだろうか(水準は同等とする)。恐らく大半の人は前者の方が快適に感じるだろう。後者は治安が悪かったり、インフラが粗悪だったりして、イライラする可能性が高い。話が合う人も見つけにくいだろう。
年収は600万〜1000万辺りから効用が増えないと言われているが、これまた上位10%のラインだろう。これ以上になると負担が大きい割に見返りは小さい。むしろ転落による精神的ショックが大きくなる。恐らくこのラインを超えると社会的に身動きが取れなくなるはずだ。転職も起業もできず、窓際で会社の文句をたれ続ける名門企業の窓際族はこうした典型例である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
