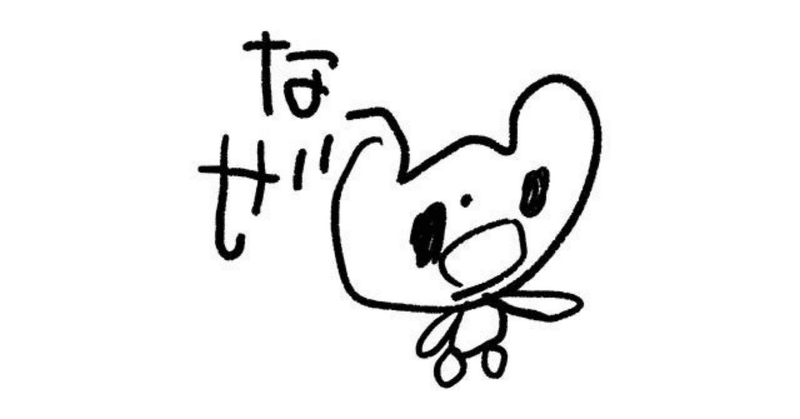
Photo by
soeji
理科の授業
昨日は大学へ。
先生の担当する子どもと保護者支援のお手伝いに。
「理科の授業して!」
と言われていたので、今回は豆電球の授業。
3年生の電気の単元を扱いました。
回路の間に金属を挟むと明かりがつくという実験をして、電気を通すものと通さないものを分ける学習。
紙、割り箸、コンビニでもらうスプーン、アルミホイル、スチール缶、10円玉を準備して、予想した後、確かめます。
金属はつくかもと導き出したところで、銀と金の折り紙が登場!
銀色の折り紙は電気がつく。
金色の折り紙は電気がつかない。
え?
となったところで、紙やすり。
金を剥がすと銀が出てきた!そしてついた!
という授業。
先生が、へーと1番驚いておられた😅
ふりかえりで、珍しく褒められた。
「さすがだね。発問のタイミングも板書もよかった!」
やった!!
でも
①周りの学生も巻き込んで意見交流する機会を作る
②しゃべりすぎ→わからないことはわからないと言わせることも大事
③ワークシートがあってもいい
子どもと1対1の授業なので、ついつい一問一答になることと、子どもが不安そうにしているとすぐに手を出すことが反省点。
日頃の授業で言われていることと同じです。
楽しかったのだけど、はて、次は何の授業をするか?考えなければなりません。
4年生の直列と並列つなぎをぼんやりと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
