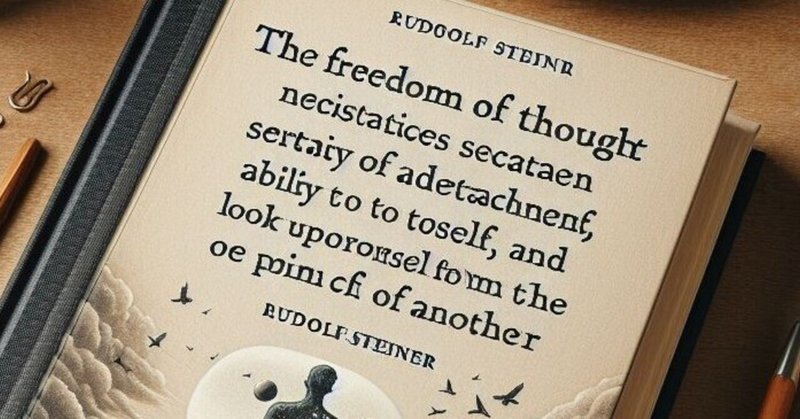
寝ながらシュタイナー『自由の哲学』(6/9)
Ⅳ 「人間意識の自己了解(理解)」と「思考の観察」
自由は、最高段階の動機(起動力と動因の重なり)による行為において認められます。
起動力の最高段階「概念的思考(実践理性)」に至るには「自己意識の拡充」が、動因の最高段階「純粋に直観把握された個々の倫理目標」に至るには「思考の強化・高貴化」が必要ではないかと見てきました。
本稿では、「自己意識の拡充」を、『自伝』の「人間意識の自己了解(理解)」との関連で、「思考の強化・高貴化」を『自由の哲学』第一部の「思考の観察」との関連で考察します。
1 人間意識の自己了解(理解) ― 自己意識の拡充
⑴ 人間意識の自己理解とは、ゲーテの外界認識を人間自身に向けるもの
ゲーテは、人間は通常の意識形態では外界の本性を認識することができないと考えていました。彼にとっては、外界認識とはその本性と合一することであり、それには別の意識形態へ移行する必要があると考えていたのです。
シュタイナーは、ゲーテの外界認識における体験を、人間が自己自身に対して向けることではじめて、この(霊的な)認識体験が完全なものになると考えていました。その際には、次のことが問題になるのです。
人間の意識が自己自身を理解するということがまず行われねばならない(2:155)
⑵ 人間意識の自己了解(理解)は、シラーには芸術体験として、シュタイナーには精神世界(霊界)の探究として
この人間意識の自己了解について、シラーは、次のように考えていました。
人間は中間的な意識の状態を自己の内に開発することができる。つまり、人間は、自然の強制にも理性の必然性にも一方的に服することのない、「美的情緒」を育てることができるのである。 この美的情緒を備えた魂は、…感覚的知覚や感性によって惹き起こされた行動の中にある精神的なものを持ち込む。…この場合、人は行動するに際して直接的欲求の満足に身を委ねはするが、彼はこの欲求そのものを、善を好み悪を嫌うべく、すでに浄化していると言える…。このとき、理性は感性との内的な結合を達成する。善は本能となる。そして、本能は、精神性を帯びているがゆえに、自らの力によって自分の進む方向を定めることができるのである(2:68)
シラーはこの中間的な意識の状態を開発することが、真の人間性を蘇生させる道だとしました。そして、それは人間が芸術を体験するときの意識の状態であるとしたのです。
それに対してシュタイナーは、そのような意識の状態においてこそ、事物の本性にある真理が開示されるとしたのです。
自由は素朴な意識においては自明なものとして存在しているのに、認識にとっては謎と化す。その理由は、人間にあっては、自己の真の存在、すなわち真の自己認識はあらかじめ与えられているのではなく、意識が自己を理解したときに初めて獲得されるものだからである。人間にとって最高の価値、すなわち自由は、それに相応しい準備を終えた後にはじめて理解されるのである。
私の『自由の哲学』は、人間の意識が自己自身を理解する体験をもとに構築されている。自由は意志において修練され、感情において体験され、思考において認識される。ただし、以上のことが達成されるためには、思考から生命が失われてはならない (2:180)
自然(事物)においては、知覚と概念ははじめから結びついていますが、私たちはこの二つのルートに分かれてもたらされたものを再び結びつけ、認識を成立させます。
ところが、人間における知覚と概念ははじめから結びついておらず、「自由な精神=倫理的人間」という人間概念をまずつくりだす必要があるのです。
この人間概念の成立に関わるのが、意識の中間状態をつくりだすことができるという自己認識、つまり自己意識を拡充することです。
そして、その拡充された意識状態としてあるのが、起動力の最高段階「概念的思考(実践理性)」だと筆者は考えています。
2 思考の観察 - 世界の根源としての〈本来の(生きた)思考〉と、そのおかげで命をもつ思考する存在・〈私〉
⑴ 自然(世界)は霊的なもの=〈本来の(生きた)思考〉である
『自由の哲学』第一部は、第二部の問い「人間は自由でありうるか」という問いに対する準備として読むことができます。その内容は、思考する存在・〈私〉の立ち上げです。
シュタイナーはまず自らの思考を観察することによって、世界の根源としての〈本来の思考〉を見出すよう読者を導きます。(〈本来の思考〉とは、直観的思考、感覚から自由な思考、生きた思考、などと同義です。)
シュタイナーは、〈本来の思考〉を精神界(霊界)の構成要素だとしますが、『自由の哲学』成立当時における次の言葉を見てください。
感覚的見方によって得られた自然の本性は霊的なものである…自然は実は霊的なもの(本来の思考—筆者註)であることを私は言いたかった(2:167)
⑵ 〈本来の思考〉は始原的、絶対的である
二つの精神的作業、「観察」と「思考」において、通常は観察が先で思考が後ですが、思考自体を観察しようとすると、事情は異なります。思考を観察することにおいて、私たちは、(創世記の、神が天地創造の後に静観したように)まず思考し、その後観察することになるのです。思考は私たちにとって観察よりも身近で根源的だと理解できます。
また、思考を観察する際に、私たちは同一の要素の内に留まります。思考には、それ自体で成立する絶対的な原理があり、私たちはこの原理から出発して、世界を認識するのです。
以上のことから、「思考の観察」によって、思考の(認識における)始原性(根源性)と絶対性(自立性)が(体験的に)理解できるでしょう。
⑶ 〈本来の思考〉は普遍性をもち、世界に広がっている
例えば、植物の概念・理念(思考内容)は、植物に属しており、その概念・理念は思考する存在・〈私〉が思考を通して関わることによって、現実化すると言えます。
世界(自然)は、そこに普遍的な思考(自然法則)が入り込んでいることによって成立しているのです。〈本来の思考〉は普遍性をもっているのです。
⑷ 世界の根源である〈本来の思考〉のおかげで、思考する存在・〈私〉は主観として命をもつ
そして、世界の根源(絶対的であり、時間的始原で、空間的普遍)である〈本来の思考〉のおかげで、思考する存在・〈私〉は主観として命をもつのです。
主観(思考する存在・〈私〉―筆者註)は思考のおかげで命をもつ…思考とは、私を私自身を越えたところに導き、客観と結びつけてくれる要素である。それと同時に、主観としての私を客観と向い合せることで、私と客観を分離する。人間の二重性の根拠はここにある。第一に、人間は思考することで自分と世界を包括する。第二に、これも思考によって、自らを事物と対峙する人間的個(個人)として規定する(1:59)
以上のように、私たち自身が、この世界生成の根源である〈本来の思考〉のおかげで命をもつ主観(思考する存在・〈私〉)であると理解できるとき、私たちは正しく世界と向き合い、世界を理解できるのです。
それを次のように言い表すことができるかもしれません。
世界の根源である〈本来の思考〉のおかげで思考する存在・〈私〉は主観として命をもち、「いま・ここ」にいて、世界(事物)とともにありながら、世界(事物)と向き合い、認識する
私たち人間は、通常、自分が思考を行使しているということは意識しますが、自らが〈本来の思考〉のおかげで命を得ている存在だということを意識することはありません。しかし、「思考自体を観察する」ことによって、〈本来の思考〉の絶対性・始原性・普遍性について洞察することができ、自らをそこから命を得ている思考する存在として確立できるのです。
それによって、思考は強く、確かなものになり、動因の最高段階「純粋に直観把握された個々の倫理目標」をその都度つくりだすことができるようになるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
