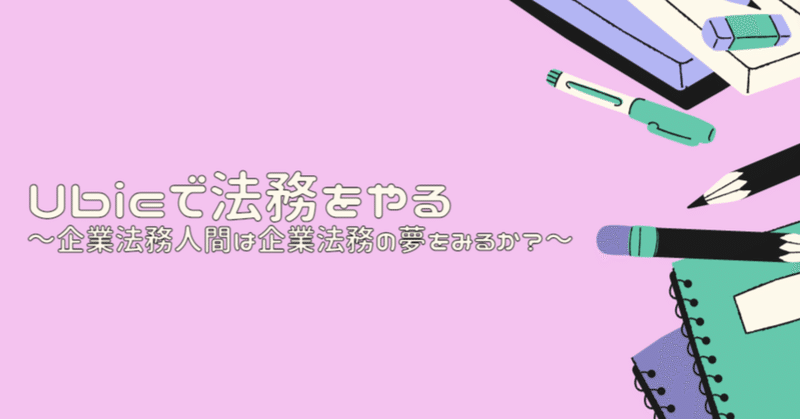
Ubieで法務をやる-企業法務人間は企業法務の夢をみるか? #UbieCorporateアドベントカレンダー
この記事は #UbieCorporateアドベントカレンダー の11日目(12/11)にエントリーしています。
イントロ
こんにちは!Ubieで法務をやっている亀井(kamachan)と申します。
Ubieに入ってからまだちょっとしか経ってないのですが、アドベントカレンダーを書く機会をいただきました。せっかくなので普段から法務をやっていて思っていることを書きたいと思います。この記事では、10年以上大企業での企業法務をやってきた企業法務人間がUbieというスタートアップに転職した入社動機や入ってからの感想を中心に書いていこうと思います。
特に、以下の方々に共感をもって楽しんでもらったり、今後のご参考になればと思っております!
企業法務やってる方
ある程度法務の経験を積んだが、今後どういう法務キャリアを歩むか悩んでいる方
企業内(スタートアップ)で働きたい弁護士の方
外から助言するだけでなく自らビジネスを動かしたいと思っている弁護士の方
自己紹介
まず簡単に自己紹介をさせてください。経歴は以下のような感じです
大学ではフランス文学を専攻。就職活動のときに「営業とか人の気持ちを推しはかったりして大変そう。文章読んでる方が気疲れしなくていいや」という安易な理由で法務を志す。
大企業(2社)の法務部門で法務人間として皆様のご指導ご鞭撻を受けながらすくすく成長。特に事業に近いところでの法務を経験。14年経過で今やアラフォーに。
数年前から副業でブロックチェーンのスタートアップにも法務として参画。
ヘルスケアスタートアップ「Ubie」の法務として参画して数か月経過。もみくちゃにされながら今に至る
また、今はUbie内のコーポレート部門であるUbie Corporate(UC)という組織に属しております。
Ubie Corporateではホラクラシーという制度を採用しており、「人的マネジメントなし!評価なし!」というフラットな組織運営をしております。私自身この制度が面白いなと思ってUbieへの入社を決めました。
ホラクラシーをごくかいつまんでいうと以下の通りです。
フラットな組織。ピープルマネジメントがない
機能毎にチーム(サークル)が組成されている。
権限がチームや役割に権限移譲されていて、権限の範囲で意思決定できる
詳しくは弊社のsonopyのnoteにまとまっておりますので興味のある方はぜひぜひ目を通してみてください。
サラリーマン法務ならではのもやもや
前置きが長くなりましたが、10年以上サラリーマンとして企業法務やってると、楽しみもありつつ、いろいろと感じてくるものもあります。
1.日本型雇用慣行に不満ありつつ、次どうするの?の答えが見えない
いわゆる日本型雇用慣行(終身雇用、年功賃金、企業別組合)が制度的疲労を起こしていると言われてるのは周知の通りかと思います。Twitterなどを見ていると、いわゆる「日本企業」だからこそ聞こえてくる意見もよくあります。(会社での年上の方に対する意見だったり、会社の先が見えずこのまま勤めてていいのかという不安だったり)。
ただ一方で、それに代わるものとして、で、どうするの?という話はこれらの話に比べてそんなに多く聞かれないようにも思います。
この手の話は私が社会人を始めたときから議論としてはあるのですが、いまだに明確なHOWが出てきていないようにも感じます。そもそも多様化の時代なので、明治に生まれて昭和のころに築き上げられてきた「日本型雇用慣行」に代わるものを現在の日本に一律に当てはめるというのも極めて困難だし無理があるようにも思いますが、、にしても、いつまで同じ話してるんだろうというもやもやは、サラリーマンやっててずっと感じているところではありました。気がつくと私もアラフォー。そろそろ次の世代にきちんとしたHOWの一つを提示して、次の世代に対してバトンを渡したいなと思っております。
2.官僚制つらい
これは法務だけに限らず大企業あるあるかもしれません。大企業はとかく官僚的になりがち。さらに法務(特にコンプライアンス)となると、ともすると上意下達で官僚的になりがちな面があると思います。これがつらい。
もちろん、官僚制のいい点・悪い点はそれぞれあると思います。実際に、大規模な組織を中央集権的に束ねるHOWとして、官僚制ほど適しているものはないかもしれません。ただ、ここではつらいポイントにフォーカスすると
上意下達で上からの指示に疑問の余地なく従わないといけない
縦割り。横の領域が気になってしまうがちょっと手が出しづらい
ともすると減点評価。責任回避をする人が適者生存する。たらい回しが発生。
とかがあると思います。
※過去あったエピソードで、とある上司から会社からの指示として降りてきたものに対して「施策の意義が分からない」というようなことを言ったことがありました。そのとき上司は一呼吸おいて「会社からのオーダーなのでやってください」という趣旨のことを言ったように思います。
今思い返すと、上司の心の中も「俺も意義なんか知らんけど、いちいち突っ込んでくるなよ、何年社会人やってんだよこいつは。そんくらい分かれよ、めんど(ry」といったことを心の中で思われていたのかもしれません。
外からすると法務の人って固いと思われがちで意外かもしれませんが、実は法務にもいろんなキャラがいます。その中にも、法務は論理を扱うお仕事ですので、ほんとは自由闊達な議論を尊ぶ人も意外に多い印象があります。そんな中で意義が感じられない・理由が分からない状態で施策をしなければいけない、もっとこうしたらいいのにと思いながらぐっとそれを飲み込んで仕事をするというのは相当にストレスがある状況だと思います。
また、私は大学でフランス文学をやっていたので、民主主義に対する憧れというのが人一倍強いのかもしれません。中央集権を排して分散化を志向するブロックチェーンに興味を持ったのもその点もあったと思います。ほんとは民主主義でやりたい。でも官僚主義の中で働かないといけない。この辺のもやもやもずっと抱えていたことでした。
3.そもそも企業法務の仕事って意味あるの?
そもそも企業法務のお仕事って意味あるのでしょうか?
例えば、法務の仕事の典型的なものである契約書の作成やレビュー、規約や規程を作ったところで、どのくらいの人が見ているのでしょう?その作った文章は作られて以来誰の目にも触れられることのないままキャビネットやフォルダにずっとしまわれっぱなし、ということはないでしょうか。そうなると企業法務のお仕事というのはどういう意味があるのでしょう?
このことを考えると、私が若い頃に定年退職したあるベテランの法務部長さんのことを思い出します。その方は定年退職したときに「私のやってきたことはほとんど意味がなかった。90%以上のことは意味がなかった。95%かもしれない。残り数%でも意味があったのならよいかなと思う」という旨の発言をしておりました。また別の場面ではよく「いざトラブルが起こると契約書なんて所詮紙切れ。吹き飛びますから」とも言ってました。
今振り返ってみると、その方は相当シニカルな方で(昔の法務部門にはそういう方がよくいたものですが)、契約書もトラブルに至らなければ見返すこともないので、その会社はそれくらい安定した会社だったということを言いたかったのかもしれません。また、「紙切れ」の裏の意図としてそれ以上に顧客との信頼関係が大事ということを言いたかったのだと思います。
ただ、まだまだ若者でピュアだった頃の自分はこの発言に衝撃を受けました。というのも、普段からこれって意味あるのかな、と思いながら契約書のレビューやっていたところも内心なくはなかったからです。そんなとき、ご経験を積まれた方が職業人生を全うするときに言ってたので、俄然現実味を帯びてしまいました。自分が辞めるときにこういうことは思いたくないと思ったものの、結局払拭できずくすぶっているところがありました。
現に、デビッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』という本では「ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」として企業内弁護士の仕事というのは度々登場しています。
もちろん、日本と国外とで事情も違うとは思います。ただ、法務の仕事の中には、意味のないペーパーワーク(ブルシット・ジョブ、クソどうでもいい仕事)におちいるときは都度都度あるようにも思います。これがともすると管理コスト過多になり、やりがいなども感じにくくなってしまうかもしれません。
いろいろ言うけどUbie(UC)に入った亀井はどう思ってるのか
さて、いろいろ書いて気の滅入る話を羅列してしまいました(申し訳ありません)。ここからは、いよいよUbie(UC)に入った亀井はどう思ってるの?について書かせてください!!
1.日本型雇用慣行の次へ!
日本型雇用慣行についてもやもやしていたところで出会ったのがUbieでした。冒頭に記載した通り、Ubie Corporate(UC)はホラクラシーでやっています。この点で全く日本型雇用慣行ではなく、新しい制度を志向していると思います。実際に日本型雇用慣行の特徴とUCとを対比すると、
終身雇用:まだできて6年なのであまり考えたことがない
年功序列:そもそもフラットなので序列がない。また、UCではあだ名文化で年齢を気にすることが少ない。また、年齢がある人・社歴の長い人の方が経験があるものの、若い人・新しく入った人の方がバイアスにとらわれず事業を進められるところもある。お互い良いところがある。お互いから学ぶことが大事という文化。状況や必要に応じて過去の経験をアンラーンすることも推奨されている。
年功賃金:職位もない。評価もない。報酬は各人バラバラ。成果連動型で目標達成すれば全員があがっていく仕組み。
企業型組合:必要なところもあるだろうがUbieでは不要(これについては特に必要性を感じない)
という感じで全く日本型雇用慣行という感じではありません。これがUCではワークしており、当然ですが日本型雇用慣行に関する不満というのは全くありません。
もちろん、ホラクラシーもHOWの一つであり、ホラクラシー至上主義というわけでもありません。絶対に日本型雇用慣行を廃絶すべしとも思っておりませんし、ホラクラシーが全ての企業に当てはまるわけではないとも思っております。(むしろホラクラシーは運営するのにそれなりの負荷もかかる制度でもあり、やるならみんなの認識合わせが結構必要だったりします。)今のUCにはこの制度が合っていると実感しておりますが、ホラクラシーというのもHOWの一つだと捉えています。UC内の共通認識として今はホラクラシーを採用しているが環境や状況、フェーズが変わったらいつでもホラクラシーを辞める可能性もありえます。
そもそも多様化している世の中なので、それぞれ自分達のマッチする制度・体制を自分たちで考えてベストなやり方を選べばいいんじゃないかなと思います。ここでは、自分たちの状況や課題に応じて組織も自分たちで変えられるし決められるということ示し、日本型雇用慣行にとらわれずに自由に組織設計できることを次の世代に渡せていければいいなと考えております。
2.官僚制からはほど遠い組織!
先の話と繋がるところですが、UCはホラクラシーをやっており、フラットな組織です。誰が偉い・偉くないということや、上下というものや政治的なものは基本的にはありません。また、法務については法務セクションの人間に権限移譲されております。権限移譲されていることはその権限の範囲にて判断ができるように設計されてます。
また、これはカルチャーもあると思いますが、縦割りではなく、たらい回しというものがない(少ない)ようにも思います。先ほど役割毎に権限移譲されていると言いましたが、一方でそれぞれ皆で助け合ってやっているという雰囲気も大きくあります。例えば、UCでは各機能の専門家たちが集まって皆で施策を動かすということも多いです。そのとき、何か問題が発覚したとしても、一瞬「ほげ~」というような空気になった後、誰かを責めるということではなく、「で、どうする?」というような感じで皆で解決に向かうということがよくあります。この辺はリソースが少ない・整ってないことも多いという理由もありますが、皆で助け合ってやってるというところがあり、いい文化だなと感じております。
同時に、各機能のプロフェッショナルが集まって施策を動かすことで、いろいろな観点を踏まえながら一緒に進められるというのも大きなメリットと思っております。例えば、法務では現在契約レビューや捺印・契約管理の運用体制を整えておりますが、今までにはないほどカジュアルにITの力を使って効率的なフローが組めたりしております。一般に、法務をやっているとどうしてもアナログな感じが出てしまうこともあるかと思いますが、ITのメンバーを簡単にアサインできるのでこの辺はとても日々助かっております(ありがとー!)
官僚制の一つの特徴として書面主義=書類めっちゃある(=煩雑)というのがあります。これがともするとブルシットジョブにつながります。また、IT化といっても、単に書面をデジタルにするだけで全然便利になってない、つらいシステムも世の中にはあると思います。そうではなく、実際にテクノロジーによって仕事を便利にしてくれるのは本当にありがたい限りです。
※ちなみに昨日弊社コーポレートエンジニアのsimonがnoteをアップしてくれてます。手前味噌ではありますが、弊社のIT部門がなんかすごいのと、クイックにいろいろなことをやってくれそうなのが伝わると思うのでこちらもよろしかったらぜひ。
上の方で官僚主義ではなく民主主義でやりたいということを書きましたが、こうなってくるとそれへのこだわりもなくなってきております。もちろん実際に施策を動かすときは適宜話し合ったり、slackで意見を合わせながら決めていてコミュニケーション量めちゃくちゃ多いです。
ただ、各分野にてそれぞれに権限移譲がされており、必ずしも自分が意思決定に参加してvoteする必要もないとも感じております。
Ubieのカルチャーの一つとしてTrust&Ownership(自分で当事者意識を持ちつつ、任せるところは信頼して任せる。背中を預ける)を掲げております。信頼できるひとが判断するのであればそれでOKで、私が決めなくてもいいかなというのが今の気持ちです。
3. そもそも企業法務の仕事って意味あるの?
ここまで話をしてきたら、いわゆる大企業的な働き方とUCでの仕事がだいぶ違うのではというのが伝わっているのではと思います。そのうえで、法務の仕事って意味あるかについていうと、明確にYESです!今のUbieでは法務は無くてはならない機能を担っていると自負しております。実際に、
ビジネス面においては、AIによる症状検索ができるということで、今までにないサービスを行っていると思います。今までにないビジネスということやヘルスケアを扱っているということで、当然リスクもあり、それがビジネスに対して大きなインパクトを与えることもあり得ます。そのリスクに対していかに立ち向かうか、日々考えながら物事を動かしております。
コーポレート面においても、UCはまだ組織もできたばかりで固まっていないところもあります。ホラクラシーというのもなかなかない制度ですが、一方でIPOに向けたガバナンスが求められてもおります。自分たちなりのガバナンスができて、社会に対しても堂々と胸をはれるような組織づくりをするためこちらも日々頭を悩ましつつ、ルールを作ってます。
それでも、意味のないペーパーワーク(ブルシットジョブ)はないの?といわれるともちろんあるにはあります。が、過去の経験に比すと少ないようには実感しております。というのも、Ubieではどのような仕事に対してもROIが求められており、結論、意味のないことは行われないようにはなっております。自分で優先順位付けをして意味のないことは積極的に行わないようにしていると、自然とブルシットジョブも行わないようになっていくのかなとは感じます(これについては、リソース的に意味のないことにまで手を回している余裕がないという面も多分にありますが)。
最後に
ここまで読んでくれてありがとうございます。私を知っている人については、亀井が元気そうにやっているというのが伝わればうれしいですし、私を知らない人については、UbieやUCのことが少しでも伝わったのであればうれしいです。
ここまで書いてきて思うのですが、ここに書いてきたことは自分にとってすごく大事なことだったなと思います。赤ちゃんでも自分としてこうしたいというものがあって、周りの環境と適合させ学習を積みながら、自分でできることを増やしていくと思いますし、こういう営みは人間の根源的な部分だと思います。「自分たちのことを自分たちで決められる」という当たり前の幸せが今のUbieにはあります。それがやっぱりいいところだなと改めて書いていて実感している次第です。
もちろん全てが思い通りというわけでは全くありません。ただ、背景が分かるから納得できるし、自分事として受け入れられるという面もあると思います。その辺がUbieやUCでワークしている部分かなとも思います。
最後に、タイトルに「企業法務人間は企業法務の夢をみるか?」と書きました。企業法務人間というと感情を排した人々が粛々と業務をこなすイメージだったり、ずっと「甲乙、甲乙」やっていて、自分の告別式のときに「一生甲乙言ってましたね」と言われることも厭わない人たちというイメージで、夢なんか持つの?と思われるかもしれません。また、私自身、小さい頃から特にこれといった夢があったわけではない人間でした。
が、この歳(アラフォー)になって、今はここに書いたようなことを何となくと考えたとき、これは夢と呼んでもいいんじゃないかなと思ってこのタイトルにしてみました。プロ野球選手やアイドル等と違って過酷な競争があるわけでもなく、誰でもかなえられるものだと思うし結構気に入ってます。
というわけで、今ではいろいろなやり方はありつつも日本でもスタンダードにしていきたいね!で、自分たち世代の責任として将来につなげていきたいね!とぼんやりと考えております。これが日本のサラリーマンとして、企業法務人間としての亀井の夢だということをお伝えして、この文章のクローズとさせてください。最後まで読んでくださってありがとうございました!
会社や日本の将来を一緒に作っていこうという人ぜひ一緒に働きましょう!
We are Hiring!
具体的な募集については募集要項をご覧ください。
カジュアル面談のお申し込みはこちらから。ぜひ詳しくお話させてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
