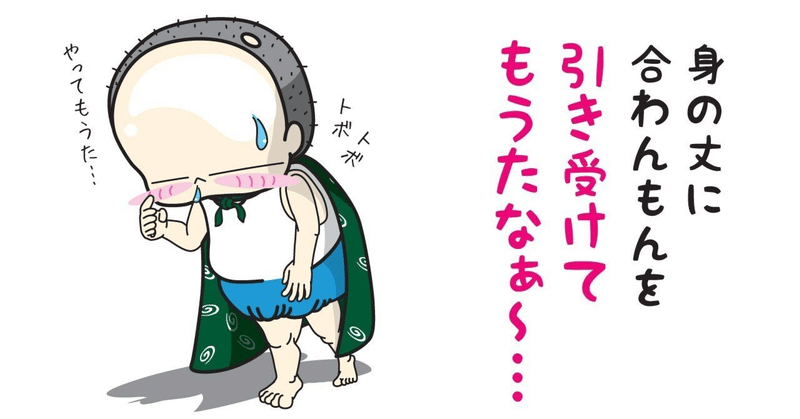
【解説】最初の対象は組織の1割で。推進チームは3名で。
おはようございます。SCC宮里です。
今日は主に人口5万未満自治体でAIなどの新規事業を考えておられる方に向けて書きます。テーマは組織論です。
〇1割変わればあとは、時間の問題。2割変われば結果は出せる。
〇2:6:2の法則 / 最初の2割ができればあとの6割はついてくる。最後の2割は"対話"でOK。
ご存じの通り、組織を実質的に引っ張るのはまずはトップ2割です。職員としては勇気がいりますが、それで御の字としてまずスタートを切ってもらえたらと思っています。2割が変わればあとのみんなはちゃんと、それぞれついてきます。またこれはご自身の業務の周りからの期待値コントロールという意味でもとても重要です。「全員ができるか」は無理な課題設定です。それは自治体だけでなくすべての組織体がそうなっています。言いにくい場合は、私のような外部の人間に言わせるのもありです。過度に全員10割を、と思うと、事業の成功の前に、自分が先に倒れてしまいます。自分自身を守るためにも大切だと思います。
そして2割って実は意外と多いので、まずは1割からでも十分。1割変わればかなり変わります。
300名の組織なら30名、100名の組織なら10名です。
〇コアチームは3人で。4人はコミュニケーション費用が効用を上回りやすい。
基本的にチームは3人が理想です。理由はコミュニケーション費用です。
Aさん,Bさん,Cさんの3名チームだと、コミュニケーションが
A - B ,
B - C,
C - A
の3通りしかありません。
それがAさんBさんCさん4名チームだと
A-B,
A-C,
A-D,
B-C,
B-D,
C-D
と人数が1人増えただけなのにコミュニケーションパターンが3通り=>6通になります。
新規事業はスピード感をもってどんどん成果を出す必要があるので、運用コストにはかなり注意をもった方がいいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
