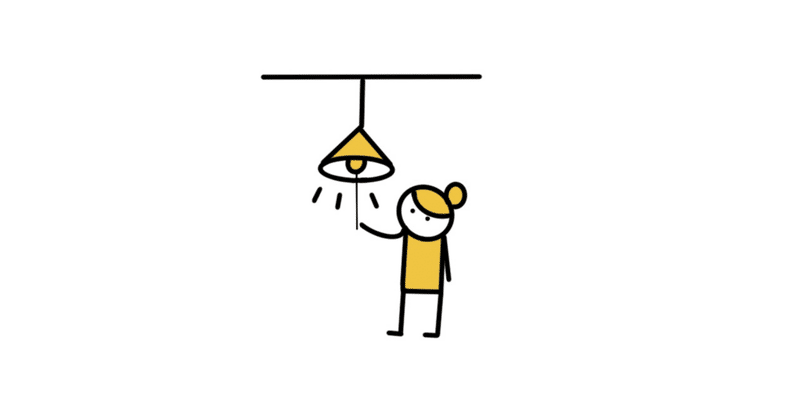
【解説】二酸化炭素を1トン減らす毎に、3000円もらえる現実世界でのゲームを始めよう
本日も人が減っても大丈夫な世界を作るために、取り組んでいる事業の解説になります。
今日はエネルギーチームの新規事業についてです。
今、エネルギーチームは「太陽光やEVを導入して二酸化炭素を減らしたら、お金が稼げるカーボンクレジット」の仕組み(現実世界を利用したゲーム)を開発しています。(※一緒に取り組んでくださる企業様や開発者の方を募集中)。今日はそれについて、説明したいと思います。
まずはSCCのwebページから当社のエネルギーチームの活動をざーっと、ご覧ください。
そしてそして、2024年2月に、当社も関わっている事業で、こういう記事がCoinDeskさんより出ました。
世界的な再生金融のブロックチェーンプロジェクトであるKlima DAOが、日本に拠点を持ち、長崎県西海市で私たちと一緒に環境価値の実証を進めること、がこの記事で書かれていますが、今回はその背景や裏側をご説明します。
◯再エネの電気以外のもう一つの価値、"カーボンクレジット"
そもそも、九州は太陽光発電がたくさんあります。たくさんありすぎて捨ててるくらいです。また再生可能エネルギーには、電気という価値の他に"環境価値"、というものがあります。これは一般的にCO2を1トン削減した価値に対して3,000円、とかの値段をつけて取引ができるものです。私たちはすでに3年ほど前から、非化石証書という形でこの価値だけを、顧客に販売したりしております。また、世界ではすでに年間何億トンものCO2取引がされています。
つまりここでやりとりしているのは電気ではなく、"環境にやさしい価値"になります。なかなかイメージが難しいかもしれませんが、炭素に値段をつけていて、実際に海外ではかなり大きなマーケットになっています。
◯炭素に値段をつけるとは? ~カーボンプライシング~
炭素に値段をつける、というのはどういうことか。
人間の活動により発生する炭素を計測することで、それを褒めたり、罰則を与えたりする、という考え方です。
ガソリンは1Lあたり2.3キロくらい排出していますから使用量から測ることができます。また自宅も、スマートメーターなどで一目瞭然になります。だいたい一般家庭は一年間で電気の使用だけで1000キロ~2000キロくらい排出しています(※家庭によります)。これらは、測定することが可能ですので、測定し、取引できるようにしよう、というのがカーボンプライシングの概念です。
これを、例えばこれまで炭素を"100"排出していたものを頑張って"90"にしたら、100-90="10"の価値を生んでいるよね、として何かしら金銭的メリットを付与したり、逆に"100"排出していたものから増えてしまって"110"にしたら、100-110="-10"で、罰金を設定したり、という具合です。
◯炭素に値段をつける方法 ~2つのアプローチ~
炭素に値段をつける方法は2つのアプローチがあります。①炭素を出しすぎている人を罰する考え方と、②炭素を減らしている人に利益を与える考え方です。
① 炭素税 / 管理経済的な考え。炭素を出す行動に課税することで、炭素排出を減らすアプローチ。
② 排出権 / リバタリアン的な考え。市場メカニズムを使う。CO2を出す人は、その分減らしている人にお金を払う。
もともとは①のアプローチからEUは政策議論を始めたそうですが、それでは世界的なカーボンニュートラルには足りず、②のアプローチが近年注目を浴びています。
実際テスラも電気自動車という環境にやさしい自動車を作り、"環境にやさしい価値"を販売して、営業利益を作ったりもしています。下記の記事をご覧ください。
西海市で説明しますと、SCCは太陽光パネルを持っています。そこは発電&売電をしていますが、このプロセスでは、CO2を発生させていません。化石燃料由来の電気を使っていた顧客が、SCCの電気に切り替えた場合、顧客はこれまで例えば、100のCO2を出していたところ、切り替えることで0に(イメージとして)なります。
電気としては再エネであろうが化石燃料由来であろうが、同じ電気なのですがこの"再エネである"ということに値段をつけよう、というのがこのカーボンプライシングの話です。
◯誰が買うのか
では、買い手は誰か。
まずは政府機関です。なぜなら各国は排出の上限目標を持っているからです。
また上場企業も買い手です。なぜなら彼らは「環境に悪い会社」と市場に認識されると、投資家から資金を引き上げられてしまうからです。
◯超えるべきハードルとその超え方
もちろんハードルはたくさんあります。大きくは3種類です。
1)技術的なハードル 技術的にできる?
2)ルール的なハードル ルール的にいいの?
3)市場的なハードル 買い手と売り手はつくの?
です。
1)の技術的なハードルは、すでに自社である程度実装が半ば完成していますし、3)の市場的なハードルは、買い手はいることはわかっていますし、直接話もしているので、あとは2)ルール的なハードルです。現在の日本の既存の仕組みであるJクレジット制度は、私たちのような規模の小さな脱炭素活動はボリューム的に審査対象になりません。そこを、僕らはいまブロックチェーンと民間認証で、ここのハードルを越えようとしています。
◯小さな脱炭素活動は、採算面から政府の制度を利用しにくい。
Jクレジットで、できるのであれば、素晴らしいことです。一方僕らがやっているのは「人が減っても大丈夫な社会」を実現するために、「エネルギー」で何ができるか、を考えており、基本的にそういう社会や地域、企業は規模が小さいことが一般的です。規模が小さいと、大きな制度は利用がしにくいことが多いですがこのカーボンプライシングについても、Jクレジットを利用しようと思うと、"時間"と"ある程度の量"が必要です。
では、私たちのような、規模が小さな地域でも、作った環境価値が「信用」され、「認証」されるにはどうしたらいいか。そこで、僕らは、
仮説① 政府ではなくブロックチェーンを信用する仕組み
仮説② 政府ではなく民間認証を取得する仕組み(VerraやGold Standard等の実績ある国際機関)
というところから実現を目指すやり方をとっています。
◯誰を信用するのか / 政府ではなく、ブロックチェーンの仕組みを信用する。
ブロックチェーンの説明は割愛しますが、 一度作ったデータの"改ざんが実質不可能"というブロックチェーンの特性を使って、ブロックチェーンにて管理することを目指しています。Jクレジットはもちろん信頼はされますが、現実問題私たちのような小さな地域の小さな組織では、認証プロセスのコストが、割りに合いません。
◯誰が認証するのか / 政府ではなく、すでに信頼されている認証機関を通す
また、認証も民間の認証機関を考えています。世界ではすでに国際認証としてVerraやGold Standardなどがあり数億トン以上の取引の実績を持っています。政府の認証が難しくても、国際的な民間の認証を通せば、買い手は、信頼してくれる、というのが僕らのポジションになります。
という感じで説明してきましたがいかがだったでしょうか。難解な言葉も使ってしまいましたが、僕としては、地域で現実的にどうやって再エネで新しい産業を作っていくの?という問いに対して、重要なアプローチだと思っています。
事実、僕らのチームは技術面、パートナー面はかなりいいチームで進められているので、もしこの文章を読んでおられるなか、長崎や九州地域の企業さんや、応援したい!というふうに思ってくださる方は、ぜひぜひお声がけください。
西の端っこで一緒に盛り上げて行きましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
