
【解説】ばりぐっどくんは、いつ・誰が作ったのか。
今回は、ばりぐっど / ばりぐっどくんについて、解説したいと思います。
まずは下記のばりぐっどくんの誕生の暦をご覧ください。
⚪️ばりぐっどの誕生から現在までの暦
2017年 ばりぐっど誕生 ←ここで誕生
2019年 文字起こしばりぐっどくん誕生 ←AIになったのはここ!
2020年 法人向けばりぐっどくん誕生
2022年 お絵描きばりぐっどくん誕生
2023年 自治体向けばりぐっどくん誕生
年表でご覧いただく通り、ばりぐっど&ばりぐっどくんは、AIのばりぐっどくんとして生まれる2年以上前に、誕生していました。
⚪️ばりぐっどの始まりは、ローカルメディア「ばりぐっど」
ばりぐっどの始まりは、ローカルメディア「ばりぐっど」がスタートです。これは私たち西海クリエイティブカンパニーのビジョンである「人が減っても大丈夫」な社会を作るために"挑戦することが尊重されるカルチャーをつくる"ことを目的に運営されているメディアです。
これは、私としては自律分散型のローカルメディアと位置付けているものです。2024年のいまではそうでもないですが、私が西海に住み始めた2016年は、地域で情報を生み出す主なメディアは「新聞」「広報誌」「テレビ」がほぼ全て。
これらは、いわゆる中央集権的な構造ですが、これは人口が減っていくとますます減っていくタイプのものです。実際西海市は長崎新聞の記者が一人担当としておられるだけですし、広報誌も市の職員さんが1、2名で作られています。
しかし西海市は非常に地理的には広いため、決してそうした地域の伝統的なメディアだけでは、いろいろなチャレンジを発信することができません。
そういう着想から、「市民のみなさん一人一人に情報発信してもらう仕組みをつくろう」ということでスタートしたのが、ローカルメディア「ばりぐっど」です。2017年に3名のライターからスタートし、いまでも6,7名の市民のみなさんと一緒に運営し続けています。
さて、話をばりぐっど/ばりぐっどくんに戻します。
⚪️"ばりかた"の「ばり」 + "Good"の「ぐっど」 = ばりぐっど
基本的に、ばりぐっどはローカルのマジで、めちゃくちゃ小さな話題を扱っています。PVは一才追っていません。地元の新聞よりも狭く小さく深く記事にすることを目的にしています。
そしてばりぐっどの名前の由来ですが、「ばり」は九州地方で「とても」という意味です。とんこつラーメンの「バリカタ」のばりです。
「ぐっど」はもちろんGood、「ばり」と「ぐっど」で"めっちゃいいね!"という意味です。
⚪️ばりぐっどの名前が決まった瞬間
これは2017年2月、東京の新宿東口の椿屋珈琲店で決まりました。その場では、プロのコピーライターの方、プロのグラフィックデザイナーの方、Webデベロッパーの方、と僕の4人で集まって、決めました。名前の候補はその日までに、コピーライターの方に、10個ほど作ってきてもらっていました。そして10個の候補名がプリントされたA4用紙を、4人で囲んで「せーの、で指さそう」ということで、「せーーの」で全員が「ばりぐっど」を指差したので、1秒で名前は、ばりぐっどに決まりました。
⚪️ばりぐっどくんは、気がついたらいた?!
ばりぐっどくんの誕生は、もっともっとカジュアルです。知らない間に、そこに「いた」のです。
名前も決まって、最後の追い込み時期の2017年3月。「グラフィックデザイン」を担当してくださっていたKさんから、「だいたいできたんで、宮里さん、一回みてください」とメッセージをもらいました。
そして、Webサイトにアクセスすると、いい感じのデザインのWebサイトが出来上がっていて、「めっちゃいい〜」と思っていたのですが、右下になにやら米粒のようなものがいました。

その米粒のようなものをクリックすると、「するするする〜」とスクロールトップ(ページの最上段までスクロールされること)され、ボタンになってることに気がつきました。

「なんですかこれ?」と尋ねるとKさんが「ばりぐっどくんです。かわいくないですか?」
という感じで、ばりぐっどくんは生まれました。後から知りましたが、米粒ではなく、親指の👍ということで、この時はものすごくノリで決まったのですがその後、いまでは380万人を超えるユーザー数を持つばりぐっどくんにまで愛されるようになったのは、Kさんのおかげです。
⚪️ばりぐっどくんは、気がついたら、地域のいろんなところに出没。
と、スタートはものすごくゆる〜く始まったのですが、そこから2017年だけで、下記のようなばりぐっどシリーズが生まれました。
・ばりぐっどLINEスタンプ

・ばりぐっどぬいぐるみ

・ばりぐっどタブロイド紙
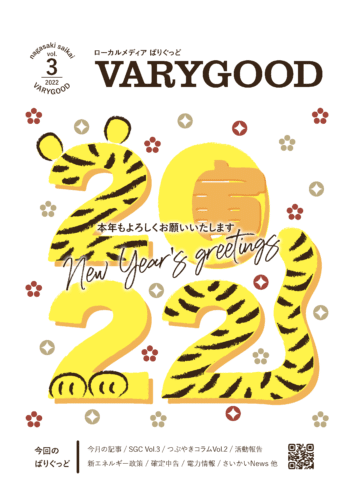
正直2017年にばりぐっどがリリースされてから、ばりぐっどくんは地域内でくまもん化しました。商標はSCCで持っていますが、コミュニティメンバーには、使用権を認可するかたちで、自由に使ってもらっています。
このようなところから「ばりぐっどくん」のライセンスを共有財産にしたいな、というアイデアも出てきて、これはブロックチェーンやDAOの話で考えていくときのヒントになりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
