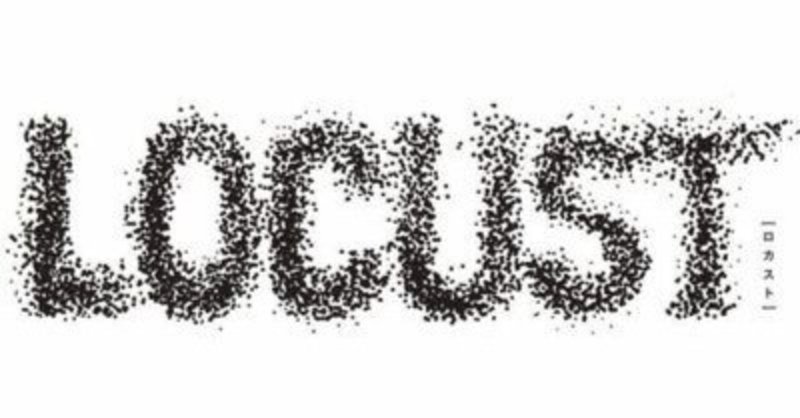
【無料】LOCUST vol.6 刊行のお知らせと巻頭言先行公開
いつも『LOCUST』をご支援いただきありがとうございます。
編集部の太田充胤です。
このたび、旅行する批評誌『LOCUST』の最新号 Vol.6が刊行となります!
きたる11月20日(日)の文学フリマ東京にて頒布後、書店や通販での取り扱いがはじまります。
この2年間、『LOCUST』的にもほんとうにいろいろありましたが、こうしてなんとか刊行のご報告ができることを大変ありがたく思います。

今回の行先は、そう、福島県です。
福島のなかでも、我々が訪れたのは郡山・福島・会津。エリアで言えば「会津エリア」と「中通りエリア」ということになります。
なぜいま福島なのか? なぜこれらのエリアなのか?
正直、私たち自身にもよくわからないまま旅は始まりました。しかし編集作業を終えた今、福島で良かったなという気がしています。また、内容もいつも通り(いつにもまして?)『LOCUST』らしいものになったのではないかという手ごたえを感じています。
刊行に先立ちまして、ロカストプラスでは記事の先行配信や、紙面には載らない各参加者の旅行記を順次公開していきます。初めましての皆様は、『LOCUST』がどういう雑誌で、どんなことを考えながら作っているのか感じていただければ幸いです。
本日はまず、巻頭言を先行公開します。
***
『LOCUST Vol.6 会津・中通り』巻頭言
パリンプセストの復元作業
『LOCUST vol.6 会津・中通り特集』をお手に取っていただき、ありがとうございます。
本誌は「旅行誌を擬態する批評誌」をコンセプトとして、編集部員・執筆者が全員でひとつの土地を訪れ、その土地に関する言葉を立ち上げる試みです。誌名の"LOCUST"とは「蝗害」で知られるイナゴ(正確にはバッタ)のことで、群れをなして襲来しその土地の景色をがらりと変えてしまうという意味合いを持っています。いわゆる「ガイドブック」ではありませんが、たとえば『坊っちゃん』を携えて松山・道後を訪れれば旅の様相が少し変わる、というようなことが起こればいいなと思って作っています。あなたの旅を言葉でハックするための道具として、お役立ていただければ幸いです。
早いもので、おかげさまで『LOCUST』も創刊から満4年が経ちました。
創刊号:千葉内房、2号:西東京、3号:岐阜美濃、4号:長崎、そして5号:北海道。COVID-19の流行が始まったのは、ちょうど3号と4号とのあいだでした。本当ならば、5号あたりで海外編かな、なんて言っていたのも今は昔。そもそも旅行に行くべきかどうか、このような雑誌を続けるべきかどうかさえ悩む日々が続きました。4号・5号の旅行は個人行動が大半でしたが、幸い今号は流行の谷間であったこともあり、思い切って「全員が集まる」という本来のやり方を再開することにした次第です。
4号・5号と旅行への参加を控えた私にとっては、『LOCUST』の制作に本格的にかかわること自体が久しぶりでした。制作の過程で、実にいろいろなことを思い出しました。そういえば創刊当初はこんなビジョンを持っていたな、とか、参加者同士でああでもないこうでもないと議論しながらする旅行はこんなに楽しかったんだな、とか。多くの人にとってそうであるように、私たちはコロナ禍を経てあまりに多くのことを考え、その代わりにあまりに多くのことを忘れてしまっていたのでした。
さて、そんな今号の行先として私たちが選んだのは、福島県です。
福島、と聞いて、どんな風に思われるでしょうか。今更言うまでもなく、福島という地名は特別なイメージを帯びています。おいそれと触れてはいけないような。それでいて、むしろ積極的に語らなければいけないような。県外の人間にとって、福島とはどうしても、そういう特殊な磁場をもった場所であると思います。
福島に行くという案は、『LOCUST』の刊行当初から常にありました。しかしながら、今日「福島特集」を標榜すれば、それは内容の如何によらず「フクシマ」の話として受け止められるだろうとも想像しました。私たちは「フクシマ」を語りたいわけでは別にない。これは政治的な議論をするための雑誌でもなければ、ダークツーリズムを提唱する雑誌でもない。しかし、「福島特集」は否応なしにそのような勘繰りの対象になってしまうだろう──と、こういうわけで、福島案は却下され続けてきたのでした。
ではなぜ今、あらためて福島なのか。正直、私にもよくわかりません。わかりませんが、編集会議で何度目かの福島案が挙がったあの瞬間、今なら行けるのではないか、むしろ行くなら今なのではないかという説明しがたい感覚を、その場の全員が共有していたことはたしかです。おそらく私たちにとって、今、福島を訪れ、福島について語ることは、何か意味があるのだと思いました。
私にとって、福島を訪れるのは実に十数年ぶりのことでした(つまり、震災以来はじめてということです)。郡山の街を歩きながら、やはりいろいろなことを思いだしました。あの時は東北本線で夜遅くに着いて、商店街で郡山ブラックラーメンを食べたっけ。帰り道の水郡線、線路沿いに広がる9月の稲穂の美しさに見とれて、思わず途中下車して一駅歩いたっけ。ああ、そうだった! あの時以来、私にとって〈福島〉とはあの黄金の海のことだった──。
そんなことはすっかり忘れていました。あの震災を経て、私は私にとっての〈福島〉がなんだったのかを忘れてしまった。さらに時間が経って、それを忘れたことさえ忘れてしまった。これは、震災によって大切なものが失われたという話ではないのです。私たちには永遠に失ってしまったものと、ほんとうは失っていないのに上書きされて忘れてしまったものとがあるという話です。
編集会議で、今の福島はまるで「パリンプセスト」みたいだと言った人がいました。
パリンプセストってご存じでしょうか。紙が普及するより前の時代、人々は高価な羊皮紙を無駄なく使いまわすために、いらなくなった写本の文字を消して再利用していました。こうして元の情報とは別の情報が上書きされた羊皮紙の写本のことを、パリンプセストと呼びます。消された文字は薬品やX線などの技術によって復元することができて、復元してみると手紙の下から貴重な教科書が出てきたり、教科書の下から聖典が出てきたりするそうです。
人々の意識を上書きするような大きな出来事のあとでは、それ以前のことについて考えるために特別な作業を必要とします。「フクシマ」という強烈なイメージに上書きされる前、私のような東京近郊在住者にとって〈福島〉とはなんだっただろうか。あるいはコロナ禍という大災害が生活規範を上書きする前、人類にとって旅とはなんだっただろうか。
つまるところ私たちは、福島へ行くことを通じて私たち自身の意識の古層へと、おそるおそる、足を踏み入れようとしていたのかもしれません。
太田充胤
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
