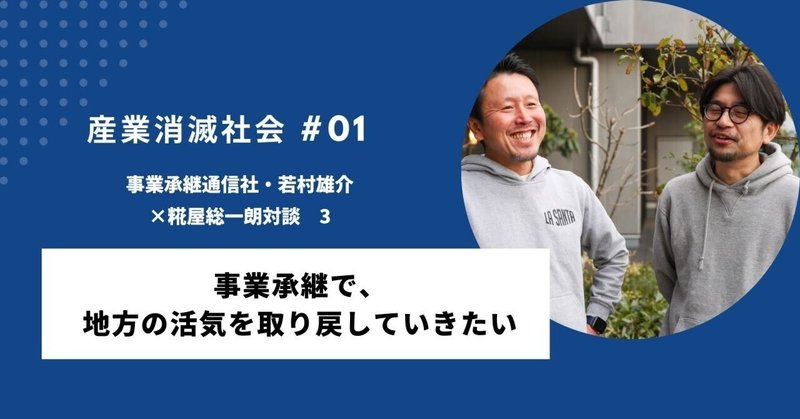
事業承継で、地方の活気を取り戻していきたい 事業承継通信社・若村雄介×糀屋総一朗対談3
事業承継に取り組む人、地域に残したい産業などを紹介し、これからの日本の産業のあり方について考えていく連載「産業消滅社会」。2018年に事業承継通信社を創業し、スモールM&Aに取り組む若村雄介さんと代表の糀屋総一朗の対談3回目は、地方において産業を承継していくことの課題感、どのように事業承継を広めていくかについてです。
前回はこちら!
成約したお客さんからの紹介が増えてきた
糀屋総一朗(以下、糀屋):2018年に創業されてから3年が経ちましたが、直近の1年では何件ぐらいを手掛けたんですか。
若村雄介(以下、若村):規模はバラバラですが譲渡成立した件数でいうと11件ですね。最初の1年は2〜3件だったんですが、ありがたいことに年々増えてきています。
糀屋:案件はそもそもどのように探すんですか。
若村:最近はやっぱり、成約できたお客さんからのご紹介が一番多いですね。本当にありがたいです。また同業にあたるM&A仲介会社のアドバイザーが売り手オーナーからの相談を受けるも、自社規定の手数料が高くて規模的に合わない、という時に弊社を紹介いただくというケースも多いです。
ここ最近、ようやく案件探しには当初よりも苦労しなくなったという感じです。あとは実績が上がるにつれて、ホームページからの問い合わせも増えていますね。
糀屋:そんなに好調なら、人を増やしてもいいんじゃないですか、そろそろ。
若村:でも案件を受託するルートが確立しているわけではないので一気にアクセルを踏んで人を雇ったり、というのは怖くて。成功報酬なので安定しませんし(笑)。近いうちに一人二人は入れたいとは思っていますが、それまでは僕たち2人プラス業務委託、アシスタントで頑張ろうと思っています。
産業が消えるインパクトは地方のほうが大きい
若村:僕が事業承継の仕事を始めた時は、必ずしも地域の問題について考えていたわけじゃなかったんですけど、明確にわかってきたことがあって。そもそも小規模事業の第三者承継、すなわちスモールM&Aを積極的に手伝う専門家が絶対的に少ないというのも問題だけど、そういう人は地方にいくとさらに少ないなと。
糀屋:少ないというか、本当にいないですね。いるとすると地元の社長とかになりますね。社長が社長に相談するというか……「あそこ売りたいらしいよ」みたいなことを持ちかけることはあるかもしれないけど、若村さんみたいな人は本当にいません。

若村:地方の方が、産業が1つなくなってしまうだけでインパクトがかなり大きいですよね。僕も山口県のある町の役所を訪問した時に、ガソリンや灯油などを販売している、町の生活をサポートしている店が廃業寸前になっていると。高齢者だらけのこの町に1軒しかない業種がなくなったらどうする?という状態を目の当たりにして。
だから事業承継って地方こそ深刻だし、スモールM&Aのサポーターがいないというのもわかったので、僕も今地方エリアで地元に根ざした案件への温度感を上げているんです。糀屋さんの話を聞いて、登ってきた道は違うけど今、同じ山小屋で出会った、みたいな感覚を持っています(笑)。
糀屋:本当にそうなんですよね。大島はもちろんですけど、宗像市にも事業承継の専門家はいないし。若い子はどんどん外に出ていってしまって、事業承継という選択肢ももうないものとなってて、廃業一択なんです。親も、しんどいから子供に継がせたくないと言うんです。でも僕から見たら「もっとこうしたら利益が上がるのに」と思ったりしますけど、そういう発想にならないので。

若村:なるほど。
糀屋:親も子供に継がせたくない、子供も戻ってこない、第三者に売るのも「体裁もあるし嫌だ」みたいな気持ちもあるのかな。そういうのがからんでいくと、もうなくなっていく一方なんですよね。悪循環です。
若村:何かそれに対して打ち手みたいなものって浮かんでいますか。
糀屋:まずもう、大島では宿泊業に関しては自分が承継していくという形でやろうかなと。ただそれは大島という小さい範囲でやるからできることで、もっと大きいところで見た時に何ができるかというと、難しいですよね。さっき言った、事業やってる人が継がせたくない、それから事業やってる人が相談できないということも問題だと思うし、どこからどう手を打ったらいい方向にひっくり返るのか、僕もまだちょっと見えていないというか。
産業の「町医者」的な存在でありたい
若村:僕が思っているのは、実績、事例しかないと思っていて。今はまだ「第三者への事業承継をすることで価値ある事業を残していける」という概念がまだ伝わっていないと感じています。ローカルの経営者の中で一つそういう事例ができたら、「どうやるの?」と狭いコミュニティ内でつながって、波及していくと思うんですよね。
先ほど話したお弁当屋さんの事例も、第三者への事業承継をすすめているというと社員や周りの人が不安になってしまうかもしれないと思い、完全に秘密裏にすすめています。でも、地域でみんなが知っているお弁当屋さんの事業承継が成功したら、その地域ではニュースになると思っています。パートさん含め数十人の雇用を守って、お客さんも美味しいお弁当を食べ続けられる。狭い街の中で「こういうやり方があるんだ」と伝えられるし、一石を投じられますよね。だからまずは採算度外視でも、そういう事例を作りたいと思います。

糀屋:小さければ小さいほど、放っておいたらなくなってしまいますよね。やっぱり圧倒的に若村さんのような専門家が地方には足りないですよね。
若村:なんというか、自分で言うのもなんなんですけど、僕と共同経営者の柳は、決して何か特別な専門知識があるわけではないですが、基本的な経営、つまり財務とか組織、人などは最低限わかった上で、経営者の気持ちにしっかり寄り添って第三者への事業承継を着地させる、ということができるんですけど、意外に士業の先生方はこれができないんですよ。
糀屋:なるほど。
若村:先生方はそれぞれ専門領域の専門知識があるわけで、感情を大事にしながら交渉役としてディールをまとめていく、というのは得意ではないですからね。でももちろん、コミュニケーション力に長けた税理士、中小企業診断士なら地方にもいるので、本当はそういう人たちが第三者事業承継のお手伝いができればいいなと思うんですけどね。
もっとスモールM&Aのお手伝いをできる人が増えれば、事例も当たり前になってくるだろうし廃業も減らせまず。同時にBATONZなどの情報プラットフォームも育ってきているから、今こそ本当に第三者事業承継、スモールM&Aの夜明け、黎明期なんだろうと思います。
糀屋:本当にそうですね。今回、いろいろお話できてよかったです。今後もぜひ情報交換をしつつ、一緒にお仕事もできたらいいなと思っています。
若村:ぜひですね。この仕事は、もし僕が一生困らないお金持ちになったとしても、続けると思います。天職だなと思っています。おこがましい言い方ですが、小規模企業の経営者の駆け込み寺とか町医者みたいな存在になりたいですね。
糀屋:すごく素晴らしい仕事ですよね。本当に今日はありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
