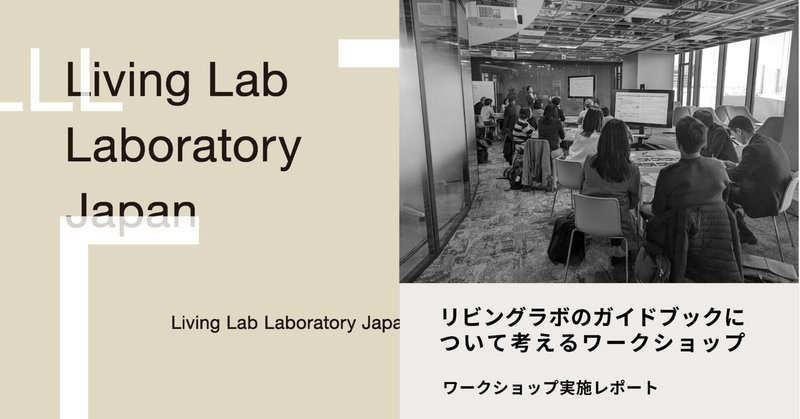
リビングラボのガイドブックについて考えるワークショップ
我々に必要なガイドブックとは?
前回の記事では、リビングラボの立ち上げや運営に関する様々なガイドブックを深掘りした結果について書きました。その中で、国内のガイドブック/ツールもいくつかピックアップしましたが、やはり、本格的なものは欧州(ENoLL)でつくられているものが殆どです。
…そうなると、基本的には英語で書かれていますね。私は研究者なので英語の資料も頑張って読みますが、国内の実践者にとっては”取っつきにくい”資料だと言わざるを得ません。また、その内容自体も、欧州の社会文化的文脈における実践経験にもとづいて記述されています。こういった現状を考えると、日本のリビングラボ実践者/研究者である「我々」が欲しいと思える(&母国語で書かれた!)ガイドブックやツールが必要です。
そこで、昨年(2023年)の11月に横浜で開催された、第5回全国リビングラボネットワーク会議の中で、「リビングラボのガイドブックをみんなで知ろう、考えよう!」というワークショップを実施しました。
今回の記事では、本ワークショップについてレポートしたいと思います。(note記事にするまでに時間がかかってしまいました…すみません!)
ワークショップの構成と参加者
今回のワークショップですが、以下のような構成で行いました。なお、JNoLL(日本リビングラボネットワーク)の長島さんにも運営・進行を手伝ってもらいました。
チェックイン(参加者間の自己紹介を含む)
リビングラボ古今東西:事前に調査した各種ガイドブックの紹介
リフレクション:気になったガイドブックとその理由
ウィッシュレター作成:こんなガイドブックがほしい!
チェックアウト
「2. リビングラボ古今東西」の時間では、前回の記事でご紹介した既存のガイドブック/ツールを「リビングラボ・ガイズ(Living Lab GuideS)」としてカード化し、参加者の皆さんに共有しました(図1)。

当日のワークショップが始まるまで、どのくらいの参加者に来ていただけるかが分からずドキドキでしたが、最終的には国内の大学、企業、シビックテッカ―などの多様な参加者16名と、来日していた韓国のKNoLL(Korean Network of Living Labs)のメンバ7名に参加していただけました(図2)。

念のため、ガイドブック/ツールというものに対する、私の前提となる考え方について少し触れておきます。私は、リビングラボに関する知識やプロセスを全て言語化・共通化できるとはまったく考えていません。むしろ、実践の現場で柔軟に組み立てていくものだと思っています。しかしながら、実践者が自身でリビングラボの場やプロセスを企画・運営する際には、その「拠り所」となる羅針盤のようなものは必要だと思っています(図3)。それがガイドブックやツールなのです。
知識化できる部分から、リビングラボ実践に役立つ知見やノウハウを言語化して、共有・参照可能にしておく。そして、それを「たたき台」にしながら、自分たちのリビングラボ実践を組み立てたり、新たな知見を追加していく。そういった、知識と実践を行き来するような取り組みが重要だと思います。
デザインの知識(特に実践的な知識)を安易に言語化・ツール化していいのか、という声があることは重々承知してます。それでもなお、我々(=コミュニティ全体)自身の「学習」のループを回していくためには、部分的にでも、知識を実体化していく営みが必要だと思います。

みんなのウィッシュレター
早速、今回のワークショップの結果として、参加者(特に、国内の研究者/実践者)の皆さんに書いてもらったウィッシュレターの中身を見ていきましょう。
参加者の中のおひとりが、グラレコを普段からやっている方だったようで、ワークショップ中に(手元のiPadを使いながら)リアルタイムに参加者の発言をまとめてくれました(図4)。ありがとうございます!(余談ですが、こういうことを何の準備も依頼もなしに、その場でパパっとやってくれるってすごいですよね。)
このまとめグラレコからでも、非常に多くの観点のウィッシュが場に出てきたのが、よく分かると思います。

ワークショップ終了後、みなさんのウィッシュレターをひとつひとつ改めて振り返りながら、全体像をさらに構造的に整理してみました。その結果が、図5です。
今回のウィッシュレターには、大きく分けて、
(i) ガイドブックのコンテンツ(=こんな内容が含まれていてほしい)
(ii) 期待する成果(=こんなことに役立ってほしい)
(iii) ガイドブックのつくり方(=こんな風につくりたい)
という3つの観点がありました。そのそれぞれについて、もう少し細かく見ていきましょう。

(i) ガイドブックの「コンテンツ」
今回のワークショップで個人的に面白かったのは、リビングラボや市民共創の場に参加・関与する際の「心構え(マインドセット)」を提示してほしいという意見が強かったことです。このワークショップを企画しているときの勝手なイメージでは、実践者を中心に、メソッド集的な実用的なガイドブックへのウィッシュがもっと集まるかなーと思っていました。ただ、蓋を開けてみたら、結果はある意味真逆で、メソッドよりもマインドセットが大事ではないか、という声が複数挙げられました。当日の参加者との議論を思い出してみると、例えば、市民を共創のパートナーではなく単なる被験者として見てしまうようなマインドセットのズレがあって、リビングラボのプロジェクト実践がうまくいかなかった、というような苦い経験もあるようです。また、共創の場全体の最低限のグランドルール(行動規範:Code of conduct)の明示も必要ではないか、という声もいただきました。私自身、あまりはっきりと意識できていませんでしたが、リビングラボは多様な人や組織が参加する場なので、差別/ハラスメント的な言動が起きないようにして、あらゆる参加者が安心して気持ちよく活動に参加できるようにすることは重要ですね。
その他には、産官学民といったステークホルダごとの、リビングラボを実践することの「メリット/価値」を整理・言語化すること、リビングラボの「事例(成功/失敗)」の収集などがありました。この2つは、これまでもよく求められてきたことですが、その必要性を改めて認識しました。特に、事例情報は、失敗体験(ワークショップ中では「残念集」と言われてましたが)を含めて、みんながアクセスできる「コモンズ(共有資源)」として集めたいですね。
また、リビングラボというと、多様なステークホルダが参加するワークショップを行うイメージが真っ先に出てくる方も多いと思いますが、実は、市民とのインタラクションは、ワークショップ以外にも、アンケートやインタビュー、立ち話、日常コミュニケーション、チャットなどの様々なアプローチがあり、経験豊富な実践者は、人や状況に応じてそれらを使い分けています。そういった、リビングラボの「多様な実践のあり方」を整理してほしいという声もありました。
もうひとつの重要なコンテンツは、「イノベーションへのアプローチ」です。これは、例えば、R&D活動や新規サービス開発活動と、リビングラボの場の接合点をいかにつくるかということをさしています。欧州におけるリビングラボの実践や研究は、イノベーション研究の一環として行われていることも多く、この観点への注目が非常に強いです。一方、日本のリビングラボは、地域活性化やまちづくりの文脈が強調されることも多く、企業や研究機関におけるイノベーション活動との接点が弱いような気もします。もちろん、リビングラボの価値は、イノベーション活動への貢献だけではありません。しかしながら、より多くの企業や組織にリビングラボを活用してもらうためには、イノベーション活動とリビングラボの関係性に着目した知見の言語化や構造化も、今後は一層必要になるなと思いました。
(ii) 期待する効果
今回のワークショップでは、「どんなガイドブックがほしいですか?」という問いかけをしたので、その中身(コンテンツ)だけでなく、利用したい文脈や期待する効果に関するアイデアも複数いただきました。
ひとつ目は、「誰でも気軽に一歩を踏み出せる」。リビングラボのキーワードである、共創や産学官民という言葉は、実践経験が少ない方から見ると、少し大変そうな(座組をつくったり、調整したりする負担が大きそうな)活動に見えるようです。そのため、ガイドブックの利用者が、”最初の一歩”を気軽に踏み出そうと思えるような仕掛け(コンテンツの構成、情報の絞り込み方など)があることが重要なのではないか、ということです。
ふたつ目は、「誰もがフラットになれる」。リビングラボには多様なステークホルダが関わります。これまでの参加型デザイン研究でもたびたび言われてきたことですが、ステークホルダ間のパワー(権力)バランスの問題は、時に共創プロジェクトの障壁になります。これに対して、ガイドブックやツールという「媒介物」があることで、プロジェクトの進め方などに関する議論をフラットな関係性で進めることができるのではないか、というアイデアです。つまりこれは、ガイドブックが、多様な背景知識や専門性、想いをもった人々をつなぐ「バウンダリ―・オブジェクト(※注1)」になるのではないか、というアイデアですね。こういう視座があるかないかで、ガイドブックの構成は大きく変わってきそうです。
三つ目は、「社内で説明しやすい」。これは企業からの参加者の声でした。上記のコンテンツで書いた「メリット/価値」や「事例(成功/失敗)」にも強く関係しますが、企業として関わる際の社内説明で効果的に活用できるツールがほしいというものです。たしかに、リビングラボとは何か?みたいなものはあっても、それが企業や研究機関におけるイノベーション活動にどのように貢献したかをわかりやすく示す資料って、あまりないんですよね。
(iii) ガイドブックのつくり方
最後に、ガイドブックのつくり方(=作成プロセス)に関する声も頂いたので、ご紹介します。それは、「みんなでつくる」というもの。つまり、ガイドブック自体も共創的につくっていきましょう!というものです。
これは、たしかにそうするべきだと思います。みんなにちゃんと使ってもらえるガイドブックにするためには、我々としての「芯」は持ちつつも、様々なご意見やアイデアを柔軟に取り入れていくことが大事だと思っています。
まとめ
今回の記事では、我々が実施した「リビングラボのガイドブックをみんなで知ろう、考えよう!」について、結果を含めてレポートしました!
参加者のみなさんのおかげで、私としても非常に学びの多い場となりました。「マインドセット」にフォーカスが当たることも意外でしたし、行動規範(Code for Conduct)の明文化は、(お恥ずかしながら、)これまでにあまり考えたことのなかった視点でした。
現在、本ワークショップの結果をもとに、ガイドブック/ツールの作成も徐々に進めているところです。「みんなでつくる」というアイデアが出たように、プロトタイプ(試作品)の段階から可能な範囲で公開・共有しながら、さらなるワークショップ等も織り交ぜ、様々なフィードバックをいただきながら進めていきたいと思っています。
ご興味のある方は、LLLのニュースレターにご登録ください。これから様々なイベントや活動の発信や報告をしていこうと思っています。
Author: Fumiya Akasaka (AIST)
注1:バウンダリー・オブジェクトとは、異なる分野やコミュニティを接続し、その間に存在する分野依存的な知識を浮き上がらせるもののことをさします。参考文献はこちら。
Star, S. L. and Griesemer, J. R. (1989) Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3): 387-420.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
