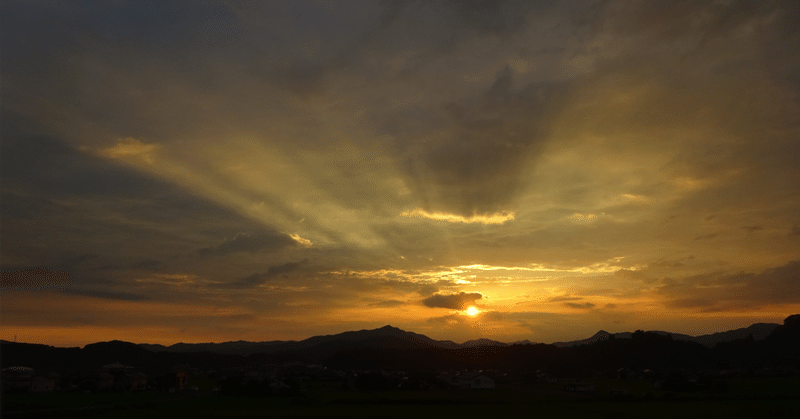
「死の恐怖」との付き合い方(3)
あなたは、「死者の世界」というイメージというか概念をどう思いますか?
あるいは、そういう「世界」を感じたことはありますか?
いわゆる霊感の強い人とかは、多分そういう「世界」の存在を当たり前のことと思っていることでせう。
また、日本の伝統として盆暮の帰省とか、墓参りとか、そういった行動の底のところには、少なくとも「先祖の霊の世界」があるという前提が根付いているんじゃないかな。
我が大先輩にして大哲学者の三木清先生も、「死者の国はある」という方に賭けると仰っていることだし。
私にとって死の恐怖は如何にして薄らいでいったか。自分の親しかった者と死別することが次第に多くなったためである。もし私が彼等と再会することができる――これは私の最大の希望である――とすれば、それは私の死においてのほか不可能であろう。仮に私が百万年生きながらえるとしても、私はこの世において再び彼等と会うことのないのを知っている。そのプロバビリティは零である。私はもちろん私の死において彼等に会い得ることを確実には知っていない。しかしそのプロバビリティが零であるとは誰も断言し得ないであろう、死者の国から帰ってきた者はないのであるから。二つのプロバビリティを比較するとき、後者が前者よりも大きいという可能性は存在する。もし私がいずれかに賭かけねばならぬとすれば、私は後者に賭けるのほかないであろう。
この場合、とても大きな問題は、果たして死者は「どういう者」として「死者の国」に存在しているのか?ということかな。
例えば認知症になった後に亡くなった人とかは、人生のどの時点の人格をもって死者の国で暮らしているのか?
もしも前回ちょっと触れたアリスのように自己を認識できないまま死んだとしたら?
執着する何ものもないといった虚無の心では人間はなかなか死ねないのではないか。執着するものがあるから死に切れないということは、執着するものがあるから死ねるということである。深く執着するものがある者は、死後自分の帰ってゆくべきところをもっている。それだから死に対する準備というのは、どこまでも執着するものを作るということである。私に真に愛するものがあるなら、そのことが私の永生を約束する。
ここは拙者が初めてこの本を読んだ時に、最も引っかかった箇所である。
三木大先輩は、郷里龍野での子供時代から敬虔なる仏教徒だったと、拙者は聞いておった。
仏教では、この世への執着を煩悩と捉え、それを捨て去ることこそ往生への王道だと説いている。
ね、矛盾するでしょ?
ということで、その遺稿『親鸞』を覗いてみると⋯⋯こんなふうに書かれていた。
(略)無常感は唯美主義と結びついて出世間的な非現実主義となった。『方丈記』の著者のごときもその著しい例である。
これに対して親鸞はどこまでも宗教的であった。宗教的であった彼は美的な無常思想にとどまることができなかった。次に彼の現実主義は何よりも出家仏教に満足しなかった。無常思想は出世間の思想と結びつく、これに対して彼の思想の特色は在家仏教にある。(略)親鸞には無常の思想がない。その限りにおいても彼の思想を厭世主義と考えることはできない。
親鸞においては無常感は罪悪感に変っている。自己は単に無常であるのではない、煩悩の具わらざることのない凡夫、あらゆる罪を作りつつある悪人である。
(略)
外には悟りすましたように見えても、内には煩悩の絶えることがない。それが人間なのである。すべては無常と感じつつも、これに執着して尽きることがない。それが人間なのである。弥陀の本願はかかる罪深き人間の救済であることを聞信している。しかも現実の人間はいかなるものであるか。
「まことに知んぬ、かなしきかな愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利の大山に迷惑して、定聚のかずにいることをよろこばず、真証の証にちかづくことをたのしまざることを、はづべし、いたむべし。」
親鸞の真骨頂は、「悪人正機説」だよね。
その「悪人」とは、ヤンチャとか半グレとか闇バイトとかのことじゃなくて、自分のことを善人だと思ってない人のこと、迷いや悩みを抱えた状態でなんとか生きてる人たち。
おお、身共たちのことではないかw
そうなのだ。
生きてる限り、善人として完成することはできないし、そもそも何が善だかも分かったもんじゃないのだ。
身共も、人間誰しも死の瞬間まではずっとペンディング状態だと思っている。
かく云う身共は仏教の専門家ではないし、特に信仰心があるわけでもないが、日本においてインド仏教がこんなにも変容した事実を実に面白く思っている。
(そういえば、かつてスリランカに住まいしていたころ、現地のインテリ・ジャーナリストと『スッタニパータ』についてお話ししていた時、このことを話すと膝を乗り出して質問攻めにあってちと困ったものであった。w)
信仰心も結構だが、何よりもまず生きた人間でありたいものだ。
死の恐怖を信仰によって誤魔化す⋯⋯いや失礼、解消するなんてのは、嘘っぽいというか、虫が良すぎるというか、金さえ供出すればなんとかなるというか、とにかくなんか鷺っぽくね?
宗教であれ哲学であれ思想であれ、なんであっても、「究極的な固定した真理なんてものはない」、ということを無視し過ぎているんじゃね?みたいな。
いろんな可能性、プロバビリティを想像し、自己を創造して(というと実存主義っぽく聞こえるかもだけど)変容を楽しんで行くこと。
それが生きているということだと、拙者は思う。
そして、その変容のプロセスは、あなたならあなた、拙者なら拙者という「唯一者」だけの、かけがえのない世界なのだ。
だからこそ、どんな他者とも繋がることができるのである。
そう、先に逝った人たちとも。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
