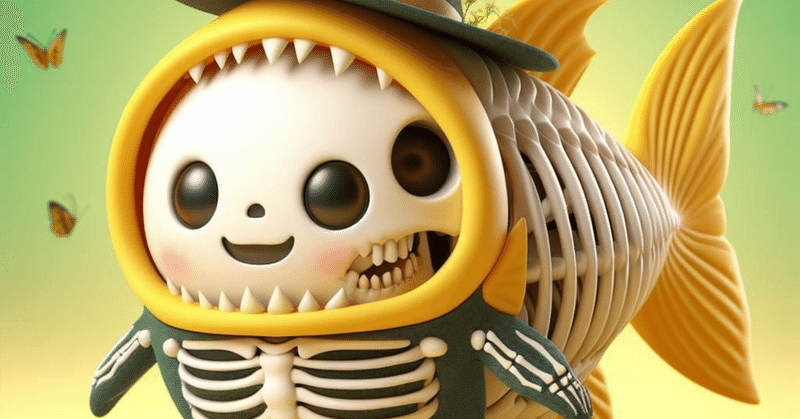
「存在不安」のからくり
前回、人生の最終目的地としての死についてちょっとお話ししてみましたが、そもそも人生という「存在」ってなんなんでしょう?
この世の中に、自分の意思で、よっこらしょと「存在」し始めた人は一人もいない(はず)。
気がついたら「存在」していたというのがフツーでしょ。
それだけに、存在は自分の意識や意図を超えてるわけだよね。
と同時に、この「未知性(了解不可能性)」つか、「わからない性」は一方でさまざまな想像や妄想を創り出す源泉ともなりうる。
哲学にしても宗教にしてもカルトにしてもオカルトにしてもそうだけど、それぞれの個人特有の「存在観」や「存在感」も産まれてくる。
死は観念である、と私は書いた。これに対して生は何であるか。生とは想像である、と私はいおうと思う。いかに生の現実性を主張する者も、飜[ひるがえ]ってこれを死と比較するとき、生がいかに想像的なものであるかを理解するであろう。想像的なものは非現実的であるのでなく、却って現実的なものは想像的なものであるのである。現実は私のいう構想力(想像力)の論理に従っている。人生は夢であるということを誰が感じなかったであろうか。それは単なる比喩ではない、それは実感である。この実感の根拠が明かにされねばならぬ、言い換えると、夢或いは空想的なものの現実性が示されなければならない。その証明を与えるものは構想力の形成作用である。生が想像的なものであるという意味において幸福も想像的なものであるということができる。
この「構想力」によって、人は自分の人生を作っていく。
自分の人生だけじゃなく、世の中の仕組みとか、構造物とか、発明とかも、この「構想力」のおかげなり。
その点、以前もちょっと触れた養老孟司氏の「我々は人が想像した世界の中に住んでいる」的な表現は上手いと思う。
今あなたや拙者が住んでたり働いてたり学んでいる建物そのものが、すでに人の想像によって「現実化」された「世界」(の一部)なんだし、経済システムその他の社会システムだって、学問やお勉強のコンテンツや体系にしても、みーんな人の構想力なしには「存在」しなかったもんだもんね〜。
で、そういう諸々の「存在」は、あなたとは関係なしにそこにある。
つまり、あなたが「存在」しなくなっても「存在」するかもしれないし、「存在」しなくなるかもしれない。
(とか言うとテツガクっぽいけど、ごくフツーにその辺の建物とか公園とか駅とかを考えればわかりやすいでしょう。)
ところが、そういう想像ができる、この「自分」は一応「存在」してはいるけれども、いつどうやってどのように消えるかわかったもんじゃない。
そこんとこが不安の源になっている。
この「存在不安」ということについては、数多の哲学者たちがいろんなことを言ってるけど、誰一人として確実な「存在」を示した人はいない。
てか、示せるはずがない。
(だって、人間だものw)
だけじゃなく、実はこうした根源的な問題には、無理やり結論を出してはいけないのである。
ネットや雑誌でやってる人生相談ぐらいならまだしも、生きてることや死ぬことについて「答え」なんて出しちゃダメw、つかありえない。
ま、人生相談っていうのは、そもそも世の中には自分がまだ知らない「答え」があると信じて、誰かに「答え」を授けてもらおうという人々のためにあるものでしょ。
拙者もそれを弁えた上で、それなりにネット相談に応じてきたけれども、答えは必ず現実的な情報か、それにつながるものに限るよう心がけていた。
例えば、認知症に関係した悩みなんかだと、公的支援情報、成年後見人制度情報、遺書作成情報、とかね、具体的で現実的なことが重要でしょ。
(実際の治療などの心理学的要因における現実的対応と、精神論とは全く別物だし、そんな一時間や十時間ぐらいで話せるものではない。)
その点、
生きる意味なんてあるんでしょうか?
みたいな話になってくると、
さあ、どうなんでしょうねぇ
としか言えない。
生きる意味なんてありません、それは自分で作っていくものです。
とか言えばもっともらしくは聞こえるかもだけど、なんの答えにもなってないしw
それより、実は「悩み」そのものが全て「作られたもの」なんだよ。
人は不安だったり不安定だったりする時、何かにしがみつこうとする。
ちょうど溺れかけた人が藁にもすがる、ように。
しかも、その時々に気になっている不安(漠然とした霧みたいなもの)の中に、なんとなく「悩み」という幻影を想像して、その幻影が自分を脅かしているんだと思い込みたがるんだね。
To be continued
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
