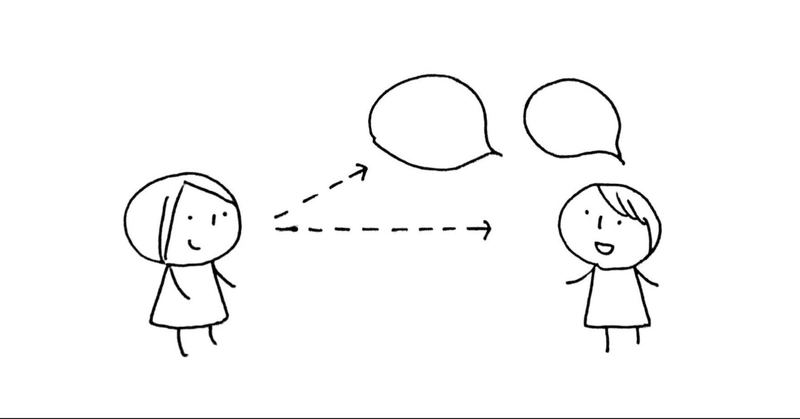
認知症以前の「エゴ」との対話
人間の死生観ということについて考えるとき、最も大きな問題は認知的能力ということになるんじゃないかな。
つまり、肉体的に「存在」していても、認知能力が十全じゃないと、果たしてどこまでその人として「存在」しているのか?ということになってくる。
2014年公開のアメリカ映画『アリスのままで』(原題: Still Alice)って観たことあります?
主人公のアリス・ハウランドはコロンビア大学で教鞭をとる50歳の言語学者。ところが、ある日の講義中に単語が出てこなくなったり、ジョギング中に道がわからなくなるなどの症状が出てきて、医師から若年性アルツハイマー病と診断される。
医師である夫ジョンと3人の子どもたち家族の介護もむなしく、アリスの記憶や知識は日々薄れていく。
そんなある日、彼女はかつてパソコンに残したビデオメッセージを発見し、自分が自分でいられるために、画面の中の自分自身が語ることを実行しよう決意する⋯⋯。
身共はこれより20年ほど前に某コンピュータメーカ販社に勤めていたころ、「抱っこできるパソコン」とか「自声で喋って対話できるコンピュータ電話」とか、いろいろとアイデアを練っていたことがあるんだけど、「ああ、惜しかったなー」とか思った。
大企業というのは面倒臭いところで、ちょっとした進言も縦割り行政で無視されちゃったりするんだよね。
今ならAIでかなり精巧な「ヒューマニティ・コンピュータ」が比較的簡単にできちゃうだろうな。
なんでそんなものが必要だと思ったかというと、当時、認知症が急増する気配がすでにあったのと、延命治療の問題が起きていたから。
その後、リビング・ウィルというコンセプトが広まっていったものの、それはあくまでも最終段階でしょう。
それ以前にも命は続いているわけだよね。
家族や友人・知人は認識できなくなっても、自分は認識できるよね、多分。
そしたら、せめてギリギリまで自分(過去の自分)と対話できたらいいのに、と思ったんだよね。
「懐かしい人」としての自分と。。。
「抱っこできるパソコン」は、もちろん柔らかな素材で包むよう作るつもりで、例のハーロウの実験で使われたタオル地の母ザルからヒントを得た。
あれはただの人形みたいなものだったわけだけど、その内部に対話機能を持たせたコンピュータを仕込んで、その人の会話パターンを記憶させておけばいいんじゃないかと。
その後、別のコンピュータ・メーカーから「相棒」をもじった名前の(ソフト素材ではないけれど)ペットロボットが発売されて、今でも愛用してる人たちが少なくないとか。
今は人間よりペットの方が身近に感じられるという人が多くなってるようだけど、それも「エゴ絡みの命の流れ」と絡んでいるだろうね。
アリスも「自分が誰だかわからなくなる日もある」と言ってるし。
だからさ、自分を認知できているうちにエゴを外在化させるといいんだよ。
そしたら、少しは自分自身のエゴをゆったりと愛せるようになるかも。
しかも人生最高の親友として。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
