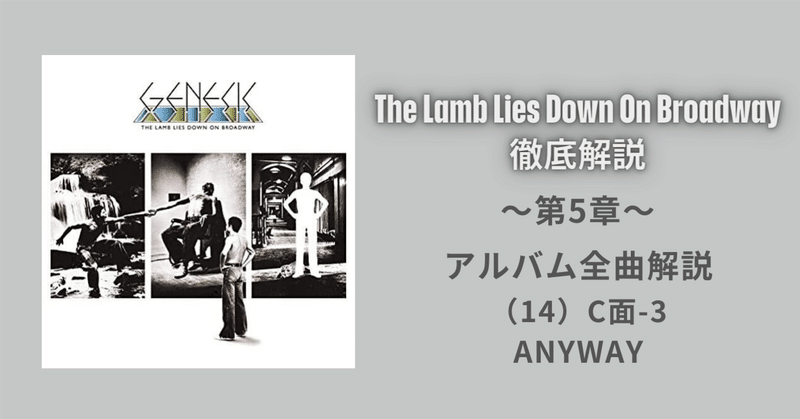
〜第5章〜 アルバム全曲解説 (14)C面-3 Anyway
トニー・バンクスの印象的なピアノで始まるこの曲は、Lylywhite Lilith 同様、彼らがそれまでのアルバムに収録していなかった、かなり古いレパートリーを流用して作られたものです。崩れてきた洞窟の岩に埋もれ、死を待つ状態となったレエルの心境が歌われますが、割と平易な言葉で歌われた Lylywhite Lilithとは違って、ここでのピーター・ガブリエルは絶好調のようです。この場面、この曲のイメージとちょっと違うのではないかとずっと思っていたのですが、これは、歌詞に歌われる「死に直面した諦めの心境」を静かに表現したものなのですね。
【テキスト】【歌詞】とその内容
光に向かって石を投げてしまった結果、レエルは落ちてきた岩に埋まってしまうわけです。
"This is it" he thinks, failing to move any of the fallen rocks. There's not much spectacle for an underground creole as he walks through the gates of Sheol. "I would have preferred to have been jettisoned into a thousand pieces in space, or filled with helium and floated above a mausoleum. This is no way to pay my last subterranean homesick dues.(*1) Anyway I'm out of the hands of any pervert embalmer doing his interpretation of what I should look like, stuffing his cotton wool in my cheeks."
「これがそうなんだ」と彼は思う。落ちてきた岩を動かすことはできなかった。地底のクレオール人が冥土の門をくぐっても、見るべき光景はない。「これなら宇宙空間にばらばらに放り出されるか、ヘリウムで満たされて霊廟の上を漂うほうがよかった。これでは最後に地底でホームシックにかかったことの、償いができない。いずれにせよ、あの変態死体処理師の手から逃れられたわけだ。自分で自分の頬に綿毛を詰め込むのだ」
通常の死を迎えないで地底でひとり岩に埋もれて死んでいくことを皮肉いっぱいに表現しているという感じです。underground creole は「地底のクレオール人」と訳しましたが、creole と頭文字が小文字で表記されているため、本来のクレオール人というよりは、混血人種の代名詞的な表現で、要するに混血のレエルのことを表現をしているのだと思います。ここでレエルはもう諦めの心境になり、その気持ちが切々と歌われるわけです。
All the pumping's nearly over for my sweetheart
This is the one for me
Time to meet the chef
Oh boy, the running man is out of death
全ての苦難はもうすぐ終わるんだ、恋人よ
これこそが僕にはお似合いなのさ
料理人に会う時が来たんだ
おお、死から逃れた男がいるぞ
と、まだ生きているけど、レエルは死を覚悟しているわけです。
Feel cold and old, it's getting hard to catch my breath
It's back to ash
"Now you've had your flash, boy"
The rocks, in time
Compress your blood to oil, your flesh to coal
Enrich the soil, not everybody's goal
寒さと年齢を感じ、息をするのが難しくなってきた
再び灰へと戻る
「おまえの輝ける時代は終わったな、若いの」
岩は時とともに
君の血を油に、肉を石炭に圧縮する
土壌を肥やすのは、全ての者の目標ではないのだが
Anyway, they say she comes on a pale horse
But I'm sure I hear a train
Oh boy, I don't even feel no pain
I guess I must be driving myself insane
Damn it all!
とにかく、彼女は薄い色の馬に乗って来るらしい
でも僕には汽車の音が聞こえるような気がする
おお、僕はもう痛みさえ感じない
自分で自分を狂わせているに違いない
くそっ、みんなめでたしさ!
Does Earth plug a hole in Heaven
Or Heaven plug a hole in Earth?
How wonderful to be so profound
When everything you are is dying underground
地球は天国の穴を塞ぐのか
それとも天国が地球の穴を塞ぐのか?
こんなに深遠なのは素晴らしいね
地下で死んで行くってときなのに
そして劇的なピアノのアルペジオに導かれた間奏のギターが入り、最後はこう歌われるのです。
I feel the pull on the rope, let me off at the rainbow
I could have been exploding in space
Different orbits for my bones
Not me, just quietly buried in stones
ロープで引っ張られてるみたいだ、虹のところで降ろしてくれ
僕は宇宙で爆発することだってできたはずだ
僕の骨には別の軌道もあった
でもそれは僕じゃない、僕はただ静かに石の中に埋められてるんだ
Keep the deadline open with my maker
See me stretch
For God's elastic acre
The doorbell rings
僕の創造主との締め切りを守ってほしい
僕が伸びてゆくのを見守ってほしい
神の弾力性のある大地へ
ドアベルが鳴る
And it's, "Good morning, Rael, so sorry you had to wait
It won't be long, yeah, she's very rarely late"
それは…「おはようRael、待たせてしまって申し訳ない もうすぐだから、彼女は滅多に遅れることはないよ」
ここでやって来る死は、she として女性に擬人化され、いよいよ死が目の前に迫った状態が切々と歌われるわけです。ちなみに、最後の And it's から会話が始まるという歌詞は、あの Supper's Ready の最後のところと同じですね。この歌詞は、The Carpet Crawlers ほどの意味不明さはないものの、実にガブリエルらしい歌詞ではないかと思います。
そしてこの展開は、多くの神話にある「クジラの腹」のモチーフであると指摘されています。以前 Cockoo Cocoon で引用された聖書のヨナの話もそうですが、英雄は危機や試練に直面して、一時的に世界から切り離された状態で、自己の発見に至ったり、新しい力を得て生まれ変わって、最終的にその試練を克服するというのが、このようなストーリーのお約束です。そして、ある意味「主人公の生まれ変わり」を示唆するこのシチュエーションが、根源的には「子宮」をイメージしているのだろうという解釈も妥当なものではないかと思います。この、ちょっと哲学的ともいえる自省を含んだ歌詞は、そういう展開を意識してのことなのでしょう。
音楽解説
この曲は、彼らが1970年頃、2ndアルバムである Trespass(邦題:侵入)を発表した後に、テレビ番組の劇伴として制作した、Frustration という曲が元ネタです。この番組は、Mick Jacksonという画家(*2)を採り上げたドキュメンタリーだったというのが定説となっています。
ところが、このドキュメンタリー番組は、結局放映されることはなく、音楽も一緒にお蔵入りしてしまいました。このとき制作された曲は4曲あり、マニアの間では、Jackson Tapes と呼ばれて、長年失われた音源となっていたのです。それが後に発見され、2008年にボックスセット「Genesis 1970-1975」のボーナスディスクとして収録されました。全部で4曲あるのですが、その中に後の曲のいろいろな断片を聞くことができます。それらの断片の中で一番最後にネタとして使われたのが、この Frustration の冒頭部分というわけです。この印象的なピアノのアルペジオは、そもそもはチャーターハウスを卒業して一度大学に進学したトニー・バンクスが、大学時代に作ったものだと言われています。そして、この Frustration では、anywayという単語も歌詞に使われているのでした。
また、この曲のエンディングで鳴っているストリングスは、トニー・バンクスがこのアルバムで初めてメロトロン以外のストリングマシン ELKA Rhapsody を使ったパートだと言われています。恐らく他のパートでも、メロトロンに被せてこのストリングマシンを使っているところがあるらしいのですが、このストリングマシンの音を生っぽく使っているのは、アルバム中この曲のエンディングパートだけかもしれません。トニーは、後のWind and Wuthering(邦題:静寂の嵐) で、ストリングマシンを多用することになりますが、このアルバムで初めてメロトロン以外のストリングマシンを使ってみたということでしょう。ちなみに、ここで使われたストリングマシンは、トニー・バンクスの私物ではなく、アイランドスタジオの備品だったものだそうです。
次の記事
前の記事
【注釈】
*1:This is no way to pay my last subterranean homesick dues. という一文は、ボブ・ディランの Subterranean Homesick Blues という曲に引っかけた表現であるという指摘があります。
*2:Jackson Tapesの楽曲は、1970年1月9日に、Mick Jacksonという画家のBBCドキュメンタリーのサウンドトラックとして、彼の4つの絵をサウンドで表現した楽曲がBBCスタジオにて録音されたと伝えられています。ところが、このMick Jacksonという画家がどうも見つからないのです。番組はボツになったとは言え、テレビでドキュメンタリーが企画される程の画家が、ネットで全く見当たらないというのはどういうことでしょうか? この少し後に活躍した同名のイギリスのテレビプロデューサーの存在は確認できましたので、ひょっとするとこれは画家のドキュメンタリーではなく、当時まだ駆け出しだったこのプロデューサーから何か頼まれて作ったという可能性はないのかなあ…?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
