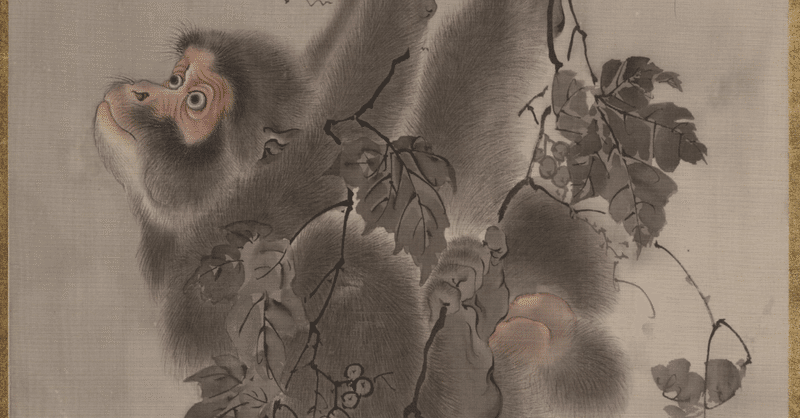
乱打、社会性怪物殺戮機械、醜悪なる夜明け、大魔神GO、
五月十八日
自然に仮面をかぶせて、仮装させてみよう。もはや、王も教皇も、司祭もなくなり、――「とうとい天子さま」などというようなものになってしまう。もはや、パリもなくなり、――「国の首都」となる。パリをパリと呼ばねばならない場合もあり、パリのことを国の首都と呼ばねばならない場合もある。
午前十一時二八分。コーヒー、柿の種チョコ。あの無教養ヤニカス糞ジジイが今夜一万円を返しにくるかがいまから心配でじゃっかん胸が痛い。俺には読みたい本や書きたいことが沢山あるわけでこんなしょうもない俗事なんかに神経を使いたくない。易々と人から金を借りるなら易々と金を返せよカス。俺が「細かいことなど気にしない」ように見えるのか? 細かいことしか気にならない人間だというのに。俺の自己愛の強さと度量の狭さをなめんな。二十代のころの俺の座右の銘は「自分には甘く、他人には厳しく」だからね。世界でいちばん性格の悪い人間をいつも目指していた。基本的に他人は不快の源泉。俺の定義によれば、友人とはその不快度が他に比べて少しはマシな人間のこと。選挙に似ている。「支持政党」などない大抵の人は(たぶん)「いい候補者」なんかではなく「少しでもひどくない候補者」に一票を投じる。ウンコ味のカレー、カレー味のウンコ、ちょっとだけカレー味のウンコ、ちょっとだけウンコ味のカレー。もっとも、「バカと老人に出来る社会貢献は選挙に行かないことと早めに死ぬことくらい」だと思っている俺は投票所なんかには行かないけど。ああ麗しき「民主主義社会」。クマのぷう様脱糞事件。
クリストフ・ニック/ミシェル・エルチャニノフ『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』(高野優・監訳 河出書房新社)を読む。
著者らは、1960年代前半にS・ミルグラムによって行われた服従実験(通称:アイヒマン実験)のようなことをテレビのクイズ番組を装って行った。本書はその報告書。その細かい設定については面倒くさいので省く。前者における権威は科学者で、後者における権威は「テレビ」だ。ミルグラムの実験ではけっきょく約60%の人間が科学者の指示に従い、サクラの解答者に電気ショックを与え続けた(最大450V)。テレビ実験では約80%もの人々が最高電圧までレバーを押し続けた。これらの人々はけっして「残酷な人々」ではない(他人を苦しめることが三度の飯よりも好きだという人々ではない)。テレビスタジオという特殊な空間が「普通人々」の「判断力」を麻痺させた、ということはいちおう出来そうだ。「どこにでもいる普通の人」といった紋切り型の表現に私はいつも違和感を覚えてしまうのだけど、その違和感を詳しく解析することにはまだ成功していない。そういえばクリストファー・R・ブラウニングというアメリカの歴史学者に『普通の人びと(原題:Ordinary Men)』という本があった。ちくま学芸文庫から出ている。ミルグラムの『服従の心理』と一緒に読むべき一冊。
もう昼飯。半額で買った「ほうれんそう」という野菜を炒める。ビジネスの世界で「ほうれんそう」といえば、包茎、蓮舫、早漏のこと。ああ夏休み。美輪明宏「私の前世はピカチュウよ」。悶々。火傷には眼薬。愛のぎみっく。ウル虎の夏。近本は一番でいいじゃないの。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
