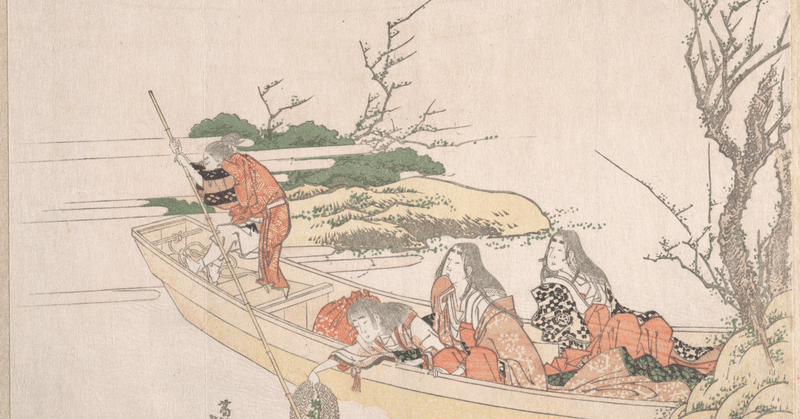
反体制的順応
五月四日
十一時起床。紅茶、ソイジョイ的なバー状の御菓子。ところで紅茶ティーバッグの詰め合わせではしばしばアフタヌーンティーだのブレックファーストだのという分類があるが、この違いがいまだに分からない。このごろいささか肩が重いんだ。本を読む時間とキーボード打っている時間が長すぎるのは明らか。派手な肩凝りに発展しないでほしい。ちかごろぜんぜん投球練習してないな。球威も制球力もかなり落ちているだろう。もうメジャーは諦めているから。
スラヴォイ・ジジェク/マルクス・ガブリエル『神話・狂気・哄笑』(大河内泰樹・他訳 堀之内出版)を読む。『なぜ世界は存在しないのか』の出版によって一般に広く認知されるようになったガブリエルと怪人ジジェクとの共著。解説によると本書収録の文章を書いたころのガブリエルはまだ二十代だったとのこと。がもうすでにすっかり<気鋭の哲学者>である。年齢のわりに参照している文献が多く、守備範囲がやたら広い。優れた哲学者とはたいへんな勉強家でもあるのだ。秀才なのだ。巷間よく言われているような、「思索は頭一つあれば出来る」という言を私は信じない。ジジェクのほうはあいかわらずの知の猛獣ぶりを発揮している。さいきんどっかで彼のインタビュー記事を読んだがやけに不機嫌そうでハラハラした。もっと自己演出といえなくもないが。ドイツ観念論やラカンみたいな怪物的思想群と付き合っていると知らぬ間に自分も怪物的になってしまう。そもそも哲学者なんて人種は皆なんらかのかたちで病んでいる。むろん哲学者でなくたって病んでいるのだが。ついでに付け加えておくとこの本の監修者兼訳者の一人として斉藤幸平の名がみえる。『人新世の「資本論」』で一躍名の知られることになる学者だ。「マルクス・ガブリエル入門」ともいうべき講演録が最後に収められていてこれがあんがい良い助けになった。だが彼のいう「世界は存在しない」論を理解するうえで重要らしい「対象領域」についてはいまだに一知半解である。これについてみっちり書かれた論考をいずれ読まねばならない。たとえば「もの」がそこにある、というとき、すでにつねにそれを認知的に包摂している「ここ」がある。私は「もの」「ここ」を区別できない。所与の「ここ」のなかから「「ここ」からは独立した<何か>」を抽出する作業はどんな認識論的契機において可能なのか。いかなる超越論的批判作業が要求されるのか。頭が痛くなってきた。この本でたびたび俎上に載せられているピッツバーグのヘーゲル学派やフランスのカンタン・メイヤスーについてはぜんぜん何も知らなかった。ガブリエルの書いた章で最もパンチ力を感じたのは、カントの「もの自体」という表象自体がその「表象」性を免れえないとする点。「それ」がそもそも認識不可能であるなら、「それは認識不可能である」という表象的把握さえ不可能ではないかと考えたところ。ここにはハッとさせられた。「もの自体」がどこかに永久に隠されているという前提にはどこか欺瞞的なところがある。すくなくとも思考停止的なところがある。この認識論的座礁を回避するためには、ヘーゲルやシェリングやフィヒテを入念に参照しつつ、なにか特別な武器を獲得しないといけない。前途遼遠にも程がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
