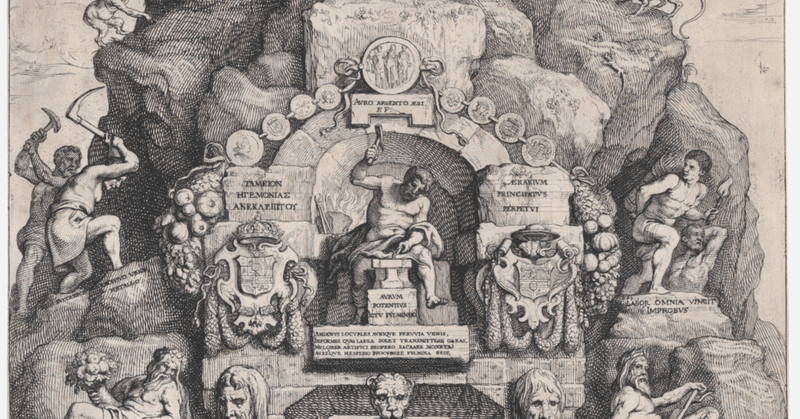
性別嫌い、女とか男とか分類されたくない、いや人間でありたくない、存在者でありたくない、骨絡み対米従属、
四月十日
「葬式のエロティシズムというものは、きっとあると思う。第一に、集まって来るのはみんなピンピンしている生きた奴らばかりだ。ぼくがモスコウにいたとき、日本語の通訳に来てくれていた女子大学生といっしょに、グリンカのオペラを見ていたら、舞台に生きた馬が登場して来たとき、『生の馬が出て来ました』と言ったものだったが、・・・・・・」
午前十時二三分。たまごなっとうかけご飯、緑茶。早く起き過ぎて気持ちが悪い。吉田拓郎の「野の仏」が聞きたい。どうせ死ぬ私がきょうも無理して生きている。種田山頭火みたいだ。やや音が気になる。でもその音の原因でもある他人を変えようなどとしてはいけない。他人は変わらない。地獄とは他人のことだ。
白井聡/内田樹『新しい戦前 この国の"いま"を読み解く』(朝日新聞出版)を読む。
対談本を読むのは久しぶり。白井の本も内田の本も私はこれまでだいたい読んでいるので彼らが何を言い出すかはおよそ予想がつく(予想を派手に裏切ってほしいと思うのだけど)。
白井のトランスジェンダー等に対する凡庸な見解はいったいどこから来るのか。さっこんの「LGBTQ運動」への懐疑を表明するのに「女装するおっさん」なんていう極端な例を持ちだすのは詭弁的。中高一貫の男子校出身だからか彼にはどこか昭和のホモソーシャル的なオヤジ臭が染みついている。「異性愛男性」はいっぱんてきに「男とはこうあるべきだ」といったジェンダー規範そのものに発情している。セクシュアリティについて内省癖のある人はそのことにあるていど自覚的でありうるが、白井のようなマチズモ人間は、その自覚されざる発情の結果、他の同性に「あるべき男の姿」を押し付けようとする。彼にとってはそうした振る舞い自体がひとつの「オナニー」なのであり、だからこれを止めさせるのは大変に難しい。つぎは北丸雄二との対談本を出すべきだろう。いっぽう内田樹は橋本治の愛読者だけあって、自分のなかの「オジサン性」にはかなり警戒的だ。「俺は男だ」的な自己愛遊戯とは一定の距離を取ろうとしている。男女という「生物学的性差」はまだ無くならないだろうけど、それが無くなっても私は何も困らない。むしろ無くなればいい。「性自認」も「性的志向」も固定されているものではない。「男らしさ」や「女らしさ」をうんぬんするにしても、たしょうのためらいがあってほしい。「らしさ」という本質規定にはどこか暴力的なものがある。
さてそろそろ図書館に行くか。早く起きたから、ねむいぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
