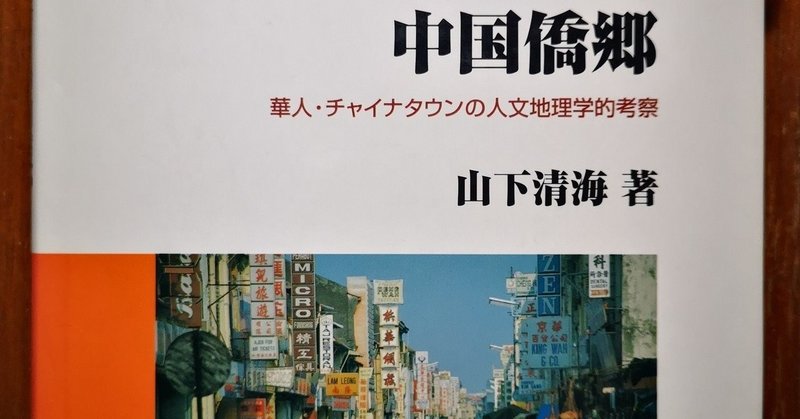
読書:東南アジア華人社会と中国僑郷 山下清海 著
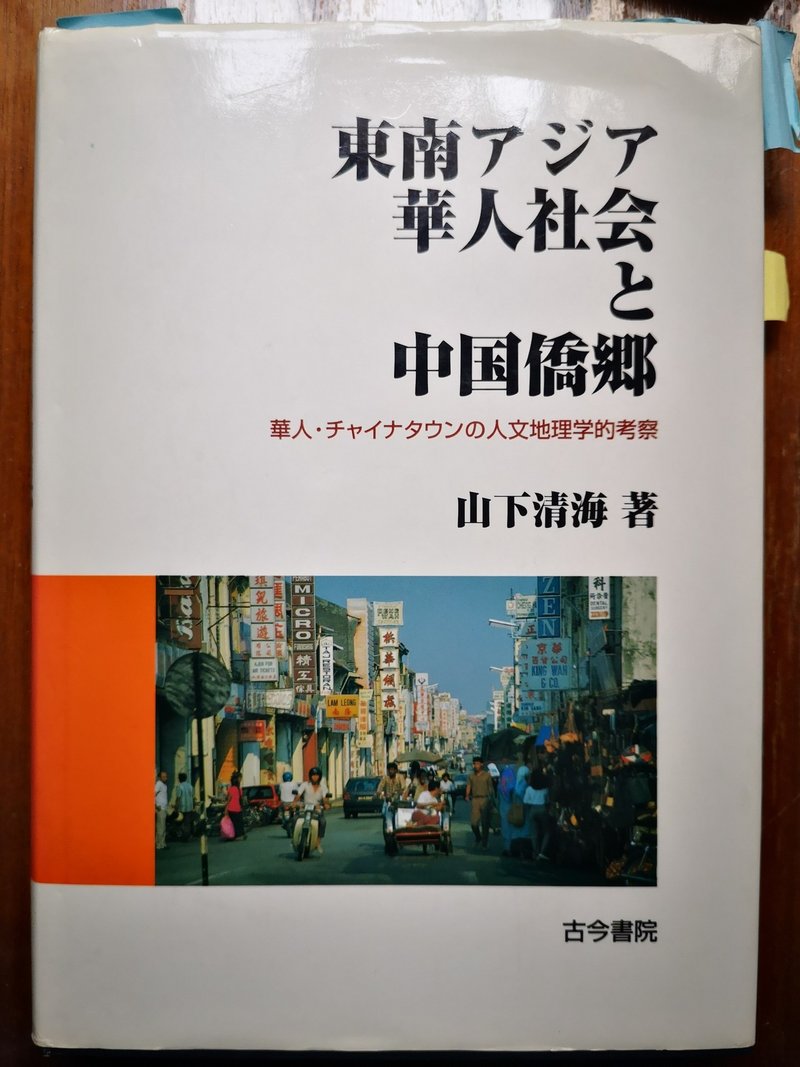
東南アジアの華人社会に加え、その華人社会とそれを構成する方言集団の故郷(=僑郷)との関係を描写している。華人社会及び僑郷は互いに影響し合いながら発展してきた。
Changは世界の華人の分布をtropical, coastal, urbanという3つの形容詞で端的に表した。熱帯におけるヨーロッパ人による植民地開発、とりわプランテーショ経営において勤勉で安価な労働力として多量の華人労働者が必要とされた。また、多くのチャイナタウンは港湾都市に形成されている。マレーシアやインドネシアでは都市そのものがチャイナタウンの様相を呈しているケースが多い。マレー半島の西武にはスズ鉱脈が分布しているが、スズの採掘に従事した華人たちによってクアラルンプール、タイピン、イポーのような鉱山都市が形成された。海南島では、かつて東南アジアに居住し、その後、故郷に戻ったいわゆる「帰国華僑」が、コーヒーを飲む習慣を僑郷に持ち帰り普及させた。本書においては、地元の中学校校長(シンガポールから22歳のときに新中国建設のために海南島へ帰った)が著者を案内した際、海南島の食堂で「kopi o」、「roti」とマレー語の呼称を用いて、ブラックコーヒーとパンを注文した様子が描かれている。サラワクの西部は旧オランダ領ボルネオと境を接し、そこはかつて金鉱業で栄え、1750-1830年にかけて多数の華人移民を吸引した。韓国においては、多くが人口が過剰傾向にあった山東省からの移民が多かった。朝鮮戦争の際には多くの華人が中国へ帰国、また華人の経済活動に対する厳しい規制強化が行われ、韓国華人の経済力は衰退していった。それに伴い韓国を離れ台湾へ渡ったり、海外へ移住する華人が増加した。台北市南部の衛星都市、永和市の中興街には韓国系華人が経営する輸入衣料品店が集中している。私の知人でも山東省出身の中国人で、台湾に親戚がいる方がいるが、文脈として関係あるのだろうか。韓国では、1992年の中国との国交正常化の後、中国語学習ブームが起こった。自分が中国に留学していた2002年頃から、今も含め中国の大学では韓国人留学生が日本人留学生よりも多い状況が続いている。韓国の漢城華僑小学校では、台湾側から無償で提供される国民小学校教材を教科書として使用している。小学1~3年は授業はすべて中国語で行われ、小学4年から韓国語と英語の両方が用いられる。最近、華人と韓国人との婚姻が増えたため、生徒の母親の半数は韓国人となっている、とのこと。福建省の夏季の気候は、福建籍華人の主要な移民先である東南アジアの気候と類似しており、高温湿潤となる。東南アジア住した華人は僑郷の伝統的な居住形態を、移住先でも展開した。東南アジアのチャイナタウンで見られるショップハウスや五脚基(華南では騎楼とも呼ばれる)はそのよい例である。とあるが、どうなのだろう。書籍により東南アジアの植民地から華南に持ち帰ったとの記述もあり、見ている限りではどちらの説もあるように思われる。日本の華人社会においては、台湾人・広東人・三江人などと並んで福建省籍華人は主要な方言集団となっている。日本における福建省籍華人の多くは福清人である。そのため、東南アジアにおいて福建人というと閩南人を指すが、日本においてはその対象が異なる。福清人は行商をしながら日本各地に分散していった。大都市に集中する広東人・三江人とは異なる傾向を持っているといえる。タイガーバームで有名な胡文虎はミャンマーのヤンゴンで生まれた客家人(祖籍は旧汀州府永定県)である。ヤンゴンには永定県出身者が多いのだそうだ。福建人の故郷のうち、集美鎮では、多くが陳姓であり、多くの華人を生み出した。多くの青年・壮年海外へ赴き、住民の多くは老人・夫人・子供となった。村中には私塾があり、その運営経費は海外に居住する華人の送金に依存していた。集美鎮が属する同安県、同安県籍の華人のなかでも有名なのは陳嘉庚(1874~1961)で、マラヤのゴム事業で大成功をおさめ、郷里に多くの学校を設立、1921年には厦門に厦門大学を設立した。
[以下は2008年に書いた記事を転載]
今とあまり視点が変わっていないのが面白い(!)
この本の著者の"チャイナタウン"という本を読んで以来、チャイナタウンに取り憑かれている。人の移動と、それに伴う文化の移動、移民同士の助け合い、現地の文化との融合、そのダイナミズムの結果としてある、いろいろな地域の現在の姿を見るのが面白い。
シンガポール華人は方言集団ごとににゴム取引は福建人、米や生鮮食料品の流通は潮州人、コーヒー店の経営は海南人や客家人とそれぞれが従事していたのだそうだ。タイには潮州人に由来する華僑が多く、アジア食材屋で売っている調味料にはタイ語が書かれているものが多いのも関連があるのだろうか。
韓国明洞にある中国大使館は、韓国が中国と国交を樹立する1992年(最近!)以前は台湾の中華民国大使館だった。その隣には漢城華僑小学・付属幼稚園がある。ここでは以前より台湾の教科書を用いて授業が行われているそうだ。現在ではお隣同士、うまくやっているのだろうか。日本が中国と国交を樹立した1972年よりも20年も後の1992年に中国と国交を樹立し、現在では日本以上に留学生を送り出している韓国の留学熱にも圧倒される。
東南アジアに移住した華人は華僑の伝統的な居住形態を移住先でも展開した。東南アジアのチャイナタウンの景観を特徴付けているショップハウスやその連続した軒下である五脚基(華南アジアでは騎楼と呼ばれる)がよい例とのこと。以前読んだ本ではチャイナタウンの五脚基(騎楼)はヨーロッパから持ち込まれたもの、更にそれが中国に持ち帰られた、と書かれてあった。どちらが本当なのだろうか、気が向いたら調べてみたい。
東南アジアに限ったことではないが、一品の料理でも歴史、社会的背景、地域の自然条件、などを反映している。それが料理の醍醐味だ。
日本のように生まれてから死ぬまで同じ場所にいるのが常識だと思っていたが、本で読んだ以外にも日本を基盤にして生活する中国人、中国に留学し事業を興す韓国人、それ以外にも様々な友人・知人と出会って感じたが世界は思っていた以上に流動的なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
