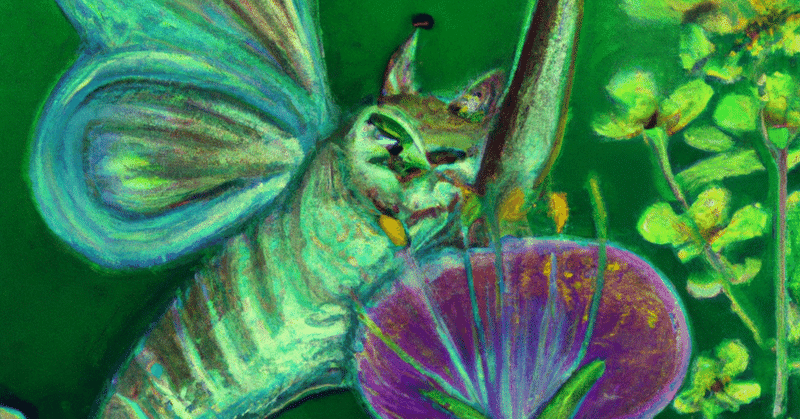
霜が降りるまでのハタラキネコたち
<前書き>
秋。菊の花に働き蜂が群がっているのを見た。刺されたら事になるので対処したいと思った。蜂スプレーを片手に持ち、どこかにあるであろう巣を探したがついぞ見つける事は出来なかった。そもそも数匹倒したところで状況は変わらないだろうと諦めてしまった。それに、奴らだって生きるために働いているだけだ。一生懸命に働いていたら突然殺されたりしたら、蜂たちだってやりきれないだろう。
同じ日の夜、コンビニの床で季節外れのコクワガタのメスがうろついていた。それを見た妻が驚いてそれを避けた後で嫌そうに「虫が全部ネコみたいだったらいいのに。」と言った。
その時、僕の頭の中に突然、働き蜂ならぬ「ハタラキ(働き)ネコ」という言葉が生まれた。それで、この「ハタラキネコ」たちが、どんな生態を持っていて、どんな風に生きているのかを考えながら書いてみたいと思った。 この前書きを書いている時点で、僕はまだこの「ハタラキネコ」たちがどんな生き物なのかわからない。だからこの小説は、まるでそれを実際に観察しているような内容にしてみる。 皆さんも、一緒に観察する気持ちで読んでいただきたい。
だが、たぶん内容はホラーだ。
1.ハタラキネコ
梅雨明けに植えた菊が熱い夏を乗り越えて、ようやく淡い紫色の花を一斉に太陽へと向けて咲いている。この品種は「もってのほか」と呼ばれる食用菊の一種で、東北地方の一部で食用としても作られているようだ。この花を摘んでさっと茹でてから酢で漬けて食べるのが一般的で、この花の甘い香りや美しい色、味は多くの人を魅了する程の旬の味である。だが花が本当に魅了したいのは人ではなく、花粉を運んでくれる虫だろう。人はそれを勝手に愛でたり食べたりして利用しているのであって、花にとっての人が都合のいい存在である、と言えるだろうか。
「ハタラキ」ネコというのは、彼らのコロニー(巣)の中での役割を指している。巣のために労働をすることを基本としたネコ、つまり「働き猫」という意味だ。今も目の前で花から花へと飛び回り、蜜やら花粉を集めている。時折クルルルルとかグルルルルというような、まるで喉を鳴らしているかのような音が聞こえるのは、きっとポカポカ陽気で気分がいいからじゃないだろうか。こいつらに気分なんてものがあればだが。
1年を通してハタラキネコたちが最も活発になるのは、夏の日差しもひと段落した10月から11月と言われている。春から夏にかけてコロニーを大きくした女王ネコが、秋の始まりには自分の後継者たる次世代の女王ネコたちを生み出す。
やがて次世代の新女王ネコたちが成長したら、元々いた女王ネコは群れの半数程度を連れて、その巣から出て行く。そして新女王は生まれ育った場所で自分のコロニーを作り始める。しかし、来るべき冬は間近であるため、急いで子供を増やして寒さを耐えるための準備をする。養蜂をやっている人達が晩夏に蜜を採取するのはそういうタイミングだからだ。その準備にハタラキネコたちが一役買っているという訳だ。ちなみに冬を越せる力があるのは新女王だけと言われているが、それは飼育されている環境下の話であって、本当のところはまだわかっていない。
ハタラキネコたちは種類によって大体が3〜7cmぐらいの大きさである。短い毛で覆われモフモフしているネコの様な体であり、手足は普通の虫の様に細く関節のある物が全部で6本ついている。背中にはちょうど蝶と蜂の間のような羽が4枚生えており、それを早く羽ばたかせることでブーンという羽音を立てて飛ぶ。羽には鱗粉がありこれはおそらくだが、蝶と同じように撥水機能や、空気抵抗に関係しているようだ。
この生き物の最も特徴的と言えるのが顔だ。ほぼ動物の猫と言っていい風体であるが、良く見ると目は複眼であり哺乳類のそれとはまったく違う。だが、虫には珍しいであろう「まぶた」のような機能がついており、動物の猫のように瞬きすることも出来る。猫の場合、瞬きをするのは親愛の情を表す為と言われているが、虫に親愛の情などあるのだろうか。
また目の上、つまり頭には猫の耳としか言いようの無い突起が2つあり、これはおそらく触覚のような物であろうと言われている。猫は耳で音を聞いているが、このハタラキネコたちのそれは、匂いや空気の動きを感知しているそうだ。
今から10年前、この生き物が発見された時、研究者たちはこれが「虫」なのか「哺乳類」なのか、はたまた新種の生き物なのかを言い切る事が出来なかった。
というのも、大部分の特徴は虫であるにもかかわらず、ハタラキネコたちはなんと胎生で繁殖しており、喉の奥にある声帯を使って鳴き声を上げる事も出来るらしいのだ。さらにある種の常温動物である事もわかっている。実際、捕まえて手のひらに乗せるとほんのりと暖かいという。こんな虫は他にいない。
口にある牙やお尻にある針で刺される事もある。特に針には毒液を出す機能があり、人によってはアレルギーで重篤な被害をもたらす。
一体、どうしてこんな生き物が今まで見つからなかったのか、そして一度見つかった後で、どうして世界中で次々と見つかるようになったのか、今でも誰にも分らずじまいなままである。
そんな訳でこのハタラキネコたちは、今でも研究者たちの興味や関心を引いてやまない。多くの研究者たちは、自分こそがこの生き物の謎に満ちた生態を解き明かす事で、歴史に名を残そうと躍起になっているのだ。
ハタラキネコは、地球上の生き物が知り尽くされてしまったような気がしていた彼らにとって、突如見つかった金鉱脈のような魅力があった。
と、まぁここまでが私がハタラキネコについて知っていることの全てである。私は研究者たちがこれまでにまとめた論文や文献を見て、おおざっぱにサマライズしただけであり、本格的に研究している訳では無い。
暇が高じてはじめた家庭菜園の花に、突然ハタラキネコたちが群がっているのを妻が見つけ、私になんとかするようにと指示して来た。命令であれば、対処法までセットで教えて欲しい所だが、いつだって命令は下るのみである。それで対処するにはどうしたら良いかと図書館で本を借りたり、インターネットで検索したりしているのだが、調べれば調べる程に不思議なこの生き物の魅力に取り込まれつつあった。
そうやって知識をむさぼる事だけをしていたところ、ついに畑仕事をしていた妻がハタラキネコに刺されてしまった。幸いにも体質的には問題無かったようで、痛みと腫れが2〜3日あったが、その後鎮静化したので大事には至らなかった。だが精神的にはそうもいかず、もはや作戦の遂行には一兵卒では不十分との事で、専門家を呼び徹底的に駆逐するようにという新しい命令を下したのであった。私はすぐにスマホを取り出して検索を始めた。
2.農学博士
駆除業社といっても、害虫だけではなく家の消毒や、ちょっとした家のお困りごとなどを頼めるような、平たく言えば便利屋みたいな存在のようだ。ハタラキネコの駆除はシーズン物だと考えれば、それ以外の事だって手広くいろいろとやらなければならないのだろう。
検索して、都合の良さそうなところへ電話をした。そして家の庭にある畑の花にハタラキネコたちが集まってしまい、妻が刺されたため出来れば早急に駆除をお願いしたい旨を伝えると、運が良い事にこれから家まで来てくれるという。家から近い業者を選んだかいがあったというものだ。
だがハタラキネコの駆除の場合は一旦状況を確認した後に、しかるべき対応策を講じる必要があるため下見が必要な案件になるようだ。すぐ来てくれるならば、ついでといっては何だがすぐに駆除してほしい所だが、段取りが必要ならば仕方がない。
電話をしてから3時間程で、駆除業社はやってきた。黒い軽のワンボックスカーから出てきたのは、定年を迎えて散歩を趣味にしていますという感じの、老人とまでは言えないが、一線を引いた年齢であろうかという男の人だった。そして降りてくるなり挨拶もそこそこに名刺を渡してきた。
ハタラキネコの事ならなんでもござれ
農学博士 飯山 照美
Dr. Terumi Iiyama
農学博士となれば、専門家と言うよりも研究者だろうか。研究が高じて駆除作業までやっているという事なのだろうか。もしかしたらお金に困っているのかも知れない。研究職はあんまり儲からないと聞いたことがあるし、大学教授になるのも割と狭い門らしい。駆除の件数さえ稼げれば、割といい商売なのかもしれない。
「では、早速ですが現場を見せてもらえますか」
飯山はまるで私の邪推を見透かすように、軽く咳ばらいをしてこう言った。別に権威に弱いという訳でもないのだが、バツが悪かったのもあって、とりあえず媚びを売っておく事にした。おそらく「先生」と呼んでおけば失礼には当たらないかな、と思った。
「では先生、宜しくお願い致します。こちらです。」
家庭菜園に案内すると数匹のハタラキネコが飛び回っていた。飯山はそっと手を出すと、驚くほど簡単に一匹のハタラキネコを捕まえた。あまりにも優しく、それでいて自然に捕まえられたため、ハタラキネコも捕まった事に気が付いていないかようだった。そして、手のひらを歩いているそれに、短く切った標識テープを結び付けた。この標識テープを目印にして後を追い巣を見つけるのだという。
突然自分の状況に気が付いたかのように、ハタラキネコは飯山の手のひらから飛び立った。どうやらテープが付いていても飛行に影響は無いようだ。テープの長さや巻く場所なども研究の成果の一つなのだろうか。飯山は立ち上がって蜂を追いかけて行く。付いて行くかどうか迷ったが、仕事の依頼主としては出来るだけ見届けるべきだろう。それに、もし危なかったら注意されるだろう。
蛍光ピンクのテープを付けたハタラキネコは途中、花や日陰の石の上で止まっていたが、どうやら家から少し離れたところにある雑木林に向かっているようであった。この雑木林は、相続の問題とかで土地の持ち主が誰だかわからなくなっており、長く放っておかれている。当然、管理などされておらず自然のままの姿に近い。そういえばいつだか、妻がこの雑木林の近くでタヌキだかハクビシンだかの生き物を見たと騒いでいたのを思い出した。そんな状態なので、やすやすと人が入れるようなところではないのだが、飯山は躊躇なくその雑木林をかき分けて入って行った。
「先生、大丈夫ですか?」
私の声に、飯山は振り返る事も無く
「そこで待っていてください」
とだけ言った。追っているハタラキネコを見失いたくないのだろう。私は飯山の言うように、そこで待っておくべきだったのだが、謎に満ちたハタラキネコの生態に少しでも迫れるかもしれないという甘い花の蜜に抗う事が出来なかった。
幸い飯山の歩いた後の草木がなぎ倒されて、ちょっとした獣道のような状態になっていたため、私もその道を行けばなんとか歩く事が出来た。一生懸命に頑張っていると、飯山が立ち止まって木を見上げていた。
「先生?見つかりましたか?」
私の声に飯山は驚いて振り向いて行った。
「危ないかもしれませんよ。」
きっとこれは、私は一応注意しましたからね。という意味だろう。
「大丈夫です、危ないようなら離れます。それより先生、巣は?」
「この木の上に来たところで、葉っぱに紛れて見失いました。でもきっとこの近くに巣があると思います。あまり大きな音を立てないようにしながら、この辺りを探します。刺激しない方が良いですからね。」
そうして、私は飯山と一緒に周辺の木々を調べて行った。草木をかき分けて、草の根を分けて・・・と言うが、これはなかなかハードワークだ。巣どころか、印の付いたハタラキネコも見つけられない。
寡黙そうである飯山だったが、見つけられない事が気まずかったのだろうか、自分からハタラキネコの生態について話しだした。
「ハタラキネコにはね、まぶたがありますでしょう?あれにはね、空気中の微細な変化や匂いを感知する役割があるんですよ。だからあれは、まぶたと言うよりも触角に近いと言えます。目と触角が同じ位置にある事で、情報の伝達を早くしているんです、あのー、その、脳へのね。ま、脳と言っても、爪の垢ほどの大きさも無いんですけどね。」
「へ、へぇ!そうなんですか、そんな事どの本にも書いてなかったな、さすが専門家の先生ですね。もしかしてそれ、最近分かった事なんですかね。」
「そうです、私が発見したんです。まだ論文にしか載せていないんで、界隈の人しか知らない事ですね。なにせマイナーですから。」
界隈の人と言うのはおそらく学会の事だろうか。良く学会などで発表されたことは業界のニュースとして報道されるが、ネット上でもこの情報は見つけていなかった。それに触角の機能は耳に見える部分がそれに当たると読んだ気がするので、それは違うんじゃないかと思ったが、ハタラキネコの種類にもよるのかも知れないので黙っていた。それに専門家に得意げに意見なぞして恥をかくなんてのは、決して褒められたことじゃない。
「ハタラキネコって良くしゃべるでしょう?お客さんは、詳しく調べてるようだから、あいつらの声、聞いたことあるんじゃないですか?」
飯山が嬉しそうに聞いてきた。そして先生と呼ばれたからだろうか、それとも専門家と呼ばれたためだろうか、少し喜々としてきた様子だ。もしかしたら、どれくらいわかっているのかを試されているのかもしれない。
「声・・・ですか?そういえば、グルルルルって唸るようなのを聞いたことがありますね。あれの事ですか?」
「いやいやあれはね、日に当たると腹の中に貯まったガスが膨張するんです。そのままにしておくと身体が破裂するかもしれないんでね、排泄口から出す時の音なんです。つまり、あいつらの屁なんです。まぁ声とは真逆ですわな。あのガスの放出が飛行能力に関係していると言ってる人もおりますがね。ひっひっひ。」
そういえばそれを聞いた時、温かい日が差していたような記憶がある。あの音が猫の様で可愛らしいと思っていたが、まさかあれが屁だとは。赤ん坊がする屁は可愛いという人もいるが、虫の屁が可愛いとは思えなかった。つくづく変な生き物だ。状況は気まずさが続いているが、せっかく専門家がしゃべりたがっているのだ、知らなかった事が聞いてみよう。
「ところで先生、ハタラキネコって胎生で増えるんですよね?そんなの常識では考えられないような気がするんですが、やっぱり虫の分類になるんですか?」
「あー虫かどうか、ね。答えにくい質問ですな。うーん、これは私の個人的な予想、なんですけどね。ハタラキネコは、なんていうかその、奇妙な進化を遂げた生物なんじゃないかなぁと思ってるんです。確かにあいつらは胎生で増えると報告されているんですが、それは”特定の状況下”と言うんですかね。絶対に安全だと言う時だけ胎生で子を確実な形で産むんです。」
「え?じゃあ・・・安全じゃないと思っている時は?」
「実はね、あいつらは卵でも子を産むんです。しかも、それを寄生の手段として利用することで、生存戦略の一つとしているようなんですわ。別の奴の体の中にね、卵を産み付けちゃうって事。このね、卵生と胎生を行き来するってところは、モンゴルハナガエルっちゅう蛙の仲間がね、卵で産んだり胎生で産んだりする事が発見されているんですがね、そいつは両生類でしょう?虫だとしたらでそんな事があるんか、ってね、我々もお手上げ状態になって議論が進んでないんです。」
額の汗を首に掛けたタオルで拭きながら、飯山は藪をかき分ける。
「だから、全く解明できてない未知の生態系の生き物、としか言いようがないんですわ。それでもってね、卵を寄生に使うってところはヤドリバチって言う蜂の種類に似てる訳でしょ?そりゃまったくもって虫の習性なんですわ。こりゃもう訳がわからんのですわ。ひっひっひ。」
楽し気に、そして饒舌でへんな笑い声の飯山をよそに、私は考えていた。
「未知の生態系の生き物」
そんなものがまだこの地球にいたなんて。
ロマン溢れる新発見というよりも、その生態を知れば知るほど、”嫌悪の影”のような物を心の中に感じていた。どこか、ザワザワすると言えばわかるだろうか。ネコみたいでカワイイ生き物だなと思っていたが、実は全く知らない生き物なのに、あまりにも不用意に近づいているのではないか、という不安が沸いてきていた。これは未知な物への恐怖とか、本能的な危険を察知しているかのようであった。
「あ、おった!印のやつ!」
飯山は年齢を感じさせない動きで、ハタラキネコを追っていく。私もその後を付いて行った。なにか腹に重たい黒い塊のような物を抱えている気がしている。そういえばいつか読んだ本にこんな一節があった。
好奇心は猫を殺す。
3.竹林
雑木林は、ちいさな小川を挟んで竹林に続いていた。飯山は一跨ぎで小川を越えると、着地と共に枝を踏んで大きな音を立てた。しばらくのそのまま硬直した後、ゆっくりと私に振り返り、あまり音を立てないようにというそぶりを見せてから、奥へと進んでいった。
管理されていない竹林は風流なんてものからは程遠い存在だ。我こそは我こそはと密集して生えているために、その間を抜けるのに苦労する事になる。足を取られるだけでなく、ところどころに生えている竹の枝葉が、足元以外の場所で通過の邪魔をしてくる。一歩進むのにも、普通の何倍ものストレスと労力が必要だ。私は汗だくになりながら、飯山とチラチラと見えては消えるハタラキネコに付いた標識テープを追った。
やがて一本の太い竹にたどり着くと、どうやらその裏でハタラキネコと標識テープは消えてしまった。
という事は、これが・・・
「いやぁまいった、こんな形とはね。」
飯山は興奮を抑えられないようで、少し震えた声でつぶやいた。専門家が見た事の無い物を見れている。となると、もしかして歴史的な瞬間ってやつに立ち会えたのだろうか。場合によっては私の名前も後世に残せるかも知れない。私は淡い期待に胸を高鳴らせた。
ハタラキネコの巣は太い一本の竹を利用して作られていた。一体どうやっているのかわからないが、硬い竹を器用にくり抜き(あるいは何らかの原因によって空いた)穴から侵入し、節を打ち破り竹のほぼ全体を巣としているようだ。
容積で言えばかなりの空間だ。身の丈20m以上のこの大きな太い竹の中が全て巣になっていると、飯山は言う。問題は、といってもこれは人間から見たらの話だが、高層ビルよろしくの構造なので入口から巣の隅まで行くのが大変そうだ。竹の中に住むなんてまるでかぐや姫みたいだな、とも思ったが、良く考えればいわば高層マンションに住んでいるんだから、むしろこいつらはお高く留まっているのかも知れない。蜂たちは自分で0から巣を作るって言うのに。
ハタラキネコたちが竹を巣にしているのは、これから冬を迎える上で合理的であるように見える。竹は他の木材と同じ様に、熱伝導率が金属やコンクリートよりも低い。そのため、外気の影響を受けにくいと言える。とりわけ寒さに弱いとされるハタラキネコにとって、簡単には外敵に打ち破られる事の無い竹は、安全と防寒をもたらしてくれているようだ。
飯山が声を殺しながらも、その興奮を抑えきれないテンションでしゃべっている。
「こんな大きなコロニーははじめて見ました。そうそう拝めるもんじゃない。これは凄いことかもしれませんよ。これまでも人間が作った構造物の中にコロニーを形成しているという報告はあったんです。使われなくなった小屋とかね、なんというんでしょうか、巣を作りやすいとでも言うんでしょうか。あいつらが入りやすい場所で、人が来ないような場所。だからとても見つけにくい。っそれがこんな自然の中にある竹の中、しかもこんなにも大きなコロニーを築いているってのはねぇ、考えられないというか、まだ誰も知らない事なんですよ。」
早口に喋り出す飯山の言葉を、出来る限り聞き逃さないようにしていると、彼は続けてこう言った。
「これは冬ごもりかも知れませんな。」
「冬ごもり?ハタラキネコって、越冬するんですか?」
「えぇ、冬を越える個体があるという事例はあるんですよ。まぁそこら辺の蜂も越冬するんでね、そんなに珍しい事じゃないんです。冬を越す虫なんてのはざらにいるんです。といってもハタラキネコで冬を越すのは、女王だけ。あとは皆、霜が降りるころに死んでしまうんです。」
そして飯山は、思い出したようにポケットからスマホを取り出すと、写真を撮ったり動画を撮ったりし始めた。それを見て自分も記録に残そうとしたが、スマホを家に忘れてきてしまっていたことに気が付いた。なんとも惜しい。これからこれを駆除するのだから、もうこの状態ではなくなるはずだ。この状態の記録はきっと貴重な資料になるだろう。
歯がゆさを感じながら、竹の巣を観察していると妙な事に気が付いた。巣となっている竹を中心として、そのまわり約2m範囲にある竹が、中心の巣の竹へと向かって傾いており、まるで三角形のテントのような形になっている。どうやら根本の近くで切り倒されているようだ。ギザギザの切り口が見えていた。それは人工的な物には見えなかったが、このように支え合うような構造であれば、真ん中にある巣の竹を、周りの傾いた竹が全方向から支える事になるだろう。
「籠(かご)か?」
飯山はそういうと上を見上げた。そして、カシャカシャと連続したシャッター音が聞こえて来た。そして、小声で言った。
「でも何のために、こんな・・・巣か?巣を揺らさないための仕組みって事か?こいつら、こんな事が出来るのか。でも一体、どうやって・・・」
それから飯山と私はしばらく観察する事に夢中で、自分たちが何をしにここに来たのかを忘れてしまっていたかのようであった。そして新たな発見と思わしきことがあれば自然と共有し合い、飯山は忙しく記録を残そうとしていた。私たちは巣の周りを歩き回り、いろいろな角度から眺めた。
だから、自分たちが彼らのテリトリーに踏み込んでいるという事。そして、相手がどんな生態を持っている生き物なのかをまるでわかっていない。という事まですっかり忘れてしまっていた。
巣からは、多くのハタラキネコたちが出て来ており、私たちを警戒しながら、まるで”観察”するかのように羽音もなく飛び回っている事に気が付いていなかった。
4.逃走
私たちが一通り満足するまで巣を観察し終わったころ、ふいにブブブという音が鳴った。そしてしばしの間があって、またブブブブブブと同じような音が聞こえてくる。その音は徐々に大きく、そして長くなっていく。
ブブブブブブブブブ。ブブブブブブブブブブブブ。ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ。
飯山と私は、互いに目配せをした後、その音がする方をゆっくりと見た。飯山は振り向きながらもしゃがんでいるようで、おそらく身を低くする方が安全だろうと考えているようだ。私もそれに倣うべきだろうか。それとも、すぐにここから走って立ち去る為に、立っているべきだろうか。
私たちの入ってきた竹と竹の隙間には、ちょうど人間一人くらいの大きさの、形を持たない物がする特有の動き、うぞうぞ、としか形容できない動きをする、「もや」があった。
言うまでもなくそれはハタラキネコの群れであり、怒れる大群衆である。号令と共に突撃しようと、息まいているように見える。そしてやっかいな事に、ちょうど私たちが来た道を塞いでいるように空中にとどまっている。
もはや来た道を行く事は許されていない。
そんな感じがする。私の汗は完全に冷え切っていた。
このブブブという音は、羽音を立てているのかと思っていたが、どうやら違うようだ。よく見ると、ハタラキネコたちは一瞬大きくなって、音の後に小さくなるように見える。まるで脈動しているようだ。どうやらの腹の部分が膨らんではしぼんでいる。飯山が言っていたやつらの屁なのかも知れない。だが、それはこんな音ではなかった。
飯山は小さくそして素早く言う。
「威嚇されています、ゆっくりしゃがんで、動かないで。」
そして私の服の裾を掴んで下へとゆっくり引っ張った。早く動く事は奴らを刺激する事になりそうである。やり過ごせるのであれば、それに越したことは無い。私は言われるがままに行動した。
すでに何匹かのハタラキネコたちは私たちの体にまとわりつき始めている。だが、すぐに刺してくるという訳では無さそうだった。
「落ち着いて。決してパニックなってはいけない。騒ぐと刺されますよ」
見れば飯山にもたくさんのハタラキネコたちがまとわりついている。私は首の後ろに手を組み、頚椎を守る様に回してガードの姿勢を取った。肌の露出している部分に手を置く事で致命傷は避けたかったのだ。そして、まるで土下座のような姿勢を取って、本当に許しを請う心境でいた。
ブブブブブブブブブブブブ。
音は耳元でなっているかのように近づいてくる。というよりももはや、私たちはこの黒い塊に飲み込まれそうになっていた。身体に当たってくるハタラキネコの数が、もうわからないくらいの多さだからである。
ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ。
叫び出してここから走って立ち去りたい。だが、それを行うリスクの大きさが私をそこに留まらせていた。今にも発狂しそうな私が今頼れるのは、専門家の飯山だけである。こんな時、専門家ならどうにかして欲しい物である。
実際には数十秒なのだろうが、永遠にも感じられるくらい長い間の後、私がゆっくりと薄目を開けて飯山を見る。
頼む、何とかしてくれ。だが飯山はハタラキネコにほとんど覆われていて、そこに人間がいるのかどうかも分からない程だった。このままじっと我慢するしかないのか。
一匹のハタラキネコが私の耳に入ろうとしてきたとき、私の理性は途端に音を上げた。この状況に耐えられるほどの強さは持ち合わせていなかった。
ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ。
「あっ!」
ふいに腰の辺りに激痛が走った。瞬間、上体を起こした私に、更なる追い打ちがやってくる。まるでボールをぶつけられたかのような衝撃が、頭と左手にもやってきた。
「!!!!!」
声にならない声が出て、私は身をかがめたまま立ち上がる。容赦ない追撃はまだ続いている。
「ああぁぁああああ!」
パニックになるな。と言われてはいた。だが、迫りくる羽音。破滅への予感。避けられないであろうという予想。そしてそれらが現実となった時。
本能的な攻撃の前では、人の理性などという物は簡単に瓦解する。あばれのたうち回りながら、死に物狂いで払い、避け、走りだした。入口に構えているハタラキネコたちの塊も、こうなってしまっては人の突破力の方が勝る。
かくして私は飯山を残して逃げ出した。
まるでスローモーションで流れる断片的なシーンの連続を見せられているかのような視界の中で、竹の間を抜け、先ほど飛び越えた小川に片足を取られて転び、それでも立ち上がり走り続けた。
耳元にはまだブブブという音が聞こえる気もするが、もはや自分の呼吸音と鼓動しか聞こえてこない。あちこちを刺され、体中には擦り傷がある。だがそれらの痛みすら無視できるほどにアドレナリンが出ている。ただただ一心不乱に走った。
そして、ついに雑木林を抜けた。幸いな事に、そこまではハタラキネコたちも追ってはこなかった。息も絶え絶えに状況を確認した私は、体中の痛みの精算が一度にやってくるのを感じる。
ブブブ。耳の奥でまだその音が鳴っている気がする。しかし、それは恐怖のあまりに聞こえてしまった幻聴だった。頭を振り、手を闇雲に頭の周りで動かして、息を何とか整えた。
5.籠(かご)
飯山はどうなっただろう。努めて冷静に対処法を伝えようとしてくれた飯山。あの状態でも冷静さを失沸かったのは、専門家としての意地だろうか?だとしたら、さすがに見上げた根性である。
私がこれだけ刺されたのだから、あの状況で飯山が刺されていないという事は無いだろう。もし仮にアナフィラキシーショックでも起こしていたら、そのまま死んでしまう事もあり得る。
かなり大きなダメージを受けてしまったが、だからと言ってこのまま放っておくという事はできないだろう。命の危険がある。
私はなるべく急いで家に戻り、蜂スプレー片手に、現場に戻る事にした。それに万が一に備えて救急車を呼ぶために、妻に声を掛けて置いた。妻は私を見て驚いていたが、詳しい事情を話している程の時間はない。とにかく蜂に襲われて大変なんだと伝えて、すぐに戻らなくてはならないと告げた。
こんな蜂スプレーがハタラキネコに効くのかもわからないし、正直お世辞にも十分な装備であるとは言えない。せめてもの対抗策として厚手のジャケットとゴーグルとマスクをつけてきた。これも役に立つのかはわからない。
しかし時間が掛かった。それはあいつらに刺されたから、というよりも、無茶苦茶になって転んだため、どうやら足首をくじいていたからだ。思うように足が出ない状況で、しかも雑木林を越えて行かなくてはならない。
先ほど転んだ小川を越える時、最初のように飛び越える事は出来ないと思った。きっと着地の時に足首に掛かる負担を思うと、その痛みの方が濡れる事よりもはるかに辛い事だと思えた。ザブザブと小川に入り、濡れて重くなった靴を何とか引き上げた。詳しく見てはいないが、きっと右足首は張れ上がっているのだろう。小川に入った時、その水の冷たさがその炎症の熱を奪っていくのを感じた。しばらくそこに立っていたくなるほどの心地よさすら感じる。
竹林に入る。あんなに無理やりに走り抜けて来たのに、まるで何年も誰も通っていないかのように、竹は行く手を阻み続ける。足をちゃんと上げないと、短い竹につま先をぶつけてしまう。普段ならちょっと躓くくらいだが、今は事情が違う。その度ににぶい痛みを抱えてしまう。それでも歯を食いしばりながらも進むしかなかった。
やがて大きな竹の巣が見えて来た。あの忌まわしい音は聞こえてこない。どうやらハタラキネコたちも落ち着いたようである。飯山の姿を探す。彼がうずくまっていたところに目をやると数十匹のハタラキネコが、ひっくり返った状態で6本の足を天に向けて横たわっている。あのもみくちゃの中で死んでしまった奴らだろう。
だが飯山はいない。「先生?先生いらっしゃいますか?」
あまり大きな声は恐怖の為に出せなかった。すぐそこに奴らがいる。同じにの轍を踏む訳には行かない。呼びかけへの答えは無かった。
私と同じ様にここを逃げ出したとしたら、この辺りにまだいるとは思えない。やつらが追ってこれなくなるまで距離を取るはずだ。ただ、雑木林を来るときもここまで来た竹林でも誰ともすれ違わなかったし、そもそも道という道がある訳でもない。
そうすると一体、彼はどこに行ってしまったというのか。それとも、たまたま私とは入れ違いになっただけで、私の家くらいまでは戻ったのだろうか。そこには彼の車が停めてある。戻るとしたら、そこだろう。
正直、それ以上の時間この場所にいる事は相当の勇気が必要だった。少しでも空中を飛ぶものが視界に入れば、どうしても身構えてしまう。それが枯葉かなにかでもだ。
私は自分に都合の良い論、つまり、飯山は私と入れ違いで家に戻っている。という物を確かめるため、そこからゆっくりと立ち去った。少なくとも、この心もとない装備で奴らと戦わなくても良いのだ。そう思うだけで、体中の痛みも少し和らぐような気がした。
道中、飯山がその辺で倒れていたりはしないかとあたりを注意深く見まわしてもいたが、ついぞ見つけられなかった。そして、家に再度戻ると、心配そうな妻と救急隊員が私を見つけるなり近寄ってきた。そこで私の都合の良い論は、やはり都合の良い論でしかなかったことを知った。
事情を説明すると応援で警察がやって来た。そして私は応急処置の後、現地へと一緒に向かった。もし飯山が危機的状況なのだとしても、まだ助けられるかもしれないからだ。
私たちが巣があった場所にもどっても、そこにはただ竹があるだけであり、あの妙な形の竹の巣は見つけられなかった。そんなはずがないと私はアチコチを歩き回ったが、体力の限界が来てしまいついに歩けなくなってしまった。あとは警察が捜索してくれるという事で、一旦、私は病院に向かう事になった。
警察官に肩を借りて、竹藪を抜ける時、またブブブという音を聞いた気がした。だが、私には振り返ってそれを確かめる程の余裕はもう無かった。
ふいに飯山が言っていた言葉が思い出される。
「籠か?」
そういえば、籠にも見えなくはなかった。だがどちらかと言うと、籠というよりは、もっとこう、虫籠と言った方がふさわしい形だった気がする。虫籠も狭い入口から捕まえた虫を入れて、入口は塞いでしまう。捕まえた虫は、その籠の中を歩き回る。籠は鳥でも虫でも、捕まえて置くための物だ。何のために?鳥や虫を飼うためだ。飼ってどうする?飼って、ペットにする?何のために捕まえる?それは・・・”観察”するため?何かに相応しいかどうかを観察していた?
「冬ごもりかも知れませんな」
飯山はそうも言っていたかもしれない。冬の間、多くのハタラキネコは死んでしまうと言う。だが、巣が生き残るために、冬を越すため、晩夏に多くの蜜を溜める。
巣・・・巣の中だ。
じゃあ、飯山は蜜の代わりって事か?人間を食う虫というのもいるだろうが、ハタラキネコもそうだと言うのか?体が動かない分、思考だけは働いている。
バカバカしい、どうやって人間をあんな竹の中に入れる事が出来ると言うんだ。ハタラキネコにそんなことが出来るってのか?人間をバラバラに切り刻んで、ちょっとずつ巣の中に入れる。そんな事が?
巣の竹を支えていた周辺の傾いた竹は、根本近くでギザギザに切り倒されていた。あれはハタラキネコがやった事だとしたら?竹を切るぐらいだ。人間の体ぐらいは切れるのかも知れない。私は切り刻まれて巣に運ばれる飯山を想像して気分が悪くなった。
だが、何のために。これだけ自然が残っているところであれば、エサになりそうなものはいくらでもある。なんだって人間を巣に運び入れるって言うんだ。
もちろん考えても分かりっこないのだが・・・
私はそのまま病院へと運ばれて行った。
6.春の息吹
病院では傷の消毒と、念のためにアナフィラキシーショック用の薬を処方された。エピペンという奴だ。あとは打撲や捻挫はしばらく経ってから様子見の為に通院する様にと言われ、2日で退院となった。
家に帰るとまだ飯山の車はそこにあり、警察も捜査をしながら、再度事情を聴きたいとかでまた私のところへと尋ねて来た。どうやら私が嘘を言っていると思っているようで、同じことを何度も聞かれた。が、そう思われても癪に障るので、その度にきちんと受け答えをし、必要であれば再度捜索の現場へと警察と共に足を運んだ。
捜索は1週間が過ぎ、2週間目へと入ったが、飯山はそれでも見つけられなかった。そして、2週間目が終わる頃、警察は捜索の打ち切りを決めた。そして1か月を過ぎるまでに、飯山の乗ってきた車は警察署預かりとなり、目の前から無くなった。
目の前から物が無くなると、私も妻も、そして周りの人達もそれほどその話をしなくなった。そして、ほどなくして飯山の痕跡は私の思い出の中にしか残っていない状態になった。
やがて季節は冬を迎えた。冬の寒さは例年通りで、それなりに気温も下がり、それなりに積雪もあった。一度、私は熱を出したことがあったが、それ以外はいつも通りに過ぎて行った。
そしてもうすぐ春になろうかというタイミングで、私はこの春に花を植える気にはならなかったし、虫が寄ってくるような植物を植えるような気にもならなかった。そして妻にもそうすべきではないと強く言った。
妻は残念そうだったが、せめて畑に防草シートを貼ってほしいと言ってきた。たしかにそのままにして何も植えないのであれば、たちまち雑草だらけになってしまう。そうすれば、当然虫も寄ってくる。至極全うな意見だ。
私はホームセンターで買ってきた防草シートの端っこを畑の隅にピンで留め、ロール状のそれを伸ばして畑を覆って行った。途中、風にあおられながらもやり直したりして、あれやこれやと格闘したが何とか必要なところへは貼り終える事が出来そうだった。
その時、ふっと視線を感じて、後ろを振り向くと、そこには飯山が立っていた。だが、全裸で汚れており、髪の毛もひげもボロボロであった。
「うわ!」
思わず叫んでしまったが、無理もない。行方不明の農学博士だったような偉い人がこんな姿で現れたのだから。驚いて固まっている私をよそに、以外にも飯山の言葉ははっきりとしていた。
「巣の駆除は終わりましたから。」
そして、飯山はバタリと倒れた。
私は恐る恐る飯山に声をかけ、抱きかかえて揺すった。
「大丈夫ですか!?先生、先生!?」
しかし、なんでこんなに痩せているのか。
そして、この妙な手ごたえはなんなのか。痩せているために骨ばっているのかと思ったが、人間のこんなところに骨なんかあるのか?よく見ると体中にその妙なボコボコはある。
私は、頭の中で飯山の言葉を反芻していた。
「巣の駆除は終わりましたから」
飯山はあれからずっと巣の駆除をしていたというのか?どこで?どうやって?それに、なぜ裸で?なぜ季節が変わるまで現れなかったんだろう?あれだけ警察が探したのに見つけられなかった人がなぜ?
今、飯山は病院で治療を受けている。彼が回復してから、警察による事情聴取があるようだ。それで何かわかる事もあるといいのだが。
しかし飯山が教えてくれた事の中に、もう一つ何か重要な事があったような気がする。
私はそれを必死で思い出そうとしていた。
何か、何か言っていたはずだ。
そしてあの手ごたえ。
彼の皮膚の下で何かが蠢いているかのような、あの感触。
最近、私の腰のあたりにも感じるあの手ごたえ。
あぁ、何と言っていた、もう少しなのにどうしても思い出せない。
春は、もうすぐそこまで来ていた。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
