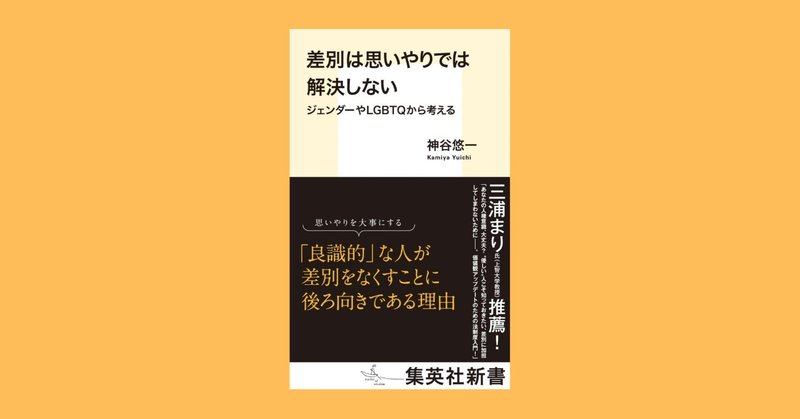
『差別は思いやりでは解決しない―ジェンダーやLGBTQから考える』神谷悠一著
「思いやりを持って、今後気を付けようと思います」という「感想」に帰結してしまいがちな、ジェンダーの講義、講演、セミナーに危機感を抱いたことから執筆されたという新書。差別を防ぐことは人権に基づくため、法整備が必要だ、と説く。
日頃から、ジェンダー、性差別についての「相手の気持ちを思いやる」「相手が傷つかないように気をつける」などという発言に、「上から目線で、他人事(ひとごと)にしている」「傷つくとか傷つかないとか(もちろん相手のそういう「気持ち」も大事だが)、そういう(だけの)問題ではなく、人権の問題、人間同士で尊重し合えているかという問題なのに」と思って気持ち悪さを感じていたので、この本のタイトルが気になって読んだ。
著者も本書に、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス。p. 26-)や、「どんな人も自分が差別をする側に回らずにいるのはあり得ない」(p. 97)こと、「気づかずに差別をしてしまうことは、誰であれ、その分野の研究者であっても例外ではありません」(p. 101)ということについて書いているが、キリンビールで女性社員が立ち上げた子会社で「見た目も色とりどりで、飲みやすいクラフトビール」(p. 34)を開発して売っている、という記述のところが残念だ。「ビールは中高年の男性が飲むもの、という固定的なジェンダーのイメージを覆し」(p. 34)とあるが、男性は(日本で一般的な)従来のビールが好きで、女性はカラフルで飲みやすいビールが好き、というのも固定観念ではあるので、その点を自覚して注記などしてほしかった。
日本では、ハラスメントについて、事業主に「ハラスメントをしてはならない」という方針を文書で明確化することなどの「防止」法制はあるが、「禁止」法制はなく、「禁止」法制がないということは、ハラスメント行為を法で直接罰する「罰則」もない(p. 54~)。一方で、「子ども同士のいじめ」については、法律で「禁止」されているという(ただし、いじめにも「罰則」はない)。禁止して罰則を設けるには、違反となる行為を細分化して明文化しなければならない。そのため、「結局、自分が加害者になるかもしれないがゆえに禁止されたくない、禁止したくない、ということなのでしょうか」(p. 58)という指摘は、まあそのとおりなのだろうなと思う。
セクシュアルマイノリティの当事者が、カミングアウトするかしないかに悩み、常に人に対して、この人にはどこまで言っても大丈夫かと気にしたり(p. 77~)、トランスジェンダーが、性別欄への記入を求められるたびに選択を迫られて苦痛を感じ、男女別のトイレや更衣室を使うときだけでなく、「普段の生活のあらゆる場面で、「あの人は女なのか? 男なのか?」という奇異の視線に晒され続け」(p. 121)たりすることは、シスジェンダー(性自認がマジョリティの人。pp. 8-9)でヘテロセクシュアル(性的指向がマジョリティの人。p. 8)の人には確かに想像しづらいところだろう。
シスジェンダーでもヘテロセクシュアルでもない(比較的マイルドな形でかもしれないが)私でさえ、男性か女性か、見た目からは判別しづらい人を目にしたとき、一瞬は「どちらだろう?」と考えてしまう。次の瞬間には、「男女二元論でどちらかに分類すべきことではないし、私がこの人を見たり、この人と関わったりする上で、そんなことは関係ないのだ」と思うのだが。それほどに、社会に巣くう男女二元論は根深い(単に私が浅はかで修行が足りないだけかもしれないが)。
「カミングアウトしない大変さ」(p. 77)には、「日常会話の些細なところにまで気を遣わなくてはならないストレスなど」(p. 77)があり、「その分の思考の負担は、肩こりのように気づかないうちに堆積して」(p. 80)いく、ということは、もっと多くの人に想像してみてほしい。私も完全には想像できでいないだろうが、子どものときから(社会の中で求められる女性像に沿う)女性の「振り」をして生きているような感覚がある(いわゆる「女性っぽい女性」とされる言動からは遠いところにいると見なされているのだろうが、それでも)。大概「自然に」できてしまうのだが、それだけに実は結構つらいことなのだと、折に触れて実感する。
直接的に性別を要件とはしていないが、実質的に性差別となる「間接差別」(p. 48-、p. 162-)も、もしあまり知られていないことなら、注目されるべき問題だ。間接差別とは例えば、女性が育児や介護を担うことが多く、女性の単身赴任が容認されづらい社会で、合理性なく、転居を伴う転勤ができることを昇進の要件とすることなどを指す(p. 48)。
間接差別のほかの例として、「一部の日本企業では、「婚姻」している/した経験があることが、昇進の暗黙の条件となっているところもあると聞きます」(p. 170)という記述が衝撃的だった。同性婚が認められていないから間接差別に当たる、というだけではなく、異性愛者でも、アロマンティックやアセクシュアルでも、仕事の実力とは関係ないはずの「結婚」が昇進要件になっているとは、理不尽なことこの上ない。結婚していなければ、人格に問題があるとでもいうのだろうか?実は、衝撃を受けたのは、この話を始めて聞いたからではなく、働き始めた若い頃に、職場のベテランの方から、「この会社では、男性も女性も、結婚している人が昇進に有利」と聞いたことがあり、その考えが単なる勘違いではなかったことが、本書の記述から判明したからだ。(以前にももしかしたらどこか別のところで見聞きしたことがあるかもしれないが、今回改めて衝撃を受けてしまった)
「「固定的な男女」しか許さない」(p. 200)と考える人たちがいて、「Xジェンダーや、ノンバイナリー(中略)など、男女どちらでもない人やどちらでもある人などを排除することにつながる懸念」(pp. 200-201)も指摘されている。
「コラム③ 戸籍制度と「『偉大なる』三角形」とは」(p. 129-)では、選択的夫婦別姓の運動に取り組んでいるジャーナリストの坂本洋子さんの論が紹介されている。それは、次のような考え方だ。
戦前の戸籍制度は、男性を戸主として、女性と子どもを無力化するもので、その「家」の三角のピラミッドは、「国家」に当てはめると、天皇を頂点とし、国民が天皇に付き従うという構図を表していた。戦後にそうした戸主権は消滅したが、依然として戦前の「国のかたち」を固守したいと考える人々がいる。その人々にとって、選択的夫婦別姓や同性パートナーに関する制度を設けることは、「国のかたち」を脅かすことであり、「国家」崩壊の危機を意味する。
まあそういうことなのだろうが、いやはや、そう考える人たちが完全にこの世からいなくなる日はいつ来ることやら。
本書は2022年8月発行だが、今なら、旧統一教会と自民党の政治家たちとの関係も、俎上に載せるべきところかもしれない。
選択的夫婦別姓や同性パートナーの制度に反対する人々が挙げる理由は、「家庭が壊れる」「子どもがかわいそう」「少子化が一層進む」など、どれも反論が容易なものばかりで、そういう人々は論理破綻しているとしか思えないのだが、本人たちには表には出しづらい「本音」と、そうした制度が自分たちの地位を危うくすると信じ込んでいる危機感があるわけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
