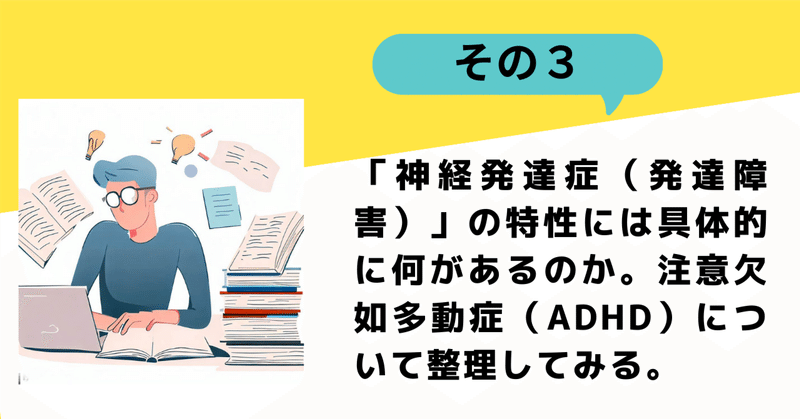
その3 「神経発達症(発達障害)」の特性には具体的に何があるのか。注意欠如多動症(ADHD)について整理してみる。
神経発達症(発達障害)に関する、現時点での自分の捉え方をまとめてみました。私の頭の中を整理するためのものであり、仮の視点を置いたものです。間違った情報があったらすみません。
私の中での、注意欠如多動症(ADHD)の特性の把握の仕方としては、まず診断基準を見ること、次にそれに準じた心理検査の項目を見ることです。そして、最近出ている書籍で挙げられている「特性(症状)」も見てみたいと思います。
それぞれで出ている特性を比較して表にしてみました(分類などにおかしい点があったらすみません)。DSM-Vの特性の基準に合わせて記載しました。

ポイントは個々の特性がありつつ、いくつかの条件の元で、診断に至るということです。一方で、書籍などでは個々の特性を、それぞれで取り扱っている形になっているので、それぞれの特性をみると、自分にも当てはまるなぁと思うことが色々と出てくると思います。グレーゾーンで日常生活や社会生活で困ったり、トラブルが起きやすい人にとって、助けになる内容だと捉えています。
ということで、順番にみてきますと、
① 診断基準からみる「注意欠如多動症(ADHD)」の特性。
診断基準は、WHOによる「ICD-10」と、米国精神医学会の診断基準である「DSM-V」をみていきたいと思います。
「ICD-10」
多動性障害(活動性及び注意の障害)➡(ICD-11にて、注意欠如多動症)
https://www.e-heartclinic.com/kokoro-info/special/motion_1.html
(ハートクリニックHP参照)
「DSM-V」
注意欠如・多動症(DSM-V-TRにて、注意欠如多動症)
https://www.e-heartclinic.com/kokoro-info/special/motion_1.html
(ハートクリニックHP参照)
ということで、ハートクリニックさんのホームページが助かります。医師が診断する際の基準になることが記載されています。
診断を下すにはいくつも条件があり、例えば、DSM-Vの「注意欠如多動症」では、6カ月持続しているか、12歳になる前からの症状はあるか、2つ以上の状況(家庭や学校など)で症状があるか、6つ以上当てはまるか、他の精神疾患の症状ではないか、などあると思います。
私の気づきとしては、DSM―Vの診断基準の項目がだいぶ具体的に症状を説明してくれている印象を受けました。また、「不適切な状況で…」「しばしば指示に従えず…」「席についていることが求められる場面で…」など、一定の価値規範によるコントロール性がある状況下で起こる症状(特性)として捉えられていたり、「だし抜いて答え始めてしまう…」「しばしば他人を妨害し、邪魔する…」などネガティブな印象を受ける表現がされている印象を受けました。
② 各種心理検査からみる「注意欠如多動症(ADHD)」の特性。
次に、各種スクリーニング検査や評価尺度の検査ですが、どういったものがあるでしょうか?
まず、注意欠如多動症(ADHD)の心理検査ですが、2つ挙げてみたいと思います。
『ASRS-v1.1』ADHD 自己記入式症状チェックリスト(スクリーニングテスト)です。
https://www.otona-hattatsu-navi.jp/self-check/adhd/
こちらは、WHOが作成したもので、「DSM-IV」を基準に作成され、無料で公開されています。対象年齢は18歳以上です。こちらの設問にも色々なADHDの特性が記載されていると思います。
次に、『ADHD-RS(家庭版)』診断・スクリーニング・重症度評価のための評価尺度です。
https://www.hospital.nagano.nagano.jp/common/img/medical/other/child_mental_center/adhd-rs-home.pdf
こちらは、対象は5~18歳で、本人ではなく親や教師が回答します。こちらもネット上で公開されています。「DSM」に基づいた設問になっているとのことです。
参照ページの設問の内容を見ると下記の特性が書いてあります。
1・学業において綿密に注意する事ができない。または不注意な間違いをする。
2・⼿⾜をそわそわと動かす。または椅⼦の上でもじもじする。
3・課題または遊びの活動で注意集中し続ける事が難しい。
4・教室やその他座っている事を要求される状況で席を離れる。
5・直接話しかけたときに聞いていないように⾒える
6・不適切な状況で、余計に⾛り回ったり⾼いところへ上ったりする。
7・指⽰に従えず課題や任務をやり遂げる事ができない。
8・静かに遊んだり余暇活動に付く事ができない。
9・課題や活動を順序⽴てる事が難しい。
10・じっとしていない。または「エンジンで動かされていうるように」⾏動する。
11・(学業や宿題のような)精神的努⼒の持続を要する課題を避ける。
12・しゃべりすぎる。
13・課題や活動に必要なものをなくしてしまう。
14・質問が終わる前に出し抜けに答え始めてしまう。
15・気が散りやすい。
16・順番を待つ事が難しい。
17・⽇々の⽣活で忘れっぽい。
18・他⼈の妨害をしたり、邪魔をする。
こちらの回答を参考に、医師が診断の判断をすることになりますが、18項目はDSM―Vの診断基準の症状の項目にそのまま当てはまる形だと思います。
③ 書籍で扱われている「注意欠如多動症(ADHD)」の特性
次に、最近出版されている書籍で扱われている「注意欠如多動症(ADHD)」の特性を見ていきたいと思います。下記の2冊を参考にしてみたいと思います。
まず、『フツウと違う少数派のキミへ: ニューロダイバーシティのすすめ』鈴木慶太著 合同出版 2023年において、ADHDに関連した特性としては下記の項目があると思います(間違っていたらすみません)。
・「モノの管理が苦手な少数派」 p46
・「落ち着きがなくじっとしていられない少数派」 p48
・「計画が立てられない少数派」p50
・「疲れやすい少数派」p78
次に『発達障害の人にはこう見えている』吉濱ツトム著 秀和システム 2023年において、ADHDに関連した特性としては下記の項目があると思います。(特にADHDの記述がなかった特性はピックアップしていません。)
・「自分の興味のある話題ではものすごく饒舌になる」p34
・「注意していても忘れ物やケアレスミスをしてしまう」p58
・「過去にも同じ失敗をしているのに何度も同じミスを繰り返す」p62
・「いくつもの仕事を整理しながら同時に進めることができない」p78
・「何度注意されても遅刻を繰り返す」p98
・「ディスクや部屋がいつもぐちゃぐちゃで片づけができない」p106
・「マルチタスクが苦手」 p114
・「衝動がコントロールできず、金銭管理ができない」p118
・「早口であちこちに話題が飛ぶ」p126
などです。
書籍の方は、その特性により、二次的に起こることも色々と記載されている印象を受けました。例えば、「疲れやすい少数派」に関しては、「多動・衝動性」により「活動量が多く、エネルギー消費が激しい」ためと記載されています。
他に、「過去にも同じ失敗をしているのに何度も同じミスを繰り返す」、「何度注意されても遅刻を繰り返す」など。
また、「いくつもの仕事を整理しながら同時に進めることができない」、「マルチタスクが苦手」というように、同時並行処理が苦手(ワーキングメモリの弱さ)という特性に関する記載もあります。
次は、自閉スペクトラム症について整理してみたいと思います。
その1 どう呼べばいいのか
その2 本当にそれは「神経発達症(発達障害)」に起因する症状なのか
その3 「神経発達症(発達障害)」の特性には具体的に何があるのか。注意欠如多動症(ADHD)について整理してみる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
