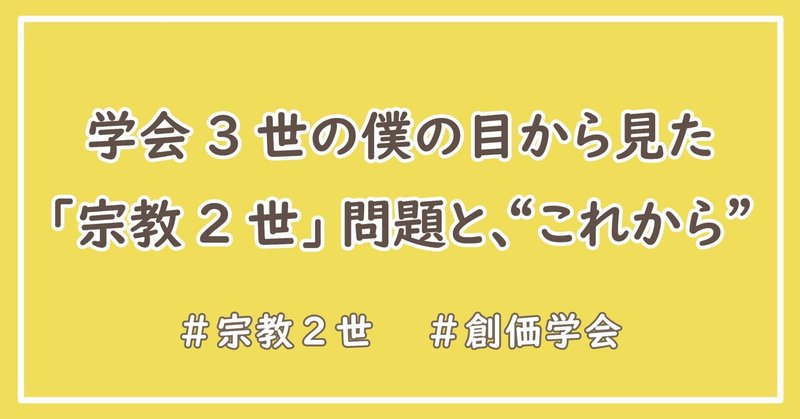
【続】学会3世の僕の目から見た「宗教2世」問題と、“これから”
事件からもうすぐ1年になる。
奈良市の近鉄・大和西大寺駅近くの交差点。
2022年7月8日午前11時31分、安倍晋三元首相がテロリストの凶弾に倒れた。
当時は、第26回参議院選挙の街頭演説中。
市内の空はどんよりと曇っていたが、最高気温は30度を超える蒸し暑い1日だった。
その場で取り押さえられた奈良市在住41歳(当時)の犯人が、「旧統一教会」への私怨を語ったことをきっかけに、メディアは「宗教と政治」あるいは「宗教2世」について一斉に報じた。
「宗教2世」という言葉が、世間に広く認知されたのもこの事件がきっかけだっただろう。
情報番組は、朝も夜も、テレビもAbemaも「宗教2世特集」を組み、電車の中吊り広告もネットニュースにも「宗教団体と関わりのある政治家」の名前が、次々と報じられた。
そんな事件から、もうすぐ1年になる。
この間、社会はどう変わり、メディアは何を報じたのか。
みなさんは最近、「宗教2世」に関する報道を見ただろうか。
中吊り広告で、特集が組まれているのを見かけただろうか。
残念ながら、一部の界隈を除いて、「宗教2世」はブームのように扱われてしまった。いくつかの心無いメディアによって、体(テイ)のよいコンテンツとして消費されてしまった。
少なくとも、僕はそう感じている。
僕は、創価学会3世だ。
申し訳ないけど(いや、別に申し訳なくはないか笑)、自分を被害者のようには考えていない。
信仰が当たり前にある家庭に生まれ、両親からは溢れんばかりの愛情を注がれて育った。創価学会の家に生まれたことを、心から感謝している。
どうしても"被害者の実態"にばかり注目が集まりがちだけど、2世に生まれてよかったと考える人もいる。
そして、そうした人の多くはあえて「感謝している」とは口にしなかったりする。
そんな危機感もあって、事件の直後に「宗教2世」について自分なりの考えをnoteに書いたところ、思いのほか多くの方に読んで頂いた。
Twitterにも多くのリプを寄せていただき、本当にありがとうございました。
noteにも書いたけど、「宗教2世問題」は創価学会も他人事じゃない。
むしろ"本丸"、解決のための"急所"といってもいいかもしれない。
ただ一つ注意したいのは、僕自身は3世だし、身の回りには学会4世も5世もたくさんいる。
つまり、創価学会はこれまでだって何度も「宗教2世」問題と直面してきたという事実だ。
僕自身は、日々の学会活動の中で信仰の歓喜を実感する青年世代の一人として、宗教2世の議論がこれからも正しく進んでいくことを心から願っています。
厚生労働省がガイドラインを公開
宗教2世を語る上で、厚労省が昨年末に公開したガイドラインは、絶対に外せないだろう。
一部メディアが被害の実態だけをやたらに煽り、一括りにされた新宗教への偏見が助長されるばかりの日々の中、“『信教の自由』に守られたデリケートな問題”に向き合い、日夜汗を流し、ガイドラインの公開にこぎつけた関係者の方々には、心から感謝の言葉を伝えたい。
ガイドラインは、以下のURLから読むことができます。
◼️厚生労働省のガイドライン
「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」
悩みの渦中にある方も、さらには、信仰活動や学会活動に肯定的に取り組む方も、必ず読んで欲しいと、個人的には強く思っています。
公開されたガイドラインだけでは読みにくさもあるので、日本大学・末冨芳(すえとみかおり)教授の解説が、とても分かりやすくておすすめです。
解説によれば、宗教・信仰によって生じうる「児童虐待」は、以下、7つのポイントに整理ができる。
(1)児童に対して宗教等行為を強制することは虐待
(2)恐怖・不安の刷り込みは虐待
(3)交友・恋愛の制限は虐待
(4)子どもとして当たり前の娯楽の禁止も虐待
(5)進路や就労の禁止・制限も虐待
(6)中絶させない、輸血を拒否することも虐待
(7) 無理やり布教活動に子どもを動員することも虐待
つまり、たとえ「信仰」という大義があったとしても、これは「虐待」ですよ、と。
子供に対して優位な立場にある親が、「やってはいけないこと」が明確になったわけです。
このガイドラインには、身体的虐待や性的虐待に加え、宗教活動を理由とした心理的虐待、ネグレクト(養育放棄や保護責任を怠ること)も含まれる。
具体的には、体罰による強制のほか、「〇〇しないと地獄に落ちる」と言って恐怖をすり込んだり、「〇〇しなければご飯を与えない」といった加害行為はもちろん、合理的な理由もなく交友関係を制限したり、進学・進路などの自由な意思決定を阻害する行為も、心理的な虐待に分類される可能性がある。
日常の生活や何気ない日々の会話の中で、自分の子供がどう感じているのか、あるいは、自分の親の振る舞いはガイドラインに照らしてみてどうなのか、考え、判断するための重要な「ものさし」になると思う。
ただこれらは、親が圧倒的に優位であることを前提に、立場の弱い子供の「権利」を守るためのものなので、極端に「こんなこといったら虐待になっちゃうかしら」と親が怯え、萎縮するのも僕はどうかと思う。
互いが自由にものをいえる信頼関係があるからこそ、相手を想う真心を伝え、なぜそれを「してほしいのか」あるいは「したくないのか」を話し、双方が納得していくプロセスが重要ではないかと思います。
また、このガイドラインは、例えば物心がつく前の「入会」や「入信」あるいは「洗礼」などを禁止するものではない。
あくまでガイドラインは「行為」への規範であって、宗教団体内の「ルール」を縛るものにはなっていない。
だからといって、何も考えなくてもいいわけじゃない。
「子供の入会」については個人的な考えもあるけど、具体的な提案はnoteの趣旨ではないからここには書きません。笑
ともあれ、課題がある限り、考え、変わり続ける姿勢は忘れたくない。
「宗教2世」問題の“これから”
色々な捉え方があると思うけど、僕自身はこのガイドラインが、何か「不自由な制限」を与えるようなものではないと考えています。
かつて「ハラスメント」という言葉が定着するときに、ある人が「モラハラ、セクハラ、あれもダメ、これもダメ、それじゃ何もできなくなっちゃうよ」とため息を漏らしていた。
そうじゃない、と僕は思う。
ハラスメントは、たまたま「顕在化していなかった課題」が、ある時を境に共通規範として明文化されたに過ぎない。
規範は、「何かを良くする」ために生まれるもので、「不自由になった」と感じるのは間違いだろう。
もともと「やっちゃダメ」だったけど、誰も「やっちゃダメ」と言わなかった、あるいは言えなかった、それだけのこと。
見つめるべきは、新たに明文化された規範ではなく、長らくアップデートされてこなかった自分自身の価値観かもしれない。
そういう意味では、2世問題のガイドラインにも同じような側面があると思う。
だからと言って、過去の出来事や発言の「責任追及」のためだけに使われてはいけない。
教科書に載る古い小説の一文が「時代にそぐわない」みたいな理由で削除されるようなことには、なって欲しくはない。
それぞれの時代と各家庭の背景に思いを馳せながら、過去の出来事を真摯に見つめ、反省と総括が丁寧になされて欲しいと思います。
なにより、ガイドラインが示しているのは、「これから」のあり方だ。
ハラスメントの明文化が、従業員の権利を守り、働きやすくなることで、会社の生産効率や企業価値が上がるように、2世のガイドラインという「ものさし」があるからこそ、親子関係の結びつきはより強く、より自由に、そして信仰はより豊かに、深化していくはずだと僕は信じています。
また、不十分な箇所や混乱を招くような文言があれば、時代や課題に合わせて修正され、アップデートされていくのが望ましい。
創価学会の両親のもとに生まれて
僕が幸運だったかもしれないと思うのは、成長過程で何かを強制されたり禁じられたり、苦痛を感じたことはなかったし、たとえ禁じられたとして自分がその言いつけをきっちり守るような人間ではなかったことだ。笑
その背景には、母親からの愛情と、互いの信頼関係があったように思う。
母親は僕のことを自分の所有物だと考えるような人ではなかったし(もちろん父親も)、むしろ小さな頃から僕の考えや行動を尊重し、尊敬すらしてくれていた。
僕もまた、共働きで忙しい母親が家にいる貴重な時間はなるべく離れたくなくて、母親が唱題をする仏間が主な遊び場だった。
年齢を重ねていっても、自分自身と同じぐらい母親は大切な存在だったし、喜ばせてあげたいと思っていた。
でも、母親のために「無理をしたり」「自分の心に嘘をついて」まで尽くしたりするようなことはなかった。
やがて僕は、自分の意志で「創価学会の信仰」を選び取ったけど、それは大学生になってからだ。学生部の活動を通して、身近な学会員や学会の事を知り、信仰による歓びと充実を知った。
だからといって、それまで(高校生まで)の期間、信仰について悩んだり、自分のアイデンティティに苦悩することも、「僕の場合は」、なかった。
自身の経験からも、宗教2世がいつかは直面するであろう「なぜ自分は信仰をしているのか」という疑問の答えを、自分の言葉で語れるようにすることは大事だと思う。
親はもちろんのこと、そのきっかけと機会を適切に提供することも“宗教側”の大切な役割の一つだ。
「なぜ自分は信仰をしているのか」という問いに対して、「親や家族がやっていたから」を超える理由をみつけたとき、その時はじめて、2世も3世も、「1世」と同じだけの誇りと確信をもって生きていける。
そしてまた、これは親子の関係性における究極かもしれないけど、
「たとえ自分の子供が、自らが信じる宗教を“やめる”と言っても、それでも我が子を愛することはできるのか」。
逆説的だけど、それだけの深い愛情と信頼があってこそ、子供は安心して正しい判断ができるのではないか、とも思います。
宗教2世の体験談を集めた、菊池真理子氏のマンガ「神様のいる家で育ちました」は、こんなセリフで締めくくられる。
「神や仏に愛されるよりも、私たち、親に愛されたかったんだから」
主に“被害者”としての体験を語る菊池氏とは、立場こそ全く違うけれど、僕自身もこの点については深く共感しています。
最後に伝えたいこと
「宗教2世」問題の議論は、今やっと始まったばかりだ。
批判的側面から語る「宗教2世」も、建設的側面から語る「宗教2世」もあるけど、僕はあくまで「宗教が社会により良く貢献する団体になっていくため」の問題提起であってほしいと願いながら、このnoteを書いています。
これから起きる変化と、時代への適応を急いだばかりに、いたずらに宗教の世俗化を促し、その価値を薄めるものであってはいけない。
悩みや厳しい現実と向き合いながら、こんなnoteを読む余裕もないほど、忙しい子育ての中で、懸命に困難に挑む方々が非難されるような文脈で語られてほしくない。
ガイドラインに照らして問題があったかも知れない当事者たちの振る舞いに、その心情や信仰心に肉薄することなく、一方的な批判に終始したくない。
そのためにも、これは学会に限らずですが、“被害者”としての意識をもつ方々への惜しみないサポートとともに、現在と今後の課題に真摯に向き合う姿勢が必要だと思う。
こと創価学会に限って話をすれば、身近な人も含め、多くの人の話を聞いてみたいと思う。
ただしもし、「より良い変化」の必要を語るなら、果たしてその人自身に心が震えるほどの歓喜と、使命に生きる充足感はあるか。誰かのための苦労を厭わず、その変化に責任を持てるだけの信仰への確信はあるかは、聞いてみたい。
そうした覚悟のない人間が、批評家気取りで語る言葉や、他人任せ、責任転嫁の議論では、人の心を動かすほどの納得感は生み得ない。
それでは、問題の一部だけを切り取り、論じただけの一部メディアとさほど変わらないからだ。
あらためて。
僕は今、自分の意思で創価学会に所属している。
課題もたくさんあるけど、僕は学会が好きだし、心から感謝をしている。
むしろ改善点があるからこそ、主体者意識をもって、自分が今いる地域で一生懸命になれるのかもしれない。
50年後、100年後を生きる学会N世の子供たちは、どんな課題を抱えているだろうか。その時代が少しでも希望の多い未来になっていて欲しい。
「信心をしていてよかった」と多くの人が語る学会であって欲しい。
いつの日か、僕が結婚をして子供が生まれたら、そしてその子供が創価学会の信仰を選んだなら、僕の子供は学会4世ということになるだろう。
もし幸運にも子供を授かることができたなら、その時はたくさんの愛情を注ぎたい。ありのままの信仰の歓喜を、遠慮することなく伝えたい。
僕の母親がそうであったように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
