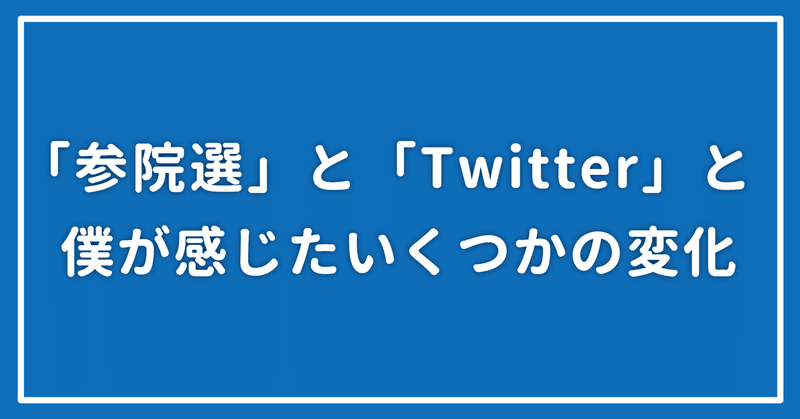
「参院選」と「Twitter」と僕が感じたいくつかの“変化”
はじめての選挙で友人から「なんで公明党なんて応援してるの?」と聞かれた。
僕は「うーん」と考えた後、「うち、学会なんだよね。」と答えた。
友人は「そういうもんなんか」と興味なさそうに言っていた。
当時は「ラッキー、なかなか言えなかった学会のことも伝えられてよかった〜」なんて喜んでいたけど、その時、友人はどう感じていたのだろうか。何を考えていたのだろうか。
そんなことをふと思い出した。
“ある1通のDM”を読んだからだ。
それが、今回のnoteを書いているきっかけです。
公明党は“学会員”ばかりが応援していると思っていた
僕は半年前にTwitterをはじめた。
少し前からは時々、noteも書いてみるようになった。
学会、公明党について書くと、否定的な意見、攻撃的な意見もいくつかあったけど、noteを読んだ何名かの方から、ありがたいDMも頂きました。
「モヤモヤが晴れて、友人へお願いする心が軽くなりました」
「言いたいことを言ってくれて感謝」
「地域の会合で紹介させてもらいました!」
等々、思ってもいない反応を頂き、ただただ恐縮の極みでした。
そうしたDMの中に1通、ある会社を経営する青年世代の方から「公明党を50人以上にお願いしました」と連絡を頂いた。しかもその方は【自分は学会員ではない】とも仰っていた。本当にうれしく、心強い限りでした。
でもそこで、冒頭の記憶とともに疑問が浮かぶ。
「あれ、この方はどうして公明党を応援してくれるんだろう」と。
学会員だから公明党を応援する、公明党を応援しているのは創価学会。勝手にそう思ってた。
でも、今回の選挙を通して、そういう考えは少しずつ改めなきゃいけないのかもしれない、と思うようになりました。
学会にあるのは、"組織票"ではない
少し話が逸れるけれど、選挙のたびに、ある程度安定した「数百万票の大きな数字」だけを見て、企業や団体と同じように「学会の組織票」なんて言葉が飛び交ったりする。
でも、実際は誰かが号令かけてなんとかなるような単純な話じゃない。学会は決して"票田"なんかじゃない。
何万票増えたとか減ったとか、選挙としての総括は必要だけど、その数字だけをみて「学会の実態」を批評しようとする記事には、もう辟易している。
一人一人が理性と感情をもって、躊躇と葛藤を乗り越えて、大切な1人にお願いをする。
その勇気の「個人票」の積み重ねが、実態を知らない"外野の人々"から見れば「組織票」に見えているに過ぎないのだと思います。
ある学会員さんのツイートにすごく共感したのだけど、「公明党を通して創価学会を理解しようとする限り学会を正しく理解することは難しい」。本当にその通りだと思います。
でも、この問題の本質って本当は「公明党を応援しているのは学会員」「公明党の票数≒学会員の数」みたいな認識が、世間の皆さんの中にあるからなんじゃないか、って思うことがある。
半分くらい正しいのかもしれないけど、半分くらい正しくない。
別に学会員だから公明党に入れなきゃいけないわけでもないし、学会員でなくたって公明党を応援してもらえたら、そんなに嬉しいことはない。
少し脱線しましたので、本題に戻ります。
僕にDMを頂いたその方に、最初に公明党の話をしてくれたのは誰だったのだろうか。
どんなきっかけで公明党を支援するようになっただろうか。
僕も、選挙のたびに仲の良い友人に連絡をしていると、向こうから「大丈夫だよ、今回は誰を応援してるの?」と聞いてくれるようになる。
涙が出るほどありがたいけれど、その多くは「学会員である僕」が「きっかけ」の役割を果たしている。
でもこのDMの方は、僕なんかよりはるかに情熱を持って公明党を語ってくれる存在が身近にいたからこそ、深い納得と共感をもって"強い味方"に変わっていったのだろう。
「きっかけ」なんてなくてもご自身が、自分の頭で判断して、自分の意思で公明党を応援している。
一度しっかり話を聞いてみたいし、僕も友人にそういう対話をしなければいけないと非常に考えさせられました。
学会員でも、学会員でなくても"遠慮せずに"応援できる政党に
党が誕生して半世紀以上。
はじめはきっと、候補者の実績よりも、支援者の血の滲むような献身と信頼、人間関係によって当選をしたのだろう。
公明党の政策理念よりも、学会員の「立正安国」を真剣に願う熱い情熱によって、党勢を拡大してきたのだと思う。
そして公明党はその期待に応えるために、時間をかけて、野党時代も、与党時代も、地道に実績を積み重ねてきた。その姿勢もまた、血の滲むような闘争だったに違いない。
そして今、公明党は与党の一角を担うまでになった。
与党だからこその批判も非難も一層強くあるけれど、「平和」「中道」「人間主義」といった党の性格や、「福祉」「教育」「生活者目線」などの得意な政策分野も、ある程度浸透してきているようにも思う。
でも、課題もたくさんある。
たとえば、公明党は「若者向け政策」に力を入れてはいるけれど、10代20代からの支持はまだまだ大きな伸び代がある。
「大衆ともに」との立党精神を掲げ続ける公明党が、今いくつかの新政党が担っている「これまで政治に興味がなかった・投票先がなかった」人たちの受け皿になるような役割をもっと果たさなくちゃいけない。
「マニュフェストの出来栄え」も「公約の実現度の高さ」もさらに広く知ってもらい、政治に失望し敬遠している人たちに、もう一度、希望と気付きを与える存在になってほしい。
それに、今はまだ「公明党」と「大衆」を繋ぐ存在として、「学会員の存在」が大きな役割を果たしている。
でもいつかは、その橋渡しの役割を誰でもできるようにならなきゃいけない。学会員だけでなく「誰もが応援できる」政党になってほしい。
それは「学会員が支援をやめる」とかそんなことじゃなくて、むしろその時は今まで以上に学会員が自信を持って公明党を応援できるようになる時だと思う。
どの党よりも衆望に応えられる政党になっていって欲しいし、公明党なら必ずそうなれるはずだと、心から信じています。
「参院選」と「Twitter」と、僕が感じたいくつかの“変化”
今回の参院選は、僕にとってはTwitterを触りながらの初めての選挙でした。
今までとは違う意見や情報に日常的に接することで、新しい発見も気づきもたくさんあった。
DMから直接お会いできた方もいたし、素晴らしい出会いもありました。
「SNSとネット選挙」みたいな難しいことは全然分からないけれど笑、今まで見聞きしてきた「自分の半径数メートル」の世界から一歩飛び出すことができました。
そうして見えてきた“外側”の意見や議論が、大きな刺激になり、自分の考え方にも変化を与えたことは間違いありません。
最後に、誤解されてしまわないように言うと、僕は「学会員だから公明党を応援する」という理由を全く悪いと思っていません。というか、僕のモチベーションの8割くらいは学会員であることが理由です笑。
僕は学会が大好きだし、公明党を創設した池田先生(創価学会の第3代会長)を心から敬愛しているし、その価値は全く揺るぎない。
でもだからこそ、より社会に開かれた価値観で、多くの人に共感と納得をしてもらえる形で、公明党のことも学会のことも理解してもらえたら良いなと願うばかりです。
ということで、今回の選挙で感じたことを忘れないうちに書いてみただけなので、とりとめのない文章になってしまいました。
読んで頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
