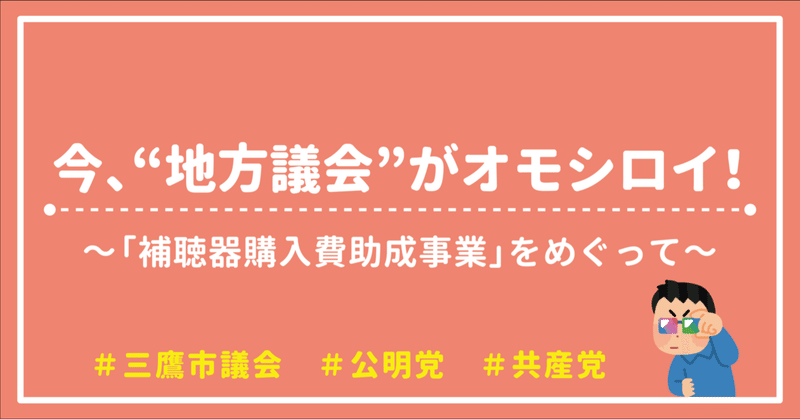
今、“地方議会”がオモシロイ!〜「補聴器購入費助成事業」をめぐって〜
《注意》このnoteは1万字くらいあります。笑
「公明党さん、そりゃないわ!!」
最近こんなツイートを見かけました。

三鷹市で2022年10月にスタートした「補聴器購入費助成事業」。
この事業成立に向けた実績の有無を巡って、日本共産党の支持者が、市議会公明党に怒りの声を上げていた。
なぜか。
2021年の三鷹市議会で、共産党が提出した「補聴器購入費助成条例案」に公明党は反対した。
それなのに、公明党が配布したビラに「補聴器購入費用の助成開始」を自党の実績として記載するなんて「そりゃないわ!」という怒りだ。
僕は、経緯を振り返りつつ、こう反論した。

公明党は確かに共産党の条例案に反対したが、公明の推進によって現実に「助成事業」は条例案よりも助成内容が拡充されて実現した。
だから、「公明がもともと助成自体に反対だった」かのような喧伝は“悪質”な印象操作だと。
三鷹市公明党の赤松市議や粕谷市議なども、相次いでこの件についてツイートをしたが、「公明が動いたという事実が、議会の議事録にない」「“水面下で動いた”なんて誰でも言える、証拠を示せ」等々、批判の声は未だ止んでいない。
特に気になったのはコレだ。

「反対したのは事実」
うーん、なるほど、その通りだ。
この言葉は、noteの最後まで覚えておいてほしい。
ほんとに公明は「動いていない」のか
数人の公明市議にDMか何かを送って経緯を尋ねれば、解決は容易だろう。
実際に僕もDMを送ってみたがすぐに返信があった。迅速な対応、ありがたし。
でも、これは万能な解決策ではない。
有権者の誰もがDMや問い合わせを送って回答を得るなんて不可能だし、他の政党の言い分も聞かなければフェアじゃないだろう。
どうせなら、誰もがアクセスできる情報から事実を検証できないだろうか。
例えば、“誰もがアクセスできる”議会の議事録から、「補聴器購入費助成事業」の成立をめぐる経緯をしりたい。
その時、いったい何が起きていたのか、誰が動いたのか。
公明党はどう動き、あるいは、動いていないのか。
半分は興味、半分はDMに返信してくれた公明市議の汚名を晴らそうと、そんな思いで調べてみました。
僕は、三鷹市民でもないし、補聴器助成の当事者でもない。
でも、そこには《地方議会》ならではの要素がたくさん詰まっていて、本当におもしろい。
これが今日のnoteの主題です。
時系列を追って確認してみる
肝心の会議録検索システムは以下のURLからアクセスできる。
興味のある方は、実際に検索をしてみてほしい。
さっきまでのツイートとか、公明がどうとか、共産党がどうかとか、一度忘れてここから先を読んでみてください。
ちなみにもし、「ややこしいことは苦手だな」という方は不本意ではありますが、「結論」まで読み飛ばして頂いても構いません。笑
それでは検証を始めていきます。
今回は「補聴器」「難聴」等の単語で検索し、その経緯を辿っていきます。
第1の波(2002年)
2022年に事業が成立したこの「補聴器購入費助成」事業だが、実は議論されてきた歴史は結構長い。なんと、20年も前から議会での質問記録が残っている。
(下線がついた文字については、URLリンクが埋め込んであるので、全文が見たい方はそちらをタップしてください)
2002/6/10 H14年 第2回定例会
公明・緒方市議が「“新生児”の難聴と補聴器に関する適切な手立て」についての質問。
議事録が残る中で一番最初に「難聴と補聴器」について議会で取り上げている。ただし「新生児」を対象としたものだ。
2002/12/2 H14年 第4回定例会
共産・大城市議が「“高齢者”の補聴器購入助成」について質問。
助成対象は高齢者に的を絞ったものだったが、当時の安田市長により「補聴器は、介護保険の給付品目外」「聞こえにくいという程度の判定が難しい」などと、反応は冷たく、却下されてしまった。
これが「補聴器購入助成」を議会で取り上げた、一番最初の質問だ。
共産党はなんと2002年から「補聴器助成」について議会で取り上げている。特に、大城市議はかなりのキーマンなので、よく覚えておいて下さい。
この後しばらくは、補聴器の問題が議会質問にあがることはなかった。
次に、議会の話題に上がるのは2008年のことだ。
第2の波(2008年~2010年)
再び「聞こえの問題」が議会で問われ始めます。
2008/6/6 H20年 第2回定例会
公明・赤松市議が「“新生児”の難聴、補聴器の対策」について質問
2009/12/1 H21年 第4回定例会
公明・赤松市議が「“高齢者”の認知症と難聴の関係」に関する質問の中で「補聴器の使用推奨の診断、聴力低下の早期発見・治療」に言及
2010/9/1 H22年 第3回定例会
共産・大城市議が「“高齢者”の難聴対策、障がい者認定による補聴器購入補助(既存制度)の周知」について質問
「新生児」または「高齢者」など対象は違えど、難聴・補聴器等の「聞こえの問題」には共産党、そして公明党が長年取り組んできたことがわかる。
第3の波(2013年~2018年)
どんどんいきます。
2013/2/27 H25年 第1回定例会
共産・栗原市議が「公的給付の対象とならない難聴者への補聴器購入助成の独自実施の予定はあるか」と質問
⇒《市・健康福祉部の担当部長》は「身体障害者手帳の対象とならない難聴者の独自助成は現在行っていない。今後の検討課題としたい」と回答
2015/12/1 H27年 第4回定例会
無所属・伊沢市議が「高齢者支援として“中等度難聴者”の購入助成を検討すべき」と提案・質問。
※この「中等度難聴」という考え方は重要で、当時
●重度難聴者→ 身体障害者手帳の対象(助成が受けられる)
●軽度・中度→助成がない
という状況でした。
ちなみに2022年に開始した事業も、“中等度難聴者”を対象としたものです。
⇒しかしこの提案は、《市・健康福祉部の担当部長》に「現時点では考えていない。車椅子が必要な人もいれば、補聴器が必要な人もいる、優先度を見極めるべき」などと否定されてしまう。
この伊沢市議はまた後で出てきます。
2017/6/2 H29年 第2回定例会
公明・赤松市議が「“新生児”の難聴と補聴器対策、聴覚健診」について質問
2018/2/26 H30年 第1回定例会
公明・赤松市議が「“中等度難聴児”への補聴器費用の一部助成(既存制度)の広報や利用状況」に関して質問
※ここで既存制度の話が出てきていますが、実はこのとき東京都の政策事業として「中等度難聴児発達支援事業」が、すでに各市区でスタートしている。これは“18歳未満を対象”とした事業だ。
2019/6/7 H31年 第2回定例会
無所属・嶋崎市議が、23区地域の既存事例を紹介しつつ「高齢者を対象として、多摩地域発の購入助成金制度」を作りませんか、と提案。
⇒《河村市長》は「財政豊かな特別区と、多摩26市は違う。三鷹市の財政状況を勘案しながら検討したい」と答弁。
2019/9/2 R1年 第3回定例会
共産・大城市議が「高齢者の“加齢性難聴者”への補聴器購入補助制度を創設できないか」と質問
⇒《市・健康福祉部の担当部長》が「多摩26市では事例がない。引き続き、他市区の状況を踏まえ検討したい。」と答弁
2019/9/25 R1年 議会運営委員会
共産・前田市議を提出者として「加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書」が提出
この2013年~2019年の間には、共産党や無所属の議員から、何度も「高齢者の補聴器購入助成」に関する提案がなされている。
その度に、「多摩地域では事例がない」「財政状況に余裕がない」などと却下されてしまったが、確実にその機運は高まってきていたはずだ。
この後、2020年初頭からの新型コロナウイルスの感染拡大による混乱期を挟むが、2020年末には集大成として一つの“条例案”が提出されることとなる。
「補聴器購入費助成条例案」を提出(2020年〜2021年)
2020/12/16 R2年 議会運営委員会
共産・大城市議を提出者として「三鷹市高齢者補聴器購入費助成“条例”案」が提出された。
条例案は、12/21の定例会で「厚生委員会(議員で構成される委員会)」に付託されることが決定した。
ご存知の通り、この条例は結果としては『否決』されるのだが、重要なのはその理由だろう。次の厚生委員会の議事録はじっくり見ていきたい。
2021/2/4 R3年 厚生委員会議事録(←全文URL)
はじめに、条例提出者の共産・大城市議から趣旨説明がされる。
《共産・大城市議》
・65歳以上の軽度・中度難聴の高齢者(所得の少ない住民税非課税世帯の方)に対し、補聴器購入費を最大3万円助成する
・三鷹市の高齢者の数や、65歳以上の約半数が難聴ということなどから推定すると、年間100人くらい
・100人に3万円だから300万。これなら市民にも理解してもらえる。
・条例のカタチにすることで、簡単に制度が廃止されないよう議会のチェック機能を働かせる
では、議論に参加した各委員の質問を見ていきます。
■無所属・伊沢議員
「私も過去(2015年)に同様の助成を求めて一般質問をしたので、制度には賛成しています。でも、三鷹市の3倍の高齢者がいる江東区の同制度で750人の利用者がいることを考えると、ちょっと100人の想定は少なすぎるんじゃないか」
⇒《共産・大城議員》
「他の区の実績から見て、ニーズはあるかもしれないけどすぐに100人を超える人が申し込むとは考えにくい」
■無所属・成田議員
「条例制定は議会の意思がなければ変更できないということですが、反対に市の財政を縛ってしまうという見方もできるが、どうか」
⇒《共産・大城議員》
「何千万円もかかるわけじゃない、予備費とか財調(三鷹市財政調整基金)とか使えばできる。(申請者は)100人に満たないと思うが、当面の間は、もし100人を超えたらそこで助成を打ち切ればいい」
■無所属・後藤議員
「なぜ65歳以上なのか、65歳未満を対象外とするのはなぜか」
⇒共産・大城議員
「年齢があがるごとに難聴になる割合が高くなるという報告書があるので、65歳以上にしました」
■無所属・後藤議員
「(コロナ禍で)来年以降はさらに財政が悪化すると言われている今、このタイミングで条例提案した理由はなにか」
⇒共産・大城議員
「加齢性難聴の初期に手を打つことは健康増進にもつながる。300万円で今後の介護費用の何千万円か(の削減)に寄与すると考えられる」
■立憲民主・岩見議員
「100人のニーズの話があったが、実際は、(どれくらい申請があるか)数量的には把握しづらいという理解でよろしいか」
⇒共産・大城議員
「正確な数字は把握しづらい。三鷹市に聞いても、どの自治体に聞いてもわからないと答える。でも65歳以上の半分が難聴、そのうちの非課税世帯で、かつ、まだ(補聴器を)買っていないとなると、もっと少なくなるのかなと」
■立憲民主・岩見議員
「とすると、ニーズ的には(100人より)もっといるんじゃないかという理解も成り立つと思いますけど。でもまあ、ある程度必要な措置なのかなとも思います」
ざっくりこんな感じで、質疑は終了します。
申請が予想される人数規模や、予算規模の詰めの甘さが目立ち、賛成意見の議員からもそこを指摘する質問が多かった。
これは要約なので、全文を読みたい方はURLをタップして下さい。
このあと、議論は討論・挙手に移ります。
《反対討論》公明・赤松議員
・高齢者の「聞こえの問題」への支援は、介護予防にもつながる有効な取り組み
・ただし、条例ではなく“助成制度”を作って支援している自治体も多い。三鷹市についても、他の自治体の“制度”の実施状況を検証し、国の助成の取り組みを注視しながら進めるべき
・条例制定は時期尚早と考え、反対します
《賛成討論》無所属・伊沢議員
・(自身が所属する)会派としても“高齢者”の補聴器購入助成制度を市に要望している
・18歳未満の中等度難聴者への助成は東京都のものがあるが、高齢者にはない。三鷹市が他市に先駆けて条例を設置して欲しい。
以上で討論は一切終了し、挙手による投票が行われる。
条例案は否決
趣旨説明、質疑、討論を経た条例案の投票では、委員会メンバーによる可否(賛否)は同数。
最後は、無所属・宍戸厚生委員長の反対によって条例案は否決された。
条例を否決された共産・大城市議はめげることなく、2021年の年末にあらためて《制度》として購入費助成を提案するのだが、このあたりから市の対応に変化が見られるようになる。
2021/11/30 R3年 第4回定例会
共産・大城市議が「高齢者の補聴器購入費補助制度を創設してはどうか」と“制度”の設置を提案する
⇒《河村市長》は「需要や他市区の状況を踏まえながら、今後しっかり検討していきたい、今しばらく待っていただきたい」と答弁
明らかに、制度の実現に向けて前向きな答弁だろう。
約20年の時を経て、ついに助成事業は実現に向けた動きを加速させます。
制度実現へ
これ以降、実現に向けた流れが見えてからは非常にテンポが早いので、時系列を丁寧にみていきたいと思います。
2022/2/3 R4年 全員協議会
《市・企画部の担当部長》より「令和4年度予算」から「補聴器購入費助成事業」の実施を行うことが紹介される。
2021年11月末に共産党が制度提案を行ってから、たったの2ヶ月で大きく事業実施の流れが見えてきた。ここまでの時系列を見ていれば、共産党の長年の主張が実ったと考えるべきだろう。
ただし、これが共産党の“要望通りに実現”したものだと考えると、一つ疑問が生まれる。それは、実施される「制度の内容」についてだ。
「共産党が提案してきた条例・制度案」と、「実際に施行されることとなる事業」には、なぜかその内容に差異が見られるのだ。
《共産党の主張》 ⇒ 《施行される内容》
「65歳以上」を対象 ⇒ 「18歳以上」を対象
「3万円」の助成 ⇒ 「4万円」の助成
この差異が、予算の関係で縮小されたのならわかる。
でも逆だ。なぜか、拡充されている。
三鷹市が「どうせやるなら」と、太っ腹な“舵切り”をしたのだろうか。
でも「財政豊かな23区と、多摩26市は違う」などと助成自体に後ろ向きだった河村市長をはじめ、そのような判断をするとは考えにくい。
そのとき、市の内部ではいったい何が起きたのか
では、市の内部でいったい何が起きたのか。
ずいぶん「前置き」が長くなってしまいましたが、ここからが本題です。
こんなに長い前置きいらないだろ、と思う方もいるかも知れませんが笑、必要だったんです。
公明党を批判されている方々が、いわゆる「水面下」と呼ぶ動きを理解するためには、「ここまでの流れ」と「この後の展開」が特に重要になってきます。
引き続き、このあとの時系列を追いかけています。
まず、制度の成立について触れたのは公明・赤松市議だ。
2022/3/3 R4年 第1回定例会
《公明・赤松市議》
「補聴器購入費助成事業が、高齢者の認知症予防に併せて、中等度難聴者(18歳以上)が対象とされたことを“大いに評価”する。どのような背景で議論、検討があったのか」と質問
⇒《市・健康福祉部長が答弁》
「本事業では対象年齢を18歳以上とすることによって、障害者手帳はないものの、聞こえに問題を抱える中等度難聴の方につきましても、幅広く市民の方をサポートしていきたいと考えている」
一方で同日、共産党の議員も質問に立った。
《共産・紫野市議》
「市民の切実な要望を真摯に受け止めて頂いたことを心から歓迎」と発言した上で「合計210万円未満の所得制限では65歳以上の高齢者の何割が対象となるのか」と質問
あくまで自分たちが主張してきた「高齢者の助成対象」となる人は何人くらいいるのか、という質問だ。
質問の内容に着目してほしい。
・「18歳以上への助成拡大」の評価を述べた公明党。
・長年の主張が実った「高齢者の助成対象」となる人数を確認した共産党。
この2党以外に、この事業成立に触れた一般質問はなかった。
もう少し議会の様子を見てみよう。
3月にはこれまで、長年にわたり助成の訴えを重ねてきた共産・大城市議が質問に立った。いったいどんな言葉を発するのだろうか。
2022/3/15 R4年 予算特別委員会
《共産・大城市議》
「私ども、条例提案もしたものですが、私どもが条例提案した内容より金額も増え、しかも対象年齢が18歳以上ということで、すごく拡充されている内容で評価をいたします。」
わかっただろうか。
もう一度見てみよう。
「私どもが“条例提案した内容より”金額も増え、しかも対象年齢が18歳以上ということで、すごく拡充されている」
つまり、「自分たちの提案内容よりも拡充」されていたことを高く評価しているわけだ。このあとに続く言葉でもやはり「高齢者の助成への期待感」のみを強調していた。
自ら直接、事業の内容について市の職員との交渉に動いて内実を知っていたのなら、「要望通り」「提案通り」と言っただろう。
かなり長くなってしまいましたが、判断に必要な材料は全て揃ったので最後のまとめに入りたいと思います。
経緯と状況を整理する
忘れかけていると思うので笑、あらためてこのnoteの目的を確認します。
“誰もがアクセスできる”議会の議事録から、「補聴器購入費助成事業」の成立をめぐる経緯をしりたい。
その時、いったい何が起きていたのか、誰が動いたのか。
公明党はどう動き、あるいは、動いていないのか。
まず、「聞こえの問題」(補聴器の助成、難聴の状況)について“議会で質問”を行ってきたのは、以下の議員たちだ。
①大城市議をはじめとした《共産党》
②赤松市議をはじめとした《公明党》
③《無所属》の伊沢市議、嶋崎市議
そのうち、“条例案の提出”や“制度の提案”を行ったのは
①大城市議をはじめとした《共産党》
③《無所属》の伊沢市議、嶋崎市議
である。
公明党は、既存制度の周知状況等について質問は行っているものの、「制度の提案」自体は行っていない。ただし、冒頭のツイートに多くのリプがついたような、公明が「制度自体に反対」していた事実はなかった。
この流れから言えば、共産党の長年の主張が、事業の成立に大きな影響を与えたと言えるだろう。
最後に残るのが、“実施内容の拡充”についてだ。
これについては、共産党市議団が拡充の要望をしていない以上
②赤松市議をはじめとした《公明党》
③《無所属》の伊沢市議、嶋崎市議
のどちらかだということになるだろうが、「高齢者を対象」に制度提案を行っていた伊沢市議、嶋崎市議が「18歳以上」を対象に含めるべく市との交渉を行ったとは考えにくい。
事業内容が決定したときですら、議会での反応を示していない。
これらの事実を総合すれば、事業成立に向けた質問で「18歳以上への拡充」に触れている公明党が「実施内容の拡充」に向けて動いたと考えるのが自然だろう。
僕は、これが“議会の議事録”だけを見て、客観的に理解しうる結論だと思う。
この件に関して言えば、共産党に「実績横取り」との批判を浴びせるのはあまりに盲目的だが、反対に公明党が「何もしていない」「実績横取り」との批判もまた間違っている。
ひとまずの結論
共産党らの長年の主張であった「高齢者への補聴器購入費助成」は、公明党の推進もあって「対象、金額ともに拡充」された形で、実現にこぎ着けた。
そもそも、発端となったツイートに載っている公明ビラの写真にもこう書いてある。
公明党として、「医師の診断の上、18歳以上の必要とされる方」への拡充を求めてきました。
批判に晒されているような、公明党の“水面下”の交渉がなければ、制度は「高齢者向け(65歳以上)」になっていただろう。
そもそも、実現していなかった可能性すらあるだろうが、これは議事録から読み取れる内容ではないので止めておく。
この“水面下”の交渉により対象が「18歳以上」となったことで、【0歳~18歳までは東京都の事業】、【18歳以上は三鷹市の事業】として、助成対象を全世代にわたって切れ目なくカバーすることができた。
この違いは非常に大きい。
ということで。
ここまで、長々と読んで頂きありがとうございました。
最後の事件
問題は、この「補聴器購入費事業」を含む予算を審議するための特別委員会で起きる。
2022/3/17 令和4年 予算特別委員会
《共産・前田市議》
「補聴器購入費助成は歓迎し、購入後も使用を続けられるような支援の検討を要望する」
「本予算は新たな施策として評価できる点がある一方、新型コロナ感染症の影響など十分に考慮したものとはいえない。具体的内容が定まっておらず、事業規模の見込みが示されず、実現可能性や実施スケジュールに疑問を感じるため、本予算に反対する。」
なんと共産党は、この事業を成立させるための予算に対し、反対の意思を示したのだ。
思い出してほしい。
公明のビラに猛批判をした方々はこう言ったのだ。

「反対したのは事実」

「反対した事実は変わらない」
条例案に反対した公明党は、条例案の内容を拡充させる形で事業の成立に貢献し、条例案を否決された共産党は、自身の長年の主張が実った事業を推進するための予算に反対をした。
これが時系列を追い続けた結果、最後に待っていた事件でした。
なお、予算は賛成多数で可決。
2022年10月より多摩初となる「補聴器購入費助成事業」がスタートしました。
これが地方議会。これが政治。
すでに文字数は8000字を超え、眠気も限界に達しました。
最後にすこしだけ、「地方議会」がおもしろいといった理由を書いて終わりたいと思います。
議会に渦巻く人間模様
「補聴器に助成を」ー
一見単純そうなこのテーマでさえ、20年以上の時間をかけて実現に結びついた。こうした細やかで身近な話題が、地方議会では日々議論されていることだろう。
ほとんどは割愛しましたが、議員の一般質問だけでなく、それに対する市職員の答弁もおもしろい。
話者の感情や質問議員への想いのようなものが見て取れる。
国会以上に、役人(市職員)との関係が近い地方議会ならではだろう。
日常的にどのようなやりとりがあるか。どの議員やどの政党を信頼し、反対にどの議員やどの政党は苦手なのか。
さらに言えば、議事録にも残らない「人間模様」が、現実の上で地方政治を動かし、時には国政にも影響を与えていることは間違いないだろう。
目に見える政治、目に見えない政治
そう考えると「目に見えない“水面下”の交渉」を事実として認めず、“政治ではない”かのような批判には、危機感を覚える。
もちろんやってもいないことを、「水面下の交渉だから」と公言するような“言ったもん勝ち”政治になってしまえば元も子もないが、今回の批判はそうじゃない。
議員自身が「“やりました”と言っていること」と、議会記録との間に不整合が見られないにもかからず、「(直接的な)証拠を出せ」というのはあまりに乱暴だ。
ただ、今回に限って言えば三鷹市の公明議員も「動いた実績」を、目に見える形でもう少し残すべきだったとも思う。Twitterでも、ブログでも、日々こまめに実績を発信するツールはいくらでもあるのだから。
とはいえ、政治は「結果」だ。何をやったかが重要だ。
「高齢者に1人3万円」でも〈財政を圧迫させる〉と言われていた内容が、「全世代に1人4万円」となって実現に結びついたことは、ある意味、矛盾しているように思える。
この矛盾に、「財源」と「明確な理由」をセットで差し出すのが政治家や政党の力だろう。
先ほどの「20年以上の時間をかけて実現に結びついた」との表現は、裏を返せば「20年の間提案を続けたが実現できなかった」とも言えるだろう。
「財源」と「理由」を携え、実現させる「交渉力」を持ち合わせていること。
その時初めて『政治は結果』の言葉が意味をなす。
今回でいえば、その役割を果たしたのが誰であったかは明白だろう。
だからこそ、人間関係の構築も、水面下の交渉・協議も含め、目に見えるもの、目に見えないもの、そのどちらも政治だし、現実の上では「目に見えない政治」の方が、占める割合は大きいと言ってもいいかもしれない。
そうした〈簡単には表面に現れない事実〉に、目を向けてみることで政治の面白さも増していくのではないかと感じた出来事でした。
まあ僕はもっと、サクッと簡単に結論だけ知りたいタイプの人間なんですけどね。
最後まで読まれたみなさんに、、、。
国と政治と男のロマンが詰まった漫画「サンクチュアリ」をおすすめして終わります。
最後の最後まで、読んで頂き大変にありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
