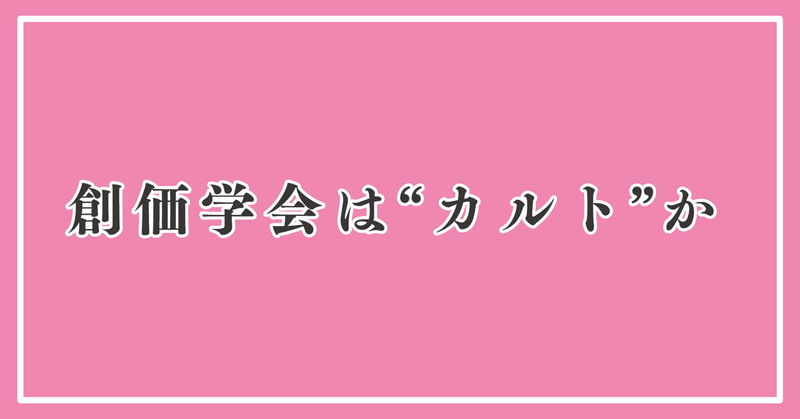
創価学会は“カルト”か
こんなこと書く必要もないし、議論するのもアホらしい。(1行目から口が悪くなってごめんなさい笑)
と、ずっと思っていましたが、今話題の「旧・統一教会」への批判に便乗して、「創価もカルト」との根拠なき言説、論拠なき暴論が平気で出回るようになりました。
んー、これは「アホらしい」で済ませずに、自分でもちゃんと検証しないといけないのかなぁ、と思っている時に、ある質問を頂きました。

ということで、今話題の「カルト」について書いてみようと思ったのですが、これが結構大変で、書きながら何回も後悔しました笑。
このnoteの結論を先に書くと「創価学会はカルトではない」、、もうほんとこれだけです。
もちろん学会員の僕がそう結論づけたところで、納得されない方も多いと思いますので、ここでnoteを閉じても構いません。笑
でももし、お時間のある方や、反論したい方は、なるべく客観的な文章に基づいて書くつもりなので、宜しければこの後もお付き合いくださいっ!
「カルト」に関するいくつかの定義
まずは、「カルト(セクト)」に関して存在するいくつかの定義を引用してみたいと思う。
僕は決して学術的な意味で、このnoteを書いているわけじゃないので「あ〜、こんな感じなんだ」と見てもらえればいいと思います。
厳密な定義を求めている方は、ごめんなさい。
日本国内でのカルト定義の例
まず日本ではどう捉えられているか。
たとえば、国内の多くのカルト団体の実態を取材した書籍「カルトの正体。」(別冊宝島編集部 編)の中では、以下のような定義がある。
「カルトとは、ある人物あるいは組織の教えが絶対であると教え込み、基本的人権や憲法、憲法の精神を否定し、法違反を行う集団」
ほかには、複数の辞書データベースを横断した検索機能が優秀なwebサイト「コトバンク」ではこう記される。
○第一に導師やグルとよばれたり、自ら救世主を名のるカリスマ的教祖をもつこと
○第二にマインドコントロールといわれる心理操作のさまざまなテクニックを用いて入信させること
○第三に外部世界から隔離された場所で共同生活を営み、閉鎖的集団を形成し、そこからしばしば反社会的行動に走る
○第四に神秘的、魔術的な儀礼を実践し、教義は異端的、シンクレティズム(宗教的折衷主義)的である
あとはこんなのもある。
1995年に設立された国内の任意団体「日本脱カルト協会」では、カルトとは“人権侵害を行う全体主義的団体”だと前置きをした上でこう定義づける。
①各メンバーの私生活を剥奪して、
②集団活動に埋没させる。そして、
③メンバーからの批判はもちろんのこと外部からの批判も封鎖し、
④組織やリーダーへの絶対服従を強いる
以上、いくつか国内の例を取り上げてみた。
フランスでのセクト定義の例
では、海外ではどうか。
2001年5月に、世界で最も厳しいと評された「セクト規制法(反セクト法)」がフランスで成立した。
カルト/セクトの話題において、今でもよく引き合いに出されるこの法の中で、「セクト的」とは、要約すれば以下のようになる。
「法的形態若しくは目的がなんであれ、その活動に参加する人の精神的又は身体的依存を作り出し、維持し、利用することを目的又は効果とする活動を行うあらゆる法人」
(セクト的団体の定義)
分かりやすく言えば、「精神的または身体的依存」を“手段”として、「参加者の維持(束縛)や利用」を“目的”とするあらゆる法人団体を指す。
なお、セクト“的”団体、と書かれているように、ここでは「宗教法人かどうか」は定義に含まれていない。
議会報告書における「フランス創価学会」のリスト掲載について
ちなみに、フランスでのセクト対策に関連して、“既に撤回されている”にも関わらず、過去に創価学会がセクト団体としてリストアップされたという事実が、今でも、あらぬ誤解と悪意ある論調とともに一人歩きしているので、少し深掘りしておきたいと思う。
そのリストとは、1995年に議会提出された調査委員会報告書(通称:ギュイヤール報告書)に基づいたもので、そこには172もの“セクト的団体”が掲載され、当時のフランス創価学会(現地法人)もそのリストに含まれている。
しかし、後に誕生するフランスのセクト対策に関する公的機関MIVILUDEによって、このリストの「妥当性の低さ」と「今後のリスト使用を避ける」旨が公表され、その法的有効性が否定されている。
この効力の否定には、報告書作成時の調査不足や「信教の自由」の保障に関して十分な議論がなされていなかったことなど様々な要素が絡みますが、ここでは「現実に法的効力が否定されていること」「今現在、創価学会をセクト的団体として取り扱うリストが存在しないこと」だけ、書き留めておきます。
「こうした警戒は、1995年の報告書に添付されているセクト団体リストの妥当性が低下しているということも含めて、セクト問題の進展を考慮したものでなければならない」
「『セクト監視所』や『MILS』などの組織への準拠は、MIVILUDESを設置した政令への準拠に取って代わられなければならず、セクト団体リストの使用を避け、基準法の適用を行っていかなければならない」
【出典】
(和訳) セクト的逸脱行為対策に関する2005年5月27日の通達
(原文)Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires
というか、そもそも規模も活動内容も多岐に渡る170以上の団体について、(団体数に比べて)少数の有志グループによる調査で取り締まろうという姿勢自体、杜撰であったと言えるだろう。
ちなみに、日本国内でも最近、このギュイヤール報告書に掲載されている「セクト的構成要素」をそのまま報じることがあるが、これは大きな誤認を孕んでいるので、気を付けてほしい。
以下が、報告書で示された「セクト的構成要素」です。
・精神的不安定化
・法外な金銭要求
・元の生活からの意図的な引き離し
・身体の完全性への加害
・児童の加入強要
・大なり小なり反社会的な言質
・公序への侵害
・多大な司法的闘争
・通常の経済流通経路からの逸脱
・公権力への浸透の企て
読めばわかる通り、このギュイヤール報告書の「セクト的構成要素」のうち、いくつかは恣意的な読み方も許されてしまう曖昧な指標であり、信教の自由、結社の自由を踏み躙る恐れがあるとして、フランス国内でも反対の声が多かった。
そこで、後に制定されるセクト規制法では、この指標に加え「団体及び指導者が“複数回の有罪判決”を受けている」という「客観的な基準」を付け加えている。
これまでの議論に即してギュイヤール報告書の指標を援用するなら、この「客観的基準」まで示すことが必要だと思うけど、そこまで報じているメディアは見たことがない。
参考(「仏教哲学大辞典」における「カルト」の記載)
最後に参考として。
では、“創価学会”自身はこの「カルト」という単語(定義)をどう見ているか、フォロワーさんの中で詳しくnoteに書いてくださっている方がいたので、(勝手に)紹介させて頂きます。
このnoteの中では2000年に発行された「仏教哲学大辞典(第三版)」に基づいて「カルト」という単語が持つ社会的意義の変遷も含め、とても詳しく書かれているので、もし興味がある方は読んでみると面白いと思います(CalorieFriendさん、ありがとうございます♪)。
共通項は「反社会性」「違法性」
ここまで読んで難しく感じた方もいるかもしれませんが、今でも国内に出回るデマへの指摘も含んだテーマだったので、少し詳しく書きました。
いくつかの「定義づけ」に共通していることは、集団が持つ「反社会性」「違法性」こそ、“カルト的である”ことの、もっとも明確で客観的な証拠になり得る、という事実です。
これらの議論の前提に立って、僕自身は「カルト」をこのように認識しています。
『法治国家で最も尊重されるべき「憲法や法令」よりも宗教団体の「教義や慣習」が優先され、結果として「権利の蹂躙」や「法違反」を肯定し「反社会性」を否定できない団体は“カルト的要素をもつ”と言える』と。
創価学会は“カルト”ではない
そういう意味で、創価学会はカルトとは言えないと思う。(もちろん僕自身の結論なので、議論、反論もご自由にお願いします)
学会の日常的な活動の中で、法外な金銭の受領、心身の束縛を伴うような勧誘行為、信者(会員)の生活基盤の剥奪など、違法性や権利の蹂躙は見られないし、日常生活に脅威を与え民主主義国家を破壊しうるような反社会性もない。
というかそもそも、会として「法令遵守」「社会への貢献」を憲章として明示している。
「創価学会は、各地の文化・風習、各組織の主体性を尊重する。各組織はそれぞれの国、または地域の法令を遵守して活動を推進し、良き市民として社会に貢献する。」
もっと現実的なことを言えば、地域の隅々にまで細かく浸透した学会員の存在と、その活動の中で法令違反が指摘されるような出来事が起きていない現実そのものが、創価学会の「社会性」「適法性」の証左にほかならない。
最初の質問にあった「偏見をなくす対話」について答えるなら、こうした正当性の根拠をまず示し、それに対する疑問・反論に一つずつ答え解消していくことが重要だと僕は思っています。
このnoteも「これでどうだ(ドヤァ)!」で終わるのではなく、できれば反論、異論が集まり対話に繋がる「きっかけ」であってほしい、と強く想います。
つまり、今求められているのは「正しさのマウンティング」ではなく「心通じ合う納得の対話」であるべきだろうというのが、僕の結論です。
もう一つの問題意識
長くなってるけど、最後にもう一つだけ。
あんまり偉そうなことは言えないけど、今回の件を調べれば調べるほどに、出てくるネット記事のエビデンスの弱さに驚きました。
一部の識者を除けば、「宗教の善悪や正邪」について議論をするために必要な、最低限の理解と尊敬が欠如しているのかもしれないと、危機感を抱きました。
「信教の自由」「結社の自由」など、“言葉”は知っていても、憲法20条を法源とするこの“考え方”をどう尊重し、どうやって既存宗教の中で適用していくのかという議論をすっ飛ばして、「宗教への嫌悪」とくに「新宗教への憎悪」とも言える論調が平気で語られてしまう。
「これもカルト、あれもカルト、新宗教はカルト」と決めつける宗教への無知と畏れこそが、宗教への正しい理解や社会への適切な浸透を妨害していること、そして、結果的にカルト的団体を増長させ、野放しにしている実態を知ってほしいと思う。
十分な定義や検証もなしに「カルトと見做す」行為こそが、これまで国内外で「カルト的団体」を取り締まるために積み重ねられてきた賢明な議論をぶち壊す暴挙だということに気づくべきだと思う。
でもこれは決して悲観的な意味で言っている訳ではありません。
むしろ、今回の事件をきっかけに宗教についてもっとオープンな場で、開かれた議論がなされてほしい、と僕は思います。
そのためのチャンスが今、訪れているのだと感じています。
そしてまた、僕自身もひとりの学会青年部として、創価学会が社会に果たしてきた役割は何か、地域に貢献してきた事実はどうなのか、こんな時だからこそ広く発信するよう努めるとともに、社会に開かれた組織であることを望んでいます。
そして、悪意あるデマにはこれからも抗議と反論を続けようと思っています。
デマってほんと腹立つけど、最近は学会について「流れされるデマ」が多ければ多いほど、「デマを流すこと以外に攻撃する材料がないことの証拠」なんだと思うようになりました。むしろ、喜ばしいことですらある。
僕たちはこんな時代だからこそ、胸を張って信仰活動を続けていくべきだし、これからも今まで以上に、誇りをもって地域貢献に取り組んでいくべきだと思います。
何か問題が起きた時に反省ができる謙虚さと、社会との認識のギャップを是正し続ける向上心さえ忘れなければ、何かに遠慮する必要なんてどこにもない。
どんな虚偽や暴言にも僕たちは折れない、屈しない。
道理に基づき「良い」と信じる行動を貫くことが、今こそ「正しい宗教」に求められる姿勢なのだと、僕は考えます。
ということで今日からもまた、胸を張って朗らかに、僕は学会員として生きていきます。
ありがとうございました^ ^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
