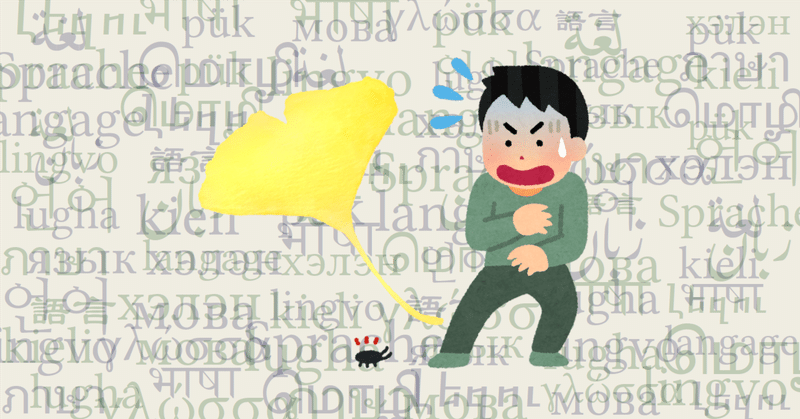
誤植が生んだ ginkgo とゴキブリ
銀杏 ginkgo
銀杏を英語で ginkgo [ɡɪ́ŋkoʊ] という。
なんとも奇妙な綴りだ。きっと他の言語から英語に入ったのだろう。
発音は日本語の「銀行」「吟行」に似ているが,まさか日本語ではあるまい。
と思ったらこれ,日本語なんですな。
Wiktionary で ginkgo を引くと,語源(Etymology)のところに大変興味深いことが書かれている。
そっけない記述だが,他の資料も参照すると,どうやら以下のような経緯があったらしい。
ドイツの博物学者で元禄年間に日本に滞在していた エンゲルベルト・ケンペル が著書に「ギンキョウ」の読みで銀杏を記載。
ケンペル流のラテン文字表記で「ギンキョウ」は ginkjo もしくは ginkio となるはずだが,誤って Ginkgo と印刷されてしまった。
植物学者の カール・フォン・リンネ がこれを参考に日本の植物の命名を行なった。
ケンペルのこの著書は “Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V” で,1712 年に出版されている。日本語では『廻国奇観』と呼ばれている。
ペルシャを中心としてアジア諸国について書かれたもの。
「V」は「第 5 部」ということなので,叢書になっていて他の部もあるわけだ。
原典にあたる
京都大学貴重資料デジタルアーカイブ で本書のページが見られることが分かった。
何かの研究者でもないただの物好きがコタツに足を突っ込んだままこんな貴重書を自由に閲覧できるなんて素晴らしすぎる。
ラテン語なので問題の箇所をどうやって探すか悩んだが(なにしろ 900 ページを超す大著),あっさり見つかった。
以下のリンクで当該箇所に飛べる。
銀杏の項を文字起こししておこう:
杏銀 Ginkgo, vel Gín an, vulgò Itſjò. Arbor nucifera folio Adiantino.
(note はイタリック体が使えないので,原文がイタリックのところもローマン体になってしまった)
後半の「Arbor nucifera folio Adiantino.」は銀杏の説明なのでパスする。
「銀杏」でなく「杏銀」となっているのは誤植ではない。当時の日本語に「左横書き」(左から右への横書き)は無かったのだ。正確に言えば,そもそも横書きが無かった。「右横書き」のように見えるのは「1 行 1 字の縦書き」だったと考えられている。
だから,左横書きのラテン語の中に日本語を組み込もうとすると,本書のように右横書きのような組み方をするか,活字を 90 度回転させて横倒しの縦書き(縦組)にするほかない。
さて,その次が「Ginkgo」。確かにあった! 堂々たる誤植だ。
続く「vel Gín an」は「『ギンアン』とも(言う)」ということらしい。
「Gín」と「an」の間にワードスペースが入っている。「Ginkgo」には入っていないのに。「ギナン」と読まれないためだろうか。
当時の日本語が「ギンアン」であったのか,それとも発音は「ギンナン」だがケンペルが字音に配慮して「Gín an」と書いたのかは分からない。
その次の「vulgò Itſjò」は「一般に『イチョウ』」ということのようだ。
「Itſjò」の綴りの第 3 字「ſ」は チンアナゴ に似ているが,これは long s と呼ばれる文字で,まあ普通の「s」の異体字のようなものだ。
だから,「Itsjò」と思ってよい(たぶん)。
ラテン語は全く知らないが,おそらくチョという発音はなくて,よその言語のチョを表すのにこういう綴り(tsjo)を使うんだろう。
ご存知の方,教えてください。
ゴキブリ
ゴキブリはその嫌われ方と音の響きが見事にマッチしているように思われる。
ゴキブリの見事な動きぶり
というダジャレもある。
しかし,どうも日本語(和語)ぽく感じられない。
オノマトペを除けば濁音で始まる和語はほとんど無いものね。
薔薇が例外だが,これは「うばら」の「う」が落ちたもの。
ゴキブリは何語なのか。
先日,図書館で何かを読んでいて,
ゴキブリはもともと「御器齧り」で,食品どころか御器(お椀のこと)まで齧るのでそう呼ばれた。
ところが岩川友太郎『生物學語彙』(明治 17 年)でルビの「カ」が抜けて印刷されたためにゴキブリになった。
というような意味の記述を見た(正確な内容は失念)。
つい先日のことなのに出典が思い出せない。「図書館だより」の余白に走り書きしたメモには「M17 岩川友太郎 生物学語彙」とだけある。
「御器まで齧る」からかどうかは異説もあるようだが,ゴキカブリと呼ばれていたのは確かなようだ。
江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(1712)にも「ゴキカブリ」で出てくるぽい(調べてない)。
しかし,「御器齧り」とルビが振られていた,という話に私は違和感を持った。
読者は「齧り」に疑問を持たなかったのだろうか。
この「いかにも間違えました」的なルビが社会全体でゴキカブリの語形を変えてしまうことがあるだろうか?
原典にあたる
明治 17 年の著名な学術書なら 国立国会図書館デジタルコレクション で丸ごと見られるに違いない。
はい,ありました(以下のリンクで『生物學語彙』に飛ぶ):
書誌情報はこちらが見やすい:
この「Cockroach」のところに
蜚蠊
とある。
以下のリンクで当該ページに飛ぶ:
「御器齧り」にルビを振ってたわけじゃなかったんだ。
いずれにせよ見事な誤記ぶりだ。
こういうのはやっぱり原典に当たらないとダメだね。
(なお,日本語が「横組」でなく「横倒しの縦組」になっている理由は既述のとおり)
この「蜚蠊」という語は漢語だった。『スーパー大辞林』にも載っていた。
Wikipedia 中国語版を見ると,ゴキブリは「蟑螂 zhāngláng」のようだが,「蜚蠊目」とある。
『超級クラウン中日辞典』では「蟑螂」と「蜚蠊 fěilián」が同義語として掲載されていた。
「蜚蠊」という表記であれば誤植を疑わなかったとしても不思議はない。
ところで,『生物學語彙』の誤植の一件は,Wikipedia「誤植」にもう少し詳しいことが書いてあった。
『生物學語彙』の刊行後について述べた箇所を引用する:
その後1889年(明治22年)に作られた『中等教育動物学教科書』にも「ゴキブリ」と記述されてしまい、この間違いは、以降の教科書や図鑑にも引き継がれ、全ての文献に「ゴキブリ」と書かれ、和名として定着した。
この文面でははっきり分からないが,『中等教育動物学教科書』の筆者が『生物學語彙』を参照して「ゴキブリ」とした,というように受け取れる。
いずれにせよ,「ゴキブリ」の普及には教科書への採用があったわけか。
まあ,そうでもなければ専門分野の用語集が一般の人の言葉まで変えてしまうということはなかなか起こらないだろう。
ところで,Wikipedia によれば,誤っていたのは二箇所のうちの一つであり,もう一方は正しく「ゴキカブリ」になっているとのこと。
当該の記述を見つけたので,リンクを貼っておく:
p. 29 の「Blatta」に「蜚蠊属」とある。
ルビの字間が空けてあり,「蜚蠊」だけにかかるはずの「ゴキカブリ」が「属」の先にまで達しているのが気になるが,おそらくそのような細部まで気を配って作られてはいないのだろう。
あとがき
図書館と偶然
図書館は偶然の出会いが起こりうるところだ。
ふだんは見ない書架の前をうろつく。
とくに強い興味を惹くわけでもない本を手に取って,パラパラとめくってみる。
すると,「お?」と思う記述を見つけることがたまにある。
本記事を書くきっかけになったのが,この「お?」であった。
デジタル資料
一方,古い書物のデジタル画像が閲覧できるサービスも魅力的だ。
国立国会図書館デジタルコレクション は何かの研究者にとってもただのヒマ人にとっても宝の山といっていい。
たとえば「野球が好きなんだけど戦前の野球ってどんなだったのかな」とか「幕末に渡米した人がなんかおもろい日記とか見聞録とか書いてないのかな」とか「『学問のすゝめ』の表紙とか扉とか奥付とか見てみたいな」などと思ったら覗いてみるといいと思う。
京都大学貴重資料デジタルアーカイブ は今日その存在を知ったが,こちらもたいへん素晴らしい(寄付を募っている)。
いま,このような古い資料のデジタル化がどんどん進んでいる。
あなたの住んでいる自治体の公共図書館でも,地域資料のデジタルデータが公開されているかもしれない。
郷土史に強い興味がなくても面白いものを発見する可能性がある。
書物だけでなく,昔の写真なんかが見られたりする。「ええっ? 駅前ってこんなんだったの?」とか。
蛇足(欧文書体)
『生物學語彙』に使われている欧文活字はイギリスの「Modern」というものに似ている,と思った。
全体に幅が狭いこと,「a」の終筆が垂直に巻き上がっていること,カンマ「,」の尻尾が長いことなどが特徴だ。
TeX をご存知の方なら,それがそのまま TeX の標準書体である Computer Modern の特徴であることに気づかれるだろう。
Modern(やその類似書体)が日本にいつ頃どんなふうに入ってきて,どのくらい使われていたのか,というのは興味深いテーマだ。
私はそれについて何も知らないが,Century Oldstyle(1909 年)が普及する前には相当使われていたのではないかと想像している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
