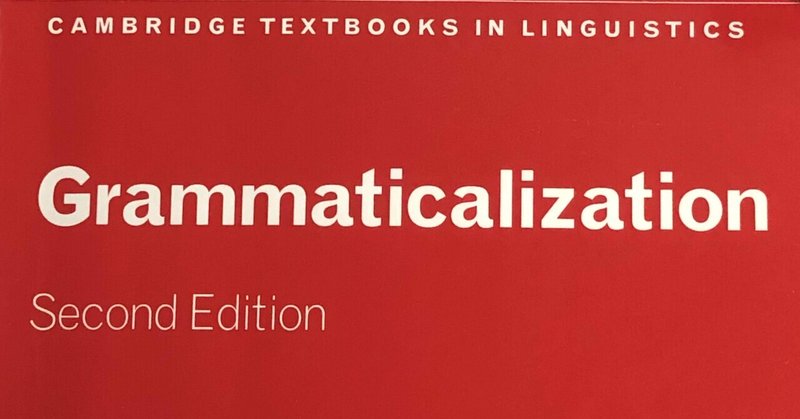
言語学の話③ 文法化(Grammaticalization)と周辺部(Periphery)のインターフェイス
1. はじめに
これまでは主に形態論の分野に関する話を書いてきました。
今回はこれまでとは異なり、どちらかというと語用論に関する話を中心に『文法化(Grammaticalization)』と『周辺部(Periphery)』、そしてそれらがどのように関わり合っているのかについて書いていこうと思います。
今回は、前回前々回よりももしかしたらつまらない内容になってしまうかもしれませんが、言語学・語用論に興味のある方はぜひ最後まで読んでみてもらえると嬉しいです。
1990年代頃から盛んになった文法化研究は、生成文法等に比べると比較的"若い"分野であると言えます。しかしながら、若い分野であるからこそ勢いがあり、様々な言語・様々な手法で研究がなされています。
文法化研究の潮流を一言で言えるほどの深い理解や洞察は僕にはありませんが、それでも、研究会で発表を聞いたり論文を読んだりする中で『文法化』と『周辺部』の関わりを考える必要性・重要性は次第に増してきているように感じています。
浅学寡聞な学部生ですが、もしかしたら今後 周辺部の研究が文法化研究、さらには歴史語用論研究を大きく発展させる時が来るかもしれないというある種の希望的観測と共に書いていこうと思います。
※言うまでもなく、このnoteにおける誤った理解・主張等は全て筆者の責任です。誤っている部分等ありましたら、コメント等でご指摘いただけると幸いです。
2. 文法化(Grammaticalization)とは
2-1. 文法化の定義
まずは『文法化(Grammaticalization)』とは一体何なのか。
Hopper and Traugott (2003: 4)では以下の通り記述されています。
Frequently it can be shown that function words have their origins in content words. When a content word assumes the grammatical characteristics of a function word, the form is said to be "grammaticalized".
"function words (grammatical words)"とは日本語で"機能語"と訳されるもので、例としてof, and, or, it, this, that のような前置詞・接続詞・代名詞・指示詞があります。
"content words (lexical words)"とは日本語で"内容語"と訳されるもので、名詞・動詞・形容詞がその例として挙げられます。
上の引用で示したように、「内容語が次第に文法的機能を示すようになり、機能語へと変化していく過程」、これが一般的な『文法化』の解釈(定義)になります。
2-2. 文法化の具体例 (再分析・音声的縮約・意味の漂白化)
上の例だけでは少ししっくりこないと思うので、文法化の例として有名な「be going to から gonnaへの変化 (Hopper and Traugott, 2003:2-3) 」を紹介します。
文法化の基本部分を学ぶ上でまず覚えておきたい基本プロセスが、①再分析(reanalysis) ②音声的縮約(phonological reduction) ③意味の漂白 (semantic bleaching)の3つです。
①再分析とは、簡単に言うと「境界線が変わること」です。
例えば、I am going to marry Bill. という文における境界線は元々"I am going [to marry Bill]."であり、「(ビルと結婚するという方向に)向かっている」という解釈でした。
しかしこの境界線は次第に"I [am going to] marry Bill."のように移り、be+~ingという進行相からwillのような未来の相を示すようになります。
再分析が生じた後、典型的な文法化においては②音声的縮約が生じます。
be going toはよくgonnaという形で用いられます。goingとtoの間にあった境界線が再分析によって取り除かれたことが、「going+to → gonna」縮約の大きな要因と考えられています。
「be+~ingという進行相からwillのような未来の相を示すようになります」と書いたように、be going toにおいて元々の意味である「(~の方向に)行く, 向かっている」という意味はあまり残っていません。むしろwillのように"未来"というより抽象的な意味を持つようになりました。
このように、本来その語句が持つ意味が薄まることを③意味の漂白、あるいは脱意味化(desemanticization)と言います。
助動詞のwillは機能語ですが、このwillに似た意味をbe going toが獲得したということはつまり「元々動詞(内容語)だったbe going toが助動詞(機能語)の役割をもつようになった → 文法化した」ということになります。
以上が文法化のざっくりとした説明になります。
特に今回の記事においては③意味の漂白が重要なポイントですので、少し頭に留めておいてください。
では「周辺部(Periphery)」の説明に移ります。
3. 周辺部(Periphery)とは
3-1. 周辺部の定義
周辺部は近年、文法化研究に続いて語用論(Pragmatics)の分野で注目されるようになった概念です。文法化研究同様、比較的若い分野であるため「周辺部をどのように定義するか、(中略)統一的な枠組みの構築はこれからという段階(小野寺, 2017: 9) 」です。とはいえ定義付けを行わないことには研究のやりようがないので、Traugott (2017: 63)は暫定的な定義付けを以下のように行っています。
Periphery is the site in initial or final position of a discourse unit where metatextual and/or metapragmatic constructions and favored and have scope over that unit.
個人的に周辺部の定義付けが難しいと思う理由が、ここでいう「a discourse unit (談話ユニット)」をどのように設定するか、ということです。
談話ユニットは基本的に書き言葉であれば"節"、話し言葉であれば"発話"になるのですが、節や発話が連鎖している(続いている)場合にはより大きなまとまりを1つの談話ユニットにすることもあります。
周辺部を定義付ける上で重要な談話ユニットの設定が研究者や分析する節・発話の大きさによって揺れがあるため、なかなかバシッと定義付けができないのが少し扱いにくいなと個人的には思っています。それが周辺部研究の楽しいポイントの1つでもありますが…
3-2. 周辺部研究者が目指すもの
談話ユニットである"発話"をどう設定するのか、少し難しいところですが「発話のはじめ(Left Periphery: LP)と発話の終わり(Right Periphery: RP)を分析する」というのは周辺部研究者の間で共通しています。
そのため、ざっくりした話をすると「周辺部=発話のはじめと終わり」と考えて問題ありません。
この周辺部において「人は何を意図し、何を言って、何をしているのか(小野寺, 2017: 3) 」を僕らは知りたいと思っています。
より専門的に言えば「「発話のはじめと終わり」ー「そこに出現する形式」ー「機能」の対応(mapping)はどうなっているのか。そこには人類共通の、言語文化的普遍性は見られるのか。 (小野寺, 2017: iv) 」を解明することを究極的な目標としています。
※具体的なリサーチクエスチョンについては小野寺(2017: 8-9)参照.
4. 文法化研究における周辺部
ここまで見てきたように、(歴史)語用論研究では文法化・周辺部という2つの概念がここ30年程でとても注目されるようになりました。
では最後に、この2つの分野がどのように関わり合っているのか考えていこうと思います。
4-1. 作用域の拡大と周辺部
文法化と周辺部の関連性というと、「文法化した語彙の作用域の拡大」という話がされがちです。
上では文法化の具体例として、be going toがgonnaへ変化した例を挙げました。これは音声や意味の観点から言えば、gonnaという発音への縮小・移動の意味の縮小(漂白)であり、「文法化=縮小」と捉えることができます。
しかしながら、移動の意味が弱まったことによってbe going to (gonna)の後ろに続くことのできる動詞(like, thinkなど)の種類は増え、未来の相も新たに獲得しました。この観点であれば「文法化=拡大」と捉えることができます。
「文法化=縮小」という考え方は伝統的な文法化(狭義の文法化)であり、「文法化=拡大」という考え方は比較的新しい文法化(広義の文法化)等と言われています(cf. 堀田, 2015) 。
広義の文法化においては、文法化した表現は「自由な発話頭(文頭)の形式となり、機能の作用域が拡大する(小野寺, 2017: 16) 」と考えられているのですが、この"作用域"というものが形式意味論(formal semantics)の領域で用いられる概念であり、まだ僕がほとんど理解できていない概念であるため今回は解説を控えさえていただきます。 (理論言語学に興味のある方・数学に興味のある方は形式意味論を勉強してみてください…)
代わりに今回は、意味の漂白と周辺部の関わりをメインに書いてまとめに入ろうと思います。
4-2. 意味の漂白と周辺部
文法化の過程において、意味の漂白という段階があることを上で述べました。ざっくりとした定義が「本来その語句が持つ意味が薄まること」でしたね。
僕はこの「意味の漂白」という段階の分析において、周辺部が大きく関わってくるのではないかなと考えています。
例えば「この表現Xは文法化している」という主張をする際に、その表現が文法化のそれぞれの段階でどのように変化したのかを分析する必要があります。再分析の段階ではどのように境界線が変化したのか、音声的縮約段階ではどのように音韻変化が起きたのか、そして意味の漂白段階では語用論的変化の分析が必須となります。
周辺部において、LPの言語形式には「話順を取る(turn-taking) 」等の役割や主観的であるという特徴があるとされており、RPの言語形式には「返答を促す(response-inviting) 」等の役割や間主観的であるという特徴があるとされています(cf. 小野寺 (2017: 25)) 。
これに「(文法化した表現は)自由な発話頭(文頭)の形式となる」という指摘を併せて考えると、意味の漂白段階の分析がかなりしやすくなるのではないかと考えています。
つまり
①文法化しているのであればその言語形式は発話のはじめ(LP)に出現する
②LP特有の役割・特徴を持っており、その語用論的特徴が原義と異なっていれば意味の漂白が起きたと考えられる(かもしれない)
みたいな感じです。
文法化した表現全部が全部LPに現れるという保証もありませんし、LPの特徴と意味の漂白を結びつけるのもなかなか無理があるかもしれません。
あくまで学部生の1つの思いつきくらいに考えてもらえると嬉しいです。
5. まとめ
あくまで今回は、自分なりに色々勉強した結果何となく思いついた考えのメモみたいなnoteなので、ここで述べた意見は全くの見当違いな考えかもしれません。
しかしこれまで見てきたように、周辺部は語用論研究においてますます重要なものになってきているのは間違いないでしょう。
文法化・周辺部 どちらも比較的若い分野ですが、これらのような若い分野に興味を持ち、それらが今後どのような発展をしていくのかをリアルタイムで追えるというのは幸せだなと思いました。
久しぶりに言語学の話を書いて、自分がまだまだ勉強不足であることを再認識しました。これからも精一杯、英語史を中心に言語学を広く深く学んで研究していきたいなと思います。
ではでは。最後までお読みいただきありがとうございました。
最後に参考文献を挙げておくので、参照してください。
参考文献
Hopper, Paul J., and Elizabeth Closs Traugott. (2003). Grammaticalization (2nd ed.). Cambridge University Press.
Traugott, Elizabeth Closs. (2017). A constructional exploration into "clausal periphery" and the pragmatic markers that occur there. 発話のはじめと終わり ー語用論的調節のなされる場所ー, 第2章. ひつじ書房
小野寺典子. (2017). 発話のはじめと終わり ー語用論的調節のなされる場所ー; Periphery: Where Pragmatic Meaning is Negotiated. ひつじ書房.
堀田隆一. (2015). hellog ~ 英語史ブログ #2106 「狭い」文法化と「広い」文法化. [online] #2106.「狭い」文法化と「広い」文法化 (keio.ac.jp)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
