
兵庫県西脇市の議会改革の取組みを視察
委員長を務める議会運営委員会で兵庫県西脇市を視察しました(R5.1.24〜25)。
1. 調査事項
(1)議会改革の取組について
(2)議会DXの取組について
2. 西脇市の概要
西脇市は、兵庫県の中央やや東に位置している。加古川、杉原川、野間川の3つの河川を持ち、染色に不可欠の水資源に恵まれた地であったことから、200年以上の歴史を持つ播州織の繁栄で全国に知られる。兵庫県北播磨地区の北側、神戸市の北約50kmに位置し、東経135度線(根室市と与那国町のほぼ中間に位置する日本の標準時子午線)と北緯35度線(稚内市と波照間島のほぼ中間に位置する)が交差しており、経緯度で日本列島の中心点に位置することにちなみ「日本のへそ」とピーアールしている。兵庫県北播磨県民局管内に区分されている。北播磨地域中心の都市であり、中国山地の西光寺山を市の頂点にして、加古川流域沿いに播磨平野があり、その流域沿いに街や農地が広がっている。(Wikipediaを参照)
① 市制施行 平成17年10月1日、1市1町合併(西脇市、黒田庄町)
② 人口 38,716人(R5.1.1現在)
③ 世帯数 17,218世帯(R5.1.1現在)
④ 面積 132.44km
⑤ 位置 兵庫県のほぼ中央部、東経135度と北緯35度が交差する「日本列島の中心・日本のへそ」に位置する。
⑥ 地場産業
《播磨織》
国内の先染織物※の70%上のシェアを占め、その独特の製法により、自然な風合い、豊かな色彩、素晴らしい肌触りの生地に仕上がり、シャツやハンカチなど様々な製品に加工されている。

工房&アン テナショップ播州織工房館を視察 (1/ 24)
※「先染織物」⋯糸を先に染め、染め上った糸で柄を織る手法。
《播州釣針》
播州釣針の一種、播州毛鉤は、わずか1cm足らずの鉤に、数種類の鳥の羽根を絹で巻き、金箔・うるしなどを用い、虫に似せた生き物に作りあげる。播州釣針は、全国の総生産量の約90%を占める。
3. 調査事項(1)議会改革の取組みについて
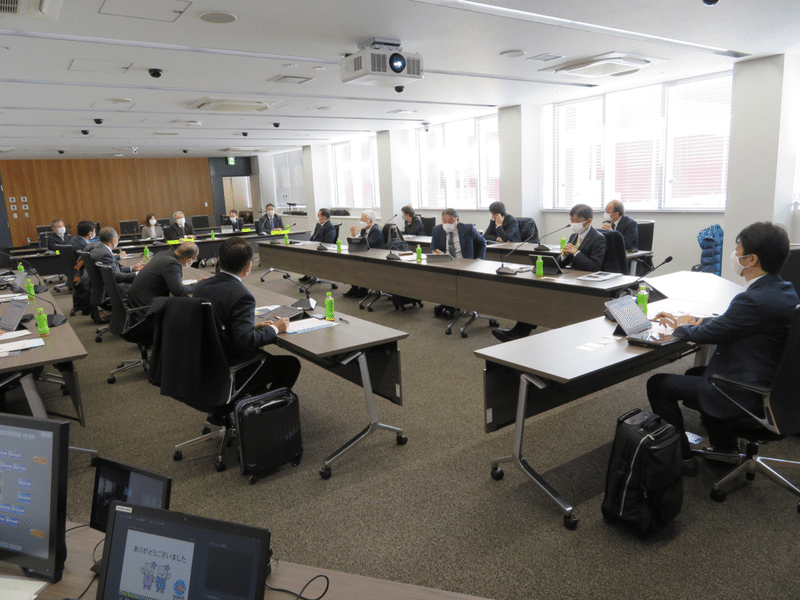
改革への経緯と3つの柱
平成20年2月29日に議員定数削減の陳情書が提出される。内容は、議員定数20人から16人へ削減を求めるもの。これを受け、平成20年6月24日、議員定数調査特別委員会設置、次いで、平成20年9月19日、議会改革特別委員会を設置。以降、数多くの議会改革に取組んできた。
平成17年の合併の際に定数削減案が提出されたがその際には否決した。その後、特別委員会を設置して定数については議論され、その間にシンポジウムなどを開催し、市民の意見を聴取も行い、定数18名の削減を経て現在の16名となった。
平成24年12月 には西脇市議会基本条例制定し、現在は議会運営委員会で議会改革全般を統括している。さらには、年に一度の基本条例の検証が条例に明文化されており、検証で課題を明らかにし、改善を加え、さらなる議会改革を進めている。市民にとって良い政策づくりを目指し、①市民参画 ②情報共有 ③議会機能強化の3つの柱に体系化し推進している。
① 市民参画
議会報告会(議会と語ろう会)の開催
5月・11月に開催、年間40会場以上
平成22年5月に第1回を開催(地区単位)
平成27年11月~町・町内会・自治会単位の開催に変更
令和元年5月まで計17回実施
令和3年8月オンラインで第18回、議会と語ろう会を開催
令和4年5月第19回、議会と語ろう会以降、通常開催に加え、オンライン議会報告会を実施。市民の評判もよく毎回行う方向となっている。
実施の形態としては、16名のうち議長を除く15名を3名ずつの5つの班に分け、1班が責任班となり、2班がサポートに回る。ワークショップ形式で開催。5月11月に開催し、2年間で80の全自治会を回る。
オンライン予算広聴会
新年度事業について市民から意見を聴取し、予算審査時の参考とするために開催するもので、令和3年度3月定例会中に初めて実施された。参加者1名。
課題懇談合(随時開催)
市内で活動する市民団体と常任委員会とテーマを決めて意見交換、市民団体からの申し込みか常任委員会からの申入れで随時開催される。
西脇市議会陳情書取扱規程を策定(令和元年7)
市民からの陳情を政策提言と位置付けるもので、従来、陳情書の受付は、定例会中の委員会で調査(年4回)し、所管常任委員会で合意形成をはかる形式だった。しかし、新制度では、毎月の定例常任委員会で審査できる。所管常任委員会で採択した場合は、本会議に意見書等をかけて、機関意思決定をする。
高校生版議会報告会
平成29年度より実施、市内3高校が対象(西脇高校·西脇工業高校·西脇北高校⦅定時制⦆)。主権者教育の部分をパワーポイントで説明し、地域課題をワークショップ形式で話し合うもので、令和元年度は7月に実施。西脇高校は1年生7クラスで、西脇工業高校は2年生6クラスで、西脇北高校は1年生2クラスでいずれも授業の一環として実施している。
当初は、中学生議会が行われていた。その感触がよく、その後、選挙権が18歳に引き下げられたのを契機に、議会が、主権者教育の必要性に鑑み、予算委員会で行政、議会、選管、教育委員で主権者教育に当たらなければならないとの提案を行った。そうした経緯から、高校生議会を行う運びとなった。当初の案は、高校生が来庁し議場で行う予定だったが、学校側が難色を示したため、議会が学校に出向く形式でスタートした。現在も、その形で行われているが、特別委員会で、高校生議会の内容の見直しが検討されており、同じような取り組みを行っている先進市の視察も行っている。
② 情報共有
会議録のインターネット公開
平成8年旧西脇市会議録より、公式の会議(本会議・全ての委員会・議員協議会)全てを対象にインターネットの配信を行なっている。
会議のインターネット中継・録画配信
公式の会議全てが対象となっている。
市議会ホームページの充実
あらゆる議会に関する情報は積極的にHPで公開している。
調査→報告→HP公開→市民と議会の共有
定例会情報·提出議案.案資料・議会活動状況・請願陳情・議会報告会・課題懇談会(一般会議)・文書質問・視察研修報告・委員会報告・議会だより・議会基本条例·政務活動費.議長交際費.行政視察資料その他
行政視察・研修等の報告書をHPに掲載
議員協議会で視察研修報告会を実施し、質疑・応答により議員間で課題の共有を図っている。
議長交際費をHPに掲載
政務活動費の収支報告・領収書をHPに掲載している。
議会だよりの充実
広報広聴特別委員会による編集発行を行っている。平成30年5月よりスマホ世代にも対応できるよう横書きレイアウトに変更。スマホアプリ「マチイロ」で配信している。市民の意見や要望を聴取し、一層の充実を図る目的で、令和4年から「議会だよりモニター」制度導入した。
議会公式フェイスブックページの開設
平成26年4月21日開設、HPの補完及び議会の取組等の情報をタイムリーに発信している。
③議会機能強化
議会における政策サイクルの導入
行政評価を実施し、年間を通しての特定所管事務調査を徹底する。最終は報告書を作成し、政策提案へ、また一般質問の成果を常任委員会へ付託し政策実現へ結び付ける。
定例会反省会の実践
毎定例会終了翌々日に議会運営委員会を開催し、前日までの定例会の反省会を行うことで、反省会で出た問題点の改善が議会機能強化に繋がる。
本会議場及び委員会室へのパソコン
タブレット等の持込みを可能にし、ペーパーレス化を推進。また議会独自のインターネット通信回線を整備した。
議員研修の充実
新人議員の研修派遣を実施
平成26年4月から改選後の新人議員を対象に、全国市町村国際文化研修所(JIAM)等に派遣し、議員力の向上に資する取組みを行っている。
年2回以上の議員研修の実施
基本条例検証に基づき、課題解決のための講師を選定し、ファシリテーション研修、周辺自治体議会との共同研修なども実施している。内容については議会運営委員会で決めている。予算は10万円。
市立図書館との連携
レファレンス機能の活用
その他
長期欠席者の報酬削減
西脇市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成22年3月制定)
議長・副議長立候補制度の導入
議場で立候補制を導入しており候補者は所信表明を行う。議場での様子はネット中継される。
議選監査委員も選挙で選出
委員会室で立候補制を採用している。ネット中継はされず非公開となっている。
議会BCPの取組み
西脇市議会災害マニュアルの策定
4. 調査事項(2)議会DXの取組について

取組内容
・平成27年に例規集の配布に替え、タブレットを配布し、例規集の更新をはじめとするペーパーレス化を推進してきたが、会議資料までには至っていない。(現在、例規集データの更新は行っていない。)
・議員専用Wi-Fを整備し、議場及び委員会室への議員個人のパソコン・タブレット等の持込を許可している。
・議会システムは導入していないが、無料クラウドサービス(Zoho Connect)を活用し、情報共有に取り組んでいる。
西脇市議会会議規則・西脇市議会委員会条例改正(令和4年2月)
災害等の発生、感染症の蔓延防止措置または育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開催する場所への委員会等への参集が困難であると委員長が認める場合には、オンラインにより委員会の会議に出席することを認め、かつ、委員が出席委員として会議に参加できるようにする。
オンライン会議の実績
オンライン委員会シミュレーション(令和4年8月26日)
オンライン文教民生常任委員会(令和4年9月6日)
課題について
議会DXに取り組む必要性があるとの意見から、議会運営委員会で「(仮称)議会DX調査小委員会の設置について」の提案がなされたが、委員からは①議案審査を充実させるのが先決である、②狙いとする成果、何のためにデジタル化を推進するのかという目的をはっきりさせるべきで、議会DXの取組みが、議会活動にどのように生かされるのか、議員活動がいかに便利になるのか等を議会として明確にする必要がある、との意見があり、委員会の設置には至っていない。現在は、有志による近隣自治体のDXについて調査が行われている。
5. 所感

視察を行った、西脇市は、議会改革において非常に高い評価を受けている先進市であり、2018年の日経グローカル議会活力ランキングは1位。早稲田大学マニフェスト研究所議会改革度ランキングでは2019年は1位,2020年では3位。そして昨年の第17回「マニフェスト大賞※」でも、「今、議会の存在意義が問われる議会が住民のなかにあるために」「―議会DXを推進し、より開かれた議会へ-」が「エリア選抜」となっており、常に高い評価を得ている。
「地方自治は民主主義の学校である」とイギリスのJ・ブライスは言ったが、これは、国の政治体制である議院内閣制とは異なり、地方自治は二元代表制をとることで市民の民意を反映しやすいということからも、現代の日本でもこの言葉は当てはまると言える。しかしながら、近年の地方選挙の状況を見ると、投票率の低さや無投票による当選も見られ、議会制民主主義の危機と言わざるを得ない状況である。政治的無関心は、国レベルはもちろん地方においては一層の広がりを見せている。こうした状況を克服するためには、議会が市民にとって、その意見を地方政治に反映する機関として、より身近で、十分に機能するものとなり、またそのようにとらえ直される必要がある。そのためにも、不断の議会改革を進めていかなければならないと考える。
議会はそもそも、制度的には「政策形成機能」と「行政監視機能」の二つの機能が求められている。これまでの地方議会は、おおむね「行政監視機能」を重視してきた。それは予算編成権が議会にないことや議会事務局の体制が十分な規模と機能を有していないことにも起因している。しかしながら西脇市議会は、議会を二元代表制の一翼を担うものとして「行政監視機能」だけではなく、「政策形成機能」の強化を進めており、①市民参画 ②情報共有 ③議会機能強化が、議会改革の柱として位置付けられており、徹底的な取組が行われている。
①市民参画では、議会報告会、市民団体との課題懇談会、高校生版報告会など、福生市議会にはない取組みが行われている。市民とのひざを交えた意見交換は、市民に議会を身近な印象を与えるとともに、様々な課題を集約し、解決に資する政策の形成に大きく寄与するものと思われる。また高校生版報告会は、政策形成に若者の意見を集約し取り入れるだけではなく、シチズンシップ教育、主権者教育といった部分を担っている。法的課題をクリアし、主権者教育の一端を担う機能を有していることは、選挙権年齢の引き下げが行われた今日、新たな議会の役割として考えていくべきだと感じた。
②情報共有については、委員会なども含め、公式の会議は、全てインターネット中継されている。議論の過程を市民と共有できる環境が整備されていることは、非常に重要で、全国にも標準化されていくと考えられる。③議会機能の強化では、定例会反省会の中で行われる議員間討論により、質問のレベルアップが図られている。議会における政策サイクルの導入では、質の高い一般質問についてさらに研究し、その成果を常任委員会へ付託し、政策提案につなげている。また議員研修については予算を計上し、充実させることで、議員個人の審査能力のみならず、政策力強化が図られている。
さて、もう一つの調査事項であった議会DXの取組みについては、「狙いとする成果、何のためにデジタル化を推進するのかという目的をはっきりさせるべきで、議会DXの取組みが、議会活動にどのように生かされるのか、議員活動がいかに便利になるのか等を議会として明確にする必要がある」との意見があったことから、現在は有志による調査が行われている。西脇市の林議長が「ペーパーレス化がDXではない。DXを進めた結果、ペーパーレスになったということ」、「市民のDXに対する関心はないが、議会だけがDXしても意味がない。行政もDXしなければ、市民の利益にはならないと考えている」との意見を述べていた。福生市もタブレット端末の導入を果たしたところであるが、議員一人一人が使い慣れてくる中において、議員活動への有効な活用が実践の中で図られていくと考える。また議会だけではなく、林議長の言葉通り、市全体のDXが進むことで、更なる有効活用の道が開けてくると考える。議会及び市全体としてのDXの推進が求められる。
議会改革は一朝一夕に成し遂げられるものではない。西脇市の議会改革は特出した一部の議員の意識の高さや技量によるところも大きいと感じたが、議会改革の必要性を議員一人一人が深く認識し、全体の意識をどのように高めていくかがカギである。そして、それは、とりもなおさず議会制民主主義や二元代表制という制度の本質的理解と当該地方議会の現状に照らし合わせて、これを機能させるには何が必要なのかを熟慮し、そのうえで実践につなげていく必要がある。またさらには、「政策形成機能」を担いうる議会となるためには、議員の努力と同時に議会事務局の体制の充実を図る必要があると感じた。その前提として、議会事務局と議員の関係性を見直す必要があると考える。
福生市議会も議会改革を進めてきた。議会改革に関する特別委員会、議会改革に関する協議会、議会運営委員会で導入に向け検討を重ね、議会改革の取組(令和元年6月から令和4年7月まで)が評価され、第17回マニフェスト大賞「エリア選抜」に選出された。今回の視察を足掛かりに、二元代表制に相応しい、さらに市民に信頼される議会となるよう、議会改革を押し進めていかなければならない。
※マニフェスト大賞実行委員会主催。地方自治体の議会、首長、市民等による、地域の民主主義向上に資する優れた取り組みを募集し表彰するもの。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
