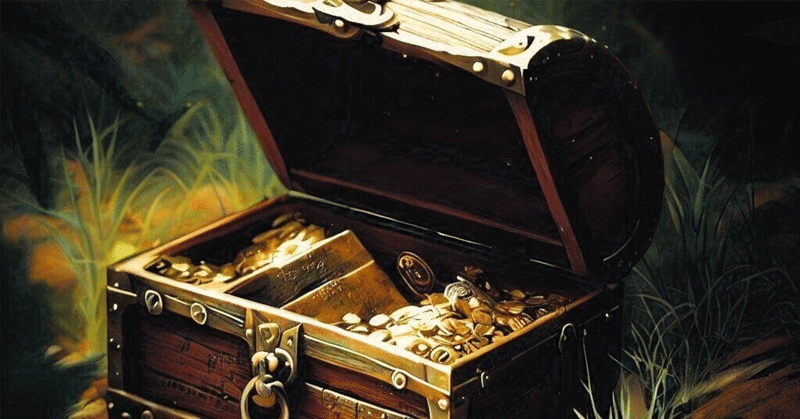
小1息子とはまっているボードゲーム
登校渋りでこのまま不登校になるかもしれない、というときに、夫が息子に買ったボードゲームがある。
"ただ遊ぶだけ"じゃなく、"頭を使って遊ぶ"が狙い。
これが、大人も楽しめるものなので、ちょっと紹介したい。
カタン
資源を獲得し、開拓地や街道を作っていくゲーム。
開拓地1ポイントなど、ポイントが割り当てられており、先に10ポイント達成できた人が勝ち。
開拓地や街道を作るには資源が必要なので、他のプレイヤーに交渉したり、銀行で他の資源に交換したりしながら獲得を目指す。
"発展カード"というチャンスカードもあるので、一発逆転の可能性もあり。
息子は「街道マスター」(街道をひたすら伸ばす)や「騎士カードマスター」(発展カードを引いて、ひたすら"騎士カード"を集める)になるのが楽しいよう。
資源交渉も積極的にやる。「お母さん、小麦あんまり手に入らんのやろ?ケンの羊毛と交換してや!」てな感じ。
夫・私・息子でやることが多く、1回につき1時間くらいはかかる。
場の見極めも大事だが、運によるところも大きいので、一番頭の良い夫でも私に負けることもある。
それがまた楽しいのだ。オセロとかだと絶対勝てんし。
ラビリンス
迷路を動かしながら、決められた宝物をゲットしていくゲーム。
ラビリンスの面白いところは「えー、これどうやっても宝物にたどり着けん!道が見えない!」と思っていても、「とりあえず動かしてみよ」と動かしてみたり、他のプレーヤーが動かした結果により、「あ!道が開けた!」ということが往々にしてあるということ。
この感覚が楽しくて好き。
そしてこれ、人生と一緒だなぁと思うのだ。
「道が見えない…」と思っても、がむしゃらに動いてみることや、他の人の働きかけで、「道が開けた!」ってことはある。
今の私が置かれてる状況もまさにそう。これだから、人生もラビリンスもやめられない。(ちょっと違うか)
アトモン
息子の「仮面ライダーのカードがほしい!」というところを見て、「それならこれも食いつくだろう」と夫が選んだアトモン。
原子記号をそろえて、アトモンをゲットしていくゲーム。
点数が高い方が勝ち。
神経衰弱のようにも遊べるし、対戦ゲームとしても遊んでもよし。
「よっしゃー!鉄が出たから鋼が作れる!」
「お母さん、それやったら水酸化ナトリウムが作れるよ!」
小学校1年生の息子からそんな言葉が出るので、ゲームをよく知らない祖父母はびっくり。
原子記号を覚えてほしいわけでもないが、化学を知るひとつのきっかけになってくれればいいなぁと思っている。
*
小学校1年生の勉強といえば、「音読」とか「ひたすら読み書き」とかそういったことが中心となる。
勉強ってそれだけじゃない。
もちろん、基礎的なところは押さえてほしいが、"頭を使って考える"楽しさも知ってほしいのだ。
そしていかんせん、息子はそういった「読み書き」が苦手だから。
他のアプローチも必要と思っている。
そして何より、楽しい。これが一番大事。
息子と夫は"レゴ"という共通の遊びがあるのだが、私はあまりレゴが得意ではない。
「お母さん、レゴしようよ!」と誘われても、「お母さんはいいわ~」ってなっていた。
でも、ボードゲームなら私も楽しい。
「お母さんもやる!」と入れてもらえる。
*
親子三人でゲームができるって楽しい。
私の子どもの頃を思い返すと、人生ゲームを買ってもらったのに、親とは遊んだことがなかった。
友だちとやるか、独りで3役くらいやって遊んでいた。
両親が忙しかったので、そんな暇もなかったのは重々わかっている。
でも、私は今、息子と遊びたい。
夫と三人で、遊びたいのだ。
娘も大きくなったら、親子四人で遊びたいと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
