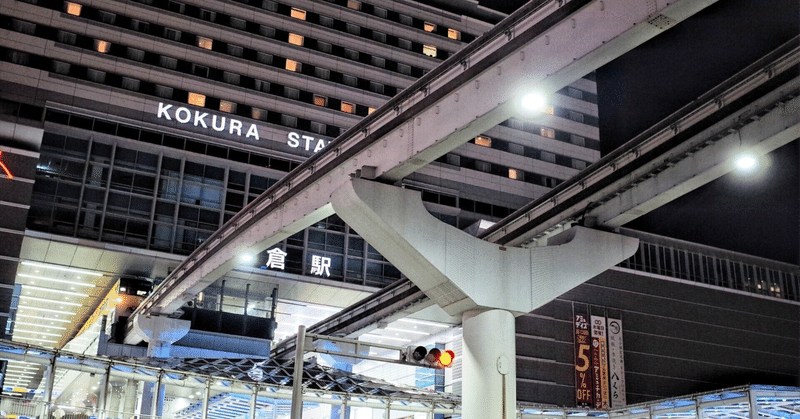
こんなことを研究しています
所属している研究室
僕は理系大学院生なので、普段どんな研究をしているのかを述べておこうと思います。僕の専攻は物理学で物性理論の研究室に所属しています。
物性理論は読んで字のごとく物質の性質を理論的に研究します。理系の研究というとフラスコとかビーカーを使った実験のことを思い浮かべる方も多いと思いますが、理論の研究では紙とペンとコンピューターを使ってゴリゴリ計算をし、実験はしません。
そしてその物性理論の研究分野の中でも僕は量子多体系を研究テーマに選んでいます。似たような研究をしていない人にとってはなんのことかさっぱりわからないと思いますが、できるだけわかりやすく簡潔に説明しようと思います。
自分もまだこの分野について知識が浅いので、うまく説明できているか怪しいですが自分の理解できている範囲で説明しようと思います。
僕たちの身の回りにある物質は原子でできています。例えば水は水素原子と酸素原子でできています。そしてこの原子をさらにこまかく見ると原子核・電子・中性子に分けられます。これらは量子とよばれます。
物質の振る舞いを説明する上では電子のはたらきが重要になり、この電子についての方程式(シュレディンガー方程式)を解くことが肝になります。
ここで問題になるのが物質内でたくさんの電子たちが相互作用しあう場合です。1つの電子だけならシュレディンガー方程式が厳密に解けるのですが、多数の電子が相互作用する場合は厳密にシュレディンガー方程式を解くことができなくなります。
そこで、厳密ではなくても物理現象を説明できるぐらいまでの精度でシュレディンガー方程式を解く方法を見つけることが必要になってきます。
それを研究するのが量子多体系の研究です。専門家からすればかなり浅い説明になっていると思いますが、僕なりの頑張った説明なのでご了承ください。
似たような研究をしていない人にとってはまったく興味のわかない話かもしれませんが、私も最初は全然この分野が面白いとは思いませんでした。
でも研究テーマにするぐらいに興味が出てきたのには理由があります。
この研究テーマを選んだきっかけ
それは大学3年生のあたりまでさかのぼります。当時の僕は合理的な判断ができるようになりたいと思っていて、それに関連した認知心理学や行動経済学の本を趣味で読んでいました。
少しでも興味があればどんどん読んでいこうと乱読していたときに、ある人の本に出会います。その人とはナシーム・ニコラス・タレブです。
https://www.amazon.co.jp/本-ナシーム・ニコラス・タレブ/s?rh=n%3A465392%2Cp_27%3Aナシーム・ニコラス・タレブ
彼は文筆家、トレーダー、大学教授および研究者という3足のわらじを履く知の巨人です。彼の主な研究テーマは運、不確実性、確率などで人間にとって理解不能な世界で生きていくためのルールを考えています。
僕は彼の考え方に多大な影響を受けました。トレーダーとして不確実性と向き合ってきた彼の合理性に対する考え方は本物だと思いました。それまでに僕が認知心理学や行動経済学で学んだ合理性は、不確実性を考慮できていないのではないかと疑問に思い始めました。
世に出回っている知識やノウハウはものごとを単純化しすぎていて、世界はもっと複雑でカオスに満ちていることを忘れているのではないかと彼の本を読んで思いました。
そして量子多体系も彼の言っているこの世界の複雑性と関係していると思いました。たくさんの電子が影響を及ばし合い一気に複雑になることと、たくさんの人間が関わり合って世界が不確実になることが僕の中で同じことのように見えました。
量子多体系の研究対象は物質ですが、この複雑性の考え方はいろんなところで応用できるのではないかと思い、この研究テーマを選んだのです。
また僕が知識系の記事をエッセイ形式で書くのも彼の影響を受けています。彼の本はどれもエッセイ形式で書かれていています。
彼は身銭を切っていない人のアドバイスは信じてはいけないということをこれまでの人生で学び、僕もその考えに賛成して自分で体験したことに関する知識しか広めたくないので、エッセイ形式で書いています。
実際に自分で行動をした上でのアドバイスの方が、ただ理論を並べただけのアドバイスよりも信用できるからです。だから自分も世界の複雑性を理解する上で、自らが率先して物理の複雑系の分野を研究しようと思いました。
まだ大学院生活は始まって1ヶ月なので量子多体系の知識は浅いですが、この研究で学んだ知見と読書で勉強したことと実生活のことをできるだけ組み合わせてこれからも記事を書いていこうと思います。
では、よい1日を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
