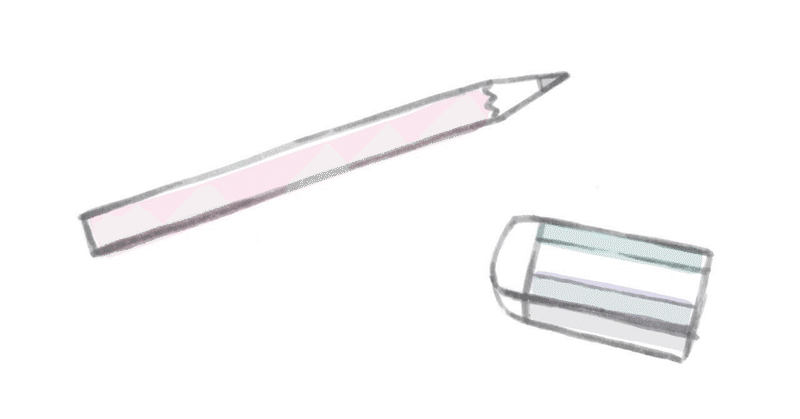
エッセイの2大流派
近頃、エッセイの書き方について勉強している。
"守破離"の言葉通り、まずはなんと言っても基本の型を身につける必要があると、感じたから。
基本を守り、身についてきたらそれを破り、最後はその型から離れてオリジナルを生み出す、という段階を踏む必要がある。
うまいエッセイを読むだけでも勉強になるが、もっとこうなんていうか、システマチックにエッセイというものを学んでみたくなった。感覚的にうまく書けちゃう人もいるのだろうけど。
そんなわけでさっそく、YouTubeで「エッセイ 書き方」と検索をかける。
幻冬舎の公式チャンネルで、【エッセイの書き方講座】というものがあった。これだ。これにしよう。
第1回の動画をポチる。ほうほう、第1回はテーマについての話か。
大学の授業動画よりも真剣な眼差しで、この解説動画に見入っていた。自分から進んでやる勉強は、やはり頭に入りやすい。
驚いたのは、テーマは大きく分けて2つに分類できる、ということだ。
モンテーニュの『エセー』のような文章と、清少納言の『枕草子』のような文章に分けられる、らしい。
モンテーニュの『エセー』のような文章とは、動画の解説文を引用すると、
人間の内面に深く切り込み思索したもの
とある。ちなみにエッセイの語源は、この『エセー』から来ている。
僕も一度読んでみたのだが、エッセイというよりは哲学書に近いイメージだ。物語形式ではなく、書きながら自分と対話をして考えを深めていくような文章。考えることが大好きな人は、この『エセー』タイプの文章を書くことが多いと思われる。
もう一つの『枕草子』は、日本人なら誰もがご存知だと思う。同じように動画の解説文を引用すると、
日常生活で体験した事実を元に鋭い観察眼で表現したもの
とある。「春は、あけぼの〜」に代表されるように、なんてことない日常の中に新たな発見を見出し、読者に気づきを与えるような文章。
実体験を元に書くので、私小説に近い文章になる。物語形式なので読みやすいが、ただの体験談だけを書いた文章になってしまう難しさもある。ユーモアセンスのある人は、この『枕草子』タイプの文章を書いていることが多い傾向にあると感じる。
*
エッセイには無数のテーマがあるが、それらも大別すれば、このどちらかのタイプになるらしい。
たしかに、これまで読んできたエッセイを振り返ってみると、『エセー』タイプか『枕草子』タイプのどちらかだった。僕自身のエッセイもそうだったと思う。最初の頃は『エセー』タイプのものばかり書いてたけど、今は『枕草子』タイプにも挑戦している。
どちらのタイプもそれぞれ良さがあるので、テーマによって使い分けることで(あるいはミックス)、より魅力的なエッセイストになれるのではないか
という月並みな感想を残して、終わろうと思います。
あとどちらのタイプも、年齢を重ねるほど、味が出そうだなあと感じました。
わいも、もっといろんな経験を重ねないとなあ、と思った次第です。オメエの文章は、まだまだ青いからナ。
第2回、第3回と【エッセイの書き方講座】の動画は続くのか。
ふう。
やっぱ違う動画見よーっと。
これぞ、易きに流れる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
