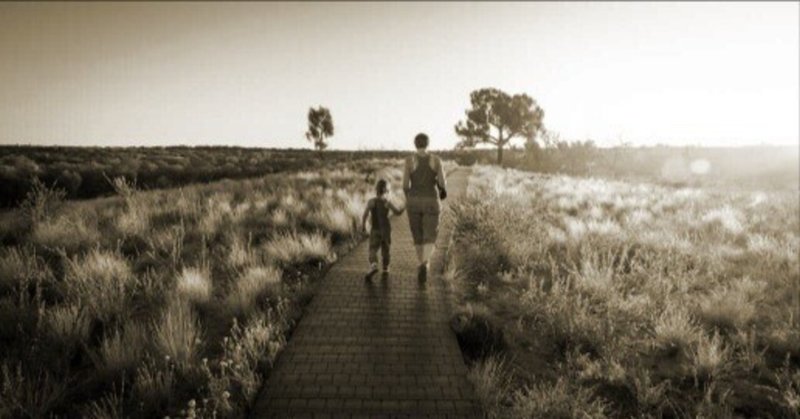
現在日本で検討されている親子交流手続きの問題点(日本語版)
この記事は、法務省が法制審議会家族法制部会に提示した「要綱案たたき台」に対してアメリカの著名な監護評価者であるケン・ルイス博士から頂いたコメントを紹介するものです。
ケン・ルイス博士のプロフィールは以下の通りです。
ケン・ルイス博士の専門は、片親疎外と高葛藤の監護権事件です。過去25年間、子の監護権分野において専任で働き、25以上の州とカナダで裁判所任命の後見人または監護評価者を務めてきました。ケン博士の子の監護権に関する著書は、「Family Law Quarterly」、「The Judges' Page」、「Child Welfare」、「Children Today」などに掲載されているほか、「The Five Stages of Child Custody」と題する書籍も出版しています。アメリカでは、ラジオやテレビなどのメディアにゲストとして頻繁に登場し、アメリカ全土でワークショップを開催しているほか、国際的なプレゼンテーションも行っています。また、全米少年家庭裁判所裁判官協議会の国際委員会のメンバーを長年務めています。
立法の流れ
諮問の目的(上川法務大臣の発言要旨)
近年,父母の離婚に伴い,養育費の不払いや親子の交流の断絶といった,子の養育への深刻な影響が指摘されている。また,女性の社会進出や父親の育児への関与の高まり等から,子の養育の在り方も多様化している。
このような社会情勢に鑑み,子の最善の利益を図る観点から,離婚及びこれに関連する制度につきまして,検討を行う段階にある。
今回,父母の離婚に伴う子の養育の在り方を中心とし,離婚制度,未成年養子制度や財産分与制度といった,離婚に関連する幅広い課題について,チルドレン・ファーストの観点で,法改正に向けた具体的な検討を行っていただくために,法制審議会に諮問することにした。
これまでの経過
2021/02/15 法務大臣が法制審議会に家族法制度の改正を諮問
2021/03/30 第1回会合が開催される
2022/11/15 第20回会合で「家族法制の改正に関する中間試案」が取りまとめられる
2023/08/25 第30回会合で「家族法制の改正に関する要綱案を取りまとめるに当たってのたたき台」について意見交換
<法制審議会での議論>
今後の予定
2023/11 法務省が法制審議会に要綱案を提出
<法制審議会での議論>
2023/12 法制審議会が要綱案を法務大臣に答申
<法務省が家族法制の改正法案を作成する>
2024/01 与党が改正法案を審査
政府が改正法案を国会に提出
親子交流に関する現状の法手続き
⑴別居後に同居親が別居親と子の交流を阻む場合
別居後に同居親が別居親と子の交流を阻む場合には、「親子交流調停」を申し立てるのが一般的です。次のような流れとなります。調停申し立てをしても、3カ月以上の期間、子どもと会うことができません。
また、交流の頻度は月1回、交流の時間は1回当り数時間が一般的です。

⑵実子誘拐された場合
実子誘拐された場合は、⒜子の監護者指定(調停/審判)、⒝の引渡し調停、⒞審判前の保全処分の3つの手続きを同時にするのが一般的です。
⒜子の監護者指定:誘拐被害者である親が自分を監護すべき者にすることを求める手続き
⒝子の引渡し調停:監護者指定を受けた親に子を引渡す命令を求める手続き
⒞審判前の保全処分:子の急迫の危険を防止するために審判前に仮決定を求める手続き
⑶裁判所が定めたことを同居親が守らない場合
同居親が、裁判所が定めたことを守らない場合の手段として、履行勧告、金員支払いの請求が用意されていますが、それ以上のペナルティは事実上ありません。監護権の変更手続きにしても、「継続性の原則」という裁判所にとって都合の良い運用ルールに基づき、同居親が養育上の問題を起こしていなければ、同居親が監護権を維持します。
なお、私は独学で法律を勉強しているので、正確を期すためには、日本の家族法制に詳しい法律家にご確認をお願いします。
中間試案における親子交流手続きに関する提案(2022/11/15)
以下の提案がパブリックコメントに掛けられました。
⑴ 調停成立前や審判の前の段階の手続
親子交流等の監護に関する審判事件又は調停事件において、調停成立前又は審判前の段階で別居親と子が親子交流をすることを可能にする仕組みを検討する。
⒜急迫の危険がなくとも、親子交流が認められてしかるべきと考えられる等の場合は、家庭裁判所が暫定的な親子交流の実施を決定できるものとする。併せて、家庭裁判所の判断により、交流支援団体等の協力を得ることを、この暫定的な親子交流の実施条件とすることができるものとする。
⒝家庭裁判所は、一定の要件が満たされる場合には、原則として、調停又は審判の申立てから一定の期間内に、1回又は複数回にわたって別居親と子の交流を実施する旨の決定をし、必要に応じて、家庭裁判所調査官に当該交流の状況を観察させるという新たな手続を創設する。
⑵ 成立した調停又は審判の実現に関する手続等
親子交流に関する調停や審判等の実効性を向上させる方策(執行手続に関する方策を含む。)について、引き続き検討するものとする。
要綱案たたき台における親子交流手続きに関する提案(2023/8/25)
中間試案で提案されていた「調停成立前や審判の前の段階の手続」並びに「成立した調停又は審判の実現に関する手続等」が削除され、別居親の申立後すぐに親子交流を再開する道が断たれました。更に、合意した交流を同居親が履行しない場合の対策(制裁措置)についても、検討が放棄されています。
寧ろ、子どもとの交流を再開する時期を遅らせ、再開できる条件を追加し、同居親に裁判所命令に対する拒否権を与え、実子誘拐犯にとって有利になる提案に入れ替わっているように思われます。要するに、現状実態をなぞった提案になっています。
以下が、要綱案たたき台に記載されている「裁判手続きにおける親子交流の試行的実施」の文面です。
⑴家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がない場合であって、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、父又は母と子との交流の試行的実施を促すことができるものとする。
⑵ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施を促すに当たって必要があると認めるときは、交流の日時、場所及び方法並びに家庭裁判所調査官その他第三者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止し、その他適当と認める条件を付すことができるものとする。
⑶ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施の状況について、家庭裁判所調査官に調査をさせ、又は当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができるものとする。
ケン・ルイス博士が指摘した問題点とコメント
調停申し立てをしても、3カ月以上の期間、子どもと会うことができません。また、交流の頻度は月1回、交流の時間は1回当り数時間が一般的です。
正当な理由なく親子を引き離すことは、子どもに懲罰を与えることと同じです。 「月1回、数時間」という指針には、「子の最善の利益」という基礎が存在していません。 この指針が頑強で、そのために、子どもは別居している親との絆を従来よりも弱める傾向があるかも知れません。
同居親が、裁判所が定めたことを守らない場合の手段として、履行勧告、金員支払いの請求が用意されていますが、それ以上のペナルティは事実上ありません。
この措置では、同居親が裕福である場合、命令不履行に対して価値のある結果は得られません。 金銭的な懲罰は往往にして効果がありません。それよりも良い措置は、両親の養育時間を交替すること、同居親の養育時間を短縮することでしょう。
「継続性の原則」
アメリカでは、家庭裁判所によっては、これを「主たる監護者 (primary caretaker)」の原則と呼んでいます、つまり、監護権は、離婚前に育児をより多くしてきた親に行くべきだという原則です。もちろん、主たる監護者は通常母親を意味します。
「主たる監護者」の原則を単独監護の要因子としている州は、たった1しかありません。 この原則は、監護権論争のあらゆる方面から批判されてきました。父親の権利擁護団体は、この原則は実際には性別に囚われないルールに見せかけた母親優先であると主張しています。母親の権利擁護派は、男女のダブルスタンダードを設定していると主張しています。最後に、フェミニストたちは、この推定が、子どもの養育に関連するジェンダー的役割を社会に定着させると主張しています。
親子交流等の監護に関する審判事件又は調停事件において、調停成立前又は審判前の段階で別居親と子が親子交流をすることを可能にする仕組みを検討する。
最良の方針は、子どもがそれぞれの親と、子どもがこれまでに経験した養育時間と同じか、または同様の養育時間だけ交流できるようにすることです。
必要に応じて、家庭裁判所調査官に当該交流の状況を観察させる。
家庭裁判所調査官は、訓練されたソーシャルワーカーであるべきであり、観察に加えて、面接を行い、関連文書を確認すべきです。
(別居親と)子どもとの交流を再開する時期を遅らせ
「(別居親と)子どもとの接触を再開する」という概念そのものが、処罰期間の終了を意味しています。この概念は児童福祉政策に反します。親と子の接触を妨げることは、通常、重要な監護権の原則「親の不祥事のために子を罰してはならない」違反です。
ケン・ルイス博士への質問と博士の回答
質問1⑴:アメリカでは、別居親が子どもとアクセスするために調停を申立てた場合、申立てから何日後に子どもにアクセスできるようになりますか?
1点目:アメリカには子どもの監護権に関する連邦法はありません。各州または管轄区域が子どもの監護に関する法律を管理します。例えば、ある州は、前回の監護命令から2年以内は監護権の変更または修正の申立てを提出できないという法律を制定し、他の州にはそのような規則はなく、いつでも変更の申立てを提出することができます。
2点目:別居親(私たちは訪問親と呼んでいます)は、既にアクセス権の命令を持っているものとして定義されます。別居親が(個人的にまたは裁判所を通じて)調停を求める唯一の理由は、既存の監護権の取決めの変更を求めるためです。調停が成功した場合、その結果は裁判所に提出される同意命令になるかもしれません。
3点目:調停プロセスを通じて、親子の接触は維持されます。この質問の仮定(何日かかりますか?)は、調停の申立て時点で子どもとのアクセスが終了することを示唆しています。このような事態は、日本の法律ではあり得るのかもしれませんが、アメリカの全ての管轄区域で容認されることはありません。児童虐待の場合を除き、親子のアクセスを拒否するという考えそのものが、単に「子の最善の利益」という私たちの主要な指令に反することになります。
質問1⑵:「監護権の原則」に基づいて、(子どもとのアクセス再開に要する)日数を法的に定めているでしょうか?(例えば、ハーグ条約では判決は6週間以内に出さなければならないとされていますが、そのような決まりはあるのでしょうか?)
アメリカでは、そのような法的に定められた日数はありません。
質問2:監護親をどちらかに決めざるを得ない場合、「主たる監護者 primary caretaker」がその判断基準に占める割合はどの程度でしょうか?(監護の割合を決定する項目とそれらが決定に寄与する典型的な割合を教えて下さい)
「主たる監護者」の原則が推定されている州は1つだけです。言い換えれば、裁判官は推定から始め、証拠が推定を覆さない限り、どちらか一方の親が優先されます。他の多くの州では、「主たる監護者」の原則は、考慮すべき多くの法定監護要素のうちの1つにすぎません。また、別の州(ニューヨーク州など)では、法定の監護要素が存在しません。
「監護の割合と、それらが決定に寄与する典型的な割合」については、全国的な統計は存在しません。私が監護評価者として任命された多くの事件では、私が確認できたデータによって強い意向が裏付けられた年長児に関する事件を除いて、「主たる監護者」の要素が決定打になることは殆どありませんでした。
質問3:日本では、「両親間の不和が子供に悪影響を与えるため、離婚後の共同親権は望ましくない」と主張する人が未だに存在しています。子どものために葛藤を減らそうという発想がないのです。とはいえ、確かに、高葛藤を解消できない事件もあると思いますが、その場合、アメリカではどのような監護が推奨されるのでしょうか。
質問3を別の言葉で言い換える:「アメリカでは、共同監護命令を支持する事件は、どのような種類の事件なのでしょうか?」
⒜ 共同監護(Joint Custody, JC)の定義。共同監護は、健康、教育、宗教、福祉などに関する子どもに関わる重要な決定を下す法的権限です。殆どの州では、決定権限は均等に共有(share)されています。しかし、一部の州では、決定権限を両親の間で分配(distribute)できます。例えば、一方の親は教育に関する決定権限を有し、もう一方の親は宗教について決定権を有する等です。養育時間(訪問、アクセスなど)は、子どもの利益を裏付ける証拠によって決定されます。共同監護に関する最初の文献(1970年代)で主に考慮されていたのは、親が子どもに利益をもたらす最小限のレベルのコミュニケーションと協力を維持できるかどうかでした。長年にわたり、殆どの管轄区域は共同監護の方向に傾くと同時に、主に養育時間をどのように配分するかに焦点を当ててきました。
⒝ 監護権の変更(C-mod)。当初の監護権が共同監護(JC)で、数年後の現在、どちらかの親が養育時間の変更を求めて、「監護権の変更」を申請する場合。どちらかの親が当初のJCを単独監護に変更しようとしない限り、JCのままです。
⒞ 当初の監護権⑴。親がJCを求める監護の手続きを申立て、申立てに対する回答もJCを求めている場合。裁判官がJCから単独監護に変更する証拠を見出さない限り、JCのままになります。この裁判では、どのような養育時間が子にとって最善の利益となるのかを中心に検討します。
⒟ 当初の監護権⑵。両親が2人とも単独監護を求めている場合。私の評価で、両親の間に特定の敵意が維持されてはいるものの、監護権訴訟を起こす前と同様に子どもに関する決定を共有し続けているという証拠が得られたなら、私はJCを推薦します。
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
