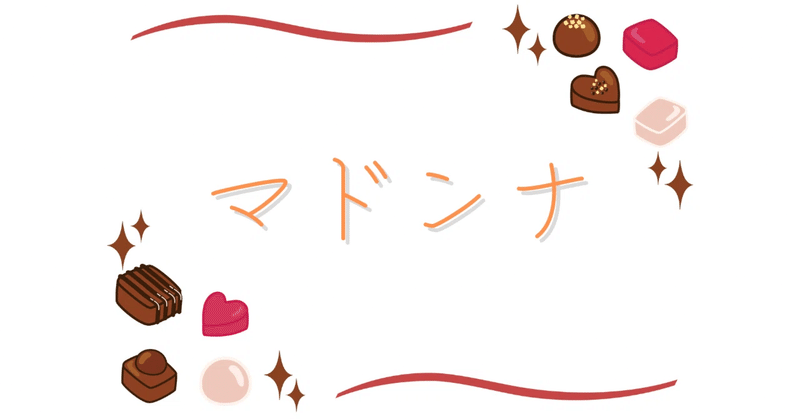
マドンナ 第3話《デートの誘い》【短編小説】
明日にデート決行を控えた前の晩。
ユースケは、二十二時を回ったところで早々に布団に入った。
『告白の前は十分に睡眠を取る』
これもサチの教えである。
五時間の睡眠時間と八時間の睡眠時間を取った人では、八時間睡眠を取った人の方が四パーセント魅力が増して見えるという。
目が活き活きとしている、声にハリが出る、肌艶が良くなる、ほんのわずかな差ではあるものの、少しでも印象を良くしようと思うなら決して侮ってはいけない要素だそうだ。
今回の告白は、これまで以上に気合が入っている。
なんとしてでも成功させたい。
どういうわけか四十歳の節目は、人生の転換期のような気がしている。
それは介護保険を徴収され始めたり、中年期という部類に属したりするせいかもしれない。
なんにせよ、この節目を華々しく迎えるためにも、明日に向けてでき得る限りの準備を整え、盤石の体制で望むべきなのだ。
まず、明日の流れを確認して置かなければならない。
待ち合わせは十五時に津先駅の改札。
ここで女を待たせるのはご法度。遅くとも三十分前には駅に着いてないとダメである。朝が早いわけでもないし、なんてことない。
もっとも、どれだけ朝が早い待ち合わせであっても、デートなら三十分前に着くようにするだろうが。
本音を言えば、朝から丸一日デートが良かった。
だが、モナが仕事明けだと言うのだから仕方がない。酒飲んで接客をし、その数時間後にデート。こっちにとってはデートだが、向こうにとってはデートなのか――少なくとも完全プライベートというわけではない。
例え、プライベートであったとしても、ロクに睡眠も取らず、酒が残った身体で遊びに出かけるのはしんどいわけで、向こうの都合を考慮することが正解であろう。
『初めてのデートで長時間のデートはやめましょう』
サチもそう言っている。待ち合わせ時間はこれで問題ない。
モナと落ち合ったら浜側美術館へと向かう。
美術館、これが鬼門なのである――。
モナは芸術に造詣のある娘だった。
ユースケがそれを知ったのは、デートに誘う直前だった。
『デートに誘うときは相手の予定を聞いて、関心の強い場所を提案する』
サチはそう言う。
デートに誘う下準備として、モナのいるキャバクラに行き、どんなことに興味があるのか聞き込んだ。
「もし彼氏がいてデートに行くとしたら、どこに行きたい?」
もう少し聞き方があるだろうと思う質問の仕方である。
「もし彼氏がいてってどういうことですか? 彼氏いないんですけど」
「仮にだよ、仮に。もしいたとしたら、どこに行きたい?」
「うーん、ルーヴル美術館展に行きたいですかね」
「ルーヴル美術館?」
ユースケは店内の喧噪の中で、思考が一瞬止まった。
このキャバクラであまりにも不釣合いな言葉に面食らったのである。
「お高いなぁ。なに? ルーヴル美術館? いきなり海外に行っちゃいます? ルーヴルねぇ、ルーヴル。ねぇ、ルーヴルってどこ?」
「なに言ってるんですか、違いますよー。ルーヴル美術館展。美術館のコレクションが浜側美術館に来てるんです」
「ああ。ああ、そういう感じの美術館ね! オッケー、オッケー」
無知丸出しである。
美術館とは想定していた範疇を大きく逸脱した回答だった。
考えていたのはせいぜい、どこかに食事に行く、買い物に出かける、映画を観るなどそんな程度のものだった。過去においてキャバ嬢をデートに誘い出せた経験がそれしかない。
同じ質問をしてディズニーランドと言う嬢もいたが、いざ誘ってもデートに結びつかなかった。貸切船でクルージングと言うものもいて、それは自ら手を引いた。
ただ美術館は冗談を言っているのではないかと思うほど、このキャバクラでは馴染みがない言葉で、ユースケにとっても無縁のものだった。
「モナちゃんは美術館、好きなの?」
「はい。そんな頻繁じゃないですけど、たまに行ったりしますよ」
「へぇ、そうなんだ。ちなみに美術館以外で他に行きたいところはあったりする?」
「うーん……クラシックコンサート?」
「ああ。クラシックねぇ。他には?」
「あとは……お能とか」
ユースケは返す言葉を失った。
無縁も無縁。芸術の「げ」の字もない人生を歩んできたユースケは、誘う相手を間違えたかもしれないと思った。
「でもどんな彼氏かによりますよ。わたしの趣味に合わない人と行っても、こっちも気を遣いますし。まぁ、合った人なんてひとりもいないですけどねー」
なんとも人を惑わせる物言いである。
まるで無縁の趣味に違いないが、これまでに趣味の合う人と出会っていないと言われると、初めて趣味の合う人に出会ったと言わせたいと思えてくる。
「モナちゃんって、そういう芸術鑑賞が好きなんだ。意外だな」
「そうですか? 小さい頃から親によく連れてってもらったんです。教育の一環で」
「すごいね。英才教育ってやつだ」
「そんなんじゃないですよ。親が好きだったんです。特に古典芸能が。でもいろいろ習ったりはしました」
「へぇ。なに習ってたの?」
「ピアノとか日本舞踊とか。絵も習いました」
「そうなんだ。けっこうイイとこのお嬢さんなんだね」
「まぁ、そう言うと、そうかもしれませんが――」
「ふーん。でも、そんなイイとこのお嬢さんがなんでキャバクラを始めたわけ?」
「あぁ。なんていうか、気分転換みたいなもんです。ちょっとした息抜き。こんなこと言ったら水商売なめんなよって店の人に怒られるんで、シーッで」
とモナは声をひそめ、口に人差し指を当てた。
ユースケは、その仕草にグラッとした。
男は「誰にも言わないでね」「他の人には内緒だよ」というフレーズに弱い。特にお気に入りの女性からこんなことを言われては、それはもう天使のささやきである。
だが、殊こういう場所では気をつけなければならない。彼女らは往々にして天使に見せた悪魔でもある。このフレーズを使いこなして男を有頂天にさせ、見事に金を吸い上げる。男もそれは心得ていなければいけないのだ。
ただモナの素性はまだよく分からない。キャバ歴の浅さから意図せず言っているようにも聞こえる。
他の派手な装いのキャバ嬢と違って、黒髪で控えめな性格でまだ場慣れしていない印象。それでも若いわりに妙な気品をまとっていて、大和撫子という言葉がよく似合う。そこが魅力だった。その正体が裕福で品格のある家庭で育ったことにあることが分かり、ユースケは得心した。
店を出てから、どんなデートに誘おうか迷った。
美術館、クラシックコンサート、お能。どれも楽しむ姿を想像できない。思い浮かぶのは、美術館ではあくびをして歩き、クラシックコンサートでは頭をうつらうつらとさせ、お能ではよだれ垂らして高鼾。そんな姿を見たらモナはがっかりするにちがいない。
だがサチのアドバイス通りに、相手の興味に合わせてやるべきなのだろう。非常にハードルは高いが、ここで”共通の趣味を持とうとしてくれている”と思わせれば、感動して付き合ってくれるかもしれない。
そう都合のいい解釈を見出して、幾ばくかでも予備知識をいれておけそうな絵画鑑賞と心を決め、美術館デートに誘ったのだった。
〈続〉
#創作大賞2024 #恋愛小説部門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

