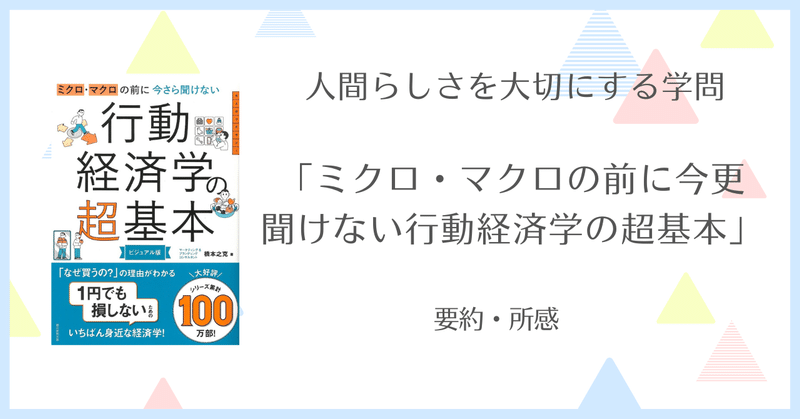
人間らしさを大切にする学問「ミクロ・マクロの前に今更聞けない行動経済学の超基本」 要約・所感
おはようございます。本日は橋本之克さん著書の「ミクロ・マクロの前に今更聞けない行動経済学の超基本」を取り上げたいと思います。
行動経済学ということば、私だけかもしれませんが最近良く見たり聞いたりするようになりました。経済学とどのように区別されているのか?どんな学問なのかと興味が湧き、その入門書である本書を読んでみました。
学問なので少なからずお堅いイメージがありましたが、読んでみると人間らしい学問というのがよく分かります。誰もが失敗したり、悩んだりしたことがある身近な事柄を例に分かりやすく解説してもらえます。
本書からの学んだことを以下にまとめておきたいと思います。
1.行動経済学って?
行動経済学とは比較的新しい学問です。それが生まれた背景には、何があるのでしょう。
かつての伝統的な経済学は「人間は機械のように完璧で合理的な判断をする」とした上での築かれてきました。難しいことばでいうとこれをホモ・エコノミカスといいます。
しかし、現実世界や消費市場においてはこれでは説明がつかなかったり、矛盾が生じたりすることが起こります。なぜなら実際の人間の行動とは、ほどほどに合理的であったり、ほどほどに自制的にであったり、ほどほどに利他的であったりするからです。
人には感情があり、それを元に行動をとります。経済を予測し考える上では、機械のような完璧な人間ではなく、ふつうの人間をもとに考えなければなりません。求められるのはふつうの人間に対する理解でした。
行動経済学は経済学に心理的な側面を加えられて生まれた学問なのです。
2.人は「得」よりも「損」を感じやすい生き物
一万円を損したときの悲しさと、一万円を得したときのうれしさは同じはずです。ところが研究の結果、同じ金額でも損する悲しさは得するうれしさよりも大きいことが明らかになりました。悲しさはうれしさの2倍以上ともされます。
この関係は価値関数とよばれ行動経済学の基本です。このために、人は無意識的損を避けるようにします。この心理を「損失回避」といいます。
そして人はよく考えもせず思考の近道で判断をします。これについては以前のnoteで取り上げました。
目先の損を避けようとするあまり、長期的にはもっと損をするような不合理な行動を取ってしまうのです。
買い物先で「期間限定商品」「今だけポイント5倍」「先着10名」このような言葉に踊らされ余計な出費をすることはありませんか?「その機会を失うことは損」と判断してしまうこと、これも損失回避が働く不合理な行動です。
人はすでに払ったお金に執着するです。
本来は支払って戻ってこないお金のことを気にしても仕方ありません。忘れて今後のお金の使い方を考えるべきですが、それを気にして無駄にしたくないと考えるのです。この心理をサンクスコスト効果と呼びます。
身近な例でいうと、ホテルのバイキングで元を取ろうとするあまり体調が悪くなるほど食べ過ぎてしまう。また、ソーシャルゲームの課金システムはこの心理を上手く突いています。
このときのコストはお金だけでなく、時間や労力など様々な形の資源まで含まれます。この心理が働くと損をすることがわかっていてもやめられなくなります。ビジネスシーンでも、費やした費用や時間などを惜しんで事業の継続を図るあまり損失が拡大していくということも起こるでしょう。
3.心理的バイアスの知識をもてば夫婦仲も良好?
行動経済学的な心理バイアスがはたらく身近な例を紹介します。
ある夫婦がお互いに家事をやってくれないと不満をもっています。そこで、夫婦がそれぞれに対して担当している家事の割合を%で表してもらいます。すると、ほとんどの場合で100%を超えてしまうと言います。
自分が行う家事は把握しているが、相手がやった家事は見えないもの。自分を過大評価して、相手を過小評価してしまう。お互いが「自分だけ頑張っている」「自分は損している」と思いそうなってしまうのです。
大切なのは2人とも悪気があるのではなく、無意識でそう判断してしまうということに気がつくことです。悪意から相手の家事を低く見積もっているわけではないのです。このような心理的バイアスを理解しておけば、家事分担の争いのリスクも減ることでしょう。
今や行動経済学は政府や自治体、企業や団体でも活用されており我々にも身近な存在となっています。それは根底にある”人間らしさを大切にする“という考えが世の中の人々にも共感されているからでしょう。
本書を読めば、今回とりあげた損失回避やサンクスコスト以外にもたくさんの人の心理を学ぶことができます。学んで楽しいと思えるのは、誰もが失敗したり悩んだことがある身近な事柄と距離が近いからでしょう。
今回は入門編ということでしたが、これを機にもう少し踏み込んだ本も読んでみたいと思いました。
より詳しく知りたいと思った方は是非手にとって読んでみてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
