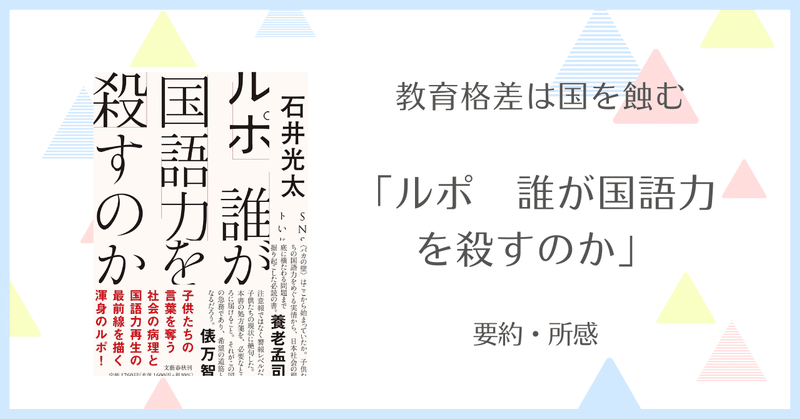
教育格差は国を蝕む「ルポ 誰が国語力を殺すのか」要約・所感
おはようございます。本日は石井光太さん著者の「ルポ 誰が国語力を殺すのか」を取り上げたいと思います。
近頃、子どもたちの読解力の低下が指摘されています。明るみになった発端はOECDが調査で行う国際的な学力テストPISA。2003年日本の子どもたちは数学的リテラシーが6位、科学的リテラシーが5位と上位にあるのに対して、読解力は15位でした。当時はPISAショックとも呼ばれ教育界に衝撃を与えました。ゆとり教育がその原因のやり玉にあげられ、様々な議論を起こしました。しかし、問題はもっと複雑なようです。その根源にあるものとは何でしょうか。
著者は国内外の貧困、災害、事件などをテーマに取材と執筆活動を行うノンフィクション作家であります。本書では文科省や学校をはじめ少年院、フリースクール、精神科病院といった様々な場所への取材から見えてきたもの。その貴重な現地報告に触れることができます。
本書からの学んだことを以下にまとめておきます。
1. 国語力とは?
改めて文科省が定義する国語力とは
①感じる力
②考える力
③想像する力
④表現する力
とあります。
小中高と年代や成長に合わせてそれぞれの配分には違いがあれど、この4つの力を積み重ねていくことが教育の基本方針になります。
目で見た耳で聞いた事を感じて、自分の心の中で考え、自分の言葉で表現する。社会的動物である人間社会を生き抜くために国語力はあらゆることの基礎になる力です。国語力は生きる力とも言い換えができると思います。
近年はプログラミングをはじめICTや情報処理といった新しい教科が加わったり、英語をはじめとする外国語教育の必要性がますます高まっているのは事実です。しかし、外国ではなく日本で育てられている以上は母国語である日本語の基礎、つまり国語力がしっかりとあることは言わずもがな大前提なのです。
ゆとり教育が批判の的ととなっている最中に、日本語の危機として世の中で話題となった藤原正彦氏著書の「祖国とは国語」という書籍があります。
そのなかではこのように表現されいます。
"国語力の低下は知的活動能力の低下、論理的思考能力の低下、情緒の低下、祖国愛の低下を同時に引き起こしている。不況が何十年続こうが国が滅びないが、この4つの低下は確実に国を滅ぼす(一部略)"
あらゆる教育の根源は国語力であるということ。これを改めて自覚する必要がありそうです。
2.何が国語力を殺すのか?
・課題集中校からみる
子どもの国語力の差には家庭環境がもっとも影響しています。
課題集中校ということばがあります。生徒の授業態度や学力の低さ、非行や校内暴力などの問題行動が原因で教育活動が困難な状態にある学校のことを指し、1980年代に高等教育を中心に登場した用語です。
近年の課題集中校はかつてのそれとは形相が変化しているそうです。一昔前の課題集中校とはいわゆるヤンキーのような不良が通う学校というイメージがありました。現在では不良文化の衰退にともないヤンキーはむしろ少数なのです。それよりも虐待やネグレクトの環境で育てられた子、発達障害から社会適合が難しい子、生活保護家庭の子、外国にルーツがあり言葉の弊害から普通校への進学が困難な子といった子が多数を占めるといいます。
かつてのヤンキーが起こすトラブルは喧嘩や喫煙、窃盗と分かりやすいものが大部分であり、その特徴は彼らも悪いことをやっているという自覚があることでした。しかし、現在のでは生徒が問題を起こしてもそれが悪いことだと理解できないケースが増えてきているそうです。教員が丁寧に面談しても言葉が出てこなくてポカンとしている、理由を聞いても「なんとなく…」で止まる。そんな問題を抱えています。
・問題行動の根源は?
非行にはしる。不登校になる。
個性によって生きづらさからくる表現の仕方は異なれど、問題行動は子どもたちからSOSであるという意味では同じです。
そういった子どもたちに共通している、問題の根源にあるのは言葉を失っているということ。自分の気持ちを誰かに伝える大切な手段が無いのです。
喜怒哀楽のうち、とりわけ怒りや哀しみの感情は理解して表現するのが難しいと言います。どちらもその程度によって表現する言葉は豊富にあります。にも関わらず、言葉を失った彼らはどんな感情も「死にたい」「コロす」だけで片付けてしまう。このような状態が続けば感情と行動のバランスが崩れてしまっても仕方ありません。
スクールカウンセリング、フリースクール、少年院。場所は違えど失った言葉を取り戻すことからその支援は始まります。
・SNS社会からみる
世の中SNS社会となって早久しいですが、子どもたちの間のコミュニケーションもかつてのメールからLINEへと変化していきました。メールとLINEの大きな違いは文章の短文化です。LINEの良さは単語や素材だけで素早い意思疎通ができる軽快さだと思います。
しかし、国語力が未熟な子どもたちにとってこの短文テキストコミュニケーションへの変化はしばし誤解を生み、争いの火種になる危険が高いといいます。
グループLINEでの誤解としてわかりやすい例をひとつ。
少女A:明日〇〇で遊ばない?
少女B:いいね!いく!
少女C:なんでくる? 少女B…
Cの子からするとそこまで来る手段を聞いたつもりでしたが、Bの子はCから何故あなたがくるんだ?と咎められたと誤解してしまいます。
このように短文であると、受け手によっては間違った解釈をされて傷付けてしまう恐れがあるのです。
また、「ヤバい」「エグい」「ウザい」この3つであらゆる事を形容してしまう。大人でも心当たりがあるのではないでしょうか。SNSに限らずですが、子どもたちの間ではより一層深刻な論理的思考能力の低下をもたらしているのです。
3.ゆとり教育とは何だったのか?
戦後高度経済成長期において、教育の目的は国力の底上げ。大学での教育にはこれだけの知識が必要だというところから逆算して、小中高と知識を系統的に積み上げることを目指しました。欧米諸国に追いつけ追い越せの時代背景では納得もいきますし、効率的な方針でした。
しかし、行き過ぎた系統主義には副作用が伴うもの。詰め込み型の教育について行けるのは小学校で7割、中学校で5割、高校で3割の七五三という揶揄することばも生まれたそうです。
ドロップアウトする子どもが非行に走り、社会問題となったのが1980年代。そこから日本の教育は知識の詰め込み一辺倒から調和の取れた教育、つまりゆとり教育へ舵をきっていきます。
問題はゆとり教育の方針を創った人たち(理想)と、実際の現場(現実)の乖離にありました。ゆとり教育はこれまでの系統主義の授業を大幅に削減して、創意工夫した探求学習の時間を割くように求めました。
国語力は家庭環境の影響をもっとも大きく受けると先に述べました。ゆとり教育を創ったのはその多くが良い家庭環境で育った文科省の官僚たち。彼らにとって基礎的な国語力は常識の範囲でわざわざ学校で教えるほどではないと捉え、削減の対象していきました。また、探求学習についても現場の先生方なら創意工夫でやってくれるだろうとやり方を示さず丸投げであったといいます。
さらに系統主義からの脱却をうたいながらも受験の形態が変わらなかったため、これまでの知識の積み重ねも求められました。知識の詰め込みと探求学習の両方を求めるちぐはぐ感。現場においての混乱は容易に想像ができます。
その後社会問題化したゆとり教育は見直されて行くことになりますが、今の公立校が抱える問題はこれだけではありません。現在でも度々話題にあがるのが教員の労働環境の悪さです。
日本の小学校の教員の平均週労働時間は54.4時間、中学校では56時間でありOECDの中でも最も長いといいます。学校の行事や事務作業が多いこと、クラブ活動の顧問やPTA保護者への対応等で先生たちの業務はてんてこ舞い。それでなくても配慮が必要な生徒は増える一方で労働環境はかなり悪いようです。
教員不足がその根本原因の一つですが、これに対して国から必要な予算が組まれているわけではないようです。政府が教育に対してかけているお金は国際的にみても最低レベルであるといいます。これでは解消は難しいでしょう。
一方で本書では私学の学校の先進的な国語の授業の様子も伺えます。
自然と調和しながら横断的に他教科を織り交ぜ言葉を学ぶ、一つの小説を時間かけて精読し、答えのない問題を生徒同士でディスカッションさせるといったものです。まさにかつてのゆとり教育が目指した探究学習がそこにあると感じました。これでは家庭環境に恵まれない子どもと教育格差もますます拡大してしまう、ゆとりとは結局は経済的ゆとりなのか。そんな皮肉も頭をよぎります。
こどもの読解力低下というテーマから見えてきたものは、単に教育の問題に収まらず様々な社会問題が複雑に絡み合っている事実でした。特に格差や貧困という課題を放置すれば、少子高齢化で経済の見通しが明るくない日本社会においては真綿で首を絞めるように国力衰退につながります。
短期的な成果主義ではなく、長期的な目線で未来をになう子どもたち一人一人に生きるための力(ことば)を付ける教育を。本書の主張を端的にあらわせばこのような言葉が浮かびます。
個人としては自分が義務教育を受けていたころとの時代変化を強く感じる経験となりました。一人の親としては学校に丸投げするのではなく、家庭でもしっかりとことばが身につくよう普段から子どもと接して行かなければと改めて思いました。
より詳しく知りたいと思った方は是非手にとって読んでみてください。
こんnoteも書いています。よろしければご覧下さい↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
