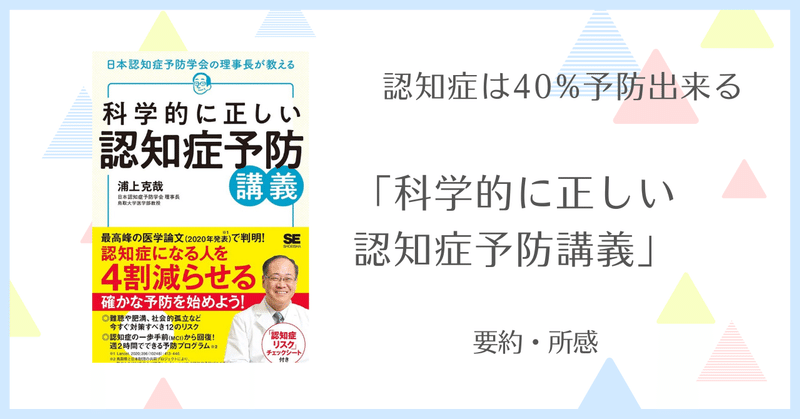
認知症は40%予防できる「科学的に正しい認知症予防」要約・所感
おはようございます。本日は浦上克哉著書の「科学的に正しい認知症予防」を取り上げたいと思います。
日本では今後10年以内に認知症の人が700万人を超え高齢者の5人に1人が認知症という時代が来るとされています。いわば親族や知り合いの中で認知症の人がいるのが当たり前の社会になります。しかし少子高齢化の進行する日本では、支え手となる若い世代が十分なほど介護人材へとやってくるとは思えません。私達は一人一人の、自助努力による認知症の予防はますます必要となってくるでしょう。
本書の著書である浦本先生は認知症予防医学の第一人者であり、タイトルの通り科学的根拠を示しながら、認知症予防について学ぶことができます。
認知症について正しい知識をつけて予防できるよう、本書からの学んだことをまとめておきたいと思います。
1.認知症はなったら治らない だから予防が重要
認知症とひとくちでいっても、いくつか種類があります。一番患者が多いのはアルツハイマー型認知症で全体の約6割を占めます。次に脳血管性認知症が2割、その他にレビー小体型認知症や前頭葉側頭葉型認知症などがあります。
認知症の症状は記憶障害(ものわすれ)、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能障害、言語障害(失語)、失行・失認がありこれらを中核症状と言います。また中核症状の影響で起こる徘徊や暴行・暴言、幻覚、妄想などは行動心理症状(BPSD)と言います。
すべての人に共通することは、認知症はなったら治らない(一部を除く)という事実です。発症するとゆっくりですが確実に症状が進行していきます。残念ながら、現代の医学では「認知症になった人」を「認知症でない人」にすることは出来ません。症状の進行を緩やかにして時間を稼ぐことしかできないのです。
認知症の原因は脳内にアミロイドβと呼ばれる異常なタンパク質が蓄積してそれが脳細胞にダメージを与えるためと考えられています。実はアミロイドβの蓄積は発症よりも20年程前から起こっているとされ、現在においてその詳細な検査には高額な医療費がかかります。またアミロイドβの蓄積で認知症が必ず発症するわけでもないのです。
認知症が治らない病気としましたが、まだ発症に至らずに引き返せる段階があります。それがMCIと呼ばれる軽度認知障害の段階であり、信号で言うならば黄色になります。具体的には記憶障害など中核症状に自分も周りの人も気づき始めているが、日常生活は自立して送れている時期を指します。
著者の浦本先生の研究だけでなくその他の研究でもMCIであれば認知症状が改善され、発症の予防が出来ることが分かってきているようです。
2.認知症は40%予防できる
近年、英国のロンドン大学の教授が書かれた論文が話題となっています。メタアナリシスという信頼性の高い手法で研究の報告で認知症の発症に関わる12のリスク因子とそれぞれの関連性がわかりました。
その報告によると私達の行動次第で認知症の40%は予防できるというものです。
たかが40%でしょうか?そう思った方大きな間違いです。5人が認知症になっていた所、2人は認知症にならずに済むのです。また、現段階で分かっているのが40%という意味で今後研究次第で他の60%のうちの少しずつそのリスク因子が明らかにされていくことでしょう。
以下にその12因子を並べます。
若年期以降
・教育歴(知的好奇心)7%
中年期以降(45歳以降)
・難聴8%
・頭部外傷3%
・高血圧2%
・過剰飲酒1%
・肥満1%
高齢期以降(66歳以降)
・喫煙5%
・社会的孤立4%
・大気汚染2%
・運動不足2%
・糖尿病1%
リスク因子の中で意外にも最大なのは難聴です。中年期に難聴になると認知症のリスクが1.9倍にも高くなります。難聴になると脳への情報量を減らすとともにコミュニケーションが取りづらくなります。会話をするが億劫になり、脳への刺激機会が減少することで脳の萎縮をもたらします。
耳には視力と同じくらい早期から気にかけて置くべきなのです。具体的には大音量や騒音などの環境に長く居ないこと、イヤホンなども使いすぎには注意すること、耳栓等を適宜使用することなどが挙げられます。また、少しでも聞こえづらさを感じたら早めに耳鼻科を受信して早期から補聴器を調整することも大切な行動です。
高齢期で気をつけたいのが糖尿病です。インスリンは数ある内分泌ホルモンのなかで唯一の血糖値を下げる効果があります。また、インスリンは脳神経を保護する方向に働き異常なタンパク質も作りにくくさせる働きがあります。肥満や糖尿病でインスリン分泌量が減ることは認知症リスクも高めてしまうのです。
3. 3つの習慣で認知症予防。私達にできること
著者の浦本先生が高齢期の認知症予防教室で取り組みに掲げたのは以下の3つの習慣です。
・運動
・知的活動
・コミュニケーション
これらの3つの習慣があれば、先に上げた12のリスク因子をおおよそカバーができるからです。
運動をすることで当然ながら運動不足の解消ができるだけでなく、肥満や生活習慣病の治療にもなります。知的活動はいわゆる知的好奇心を刺激して脳を若く保ちます。コミュニケーションは社会的孤立や抑うつを遠ざけます。
現在若年期、中年期の方が出来ること。それは科学的にわかったリスク因子のうち自分に当てはまっている認知症のリスク因子を知り日常生活を改めること。また当てはまっていないリスクについては今後も該当しないように対策をしていくことでしょう。
少子高齢化社会において認知症は必ず直面する社会課題の一つです。高齢者自身が予防意識を持って生活習慣を変えたりすることももちろん必要ですが、特にMCI段階では周囲の人の気づきも大切でしょう。家族や友人の正しいサポート、適切な医療提供があれば認知症発症を予防することが可能だということを社会全体で共有できると良いですね。
認知症リスク因子に関しては今回挙げた以外にも、不眠症状や口腔環境なども影響が指摘されておます。認知症については他の書籍を取り上げる形で今後も追っていければと思います。
より詳しく知りたいと思った方は是非手にとって読んでみて下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
