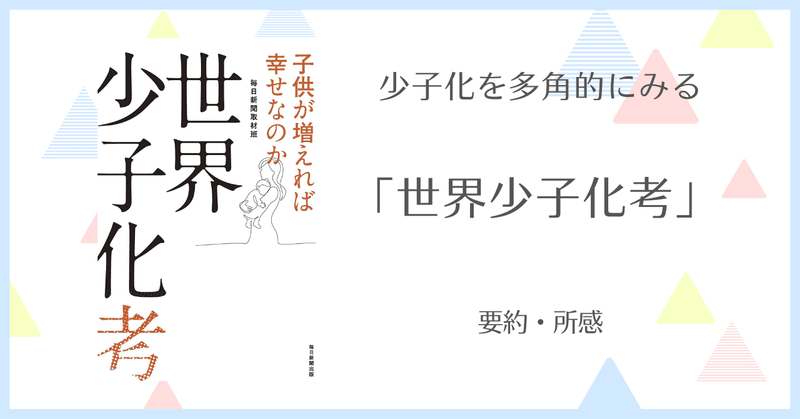
少子化を多角的にみる「世界少子化考 子どもが増えれば幸せなのか」要約・所感 ②
おはようございます。本日も毎日新聞出版の「世界少子化考 子どもが増えれば幸せなのか」を取り上げたいと思います。
前回のnoteでは、世界各国の少子化事情やその対策を紹介するの形でまとめました。
今回はそもそも少子化はなぜ起こるのか?少子化は絶対悪なのか?そして最後に改めて日本の少子化を考える。
この点に焦点をあてて本書からの学んだことをまとめて行ければと思います。
1.少子化対策が難しいのはなぜか?
社会が豊かになれば少子化は進む。これは先進国の経済成長と人口動態の歴史をみれば、その関係は明らかです。人口のボリュームゾーンである中間層が豊かになり、自分の生活水準や子どもの教育水準を高く保とうとして将来の出生数を制限することがその要因です。
また、女性の社会進出は少子化の一因となると言われています。これは、女性が社会進出することで、結婚や出産を遅らせる場合があるためです。また、結婚や出産後にも女性が仕事を続け、子育てをする時間・負担が増えたことが少子化につながっていると考えられています。
しかし、フランスの例でもみたように女性の権利は自由で平等な社会を目指す人々の社会運動という長い歴史の中で勝ち取られてきた尊いものです。ましてや人口が減っていき労働人口が限られた社会では女性の力がますます必要なのは火を見るよりも明らか。
日本は世界的にみれば残念ながらまだまだ男女格差は大きい国の一つです。そこで、政府はフランスやスウェーデンなどの女性の労働率も出生率も高い国に着目して、女性が活躍できる社会を目指せば少子化にも歯止めがかかるという考えに基づき対策を進めてきました。
フィンランドの例を見ていきます。フィンランドは男女格差を図るジェンダーギャップによると世界で二番目に格差の少ない国です。男女平等は子育てでも進んでおり、政府は父親の育児参加を促し育休取得は8割を超えています。また、家族担当制で保健師が付き家族全体を支えてくれるネウボラというシステムが整っています。
そんなお母さんに優しい国ランキングたびたび1位獲得しているフィンランドでは、近年合計特殊出生率が低下傾向にあり、19年は1.35と日本より低くなっています。背景にあるのは若者の中で、子どもを持たない選択をする人の割合が増しているといいます。(2015年、理想の子どもの数を答えるアンケートで「0」の回答が14%)
フィンランドのようなリベラルな国(男女格差が少なく、自由と権利意識が強い)で苦悩する少子化という社会問題。個人の自由と社会全体の利益の歪み、少子化対策の難しさが垣間見えます。
2.気候変動の視点では少子化のほうが良い?
現在、世界規模課題とされる気候変動問題。この問題側の視点に立つと、少子化というのが違う表情に見えてきます。
2019年に出された国連の報告書によると78億人の世界の人口は2050年までに97億人を超えて、2100年には109億人に達する可能性があると推計されています。先進国が少子化から人口が減っていく一方で、アジアやアフリカ地域の発展途上国では爆発的に人口が増えるからです。
温暖化の原因となるCO2排出量は人口で決まるのではありません。人口が増える発展途上国よりむしろ、都市化した大量消費社会である先進国のほうが温暖化の原因をつくっているのです。
北半球の先進国の個人がCO2排出量を長期的に削減する最も効果的で唯一のことは子どもの数を一人に抑えることなのです。
温暖化目線で見れば先進国の人口の安定、緩やかな人口減少があるほうが問題への対処が容易になります。
3.日本の少子化問題について
日本はそもそも子育ての経済的支援が少ない国です。OECD加盟国で比較すると2017年時点で児童手当や保育サービスなど家族政策に対する公的支出のGDP比は1.79%で37カ国中26位。初等教育への公的支出GDP比2.4%で35位といずれもが低い水準です。
しかし、子どもが生まれてからの支援だけでは止まらないのが少子化。なぜなら少子化の要因として未婚化と出生率の減少どちらが大きいかというと9対1で未婚化と言われているからです。韓国や中国と同様に子どもを持つ前提が婚姻という意識が強い日本では、適齢期のカップルが結婚に踏み切れないことにこそ大きな課題があるのです。
それ以外にも課題は山積みです。男女格差、父親の育児参加、同性婚、LGBTQ、先進医療の保険適応、代理母出産など…他国の事情を知れば知るほど少子化に関連する課題が遅れていることが分かります。
それにも関わらずOECDの主要国では最も少子高齢化が進む日本。日本は世界の実験室ともされ今後どのように政策的解決策を生み出していくかは、世界の注目的にもなっているのです。異次元の少子化対策と目して議論される昨今、それほどまで追い込まれているのは事実です。
やり方を選ばなければ未婚の人に課税をしたり、お見合いを義務化したりするのも考えられます。けれど、そんな社会は誰も望まないでしょう。改めて、結婚して子どもを持ちたいと思っている人に寄り沿った政策が求められる。一周して戻ってきたのはそんな当たり前な結論でした。世界の少子化事情を多角的な視点で捉えるよい機会となりました。
より詳しく知りたいと思った方は、是非手にとって読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
