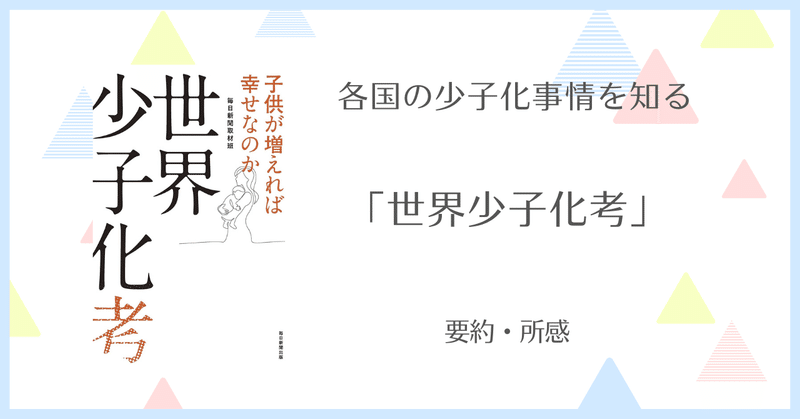
各国の少子化事情を知る「世界少子化考 子どもが増えれば幸せなのか」 要約・所感
おはようございます。本日は毎日新聞出版の「世界少子化考 子どもが増えれば幸せなのか」を取り上げたいと思います。
今年の3月に「2022年日本の出生数が80万人を切った。想定よりも8年はやいペースで少子化が進行」このニュースを皮切りに岸田政権も「異次元の少子化対策」と称し政策へと舵を取り、国内では様々な議論が起こっています。
一方で国外に目を向けてみると日本と同様に少子化に悩む国もあれば、対策を講じて歯止めをかけた国もあります。そうした国々は日本と何が似ていて、何が異なるのか…
本書は韓国、中国、フランス、イスラエル、米国、ハンガリー、フィンランドの現地取材を通じ各国の社会や政策からみる少子化問題について学ぶことができます。
また、そもそも子どもが少ないのは本当に悪いことなのか。子どもが増えれば幸せなのか。この辺りについても論じられています。
本書の良い点は一人の筆者ではないこと、取材班だけでなく少子化に精通した様々な論客からの考察も含まれており、この問題について多様な視点で深く考えさせらます。
このnoteでは各国の少子化の現状とその対策についてまとめていきたいと思います。
1.韓国
日本と地理的にも文化的にも近いお隣の国、韓国。実は日本よりも少子化が厳しい状況にあります。合計特殊出生率は0.81、低いとされる日本の1.34ともかけ離れています。
韓国では結婚しない若者の増加と晩婚化が社会問題となっています。
朝鮮戦争を休戦中であり分断国家である韓国は、男性には兵役義務があります。大学在学中に2年程度で終えるのが一般的であり、その後就職するのは20代後半になります。
韓国には儒教の精神が色濃く残り、結婚の際には男性側が家を用意するという考えがあります。2017年の文政権発足移行、首都ソウルの約100m2のマンション価格は5年で2倍にもなっていると言います。稼ぎ始めるのが遅く、家も高い。これが結婚を遠ざけているのです。
何故そうなっているのか。ソウルには人口の約半数の2600万人が住んでいます。日本でも東京一極集中と言われますがそれでも人口の1/10程度、韓国の人口が約5000万人であることからソウル一極集中は日本の比ではありません。
韓国は一握りの巨大財閥主導で経済発展してきた経緯があります。大企業の比率は0.09%と言われ、中小企業との賃金格差は日本よりも大きいです。僅かな大企業への就職を目指す競争は熾烈さを増し、受験戦争がそのスタートラインとなっています。
総じて韓国は日本以上の格差社会、学歴競争社会、都市型社会でありそれが晩婚化と結婚をしない若者をつくり少子化となっているのです。
政治体制にも要因がありそうです。一人の大統領に権力が集中する韓国では大統領の鶴の一声で大きな政策転換が起こることも珍しくありません。
しかし、大統領は5年の任期制。最初の1~2年は効果の出る政策課題に熱心に取り組むものの、後半1~2年はレームダック化して新たな政策をうち出せなくなるのが実情です。
少子化対策のような数十年単位で成果が出る問題はどうしても後回しにされる。5年に一度政権が変わり方針も変わるので少子化問題の解決に向けた取り組みが難しいとされます。
2.フランス
先進国では例外的に合計特殊出生率が1.88と高い水準で推移するフランス。少子化優等生として、各国のお手本ともされる国です。
日本でも医療費や教育費の無償化や家族手当など、子どもを産み育てるための経済的支援が倣われています。しかし、本当にお手本にすべきはフランス人が共有している社会的な価値観の方にありそうです。
フランスでは未婚のカップルに結婚と同等の権利を与える連帯市民協約パックスが法制化され、今ではカップルが選択する結婚とパックスの割合は半々となっています。
2013年には同性婚が認められました。その後同性婚女性への生殖補助医療の適応が実現し、平等の観点から独身女性も対象となりました。
このような多様な家族のあり方、価値観の定着はは昨日今日で浸透するものではありません。フランスもかつては女性だけでは銀行口座が持てず、一家の父親に強い権限が与えられた保守的な社会でした。
転機となったとは1960年代の社会運動です。とりわけ女性の権利、自由平等を求めて立ち上がった68年の5月革命は社会の変化を促しました。
日本が特に留意しなければならないのは、経済的支援や法制度の改定が決して少子化対策の目的で執り行われているわけではないこと。国民それぞれの幸福感や家族感に応じて個人の権利を保障するのがその目的であり、合計特殊出生率の増加はその副産物に過ぎないのです。
3.イスラエル
先進国で少子化優等生のフランスを大きく上回る国が中東のイスラエルです。2019年には合計特殊出生率が3.01に達しました。共働きで4人の子育てを可能にするユダヤ人社会の秘密とは何か。
ユダヤ人の国イスラエル。その一番の特徴は家族の絆の強さです。安息日とされる金曜、土曜や宗教上の祝日を親族一同が集まって過ごすことも多いと言います。親族との距離と近いため、何が起こっても子どもの面倒を頼むことが出来るのです。助け合う家族がユダヤ人の理想です。
堅調な経済も出生率を後押ししています。イスラエルは年率3%超えの経済成長を続けており、一人あたりのGDPは2015年に日本を上回っています。国土面積は四国ほどだが技術革新によって産業を発展させてきました。
世界一手厚い体外受精制度があります。1995年以降18-45歳の女性の体外受精を二人目の子どもが生まれるまで全額保証している唯一の国です。2018年には年間48,294回の体外受精が実施され9,399人の生まれました。これは全出生数の5%にあたります。
教育にお金がかからないのもイスラエルの魅力。3歳以上の公立の保育園から大学の教育費が格安で、多くの生徒は公立大学に入学が出来てその授業料は年間36万円ほど。日本や韓国ほど受験戦争も厳しくありません。
社会全体が家族のが家族や子どもを大切にし、それが幸福に繋がるという価値観を共有している。それが、日本との大きな違いと言えそうです。このような価値観は時に強い同調圧力となり居心地の悪さを感じる人もいます。それでも家族幸せを考え、生活の質を上げるためにお互いが助け合う姿には何らかの学ぶべきものがありそうです。
今回は3カ国のみの紹介となりましたが、その他の国も少子化対策に上手く行っているところ、苦戦しているところ多種多様でその原因も様々。改めて感じるのは少子化対策に絶対的な正解は無いということ。少子化問題はその国の歴史や民族性も色濃く反映されており、一国の成功例をそのまま倣って成功するわけではありません。
また、フランスの例のように直接的な少子化対策ではなく個人の権利を追求していくことは理想とも思いますが、社会の価値観を変化させるのには膨大な時間を要します。少子化対策の難しさを痛感する読書経験やとなりました。
興味を持たれた方は是非手にとって読んでみてください。
次回のnoteでは少し視点を変えます。少子化対策以前に、子どもが増えることはそもそも幸せなのか、そして日本の少子化対策はどのようにすれば良いのか。この点の議論をまとめる回としていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
